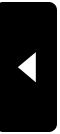2018年04月02日
議会報告(私の代表質問その2)
昨日の続きです。
●質問3
施政方針から、「活気にあふれ、産業が躍動するまち(産業・雇用)」の中から
お聞きいたします。
農業や水産業において、農業水産事業者の高齢化や減少による労働者不足、
耕作放棄地の増加など厳しい状況が続いており、情報通信技術ICTの活用と
AIの先進的導入にはどのように取り組んでいくのかをお聞きいたします。
また、三豊市農業振興計画は、どう見直され反映されていくのかもお聞き
いたします。
次に、シティープロモーション活動という点、私から数年前に一般質問もさせて
いただきましたけど、これは人口減少時代に入った日本において、全国の
自治体が生き残りをかけてさまざまな施策を行っている中、観光客の増加、
定住人口獲得、企業誘致などを目的として、地域のイメージを高め、知名度を
向上させる活動や自治体におけるマーケティングや営業の活動を総称して、
シティープロモーション、またはシティーセールスと呼ばれるものであります。
いわばこの言葉は、地域の売り込みとも捉えられますが、現在、関東学院
大学法学部地域創生学科准教授で、私もセミナーを受講させていただいて
から個人的にメールでのやりとりもさせていただいております牧瀬稔先生の
提唱されているシティープロモーション活動とは、1、認知度を高めること、
2、情報交流人口、これは自地域外に居住する人に対して何らかの情報提供
サービスを行うことですが、この情報交流人口プラス交流人口や定住人口の
獲得を目指す活動、3、現在生活している住民、既存住民が愛着心を持ち、
シビックプライドですね、引っ越ししていかないことを目指し、4、企業誘致にも
つなげていく活動として、さまざまな住民や事業者、各種団体から選ばれる
自治体へと変貌するための取り組みであると定義づけがあります。
シティープロモーションは、いわば自治体間競争の幕あけだとも考えられます
が、今後どのような具体策を展開する予定なのかをお聞きいたします。
3点目は、昨年度からの継続事業として、地域商社、ふるさと納税、ふるさと
住民票制度など、昨年度の成果としてどうだったのかお聞きいたします。
特に地域商社は、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が、地域商社
機能の設立・普及に向け、地方創生のな鳴り物として地域商社協議会が
設立されております。
昨年度には、瀬戸内うどんカンパニー株式会社、若い北川智博CEOが
選ばれました。
私も何度かお会いしましたが、本当にすばらしい若者で、今後最も本市を
PRできるすばらしい事業人でもあるとは思いますが、今年度の展開などを
お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁
浜口議員の御質問にお答え申し上げます。
まず最初に、農業、水産業の現状につきましては、議員御指摘のとおり、従事
者の高齢化による労働力不足や耕作放棄地の増加により、厳しい状況であり
ます。
御質問のICTの活用とAIの導入の現状では、現在、三豊・観音寺地区において
野菜、果樹の生産技術の構築のための実証実験を進めているところです。
本市としては、その後の実証結果を受け、マニュアル化したものを普及センター、
JAと連携して、農家への指導に努めるとともに、さきの質問でも御答弁申し上げ
ましたように、IoT、AIの先端技術を導入し、新たな農業、水産業の創出にも
積極的にチャレンジしてまいりたいと考えています。
農業振興計画につきましては、平成30年度に策定される第2次総合計画との
整合性も図りながら、時代背景を考慮し、見直しに取り組んでまいります。
次に、今後のシティープロモーション活動を人口減少対策にどうつなげて行く
のかという御質問ですが、知名度向上プロジェクトや瀬戸内国際芸術祭を初め
とするさまざまな取り組みの成果もあり、三豊の認知度も徐々に高まっていると
感じております。
また、父浜ヶ浜などのインスタ映え効果などにより、本市の交流人口、関係人口
は近年著しい勢いで増加しております。
時期を逸することなく、民間企業、市民、行政が役割を明確にして、この豊かな
資源を使ったシティープロモーションに取り組み、関係交流人口を移住定住人口
につなげなければなりません。
一方で、この中に長くお住まいの市民の中にあっては、三豊というよりも、まだ
まだ旧町の感覚を持たれているほうもおいでになることから、三豊のシビック
プライドを抱いていただくためにも、旧町ごとのハードルを下げ、三豊は一つと
いう意識の醸成に取り組まなければいけないと感じています。
最後に、昨年度から継続しております。地域商社、ふるさと納税、ふるさと住民
票制度につきましては、まず、ふるさと住民票は現在74名の方に発行し、三豊
との緩いつながりの中で関係を持っていただいており、今後は保有者へのイン
センティブについても検討してまいりたいと考えています。
次に、平成20年度から寄附の受け入れを初めて、来年度で11年目を迎える
ふるさと納税ですが、平成27年にインターネットで寄附受け付けを開始し、
6,800万円にまで寄附額がふえましたが、その後、徐々に減少しております。
寄附者の立場から見ると、三豊市の返礼品の魅力が他の自治体と比べ弱く
見えていることが一因に上げられます。
こうした状況に対し、来年度はインターネット上での寄附窓口をふやし、返礼品
の充実を図ることで、三豊産品のPRを強化し、寄附拡大につなげてまいりたい
と考えております。
最後に、地域商社瀬戸内うどんカンパニーですが、昨年8月のCEO決定、9月
に法人設立を経て、その後、市内の生産者、事業者や金融機関等、また地域外
での地域商社や企業と連携しながら、商品開発事業、うどんハウス事業、ツーリ
ズム事業の三つの事業の構築とトライアル行っております。
準備期間を経て、30年度から本格的に事業展開する予定であり、市も早期に
法人が自立し、地域に稼ぐ仕組みをもたらせるよう、事業構築、トライアルに係る
側面支援を行ってまいります。
●再質問
ありがとうございます。
まず農業なんですが、私たちがICTとかAIとか考えると、やはり労働力の負担が
軽くなるがゆえの、気象条件とか土壌分析、こういうのが進められるのかなとか、
単純に考えてしまいがちになんですけど、新たな農業として、企業、生産者と
タイアップ、行政がマッチングするという点、非常によくわかりました。
今後は、それらを実現するための耕作放棄地の解消ですね。
これによる大規模な農地の集約があって、農業法人とか大規模農家とか企業、
若者、それらが大がかりにICTとかAIを使って新しい農業を行っていくのかなと、
農業の将来像を考えてしまいます。
それらを考慮すると、耕作放棄地に関しては、農地の集積、農地中間管理機構
の役割ですね。
今後もこの中間管理機構への貸し付けが増加するとは思うんですが、基盤整備
が行われていない農地については、担い手が借り受けない状態になると。
機構に貸し付けた所有者が、基盤整備のための費用を負担する用意がなくて、
結果として担い手への農地の集積、集約化が進まなくなる可能性があり、農地
中間管理機構が借り入れている農地については、農業者の申請、同意、費用
負担によらず、都道府県が基盤整備を推進していただける整備事業があると
いうふうにお聞きいたしております。
これ、平成35年までに担い手が利用する面積が全農地面積の8割となるよう
農地の集約が推進されると、非常に有効な耕作放棄地対策であるとは思います
が、この点について、今後、県とは事業がどう進む予定なのかを、まず1点お聞き
いたします。
次に、シティープロモーション活動についてですが、民間企業の組織には営業部
というのがあります。
地方自治体にはない営業活動、人口が減り、税収が減ると嘆くばかりではなく、
これからの自治体では営業という視点を組み込んでいく必要性というのを牧瀬
先生が説いています。
それゆえ、企画の強化策として、流山市のマーケティング課や箕面市や武雄市
のように、営業という文字を組織名に入れる傾向、近隣では善通寺市でも営業
課というのがありまして、地方自治体の営業という視点が非常に強まってきて
おります。
企業立地対策課も必要だとは思いますけど、営業という観点からシティープロ
モーション活動をどこかの課で進めるべきであると考えます。
この点、どうお考えでしょうか。
それと、ふるさと納税についてはいいんですけど、ふるさと住民票制度ですね。
これが74名、本市と心のつながる人たちの裾野を広げ、ふるさと会の充実や
本市へのふるさと回帰も視野に入れ、多くの人と緩くつながる関係づくりの
取り組みとして進められてきたということだったんですけど、このあたりの成果
といいますか、緩くつながって何がどうなったのかをお聞きしたいと思うんです
けど、お願いいたします。
●答弁
それでは、浜口議員の再質問にお答えをいたします。
先ほど言われました耕作放棄地、農地の大集積化等々の話でございますけども、
香川県の農地中間管理機構、平成26年に設立されまして、毎年毎年その貸し手、
借り手の募集をやって、契約行為をやっているわけなんですけども、始まりまして、
この2月現在で約120ヘクタールの契約が成立をしております。
当然のことながら、貸し手、借り手ともに協力金が得られるような制度となっており
ますし、売買につきましてもあっせんをしておりまして、税の控除等も行われると
いうところでありまして、ただ一つ難点が、耕作放棄地、中山間部等々も、そういう
ところに預けたいという話もあるんですけども、なかなか道がないとか、耕作しづら
いとかいうのは、契約がなかなかマッチングしないというような状況もございます。
そういうことを受けまして、先ほど議員御指摘の補助整備ですよね。
中山間における補助整備ということもとも国のほうでは対策をとられております。
今年度、平成29年度、土地改良法が改正となりまして、議員御指摘のとおり担い手
に集積されれば、国の施策としましては、担い手、新規就農者、そういうふうな
大規模な農業をやる方に農地の8割を集約したいという目標を立てております。
そういう中で、補助整備につきましても、そういうふうないろんなメニューがあるん
ですけども、中間管理機構へ預ける意思を持ったその集積率の度合いによって、
個人の負担金を軽減すると、極論となれば負担がゼロというような補助整備も
創設されております。
三豊市の場合、もう既に県とともに、そういう制度ができましたので補助整備の
推進活動ももう既に行っております、何カ所かでやっています。
そういうことを踏まえまして、耕作放棄対策等にもつなげていきたいと考えて
おります。
2点目のシティープロモーションの件ですけれども、これは議員御指摘のように、
これまでには自治体の感覚では少なかった営業という感覚をこれから持たなけ
ればいけないということで、シティープロモーションとあわせたシティーセールス
というような言葉がございますが、シティーセールスという観点で三豊の資源を
売っていくというような感覚が、これからもう必要なんだろうなと思っています。
議員御指摘のありましたように、先進地では既に営業課、シティープロモーション
室等々が設けられているようですけれども、先進事例も参考にしながら、組織
については勉強していきたいなと考えています。
3点目につきましては、ふるさと住民票、これは昨年スタートアップしたばかり
ですので、まだまだ成果という点では出ておりませんけれども、この緩い関係
を持つことで、三豊と何らかのつながりを持って、このことを定住移住、また産業
の振興に生かしていけたらというようなことの目的で行っておりますので、今後、
この輪を広げながら、もっと強化していく中で、先ほど申し上げましたように三豊
市のインセンティブ等々を設けて、三豊市にもっと魅力を持ってもらえるような
組織体制をつくっていきたいなと考えております。
●質問4
「豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち(環境・生活)」の施政方針の中から、
定住政策、平成20年度から始まった空き家バンクを初めとする定住施策も
多くの課題が出てきております。
各町で空き家のばらつきが見られることはもちろん、一番には相続の問題が
あって、その住宅には関与できないケース、要は相続人がもめているケース
とかだと思いますが、このケースが一番多いかと思いますが、その他、仏壇が
ある、荷物置き場として使用している等々の理由もあるとは思います。
特に、三豊市空家等実態調査結果報告書によりますと、詫間町の志々島、
ここは空き家率が40%を超えています。
粟島、荘内箱地区、生里地区、積地区などがおおむね10%以上を超えており
ます。
本市の平均は3.1%ですから、まず詫間町の空き家の多さが突出している点、
特に島の物件、危険家屋も含めて、これらを今後どのようにしていくかという
ことにもつながる調査結果であると思います。
本市では、昨年宝島社の雑誌『田舎暮らしの本』で住みたい田舎ランキング、
四国エリア堂々の総合5位という点、空き家バンクの成約実績ベスト100の
ランキングでは、全国517自治体の中で累積7位という点では、本市が取り組
んできた空き家バンク制度、リフォームの支援、また若者定住施策も含め、
一定の効果が出てきているとは考えますが、現在は賃貸の希望者が多くて、
売り家はあるが貸してくれる家が少ないという需給ギャップとか、国交省が空き
家バンクのシステムを一元化した全国版のシステムをスタートさせるようですが、
全国の空き家バンク情報の提供に今後どうしていくか、現在の香川県とのリンク
だけでも十分かとは思いますが、このようなホームページのリンクなども、今後
ホームページというか、システムのリンクをどうお考えなのかをお聞きいたします。
また、三豊市空家等対策推進協議会が設置され、どのような議論が進んでいる
のか。
危険家屋については空家等対策計画に基づき、自治会などとの連携により
見守り体制、最初に言ったように被相続人はわかるが、世代がかわって相続人
が誰なのかわからないケース、都会に行って相続放棄をしている状態などで、
自治会でも管理ができない状況などがあると思いますが、このあたりをどう対応
するのかをお聞きいたします。
●答弁
それでは、浜口議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず、御質問にあります賃貸での利用希望者と売買での登録希望の所有者との
需給ギャップについてですが、市の空き家バンク登録件数において、賃貸での
登録が93件に対し、売買での登録は203件、売買での登録が多い状況となって
おります。
定住施策としまして、賃貸での利用希望者の方には、県内で3年以上住んで
からの移住に限りますが、空き家バンク登録物件以外の賃貸物件も含めた
賃貸物件を対象に、家賃補助と補助金交付を実施しております。
本市以外の空き家バンク等実施機関との連携につきましては、香川県の移住
ポータルサイトで三豊市の空き家バンク情報も掲載されており、東京、大阪、
高松に配置された移住コーディネーターが三豊市の物件の紹介もしております。
また、賃貸物件を希望される方へは、空き家バンク物件に限らず、アパート等の
賃貸物件についても紹介をしております。
平成29年10月から開始された全国版空き家バンクへの参加については、全国
版では本市の補助金制度を初めとするさまざまな移住定住に関する情報と
空き家バンクとの連携がとりづらくなること、他自治体と本市の情報公開や利用
方法が違うため利用者に不便になると考えられること、また、物件の掲載を
しているのが全国の自治体数の1割程度と少なく、全国版としての意義が薄いと
考えられることから、現在のところ参加しておりません。
空き家バンクの利用者数をふやし、成約件数を伸ばすために、全国版空き家
バンクの運営状況を見守りながら、参加が有利であるかを今後も検討して
まいります。
次に、三豊市空家等対策推進協議会の協議内容についての御質問ですが、
市の空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、三豊市空家
等対策計画の策定と変更について、特定空家等の認定と措置について、その他
空家等対策を実施する上で必要な事項について協議を行っております。
次に、適切な管理が行われていない危険な空き家等と自治会との連携につき
ましては、本計画書の基本的施策の中に空き家等の適切な管理の促進として
掲げておりまして、空き家等の所有者が適切な管理を行うのが原則ではあり
ますが、地域に密着している自治会等から地域内の空き家情報や周辺環境の
状況等を市に報告していただくなど、見守り体制を整えることが空き家の適切
管理、また、地域の安全安心のために重要であると考えております。
今後は、自治会連合会等に対し具体的な施策を提案し、協議を進めてまいり
たいと考えております。
また、自治会において空き家等の相続人が不明な場合、窓口であります建築
課に相談をしていただきましたら、相続人を特定できるよう関係部署に照会を
いたしまして、相続人の了解が得られれば連絡先の公表等も行っております。
●質問5
松崎保育所などの指定管理者について、モニタリングについてお聞きいたします。
自治体サービスの市場化の歴史については、1960年代から自治体の現業部門
で民間開放が始められ、1980年代には多くの分野が民間委託を行ってきました。
2003年には公の施設について指定管理者制度が導入され、本市でも30近くの
公の施設が指定管理者制度に基づく運用がされております。
この公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため
の施設と定義され、指定管理者とは公の施設を管理運営する自治体のパート
ナーであるという点が重要であります。
自治体サービスの市場化手法としては、指定管理者制度のほかに通常の民間
委託、業務委託ですね、これは。
これ以外にも包括的民間委託や一括型民間委託、PFIなどもこれに含まれます
が、まず、本市として指定管理者の民間委託の基準といいますか、民間委託の
方針と評価制度の見直しやモニタリングについて、もちろんモニタリングです
から、適切なサービスが提供されているかを日常的に監視するものであり、
必要な場合に適宜行われる軽微な指導や助言も含まれています。
本市では、昨年まで公の施設については施設管理課で管理され、平成26年度
からモニタリング制度は導入されてはいるようですが、本市の基準となる指定
管理者モニタリング制度指針について統一的な基準がなく、今後適正な
サービスの継続的提供とサービス水準を高めていく必要があると考えますが、
基本方針ともいうべき指針を作成する予定などについてお聞きいたします。
特に、保育所での一例を上げれば、詫間町の松崎保育所ですが、今回議案
に上がっておりますけど、指定管理料、これは高瀬南部保育所が約1億6,182
万円、松崎保育所が約1億2,337万円と、高額な指定管理料、債務負担行為
が設定され、10年間も続きます。
これはいわば小学館集英社プロダクションに両所で約2億8,000万もの大金が
10年間支払われるということですから、本当にモニタリングが必要であると私は
考えます。
一般的に、指定管理者制度の指定期間、これは全国的に56%が5年間で、
次いで3年が多く、10年以上は5.8%だそうですが、この10年という期間も、
10年後に新たな新規事業者があらわれない可能性が高く、全国的に長期化
の傾向が非常に問題となってもいます。
施設にしても、松崎保育所は昭和55年3月建築で築37年、指定管理する上で
老朽化部分はどうなるのか、そのままにしていないか、修繕についてはリスク
分担をどのようにしているか、その分担が守られているのか、モニタリングが
点検したという事実のみで終了していないかなど、古い施設がゆえ、いろいろな
ことを考える必要がありますが、このあたりもどうお考えなのかをお聞き
いたします。
●答弁
浜口議員の御質問にお答えを申し上げます。
最初に、指定管理者モニタリング制度指針については、平成26年度に策定され、
現在各所管課において指定管理者制度の効率的・効果的な運営管理と市民
サービスの向上のため、この指針をもとにモニタリングを行っています。
御質問の統一的な指定管理者モニタリング制度指針につきましては、安全
かつ良好な公共サービスを確実、効率的かつ正確に実施させるためには
必要がありますので、現在策定済みの指針を参考に検討してまいります。
次に、指定管理の期間については、3年または5年が一般的ですが、保育所
の指定管理を考えたときには、入所する子供は最大で6年間利用することに
なるため、子供の成長過程で保育が途切れないようにするためには最低
6年間の期間が必要でありますし、保育士の雇用の安定といった人材確保の
観点、また、保育所の安定的な運営を期待するという考えから、指定管理
期間を10年間に設定しております。
指定管理候補者の選定の際も、保育所の運営を10年間安心して任せること
ができる事業者という視点で選考委員会において選考を行いました。
指定管理期間については、その施設の目的、内容等において適切な期間
設定の長さを検討する必要があると考えています。
次に、施設修繕のリスク分担ですが、松崎保育所については築37年を
超えており、施設も朽化しております。
今後、施設の改修が必要な場合も考えられますので、これから締結する
基本協定でリスク分担を規定し、原則として1件当たり10万円以下の小規模
修繕以外は市が実施することとし、実施が必要な場合は指定管理者と協議
を行い、修繕等を行うことにしています。
また、保育所におけるモニタリングは、指定管理者が行う保育サービスの
履行に関し、各種条例規則等に従い、適切かつ確実な保育サービスの
提供が確保されているかを確認する手段であり、保育所の指定管理業務が
継続的、また、安定的に提供されているかを確保するためのものですから、
サービス提供が適切に行われていない場合には、必要に応じた対策をとる
など、改善勧告が必要と考えております。
高瀬南部保育所においては、保護者アンケートなど指定管理者による
セルフモニタリングを実施しており、今後、指定管理者から提出される年度
評価表について評価を行う予定としており、その評価内容に応じて必要な
改善指導、助言を行うこととしております。
●再質問
ありがとうございます。非常によくわかりました。
先ほど言いました指定管理料ですね。例えばモニタリングの進んでいる
四日市市では、1,000万円以下の指定管理料を払っている事業所には非常に
簡素なモニタリング手続をするようにしています。
本市の保育所、これはやはり1億円以上の指定管理ですから高額と言わざる
を得ませんので、ぜひきちんとしたものをしていただきたい。
統一的な基本方針が必要であると思うんですが、その上で、実施手順書とか
モニタリングマニュアルを作成して、本市での外部委員を含む評価委員会、
これを作成していただきたいと考えます。
総務省が平成28年3月に公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する
調査結果、これが出ているんですが、平成24年4月から平成27年4月までで
指定管理者の取り消し、これは保育所以外にもたくさん指定管理しているとこ
ろがありますから、これが全国で2,308施設もあったということです。
この中で、運用上の理由としては、市区町村の指定管理では、指定管理者の
経営困難による撤退、指定の返上が一番多くて、次いで、費用対効果、
サービス水準の検証の結果が2番目、指定管理者の不正へと続いており
ました。
これらはモニタリングの実施である程度防げるとも思いますが、最大限の
努力をして指定管理者が選定されたのですから、その指定管理者の経営
状況を保育所問わず、税理士や公認会計士などに入っていただいて、財務
諸表などの点検をしていただくことが今後は必須になってくるのかなという
気がしております。
保育所は県の監査もあるからということをこの前お聞きしたんですけど、
セルフモニタリングというのは基本協定書の中にあるんですけど、どうしても
事業所内だけのチェックになるような感じがして、そのチェックが甘くならざるを
得ないのかなと考えてもしまいます。
保護者アンケート、職員のアンケート、このような形でも必要だと思うんです
けど、松崎保育所の基本協定書も見させていただきまして、リスク分担表も
ありましたから、問題なくリスク管理もされているようだと思いますが、やはり
指定管理者の統一的な基本方針があって、定期的な評価委員会が開催
されまして、財務諸表とかその他の点検を第三者の目で公平に判断いただき
たいと私は思うんですけど、このあたりどうお考えでしょうか。質問をいたします。
●答弁
浜口議員の再質問にお答えいたします。
御指摘の基本方針でありますけれども、指定管理者制度を含むアウトソー
シングを有効に活用するという手段を推進するに当たりましては、市民から
行政サービスの質の低下や行政そのものの体制を問われることのないよう
十分な検証を行った上で進めるため、アウトソーシングに関する指針に
ついて、平成23年3月に発出しているところでありますが、指定管理者
制度に限った詳細な方針は発出しておりません。
したがいまして、現在は各担当課により個別対応を行っているという状況
であります。
なお、4月の組織再編におきまして、政経営課と名称変更を行い、指定
管理者制度など経営的感覚を持った取り組みを強化してまいりたいと
考えております。
そうしたことから、御指摘の指定管理者制度導入施設のモニタリング
マニュアルの策定や評価委員会の設置などについて、成立趣旨を再確認
するとともに、公共施設が有する潜在力を最大限に発揮させる手段として、
同制度の活用方法について全庁的な取り組みを進めてまいりたいと考えて
おります。
以上で、ジャスト一時間!・・・瀧本議員へバトンタッチしました!
●質問3
施政方針から、「活気にあふれ、産業が躍動するまち(産業・雇用)」の中から
お聞きいたします。
農業や水産業において、農業水産事業者の高齢化や減少による労働者不足、
耕作放棄地の増加など厳しい状況が続いており、情報通信技術ICTの活用と
AIの先進的導入にはどのように取り組んでいくのかをお聞きいたします。
また、三豊市農業振興計画は、どう見直され反映されていくのかもお聞き
いたします。
次に、シティープロモーション活動という点、私から数年前に一般質問もさせて
いただきましたけど、これは人口減少時代に入った日本において、全国の
自治体が生き残りをかけてさまざまな施策を行っている中、観光客の増加、
定住人口獲得、企業誘致などを目的として、地域のイメージを高め、知名度を
向上させる活動や自治体におけるマーケティングや営業の活動を総称して、
シティープロモーション、またはシティーセールスと呼ばれるものであります。
いわばこの言葉は、地域の売り込みとも捉えられますが、現在、関東学院
大学法学部地域創生学科准教授で、私もセミナーを受講させていただいて
から個人的にメールでのやりとりもさせていただいております牧瀬稔先生の
提唱されているシティープロモーション活動とは、1、認知度を高めること、
2、情報交流人口、これは自地域外に居住する人に対して何らかの情報提供
サービスを行うことですが、この情報交流人口プラス交流人口や定住人口の
獲得を目指す活動、3、現在生活している住民、既存住民が愛着心を持ち、
シビックプライドですね、引っ越ししていかないことを目指し、4、企業誘致にも
つなげていく活動として、さまざまな住民や事業者、各種団体から選ばれる
自治体へと変貌するための取り組みであると定義づけがあります。
シティープロモーションは、いわば自治体間競争の幕あけだとも考えられます
が、今後どのような具体策を展開する予定なのかをお聞きいたします。
3点目は、昨年度からの継続事業として、地域商社、ふるさと納税、ふるさと
住民票制度など、昨年度の成果としてどうだったのかお聞きいたします。
特に地域商社は、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局が、地域商社
機能の設立・普及に向け、地方創生のな鳴り物として地域商社協議会が
設立されております。
昨年度には、瀬戸内うどんカンパニー株式会社、若い北川智博CEOが
選ばれました。
私も何度かお会いしましたが、本当にすばらしい若者で、今後最も本市を
PRできるすばらしい事業人でもあるとは思いますが、今年度の展開などを
お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁
浜口議員の御質問にお答え申し上げます。
まず最初に、農業、水産業の現状につきましては、議員御指摘のとおり、従事
者の高齢化による労働力不足や耕作放棄地の増加により、厳しい状況であり
ます。
御質問のICTの活用とAIの導入の現状では、現在、三豊・観音寺地区において
野菜、果樹の生産技術の構築のための実証実験を進めているところです。
本市としては、その後の実証結果を受け、マニュアル化したものを普及センター、
JAと連携して、農家への指導に努めるとともに、さきの質問でも御答弁申し上げ
ましたように、IoT、AIの先端技術を導入し、新たな農業、水産業の創出にも
積極的にチャレンジしてまいりたいと考えています。
農業振興計画につきましては、平成30年度に策定される第2次総合計画との
整合性も図りながら、時代背景を考慮し、見直しに取り組んでまいります。
次に、今後のシティープロモーション活動を人口減少対策にどうつなげて行く
のかという御質問ですが、知名度向上プロジェクトや瀬戸内国際芸術祭を初め
とするさまざまな取り組みの成果もあり、三豊の認知度も徐々に高まっていると
感じております。
また、父浜ヶ浜などのインスタ映え効果などにより、本市の交流人口、関係人口
は近年著しい勢いで増加しております。
時期を逸することなく、民間企業、市民、行政が役割を明確にして、この豊かな
資源を使ったシティープロモーションに取り組み、関係交流人口を移住定住人口
につなげなければなりません。
一方で、この中に長くお住まいの市民の中にあっては、三豊というよりも、まだ
まだ旧町の感覚を持たれているほうもおいでになることから、三豊のシビック
プライドを抱いていただくためにも、旧町ごとのハードルを下げ、三豊は一つと
いう意識の醸成に取り組まなければいけないと感じています。
最後に、昨年度から継続しております。地域商社、ふるさと納税、ふるさと住民
票制度につきましては、まず、ふるさと住民票は現在74名の方に発行し、三豊
との緩いつながりの中で関係を持っていただいており、今後は保有者へのイン
センティブについても検討してまいりたいと考えています。
次に、平成20年度から寄附の受け入れを初めて、来年度で11年目を迎える
ふるさと納税ですが、平成27年にインターネットで寄附受け付けを開始し、
6,800万円にまで寄附額がふえましたが、その後、徐々に減少しております。
寄附者の立場から見ると、三豊市の返礼品の魅力が他の自治体と比べ弱く
見えていることが一因に上げられます。
こうした状況に対し、来年度はインターネット上での寄附窓口をふやし、返礼品
の充実を図ることで、三豊産品のPRを強化し、寄附拡大につなげてまいりたい
と考えております。
最後に、地域商社瀬戸内うどんカンパニーですが、昨年8月のCEO決定、9月
に法人設立を経て、その後、市内の生産者、事業者や金融機関等、また地域外
での地域商社や企業と連携しながら、商品開発事業、うどんハウス事業、ツーリ
ズム事業の三つの事業の構築とトライアル行っております。
準備期間を経て、30年度から本格的に事業展開する予定であり、市も早期に
法人が自立し、地域に稼ぐ仕組みをもたらせるよう、事業構築、トライアルに係る
側面支援を行ってまいります。
●再質問
ありがとうございます。
まず農業なんですが、私たちがICTとかAIとか考えると、やはり労働力の負担が
軽くなるがゆえの、気象条件とか土壌分析、こういうのが進められるのかなとか、
単純に考えてしまいがちになんですけど、新たな農業として、企業、生産者と
タイアップ、行政がマッチングするという点、非常によくわかりました。
今後は、それらを実現するための耕作放棄地の解消ですね。
これによる大規模な農地の集約があって、農業法人とか大規模農家とか企業、
若者、それらが大がかりにICTとかAIを使って新しい農業を行っていくのかなと、
農業の将来像を考えてしまいます。
それらを考慮すると、耕作放棄地に関しては、農地の集積、農地中間管理機構
の役割ですね。
今後もこの中間管理機構への貸し付けが増加するとは思うんですが、基盤整備
が行われていない農地については、担い手が借り受けない状態になると。
機構に貸し付けた所有者が、基盤整備のための費用を負担する用意がなくて、
結果として担い手への農地の集積、集約化が進まなくなる可能性があり、農地
中間管理機構が借り入れている農地については、農業者の申請、同意、費用
負担によらず、都道府県が基盤整備を推進していただける整備事業があると
いうふうにお聞きいたしております。
これ、平成35年までに担い手が利用する面積が全農地面積の8割となるよう
農地の集約が推進されると、非常に有効な耕作放棄地対策であるとは思います
が、この点について、今後、県とは事業がどう進む予定なのかを、まず1点お聞き
いたします。
次に、シティープロモーション活動についてですが、民間企業の組織には営業部
というのがあります。
地方自治体にはない営業活動、人口が減り、税収が減ると嘆くばかりではなく、
これからの自治体では営業という視点を組み込んでいく必要性というのを牧瀬
先生が説いています。
それゆえ、企画の強化策として、流山市のマーケティング課や箕面市や武雄市
のように、営業という文字を組織名に入れる傾向、近隣では善通寺市でも営業
課というのがありまして、地方自治体の営業という視点が非常に強まってきて
おります。
企業立地対策課も必要だとは思いますけど、営業という観点からシティープロ
モーション活動をどこかの課で進めるべきであると考えます。
この点、どうお考えでしょうか。
それと、ふるさと納税についてはいいんですけど、ふるさと住民票制度ですね。
これが74名、本市と心のつながる人たちの裾野を広げ、ふるさと会の充実や
本市へのふるさと回帰も視野に入れ、多くの人と緩くつながる関係づくりの
取り組みとして進められてきたということだったんですけど、このあたりの成果
といいますか、緩くつながって何がどうなったのかをお聞きしたいと思うんです
けど、お願いいたします。
●答弁
それでは、浜口議員の再質問にお答えをいたします。
先ほど言われました耕作放棄地、農地の大集積化等々の話でございますけども、
香川県の農地中間管理機構、平成26年に設立されまして、毎年毎年その貸し手、
借り手の募集をやって、契約行為をやっているわけなんですけども、始まりまして、
この2月現在で約120ヘクタールの契約が成立をしております。
当然のことながら、貸し手、借り手ともに協力金が得られるような制度となっており
ますし、売買につきましてもあっせんをしておりまして、税の控除等も行われると
いうところでありまして、ただ一つ難点が、耕作放棄地、中山間部等々も、そういう
ところに預けたいという話もあるんですけども、なかなか道がないとか、耕作しづら
いとかいうのは、契約がなかなかマッチングしないというような状況もございます。
そういうことを受けまして、先ほど議員御指摘の補助整備ですよね。
中山間における補助整備ということもとも国のほうでは対策をとられております。
今年度、平成29年度、土地改良法が改正となりまして、議員御指摘のとおり担い手
に集積されれば、国の施策としましては、担い手、新規就農者、そういうふうな
大規模な農業をやる方に農地の8割を集約したいという目標を立てております。
そういう中で、補助整備につきましても、そういうふうないろんなメニューがあるん
ですけども、中間管理機構へ預ける意思を持ったその集積率の度合いによって、
個人の負担金を軽減すると、極論となれば負担がゼロというような補助整備も
創設されております。
三豊市の場合、もう既に県とともに、そういう制度ができましたので補助整備の
推進活動ももう既に行っております、何カ所かでやっています。
そういうことを踏まえまして、耕作放棄対策等にもつなげていきたいと考えて
おります。
2点目のシティープロモーションの件ですけれども、これは議員御指摘のように、
これまでには自治体の感覚では少なかった営業という感覚をこれから持たなけ
ればいけないということで、シティープロモーションとあわせたシティーセールス
というような言葉がございますが、シティーセールスという観点で三豊の資源を
売っていくというような感覚が、これからもう必要なんだろうなと思っています。
議員御指摘のありましたように、先進地では既に営業課、シティープロモーション
室等々が設けられているようですけれども、先進事例も参考にしながら、組織
については勉強していきたいなと考えています。
3点目につきましては、ふるさと住民票、これは昨年スタートアップしたばかり
ですので、まだまだ成果という点では出ておりませんけれども、この緩い関係
を持つことで、三豊と何らかのつながりを持って、このことを定住移住、また産業
の振興に生かしていけたらというようなことの目的で行っておりますので、今後、
この輪を広げながら、もっと強化していく中で、先ほど申し上げましたように三豊
市のインセンティブ等々を設けて、三豊市にもっと魅力を持ってもらえるような
組織体制をつくっていきたいなと考えております。
●質問4
「豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち(環境・生活)」の施政方針の中から、
定住政策、平成20年度から始まった空き家バンクを初めとする定住施策も
多くの課題が出てきております。
各町で空き家のばらつきが見られることはもちろん、一番には相続の問題が
あって、その住宅には関与できないケース、要は相続人がもめているケース
とかだと思いますが、このケースが一番多いかと思いますが、その他、仏壇が
ある、荷物置き場として使用している等々の理由もあるとは思います。
特に、三豊市空家等実態調査結果報告書によりますと、詫間町の志々島、
ここは空き家率が40%を超えています。
粟島、荘内箱地区、生里地区、積地区などがおおむね10%以上を超えており
ます。
本市の平均は3.1%ですから、まず詫間町の空き家の多さが突出している点、
特に島の物件、危険家屋も含めて、これらを今後どのようにしていくかという
ことにもつながる調査結果であると思います。
本市では、昨年宝島社の雑誌『田舎暮らしの本』で住みたい田舎ランキング、
四国エリア堂々の総合5位という点、空き家バンクの成約実績ベスト100の
ランキングでは、全国517自治体の中で累積7位という点では、本市が取り組
んできた空き家バンク制度、リフォームの支援、また若者定住施策も含め、
一定の効果が出てきているとは考えますが、現在は賃貸の希望者が多くて、
売り家はあるが貸してくれる家が少ないという需給ギャップとか、国交省が空き
家バンクのシステムを一元化した全国版のシステムをスタートさせるようですが、
全国の空き家バンク情報の提供に今後どうしていくか、現在の香川県とのリンク
だけでも十分かとは思いますが、このようなホームページのリンクなども、今後
ホームページというか、システムのリンクをどうお考えなのかをお聞きいたします。
また、三豊市空家等対策推進協議会が設置され、どのような議論が進んでいる
のか。
危険家屋については空家等対策計画に基づき、自治会などとの連携により
見守り体制、最初に言ったように被相続人はわかるが、世代がかわって相続人
が誰なのかわからないケース、都会に行って相続放棄をしている状態などで、
自治会でも管理ができない状況などがあると思いますが、このあたりをどう対応
するのかをお聞きいたします。
●答弁
それでは、浜口議員の御質問にお答えを申し上げます。
まず、御質問にあります賃貸での利用希望者と売買での登録希望の所有者との
需給ギャップについてですが、市の空き家バンク登録件数において、賃貸での
登録が93件に対し、売買での登録は203件、売買での登録が多い状況となって
おります。
定住施策としまして、賃貸での利用希望者の方には、県内で3年以上住んで
からの移住に限りますが、空き家バンク登録物件以外の賃貸物件も含めた
賃貸物件を対象に、家賃補助と補助金交付を実施しております。
本市以外の空き家バンク等実施機関との連携につきましては、香川県の移住
ポータルサイトで三豊市の空き家バンク情報も掲載されており、東京、大阪、
高松に配置された移住コーディネーターが三豊市の物件の紹介もしております。
また、賃貸物件を希望される方へは、空き家バンク物件に限らず、アパート等の
賃貸物件についても紹介をしております。
平成29年10月から開始された全国版空き家バンクへの参加については、全国
版では本市の補助金制度を初めとするさまざまな移住定住に関する情報と
空き家バンクとの連携がとりづらくなること、他自治体と本市の情報公開や利用
方法が違うため利用者に不便になると考えられること、また、物件の掲載を
しているのが全国の自治体数の1割程度と少なく、全国版としての意義が薄いと
考えられることから、現在のところ参加しておりません。
空き家バンクの利用者数をふやし、成約件数を伸ばすために、全国版空き家
バンクの運営状況を見守りながら、参加が有利であるかを今後も検討して
まいります。
次に、三豊市空家等対策推進協議会の協議内容についての御質問ですが、
市の空き家等に関する対策を総合的かつ計画的に実施するため、三豊市空家
等対策計画の策定と変更について、特定空家等の認定と措置について、その他
空家等対策を実施する上で必要な事項について協議を行っております。
次に、適切な管理が行われていない危険な空き家等と自治会との連携につき
ましては、本計画書の基本的施策の中に空き家等の適切な管理の促進として
掲げておりまして、空き家等の所有者が適切な管理を行うのが原則ではあり
ますが、地域に密着している自治会等から地域内の空き家情報や周辺環境の
状況等を市に報告していただくなど、見守り体制を整えることが空き家の適切
管理、また、地域の安全安心のために重要であると考えております。
今後は、自治会連合会等に対し具体的な施策を提案し、協議を進めてまいり
たいと考えております。
また、自治会において空き家等の相続人が不明な場合、窓口であります建築
課に相談をしていただきましたら、相続人を特定できるよう関係部署に照会を
いたしまして、相続人の了解が得られれば連絡先の公表等も行っております。
●質問5
松崎保育所などの指定管理者について、モニタリングについてお聞きいたします。
自治体サービスの市場化の歴史については、1960年代から自治体の現業部門
で民間開放が始められ、1980年代には多くの分野が民間委託を行ってきました。
2003年には公の施設について指定管理者制度が導入され、本市でも30近くの
公の施設が指定管理者制度に基づく運用がされております。
この公の施設とは、住民の福祉を増進する目的をもって、その利用に供するため
の施設と定義され、指定管理者とは公の施設を管理運営する自治体のパート
ナーであるという点が重要であります。
自治体サービスの市場化手法としては、指定管理者制度のほかに通常の民間
委託、業務委託ですね、これは。
これ以外にも包括的民間委託や一括型民間委託、PFIなどもこれに含まれます
が、まず、本市として指定管理者の民間委託の基準といいますか、民間委託の
方針と評価制度の見直しやモニタリングについて、もちろんモニタリングです
から、適切なサービスが提供されているかを日常的に監視するものであり、
必要な場合に適宜行われる軽微な指導や助言も含まれています。
本市では、昨年まで公の施設については施設管理課で管理され、平成26年度
からモニタリング制度は導入されてはいるようですが、本市の基準となる指定
管理者モニタリング制度指針について統一的な基準がなく、今後適正な
サービスの継続的提供とサービス水準を高めていく必要があると考えますが、
基本方針ともいうべき指針を作成する予定などについてお聞きいたします。
特に、保育所での一例を上げれば、詫間町の松崎保育所ですが、今回議案
に上がっておりますけど、指定管理料、これは高瀬南部保育所が約1億6,182
万円、松崎保育所が約1億2,337万円と、高額な指定管理料、債務負担行為
が設定され、10年間も続きます。
これはいわば小学館集英社プロダクションに両所で約2億8,000万もの大金が
10年間支払われるということですから、本当にモニタリングが必要であると私は
考えます。
一般的に、指定管理者制度の指定期間、これは全国的に56%が5年間で、
次いで3年が多く、10年以上は5.8%だそうですが、この10年という期間も、
10年後に新たな新規事業者があらわれない可能性が高く、全国的に長期化
の傾向が非常に問題となってもいます。
施設にしても、松崎保育所は昭和55年3月建築で築37年、指定管理する上で
老朽化部分はどうなるのか、そのままにしていないか、修繕についてはリスク
分担をどのようにしているか、その分担が守られているのか、モニタリングが
点検したという事実のみで終了していないかなど、古い施設がゆえ、いろいろな
ことを考える必要がありますが、このあたりもどうお考えなのかをお聞き
いたします。
●答弁
浜口議員の御質問にお答えを申し上げます。
最初に、指定管理者モニタリング制度指針については、平成26年度に策定され、
現在各所管課において指定管理者制度の効率的・効果的な運営管理と市民
サービスの向上のため、この指針をもとにモニタリングを行っています。
御質問の統一的な指定管理者モニタリング制度指針につきましては、安全
かつ良好な公共サービスを確実、効率的かつ正確に実施させるためには
必要がありますので、現在策定済みの指針を参考に検討してまいります。
次に、指定管理の期間については、3年または5年が一般的ですが、保育所
の指定管理を考えたときには、入所する子供は最大で6年間利用することに
なるため、子供の成長過程で保育が途切れないようにするためには最低
6年間の期間が必要でありますし、保育士の雇用の安定といった人材確保の
観点、また、保育所の安定的な運営を期待するという考えから、指定管理
期間を10年間に設定しております。
指定管理候補者の選定の際も、保育所の運営を10年間安心して任せること
ができる事業者という視点で選考委員会において選考を行いました。
指定管理期間については、その施設の目的、内容等において適切な期間
設定の長さを検討する必要があると考えています。
次に、施設修繕のリスク分担ですが、松崎保育所については築37年を
超えており、施設も朽化しております。
今後、施設の改修が必要な場合も考えられますので、これから締結する
基本協定でリスク分担を規定し、原則として1件当たり10万円以下の小規模
修繕以外は市が実施することとし、実施が必要な場合は指定管理者と協議
を行い、修繕等を行うことにしています。
また、保育所におけるモニタリングは、指定管理者が行う保育サービスの
履行に関し、各種条例規則等に従い、適切かつ確実な保育サービスの
提供が確保されているかを確認する手段であり、保育所の指定管理業務が
継続的、また、安定的に提供されているかを確保するためのものですから、
サービス提供が適切に行われていない場合には、必要に応じた対策をとる
など、改善勧告が必要と考えております。
高瀬南部保育所においては、保護者アンケートなど指定管理者による
セルフモニタリングを実施しており、今後、指定管理者から提出される年度
評価表について評価を行う予定としており、その評価内容に応じて必要な
改善指導、助言を行うこととしております。
●再質問
ありがとうございます。非常によくわかりました。
先ほど言いました指定管理料ですね。例えばモニタリングの進んでいる
四日市市では、1,000万円以下の指定管理料を払っている事業所には非常に
簡素なモニタリング手続をするようにしています。
本市の保育所、これはやはり1億円以上の指定管理ですから高額と言わざる
を得ませんので、ぜひきちんとしたものをしていただきたい。
統一的な基本方針が必要であると思うんですが、その上で、実施手順書とか
モニタリングマニュアルを作成して、本市での外部委員を含む評価委員会、
これを作成していただきたいと考えます。
総務省が平成28年3月に公の施設の指定管理者制度の導入状況に関する
調査結果、これが出ているんですが、平成24年4月から平成27年4月までで
指定管理者の取り消し、これは保育所以外にもたくさん指定管理しているとこ
ろがありますから、これが全国で2,308施設もあったということです。
この中で、運用上の理由としては、市区町村の指定管理では、指定管理者の
経営困難による撤退、指定の返上が一番多くて、次いで、費用対効果、
サービス水準の検証の結果が2番目、指定管理者の不正へと続いており
ました。
これらはモニタリングの実施である程度防げるとも思いますが、最大限の
努力をして指定管理者が選定されたのですから、その指定管理者の経営
状況を保育所問わず、税理士や公認会計士などに入っていただいて、財務
諸表などの点検をしていただくことが今後は必須になってくるのかなという
気がしております。
保育所は県の監査もあるからということをこの前お聞きしたんですけど、
セルフモニタリングというのは基本協定書の中にあるんですけど、どうしても
事業所内だけのチェックになるような感じがして、そのチェックが甘くならざるを
得ないのかなと考えてもしまいます。
保護者アンケート、職員のアンケート、このような形でも必要だと思うんです
けど、松崎保育所の基本協定書も見させていただきまして、リスク分担表も
ありましたから、問題なくリスク管理もされているようだと思いますが、やはり
指定管理者の統一的な基本方針があって、定期的な評価委員会が開催
されまして、財務諸表とかその他の点検を第三者の目で公平に判断いただき
たいと私は思うんですけど、このあたりどうお考えでしょうか。質問をいたします。
●答弁
浜口議員の再質問にお答えいたします。
御指摘の基本方針でありますけれども、指定管理者制度を含むアウトソー
シングを有効に活用するという手段を推進するに当たりましては、市民から
行政サービスの質の低下や行政そのものの体制を問われることのないよう
十分な検証を行った上で進めるため、アウトソーシングに関する指針に
ついて、平成23年3月に発出しているところでありますが、指定管理者
制度に限った詳細な方針は発出しておりません。
したがいまして、現在は各担当課により個別対応を行っているという状況
であります。
なお、4月の組織再編におきまして、政経営課と名称変更を行い、指定
管理者制度など経営的感覚を持った取り組みを強化してまいりたいと
考えております。
そうしたことから、御指摘の指定管理者制度導入施設のモニタリング
マニュアルの策定や評価委員会の設置などについて、成立趣旨を再確認
するとともに、公共施設が有する潜在力を最大限に発揮させる手段として、
同制度の活用方法について全庁的な取り組みを進めてまいりたいと考えて
おります。
以上で、ジャスト一時間!・・・瀧本議員へバトンタッチしました!
2018年04月01日
議会報告(私の代表質問その1)
議会報告は、私自身の代表質問から。
私ども三豊市議会会派「清風会」で、瀧本文子副会長と一緒に、「代表質問」を
させていただきました。
会派「市民の会」(8名)の後で、「清風会」(7名)での質問時間は、7名以上の
会派は2時間となっています。
1.市長の政治姿勢
横山前市長が築き上げてきた基盤を守りつつ、新しいことにも挑戦していく
山下新市長の「心をひとつに三豊市のまちづくり」に向けた政治姿勢と決意を聞く。
2.財政問題
本年度の予算編成上での重点項目と、合併特例債など。
平成30年度における重点施策と財政見通しについて、プライマリーバランスなど
見据えた将来の財政計画について聞く。
3.活気にあふれ、産業が躍動するまち(産業・雇用)
①農業や水産業においての、情報通信技術(ICT)の活用とAIの先進的導入とは。
②シティプロモーション活動とは、今回の最重要テーマである「人口減少対策」に
繋げるべく具体的にどう展開していくのか。
③地域商社、ふるさと納税、ふるさと住民票制度、など昨年度の成果と今年度の
展開について聞く。
4.豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち(環境・生活)
①空き家バンク活用の今後について
②危険空き家の「空き家等対策計画」に基づく、自治会等との連携による見守り
体制とは。
5.指定管理者制度
松崎保育所などの指定管理者へのモニタリングについて、現状とモニタリング
制度指針は。
以上5問で、子育てや教育関係を瀧本副会長へ頼みました。
まずは1と2をご報告致します。
●質問1
5番、浜口恭行、清風会の代表質問をさせていただきます。
まず初めに、市長の政治姿勢についてお聞きします。
合併来、横山前市長は激変する社会情勢の中で、自治体の本来のあるべき姿、
また未来を見据えた形を具現化してこられましたと施政方針で山下新市長が
述べられておりますが、その上で、横山前市長が築き上げてきた基盤を守りつつ、
新しいことにも挑戦していく、山下新市長の「心をひとつに三豊市のまちづくり」
に向けた政治姿勢、また、本市の最重要テーマは人口減少対策だと言われて
おりますが、これはもう全国どこの地方自治体でも抱える問題でありますし、
横山前市長がおっしゃった、若い女性をターゲットにした各種子育て支援策、
また、全国に先駆け地域内分権推進交付金を使ったまちづくり推進隊が7町に
誕生し、委譲業務と自主事業が実施されておりますが、このような施策を継続
しつつ、新市長の言われるインターネット、AIなどの先端技術がどのような形で
融合されていくのか、少しわかりにくい部分があるとの市民からの御指摘もあり
ますし、市民の会の代表質問とダブるところがありますが、このあたりの山下新
市長の決意をまず最初にお聞きいたしますので、よろしくお願いします。
●答弁1
浜口議員の御質問にお答えいたします。
七つの町が合併し、既に12年が過ぎました。
当然ながら、それぞれの地域で育まれてきた歴史や文化があり、それは大切に
していかなければなりません。
しかしながら、三豊市としての一体感を持ったまちづくりにも取り組まなければ
ならないと考えております。
これまで横山前市長が進めてきた地域内分権の推進は、将来にわたって自立
して持続するまちであるための仕組みづくりであったと理解をしております。
この地域内分権の一端を担うまちづくり推進隊も、七つの町ごとに設置されて
おります。
設立の段階では、まだ旧町の枠を越えた体制をつくり上げるというのは困難
だったのかもしれません。
しかしながら、今、自然発生的に推進隊の間で連携を模索する動きも出てきて
います。
まさに、「心をひとつに三豊市のまちづくり」が生まれようとしています。
このような旧町の枠を超えた三豊市として、市民主体のまちづくりに期待して
いるところであり、その市民力とともに、行政としてのまちづくりを積極的に
進めてまいります。
また、御発言のあった若い女性をターゲットにした各種子育て支援対策にも
引き続き取り組みます。
統計データによりますと、地元の高校を卒業した若者が大学等に進み、卒業
後に三豊に返ってくる割合を男女別で比較した場合、男性よりも女性のほう
が少ないというデータ結果があります。
若い女性が帰ってきたいと思える生活環境の整備、市外の若い子育て世帯
が住みたいと考えるような町となるように、施策に取り組んでまいります。
このように、前市政を継承して取り組んでいくことに加え、新たにチャレンジを
開始するものもあります。
それがICTやAIといった先端技術の導入です。
このことについては、市民の会の代表質問の答弁でも申し上げましたが、まず
はこの分野の民間や学術機関の保有する技術と市内産業とのマッチングを行
い、市内での実証実験から開始していきたいと考えております。
そのような取り組みの中から、三豊オリジナルの技術もシステムが生まれます。
これは市内の企業における雇用の拡大や生産性向上による市民の豊かさへ
直結するものであります。さらには、地域間競争に打ち勝ち、三豊の企業が世
界にも打って出ることのできる力にもなります。
さらには、企業の発展のみならず、三豊オリジナルの技術とシステムそのもの
が、特許や著作権などの知財ともなります。
将来的にもうかる産業、地域振興へつなげることで、行政の税収増にもつなが
りますので、この点につき、果敢にマッチングを進めてまいります。
こうした観点からも、三豊市を一つの区域と捉えた土地利用のゾーニングにも
着手いたします。
観光振興ゾーン、農業振興ゾーンといった形を旧町の区域を超えて設定し、
そのゾーニングの中で、めりはりをつけた施策展開や集中投資が可能になるも
のと考えております。
守るべきは守りながら、新たなことにも果敢に挑戦し、明るい三豊の未来を実現
するため、市民の皆様とともに心を一つにしたまちづくりに取り組んでまいります。
●再質問
ありがとうございます。
地域内分権、これはまちづくり推進隊ですけど、私、以前にも発言させてもらい
ましたけど、三豊市全域で効果を発揮することを目指して推進隊同士の連携が
図られるようにするということ、非常に、今ありましたようにいいことだと思うん
ですけど、これ以上に公民館や既存の他団体と連携して、活動内容のダブりを
解消するとともにそれぞれ独自に実施している市民運動の調整役となること、
また事務局への指導など、市民の声を反映できる推進隊となるためには、市
当局が率先して関与していくという見直しが必要だと考えます。
地域内分権特別委員会というのが過去にあったんですけど、これで行った長野
市では、地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、自分たちの地域は
自分たちでつくるという意識を持って活動していまして、その活動を市当局が
積極的に支援していく仕組みをつくり出していました。
その上で、市の連合組織や交通安全推進委員、保健指導委員などの委嘱制度
をも廃止して、各種団体や委嘱廃止に伴う依頼事務を洗い出しまして見直しも
行っている点、本当に長野市の分、参考になったんですけど、本市にも公民館
を初め各種団体活動が存在していますので、これらの見直しといいますか、
ダブりを解消して統合していく仕組みづくりというのがそろそろ必要であると思い
ますが、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2
浜口議員の再質問にお答えいたします。
まちづくり推進隊の活動について、市域全体で効果を発揮することを目指し、
連携が図られるよう促してほしいということに関しましては、先ほどの答弁でも
申し上げましたとおり、自発的に横の連携が生まれつつありますので、その
経過を見守りたいと思います。
旧町の枠を超え、三豊市全体のエリアで自発的な活動は、「心をひとつに
三豊市のまちづくり」に向けた大きな一歩だと思います。
次に、公民館活動や他団体等の活動の内容にダブりが生じているという指摘に
つきましては、行政が実施しております事務事業も含め、推進隊を初め市民の
活動にお任せしても同等もしくはそれ以上の効果が見込める事業、また連携
してさらに大きな効果、高い成果を見込める事業につきましては、選択を行って
いくべきであると考えておりますので、行政におきましては事業評価の中でその
可能性を検証できるよう検討していきたいと思います。
いずれにいたしましても、人口減少時代にあって、地域の課題はみずからの責任
と判断で乗り越えることのできる地域コミュニティー組織として発足したまちづくり
推進隊です。これからも持続可能なまちづくりを行っていくための仕組みとして、
引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
●再質問
ありがとうございます。
市長答弁の中でありましたICTやAIの先端技術の導入という点ですね。
私たちが必ずしも都市や集落に依存しなくても暮らしていける環境を提供して
いくと考えられます。
こうした社会基盤の整備と発展は、人口減少が進む本市のような地方自治体、
山下市長の言う三豊オリジナルの技術が生まれるという点では、本当、特に
条件が不利とされている過疎地域をも持続可能な暮らしの場へと変容させて
いく、このような可能性を秘めていると思います。
私自身、山下市長の言う先端技術とは、人口が減少してもより豊かに安心して
暮らすことのできる社会が形成される、築かれるのではと考えます。
これらにより社会の仕組みが変わり、人口が減っても暮らしの利便性や快適
性を低下させることなく、誰もが暮らし続けられる社会基盤を整えることもできる
と。
今考えるべきは、人の奪い合いではなく、たとえ人口が減少してもより豊かに
安心して暮らすことのできる社会、市長の言われる市民力、これを築くことが
大切なのではないかという私の理解なんですが、それでよろしいでしょうか。
●答弁3
浜口議員の再質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおりであります。
これほど人口減少によって企業や農水産業、人手不足が深刻な状況の中で、
人の奪い合い、労働力の奪い合いというのは、本当に生産性がございません。
そういった意味で、本来機械とか、そういうものに任せられる部分においては、
AI、ICTを活用して生産力を高め、そこに本来必要だった人を別の分野に、
さらに生産性を高めるところに配置することができるという考え方であります。
議員が御指摘されましたように、そういうことによって企業本来の持続性また
は生産性向上につなげるという目的でのICT、AIでの導入を考えております。
そのためには、まずは実証実験等で、三豊市がその先端を走るんだという
意思表示が必要でありますので、そういった分野での実証実験という意味で
やってまいりたいと考えております。
いずれにおきましても、やはり、今後の人口減少傾向等もかんがみながら、
今暮らしている人たちの今の暮らしというものをいかに豊かにしていくか、
そして発展させていくかということが重要であると思いますので、その点に
ついての御理解を賜ればと思います。
●質問2
次に、財政問題についてお聞きいたします。
一般会計当初予算案ですが、308億4,000万円が計上されております。
大型建設事業が重なった平成27年度がピークであり、今年度はこの額で新
総合計画第10期実施計画で示された額が基本数値として編成されているよう
ですけど、経常的経費や継続事業を中心とした骨格予算であるとのことですが、
平成30年度における重点施策と財政見通しについてお聞きいたします。
また、合併特例債は有利な起債であるとはいえ、借金には変わりませんが、
発行期限再延長が実現すればどのような事業を考えているのか、30年度末の
特例債借入合計とか今後の予定、また交付税の一本算定に伴う交付税の縮減
とあわせて、将来のプライマリーバランスも、本年度は黒字化していまして、
先ほど丸戸議員の代表質問の中で答弁もありましたが、将来を見据えた財政
状況がどのようになるのかを再度お聞きいたします。
●答弁1
浜口議員の御質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおり、平成30年度当初予算は新規事業や拡大事業を基本的に
見送り、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費及び施設管理等の経常的経費、
債務負担行為設定済みの事業費等を計上した骨格予算として編成いたしました。
平成30年度における重点事業につきましては、市長から施政方針で述べられた
とおり、人口減少問題を最重要課題として捉え、中小企業の振興や雇用確保に
資する施策、また、子育て支援施策を中心に当初予算に盛り込んでおります。
具体的に申し上げますと、若者定住の補助事業、賃貸住宅補助を行い移住
定住を図る定住促進事業、中小企業振興や企業立地、雇用の点からは、
企業立地促進事業、工業用水対策事業が上げられます。
また、子育て支援施策の面からは、15歳年度末までの子供の医療費の一部
助成を行う子ども医療費助成事業の継続実施、同じく継続実施する生活困窮
世帯のうち高等学校に進学する者を対象に学習支援を行う子供の学習支援
事業、新規事業として産後退院した母子に対して心身のケアを行う産後ケア
事業が上げられます。
合併特例債についてですけれども、御存じのとおり本市を含む全国の自治体で
組織する合併特例債再延長を求める市長会からの要望が認められ、議員立法
として可決成立、5年の再延長がほぼ確実視されている状況です。
本市における合併特例債に関する状況を申し上げますと、発行上限額約446億
6,000万円に対し、平成30年度末の発行見込み額は約215億7,000万円と
なっております。
また、今後関係法案が可決成立し、発行期限が平成37年度まで延長された
場合の具体的な充当事業につきましては、現時点での可能性という前提で申し
上げますと、詫間支所周辺整備事業や北部地区給食センター整備事業等の
各種普通建設事業に充てていくことを想定しております。
先ほど申し上げましたとおり、三豊市の場合、現在の合併特例債発行見通しに
おいて、発行上限額には達しておらず、延長される5年間で新たな事業への
充当も可能ではありますが、現発行期限の平成32年度までで計画上充当して
いる各種ハード整備事業の平準化することを基本的な考え方としております。
議員御指摘のとおり、この合併特例債については充当率、交付税措置率が
通常債と比較して有利であるものの、借金には変わりありません。
この点については我々も浜口議員と同じ認識を持っているところであります。
そのような意味から、将来世代への過度な負担先送りを防ぐためにも、不要
不急な事業は凍結し、各種基金と合併特例債を初めとした市債、すなわち
貯金と借金を有効に活用しながら、プライマリーバランスの黒字化を前提とした
予算編成に努めていきたいと考えております。
●再質問
ありがとうございます。2点質問します。
まず、本市の自主財源が非常に乏しい点、これは今後ますます人口減少とか
事業所の閉鎖などマイナス要因が考えられる中で、どのように市当局が
お考えなのかというところが1点です。
もう1点は、ハード整備に使われるということなんですけど、今、除却に合併
特例債を使えると思うんですけど、今後取り壊し、解体等いろいろ、公共施設
の再編に伴う利用の仕方が必要になると思うんですけど、除却のためには
どのくらい使う予定があるのかという点、2点お聞きいたします。
●答弁2
議員御指摘のとおりですが、本市の財政構造において最大の弱点は自主財源
比率が低いということであり、自主財源の確保は本市発足以来の大きな課題
でもあります。
先ほど市長が申しましたように、産業の活性化を図っていくということが、これが
地域の活性化につながっていくというふうなことにつながってまいりますので、
これがまず1点と、歳入確保策としては、滞納税はもとより未利用地の売却を
積極的に進めるとともに、ふるさと納税を含めた財源確保に全庁的な取り組み
として、これまで以上に努めていきたいなと思っています。
2点目の御質問ですけれども、合併等に伴い役目を終えた公共施設等の除却
に対しましては、合併特例債を活用する計画としております。
なお、合併特例債の平成30年度以降の発行見込み額は108億円余りですが、
このうち建てかえを除き、単に除却に係るものにつきましては、その事業費総額
を5億4,000万円と見込んでいることから、充当率を乗じると、約5億円余りの発行
を計画しているところであります。
なお、これにつきましては、予算編成時の収支計画の中で財政当局がつかんで
いる数値でありますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。

仕事中に見る・・・きれいですねー。
私ども三豊市議会会派「清風会」で、瀧本文子副会長と一緒に、「代表質問」を
させていただきました。
会派「市民の会」(8名)の後で、「清風会」(7名)での質問時間は、7名以上の
会派は2時間となっています。
1.市長の政治姿勢
横山前市長が築き上げてきた基盤を守りつつ、新しいことにも挑戦していく
山下新市長の「心をひとつに三豊市のまちづくり」に向けた政治姿勢と決意を聞く。
2.財政問題
本年度の予算編成上での重点項目と、合併特例債など。
平成30年度における重点施策と財政見通しについて、プライマリーバランスなど
見据えた将来の財政計画について聞く。
3.活気にあふれ、産業が躍動するまち(産業・雇用)
①農業や水産業においての、情報通信技術(ICT)の活用とAIの先進的導入とは。
②シティプロモーション活動とは、今回の最重要テーマである「人口減少対策」に
繋げるべく具体的にどう展開していくのか。
③地域商社、ふるさと納税、ふるさと住民票制度、など昨年度の成果と今年度の
展開について聞く。
4.豊かな自然と共生し、環境にやさしいまち(環境・生活)
①空き家バンク活用の今後について
②危険空き家の「空き家等対策計画」に基づく、自治会等との連携による見守り
体制とは。
5.指定管理者制度
松崎保育所などの指定管理者へのモニタリングについて、現状とモニタリング
制度指針は。
以上5問で、子育てや教育関係を瀧本副会長へ頼みました。
まずは1と2をご報告致します。
●質問1
5番、浜口恭行、清風会の代表質問をさせていただきます。
まず初めに、市長の政治姿勢についてお聞きします。
合併来、横山前市長は激変する社会情勢の中で、自治体の本来のあるべき姿、
また未来を見据えた形を具現化してこられましたと施政方針で山下新市長が
述べられておりますが、その上で、横山前市長が築き上げてきた基盤を守りつつ、
新しいことにも挑戦していく、山下新市長の「心をひとつに三豊市のまちづくり」
に向けた政治姿勢、また、本市の最重要テーマは人口減少対策だと言われて
おりますが、これはもう全国どこの地方自治体でも抱える問題でありますし、
横山前市長がおっしゃった、若い女性をターゲットにした各種子育て支援策、
また、全国に先駆け地域内分権推進交付金を使ったまちづくり推進隊が7町に
誕生し、委譲業務と自主事業が実施されておりますが、このような施策を継続
しつつ、新市長の言われるインターネット、AIなどの先端技術がどのような形で
融合されていくのか、少しわかりにくい部分があるとの市民からの御指摘もあり
ますし、市民の会の代表質問とダブるところがありますが、このあたりの山下新
市長の決意をまず最初にお聞きいたしますので、よろしくお願いします。
●答弁1
浜口議員の御質問にお答えいたします。
七つの町が合併し、既に12年が過ぎました。
当然ながら、それぞれの地域で育まれてきた歴史や文化があり、それは大切に
していかなければなりません。
しかしながら、三豊市としての一体感を持ったまちづくりにも取り組まなければ
ならないと考えております。
これまで横山前市長が進めてきた地域内分権の推進は、将来にわたって自立
して持続するまちであるための仕組みづくりであったと理解をしております。
この地域内分権の一端を担うまちづくり推進隊も、七つの町ごとに設置されて
おります。
設立の段階では、まだ旧町の枠を越えた体制をつくり上げるというのは困難
だったのかもしれません。
しかしながら、今、自然発生的に推進隊の間で連携を模索する動きも出てきて
います。
まさに、「心をひとつに三豊市のまちづくり」が生まれようとしています。
このような旧町の枠を超えた三豊市として、市民主体のまちづくりに期待して
いるところであり、その市民力とともに、行政としてのまちづくりを積極的に
進めてまいります。
また、御発言のあった若い女性をターゲットにした各種子育て支援対策にも
引き続き取り組みます。
統計データによりますと、地元の高校を卒業した若者が大学等に進み、卒業
後に三豊に返ってくる割合を男女別で比較した場合、男性よりも女性のほう
が少ないというデータ結果があります。
若い女性が帰ってきたいと思える生活環境の整備、市外の若い子育て世帯
が住みたいと考えるような町となるように、施策に取り組んでまいります。
このように、前市政を継承して取り組んでいくことに加え、新たにチャレンジを
開始するものもあります。
それがICTやAIといった先端技術の導入です。
このことについては、市民の会の代表質問の答弁でも申し上げましたが、まず
はこの分野の民間や学術機関の保有する技術と市内産業とのマッチングを行
い、市内での実証実験から開始していきたいと考えております。
そのような取り組みの中から、三豊オリジナルの技術もシステムが生まれます。
これは市内の企業における雇用の拡大や生産性向上による市民の豊かさへ
直結するものであります。さらには、地域間競争に打ち勝ち、三豊の企業が世
界にも打って出ることのできる力にもなります。
さらには、企業の発展のみならず、三豊オリジナルの技術とシステムそのもの
が、特許や著作権などの知財ともなります。
将来的にもうかる産業、地域振興へつなげることで、行政の税収増にもつなが
りますので、この点につき、果敢にマッチングを進めてまいります。
こうした観点からも、三豊市を一つの区域と捉えた土地利用のゾーニングにも
着手いたします。
観光振興ゾーン、農業振興ゾーンといった形を旧町の区域を超えて設定し、
そのゾーニングの中で、めりはりをつけた施策展開や集中投資が可能になるも
のと考えております。
守るべきは守りながら、新たなことにも果敢に挑戦し、明るい三豊の未来を実現
するため、市民の皆様とともに心を一つにしたまちづくりに取り組んでまいります。
●再質問
ありがとうございます。
地域内分権、これはまちづくり推進隊ですけど、私、以前にも発言させてもらい
ましたけど、三豊市全域で効果を発揮することを目指して推進隊同士の連携が
図られるようにするということ、非常に、今ありましたようにいいことだと思うん
ですけど、これ以上に公民館や既存の他団体と連携して、活動内容のダブりを
解消するとともにそれぞれ独自に実施している市民運動の調整役となること、
また事務局への指導など、市民の声を反映できる推進隊となるためには、市
当局が率先して関与していくという見直しが必要だと考えます。
地域内分権特別委員会というのが過去にあったんですけど、これで行った長野
市では、地域の課題を迅速かつ効果的に解決するために、自分たちの地域は
自分たちでつくるという意識を持って活動していまして、その活動を市当局が
積極的に支援していく仕組みをつくり出していました。
その上で、市の連合組織や交通安全推進委員、保健指導委員などの委嘱制度
をも廃止して、各種団体や委嘱廃止に伴う依頼事務を洗い出しまして見直しも
行っている点、本当に長野市の分、参考になったんですけど、本市にも公民館
を初め各種団体活動が存在していますので、これらの見直しといいますか、
ダブりを解消して統合していく仕組みづくりというのがそろそろ必要であると思い
ますが、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2
浜口議員の再質問にお答えいたします。
まちづくり推進隊の活動について、市域全体で効果を発揮することを目指し、
連携が図られるよう促してほしいということに関しましては、先ほどの答弁でも
申し上げましたとおり、自発的に横の連携が生まれつつありますので、その
経過を見守りたいと思います。
旧町の枠を超え、三豊市全体のエリアで自発的な活動は、「心をひとつに
三豊市のまちづくり」に向けた大きな一歩だと思います。
次に、公民館活動や他団体等の活動の内容にダブりが生じているという指摘に
つきましては、行政が実施しております事務事業も含め、推進隊を初め市民の
活動にお任せしても同等もしくはそれ以上の効果が見込める事業、また連携
してさらに大きな効果、高い成果を見込める事業につきましては、選択を行って
いくべきであると考えておりますので、行政におきましては事業評価の中でその
可能性を検証できるよう検討していきたいと思います。
いずれにいたしましても、人口減少時代にあって、地域の課題はみずからの責任
と判断で乗り越えることのできる地域コミュニティー組織として発足したまちづくり
推進隊です。これからも持続可能なまちづくりを行っていくための仕組みとして、
引き続き支援をしてまいりたいと考えております。
●再質問
ありがとうございます。
市長答弁の中でありましたICTやAIの先端技術の導入という点ですね。
私たちが必ずしも都市や集落に依存しなくても暮らしていける環境を提供して
いくと考えられます。
こうした社会基盤の整備と発展は、人口減少が進む本市のような地方自治体、
山下市長の言う三豊オリジナルの技術が生まれるという点では、本当、特に
条件が不利とされている過疎地域をも持続可能な暮らしの場へと変容させて
いく、このような可能性を秘めていると思います。
私自身、山下市長の言う先端技術とは、人口が減少してもより豊かに安心して
暮らすことのできる社会が形成される、築かれるのではと考えます。
これらにより社会の仕組みが変わり、人口が減っても暮らしの利便性や快適
性を低下させることなく、誰もが暮らし続けられる社会基盤を整えることもできる
と。
今考えるべきは、人の奪い合いではなく、たとえ人口が減少してもより豊かに
安心して暮らすことのできる社会、市長の言われる市民力、これを築くことが
大切なのではないかという私の理解なんですが、それでよろしいでしょうか。
●答弁3
浜口議員の再質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおりであります。
これほど人口減少によって企業や農水産業、人手不足が深刻な状況の中で、
人の奪い合い、労働力の奪い合いというのは、本当に生産性がございません。
そういった意味で、本来機械とか、そういうものに任せられる部分においては、
AI、ICTを活用して生産力を高め、そこに本来必要だった人を別の分野に、
さらに生産性を高めるところに配置することができるという考え方であります。
議員が御指摘されましたように、そういうことによって企業本来の持続性また
は生産性向上につなげるという目的でのICT、AIでの導入を考えております。
そのためには、まずは実証実験等で、三豊市がその先端を走るんだという
意思表示が必要でありますので、そういった分野での実証実験という意味で
やってまいりたいと考えております。
いずれにおきましても、やはり、今後の人口減少傾向等もかんがみながら、
今暮らしている人たちの今の暮らしというものをいかに豊かにしていくか、
そして発展させていくかということが重要であると思いますので、その点に
ついての御理解を賜ればと思います。
●質問2
次に、財政問題についてお聞きいたします。
一般会計当初予算案ですが、308億4,000万円が計上されております。
大型建設事業が重なった平成27年度がピークであり、今年度はこの額で新
総合計画第10期実施計画で示された額が基本数値として編成されているよう
ですけど、経常的経費や継続事業を中心とした骨格予算であるとのことですが、
平成30年度における重点施策と財政見通しについてお聞きいたします。
また、合併特例債は有利な起債であるとはいえ、借金には変わりませんが、
発行期限再延長が実現すればどのような事業を考えているのか、30年度末の
特例債借入合計とか今後の予定、また交付税の一本算定に伴う交付税の縮減
とあわせて、将来のプライマリーバランスも、本年度は黒字化していまして、
先ほど丸戸議員の代表質問の中で答弁もありましたが、将来を見据えた財政
状況がどのようになるのかを再度お聞きいたします。
●答弁1
浜口議員の御質問にお答えいたします。
議員御指摘のとおり、平成30年度当初予算は新規事業や拡大事業を基本的に
見送り、人件費、扶助費、公債費等の義務的経費及び施設管理等の経常的経費、
債務負担行為設定済みの事業費等を計上した骨格予算として編成いたしました。
平成30年度における重点事業につきましては、市長から施政方針で述べられた
とおり、人口減少問題を最重要課題として捉え、中小企業の振興や雇用確保に
資する施策、また、子育て支援施策を中心に当初予算に盛り込んでおります。
具体的に申し上げますと、若者定住の補助事業、賃貸住宅補助を行い移住
定住を図る定住促進事業、中小企業振興や企業立地、雇用の点からは、
企業立地促進事業、工業用水対策事業が上げられます。
また、子育て支援施策の面からは、15歳年度末までの子供の医療費の一部
助成を行う子ども医療費助成事業の継続実施、同じく継続実施する生活困窮
世帯のうち高等学校に進学する者を対象に学習支援を行う子供の学習支援
事業、新規事業として産後退院した母子に対して心身のケアを行う産後ケア
事業が上げられます。
合併特例債についてですけれども、御存じのとおり本市を含む全国の自治体で
組織する合併特例債再延長を求める市長会からの要望が認められ、議員立法
として可決成立、5年の再延長がほぼ確実視されている状況です。
本市における合併特例債に関する状況を申し上げますと、発行上限額約446億
6,000万円に対し、平成30年度末の発行見込み額は約215億7,000万円と
なっております。
また、今後関係法案が可決成立し、発行期限が平成37年度まで延長された
場合の具体的な充当事業につきましては、現時点での可能性という前提で申し
上げますと、詫間支所周辺整備事業や北部地区給食センター整備事業等の
各種普通建設事業に充てていくことを想定しております。
先ほど申し上げましたとおり、三豊市の場合、現在の合併特例債発行見通しに
おいて、発行上限額には達しておらず、延長される5年間で新たな事業への
充当も可能ではありますが、現発行期限の平成32年度までで計画上充当して
いる各種ハード整備事業の平準化することを基本的な考え方としております。
議員御指摘のとおり、この合併特例債については充当率、交付税措置率が
通常債と比較して有利であるものの、借金には変わりありません。
この点については我々も浜口議員と同じ認識を持っているところであります。
そのような意味から、将来世代への過度な負担先送りを防ぐためにも、不要
不急な事業は凍結し、各種基金と合併特例債を初めとした市債、すなわち
貯金と借金を有効に活用しながら、プライマリーバランスの黒字化を前提とした
予算編成に努めていきたいと考えております。
●再質問
ありがとうございます。2点質問します。
まず、本市の自主財源が非常に乏しい点、これは今後ますます人口減少とか
事業所の閉鎖などマイナス要因が考えられる中で、どのように市当局が
お考えなのかというところが1点です。
もう1点は、ハード整備に使われるということなんですけど、今、除却に合併
特例債を使えると思うんですけど、今後取り壊し、解体等いろいろ、公共施設
の再編に伴う利用の仕方が必要になると思うんですけど、除却のためには
どのくらい使う予定があるのかという点、2点お聞きいたします。
●答弁2
議員御指摘のとおりですが、本市の財政構造において最大の弱点は自主財源
比率が低いということであり、自主財源の確保は本市発足以来の大きな課題
でもあります。
先ほど市長が申しましたように、産業の活性化を図っていくということが、これが
地域の活性化につながっていくというふうなことにつながってまいりますので、
これがまず1点と、歳入確保策としては、滞納税はもとより未利用地の売却を
積極的に進めるとともに、ふるさと納税を含めた財源確保に全庁的な取り組み
として、これまで以上に努めていきたいなと思っています。
2点目の御質問ですけれども、合併等に伴い役目を終えた公共施設等の除却
に対しましては、合併特例債を活用する計画としております。
なお、合併特例債の平成30年度以降の発行見込み額は108億円余りですが、
このうち建てかえを除き、単に除却に係るものにつきましては、その事業費総額
を5億4,000万円と見込んでいることから、充当率を乗じると、約5億円余りの発行
を計画しているところであります。
なお、これにつきましては、予算編成時の収支計画の中で財政当局がつかんで
いる数値でありますので、御理解賜りますようよろしくお願いします。
仕事中に見る・・・きれいですねー。