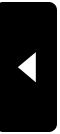2025年03月29日
私の代表質問(その1)
代表質問のトップバッターでした。
会派「清風会」は2時間枠ですので、私と三谷幹事長で手分けして。
私の部分を公開します。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
清風会の代表質問を2人でさせていただきます。
さて、本日は主権者教育の一環として、12月定例会の高校生に続き、
市内の中学生が傍聴に来ていただきました。
中学生の皆さん、おはようございます。
少し難しい用語も出てきますが、市政、議会へ少しでも関心を持って
いただければ幸いです。
さて、私にとって議員になってから50回目の質問となりました。
ここも節目であります。
代表質問ですから、市長の施政方針に沿って、時間枠の中でできる
だけお聞きしたいと思いますので、当局の皆様も簡潔明瞭な答弁を
お願いいたします。
まず初めに、首長、市議とも残任期1年を切りました。来年1月1日
には本市誕生20年目の節目を迎えるこの令和7年度第2次総合計画
後期基本計画における四つの重点プロジェクトがありますが、この
具体的な中身は2問目以降でお聞きしていきます。
その上で、健康、教育、三豊市独自の脱炭素など、多くの施策や事業、
またメニューの中で、山下市長の総仕上げのこの1年には何を優先
して取り組んでいくのでしょうか。
人口減少に対する危機感、地方創生2.0に関連して、山下市長の
本市の未来に向けたまちづくりの政治姿勢と施政方針のキーワード
でもある進歩とは、これ、昨年は選択肢でしたが、本年の進歩とは
具体的に何なのか。
施政方針にあるように、「革新や刷新が行われず、日本が進歩を
忘れていた」と書かれておりますが、ここは全くに同感であります。
世界全体の流れは、我々が感じているより驚異的な速さで進歩して
います。
気がついたら世界に、社会に取り残されているのです。
それでは、いつかの時代と同じ繰り返しになります。
まさに失われた30年です。全くそのとおりであるがゆえの進歩だと
思いましたが、それで合っているのでしょうか。
また、結びにある『戦艦大和ノ最期』の臼淵 磐大尉が士官たちに
語った言葉、山下市長の一つの指針となっていると書かれております。
私なりに理解するに、失われた30年で日本は進歩を忘れてしまい、
まず施政方針の節目とは、まさに今年は太平洋戦争が終わり80年目
の節目であり、この節目に先人の言葉を通して、私たちが改めて当事
者に寄り添い、自分事として捉え、未来につながるための重要な機会
を私たちは先人から、先人たちが歩んできた苦難や成功の歴史から
学び、未来へつなげ、子供たちから高齢者まで、皆が夢と希望を持ち
続けられる社会、豊かな生活を目指し、改めて日本、また本市を前に
進め続けられなければならないという思いの中で、まさに、
「One MITOYO~心つながる豊かさ実感都市~」を目指すという
理解なのかなと私は思いますが、その理解でよいのかお聞きしたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
●答弁1
清風会、浜口議員の御質問にお答え申し上げます前に、高瀬中学校
の皆さん、本当にようこそお越しいただきました。
なかなか難しい言葉もいっぱいあると思います。
その中で、一つお願いがあります。
皆さんで興味を持った言葉、一つでいいので覚えて帰って、それを調べる
ということをしていただけたらなと思います。
この質問でもよく出てきます、施政方針って何だろう。
そういうことを考えていただけたら、何か皆さんの今後のプラスになると
思います。
この場では、本当に市の大切なことを話し合っております。
ぜひそういうことをやっていただけたらと思います。
それでは、浜口議員の御質問にお答えいたします。
回答の順番が前後して申し訳ございませんが、まず2点目の市長の
本市、未来に向けた持続可能なまちづくりの政治姿勢と施政方針の
キーワードである進歩とはとの御質問ですが、本市はその誕生以来、
人口減少が続いており、その傾向は今後も続いていくものと予測
されております。
なので、大変厳しい危機感を持つ状況でございます。
しかしながら、そういった中にあっても、若者、女性にも選ばれる町、
高齢者も含めて、誰もが安心して住み続けられる町を実現し、10年後
も20年後も未来に向けて持続的に発展する本市を市民の皆様とつくり
上げていきたいと考えております。
そのときに重要なことが進歩であります。
社会や環境などが大きく変化する中で、これまでどおりのやり方を
続けるだけでは、守りたいものも守れなくなってしまいます。
例えば、本市の基幹産業である農業につきましても、農業生産者は
減り、耕作放棄地は増えておりますが、これまでどおりのやり方を
続けるだけでは、その傾向を変えることができないと思ったからこそ、
新たな取組として薬用栽培や有機栽培に取り組んできたのであり、
さらにスマート農業というテクノロジーを加え、強化を図っていきたい
と考えております。
このように、進歩とは単にデジタル化を進めるという話ではなく、
これまでもこうやってきたのだから、それを続ければよいと思考を
停止するのではなく、社会や環境の変化に合わせて柔軟に対応
する考え方を持ち、必要なら失敗を恐れず新しいものを取り入れ、
よりよい方向に、現状より一歩でも前に進めていくことだと考えて
おります。
それが既存の考え方を変えることもあれば、既存の手法を変える
こともあるのだと思います。
変えるべきは変える。変えないものは変えない。
そういった取組を積み重ねていくことによって、三豊市を持続的に
発展していく。
市民の皆さんの暮らしを守っていきたいと考えております。
次に、1点目の市長の総仕上げのこの1年には、何を優先して
取り組んでいくのかとの御質問ですが、令和7年度は合併特例債
の発行期限を迎えますので、大型建設事業をしっかりやりきること
が重要だと考えております。
その上で、施政方針に記載させていただいたスマート農業、地元
企業及び地元経済の革新やDXへの支援、放課後改革、国際バカ
ロレア教育など、進歩のための取組につきましては、今後の本市の
ため、いずれも重要な取組だと考えておりますので、しっかりと取り
組んでまいりたいと考えております。
最後に、3点目の結びにある『戦艦大和ノ最期』の臼淵大尉が士官
たちに語った言葉の意味を聞きたいとの御質問ですが、これは議員
が御指摘いただいたように、非常に私の考えの部分に近いものを
御示唆していただいたと思っております。
最初に申し上げましたように、節目というのは、議員御指摘のとおり、
この施政方針にも書かせていただきました。
先人の苦難や成功に学んで、未来へつないでいくという意味で、この
言葉を使わせていただきました。
これは引用でございますので、基本的に私がその言葉に対しての
解釈を添えるということは差し控えさせていただきたいと思います。
これはなぜかというと、臼淵大尉が本当に自分の死を前にして発した
言葉です。
その臼淵大尉の言葉自体の意味というのは、臼淵大尉の本人しか
分からない言葉でございますので、それを私がああだこうだと解釈
するよりも、皆さんがこの80年目の節目に自分事として何かを感じて
いただける、そういったことを望んで書かせていただきました。
そして、施政方針の中にも書かせていただきましたけれども、その
意味という部分では、本当に日本が戦後同じことを繰り返している
のではないのか。
失われた30年で何を失ったのか。そういったものをもう一度振り返る。
これはまさに節目のことであるというふうに考えております。
そういった意味では非常に御指摘の部分、私の考え方に近いもので
あると思っております。
ここの部分に関しては感謝申し上げたいと思います。
ですので、そういった意味では、皆さんも、できれば様々な節目に
おいて、今後もいろいろな形での自分たちの考え、自分が感じた
ものというものをこれから大事にして、そして前に進んでいく。
その原動力、進歩というものにつながっていく。
それを我々としては一緒に議員各位の皆様と進めてまいりたいと
思い、ここに書かせていただきました。戦後80年、我々が本当にもう
一度考えなきゃいけないもの、そういったものをここに、議会の中に、
三豊市議会の中に、私としては残しておきたいという思いがまず
ありました。
●質問2
大変すばらしいお考えをお聞きしまして、ありがとうございます。
次に、「みとよでスマイル~持続と豊かさ~」、四つの重点プロ
ジェクトの詳細をお聞きしていきます。
特に今回思いましたのは、この「みとよでスマイル~持続と豊かさ~」、
防災、健康福祉、インフラ、産業の充実といいますか、重点施策が多い
です。
施政方針の9ページ以上が割かれておりますが、この中で、防災全般
は同僚議員がお聞きしますので、私からは緊急防災・減災事業費の
対象事業が拡充されるとともに、特別交付税措置の制度の拡充に
ついてのみお聞きします。
画面を切り替えてください。
南海トラフ大地震に備え、緊急防災・減災事業費を活用する予定が
あるのかをお聞きいたします。
私の代表質問はいつもなんですが、地方財政対策から、総務省が
出しているところからの抜粋が多いんですが、緊急防災・減災事業債
というのは充当率です。
充当率100%かつ地方交付税措置率70%で、簡単に言いますと、
7割補助と同様の財源的な有利さがあります。
この緊防債、短く言ってあれなんですが、緊防債は過疎債の次に
有利な起債だと私は思いますが、これを有効に活用する予定がある
のかをお聞きいたします。
それと、本市も能登半島地震と同じく、詫間、仁尾両町で最大震度
7が予想される地域があります。
その上で、能登半島地震では、輪島市と珠洲市が市内の建物被害
を調べた結果、両市とも建物の3割以上が全壊でありました。
住宅の耐震診断と耐震対策、ちゅうちょしている市民を促進する
具体施策があるのかをお聞きします。
画面を切り替えてください。
特に、写真の最大震度7が予想される地域、赤い部分ですが、この
地域には優先して取り組むべきだと考えます。
どのようにお考えでしょうか。
また、みとよ市民病院を地域に根差した病院とするため、経営改善
に取り組んでいますが、十分な成果が出ていないということです。
それゆえ、今回の補正で一般会計から長期借入金2億3,000万が
計上されておりますが、全力で取り組んだ結果がこうなのか、これ
以上はどうしていくのか、市長の判断が必要です。
書かれているように、公立病院の経営状況はどこも厳しいところ
ばかりです。
コロナ以降、赤字経営がほとんどでありますが、私は「住民ニーズを
踏まえ」というところ、ここが一番重要だと感じます。
というのも、お正月に市民の方からお電話いただきましたけど、
行きたいと電話したら、どこの病院にかかっているのか、病気の
状況とか現在の状態をさんざん聞かれた挙げ句に、最後は先生
がいませんからと言われました。
それなら最初に言ってほしかったとか、ベッドが空いていませんと
強い口調で電話口で言われたとか、先生や看護師から少しきつい
言葉で言われましたなどの意見を多々お聞きしております。
最後は、本当に市民のための病院なんですかと言われる方がいます。
これ、本当にサービスの類いで、住民ニーズを捉え、市民病院は
駄目だという評判が広がりかねません。
一番に改善するべきであると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
次に、三豊市の玄関口、また顔となるJR高瀬駅はどのように
考えているのかもお聞きいたします。
JR四国は人手不足などにより、高瀬駅2024年3月中旬から無人化
されております。
JRも民間企業です。
利用者観点から、なるべく早い整備をJR四国と協議いただきたい
のはもちろん、議会運営委員会で訪れたJR浜田駅には待合所に
自習スペースがありました。
これ、市の教育委員会が整備したそうですが、JR高瀬駅や詫間駅
にも欲しい。
それよりも駅の整備とともに、三豊市役所のある高瀬駅でICカード
が利用できるようにしてほしいと私は切に思いますが、どうでしょうか。
また、公共設置施設についても具体的な部分は同僚議員がお聞き
します。
清風会では、防災と公共施設再編は非常に重要だと感じますので、
2人から質問をしますが、私からは公共施設等適正管理推進事業債
についてお聞きします。
画面を切り替えてください。
総務省は、集約化、複合化を推進させるために、起債の充当を見直し
て、例えば施設の整備を行い、施設を統合する場合に、除却事業は
起債対象になっていましたが、交付税措置率の50%がありません
でした。
ただの除却はただの借金でしかできなかったのですが、機能統合
する除却であれば、50%の交付税措置する有利な起債が使える
ようになっております。
施設の整備は行わず、機能を統合する場合も同じで、もちろん、
公共施設等総合管理計画の進捗度を確認して、計画的に予算措置
されているかという確認はあります。
また、複数団体による公共施設の集約化、複合化に係る特別交付
税措置の創設もできました。
特別交付税措置が今回、この地方財政対策の中でたくさん出てきて
いるんですよ。
特別交付税をうまく取れれば私はいいかなと非常に思うんですが、
どうでしょうか。
また、昨年、交通システム事業団MiLAISが設立され、この事業団
の目標は何か、また地域公共交通をどうしていくのか、産・学・官、
香川高専や地元企業、スタートアップ企業の支援やDX、AIにはどの
ように取り組んでいくのか、市長の先ほどの答弁の中にもありました。
また、脱炭素経営認定制度とは何か、三豊市独自の脱炭素について
はどう取り組んでいるのか、いくのかをお聞きいたします。
●答弁2
浜口議員の御質問にお答えいたします。
高瀬中学2年3組B班。ようこそいらっしゃいました。
引き続き、議会を見ていてください。
それでは、浜口議員の御質問にお答え申し上げます。
質問が多岐にわたりますので、少し長くなりますことをお許しください。
南海トラフでは、令和7年1月1日現在、海溝型地震の30年以内の
発生確率が80%程度と評価され、大きな数値になっているのは、
地震発生が切迫していることを示しております。
南海トラフ地震が発生すれば、甚大な被害を及ぼす可能性が
あるため、日頃から耐震補強や家具の固定などの対策を講じること
が重要です。
緊急防災・減災事業債を活用する予定につきましては、全国的に
緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災減災のための
地方単独事業等が緊急防災・減災事業債の対象となっており、
これまでも防災センターの建設や防災行政無線更新事業などで
活用しております。
充当率100%で、元利償還金の70%を地方交付税措置される有利
な財源であり、対象事業も拡充されてきておりますので、消防施設
や防災資機材の更新など整備を進めております。
次に、耐震対策にちゅうちょしている市民への具体策につきまして
は、ちゅうちょする理由としては、高額な改修費用、耐震対策への
疑問、手続が分からない、未耐震住宅の所有者に高齢世帯が多い
ことなどが考えられます。
引き続き、無料相談会や地域の防災訓練などの機会を捉えて、
低コスト工法の紹介や補助制度の丁寧な周知等に努めてまいり
ます。
また、市内でも最大震度が高い地域等を耐震化重点エリアに
設定し、住民の耐震化を進めるため、香川県と連携して戸別訪問
を実施しました。
また、震度7が想定される自治会の防災研修会へ参加し、建物
被害を減少する啓発を行いました。
なお、令和6年度の本市における民間住宅耐震対策支援事業
については、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表など
を背景として、市民の危機意識が高まり、耐震診断は、前年度比
の約6倍となる64件、簡易改修等を含む耐震改修工事は3倍の
30件と大幅に増加いたしました。これにとどまることなく、市民の
耐震対策に対する機運が高まっているこの機を逃さずに取り組ん
でまいりたいと考えております。
次に、みとよ市民病院の方向性につきましては、議員御案内の
とおり、令和5年度に三豊市公立病院経営強化プランを策定し、
経営改善に取り組んでおります。
市民の皆様からの御意見も賜りながら進めておりますが、公立
病院の経営状況は全国的にも厳しいものがあると考えております。
施政方針でも触れさせていただきましたが、公立病院の役割は、
収益だけで語れるものではありませんが、現下の状況改善は
間違いなく大きな課題であります。
いずれにいたしましても、病院職員一人一人が現在の厳しい
経営状況を認識した上で、各部署が具体的な行動計画を策定し、
安定した経営状態のもとで、市民の皆様が求めている安全で
良質な医療を継続的に提供していける病院、また、職員の意識
改革を進めるとともに、患者ファーストに努め、選ばれる病院と
なるよう取り組んでまいります。
次に、JR高瀬駅の整備についてでございます。
令和7年度中の完成を目指し、JR四国と共同で計画を進めて
おります。
整備の主な内容としては、これまでに特に要望の声が多く寄せ
られていたトイレについて、どなたも安全かつ衛生的に利用できる
よう整備するとともに、駅利用者の滞在空間や市民が集える
パブリックスペース、そして駐輪場を建設いたします。
また、駅前広場においては、交通結節点としての機能を強化
するため、コミュニティバスの乗り入れができるロータリーを新設
し、鉄道とバス、両公共交通の乗り継ぎのシームレス化を図る
ほか、敷地内における車両や歩行者の安全性確保も考慮して
設計を進めております。
御質問の改札における交通系ICカードの対応につきましては、
これまでも市民からの要望もありましたが、JR四国からは導入
には多額の初期投資、将来の更新費用を要するため、当面の間、
ICカードの利用可能駅の拡大は見送っている。四国内のお客様
にはチケットアプリの利用を推進しているとのことでした。
いずれにいたしましても、今回の駅舎建て替えを契機に、本市の
玄関口として、皆様に快適に御利用いただける駅になることは
もちろんのこと、改善と新たな機能の付加により、人の流れや
交流を生み出す拠点となるよう整備してまいります。
次に、公共施設等適正管理推進事業債の利活用につきまして
は、議員御案内のとおり、総務省より発表されました令和7年度
地方財政対策の概要によると、公共施設等適正管理推進事業債
につきましては、公共施設等総合管理計画等に基づいて実施する
公共施設の集約化、複合化等に伴う施設の除却事業が対象に
追加されることとなりました。
これまで有利な合併特例債を活用し、事業を実施してまいりました
が、特例債終了後には、公共施設等適正管理推進事業債を活用
してまいりたいと考えております。
また、公共施設の除却債については、交付税措置の対象では
ありませんが、今回追加されることで、公共施設を解体する必要
がある場合においても、条件付ではありますが、有効活用できる
起債であると考えております。
市にとって一番有利な条件で事業実施ができるよう努めてまいり
たいと考えております。
次に、交通システム事業団MiLAISの目標、また、地域公共交通
につきましては、一般社団法人三豊交通システム事業団MiLAIS
については、昨年7月29日に設立され、その目標としては、人口減少
や人口構造の変化、さらにはライフスタイルの多様化の影響で移動
困難者が増え、交通、移動ニーズの高度化が進む中で、本市の
地域公共交通計画の基本理念である全ての人が「行きたいときに
行きたいところへ行けるまち」を享受し、持続するまちで豊かに幸せ
に暮らし続けられるよう、地域におけるモビリティに関する課題解決
を目指すこととしております。
具体的には、市内交通事業者や地域の皆様のハブとなりながら、
あらゆる移動手段の確保に努めてまいります。
本市の運転免許証自主返納者数は、過去10年間で申し上げます
と3,604人、年間平均約360人の方が自ら移動することを断念し、
誰かに頼らなければ行きたいところへ行くことができない状況と
なっております。
このような中で、日常生活の最も基盤となるエリアでのファースト
ワンマイル、ラストワンマイルの課題も解決しなければなりません。
過去の御質問でもお答え申し上げましたように、詫間町、大浜地域
でこれらワンマイル解決に向けた移動サービスの事業が地域の
皆さんや事業者の御協力を頂きながら形になってまいりましたので、
これをモデルとなるようさらに進めてまいりたいと思います。
さらに、高齢化に伴う移動困難者の増加の一方、生産年齢人口
の減少の影響は、運転士を含む働き手不足にも及んでいます。
国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、2050年の
生産年齢人口は、現在の約3万人弱から約1万9,000人と、およそ
37%の減少が予測されており、社会全体の働き手の確保が極めて
困難な時代が到来することとなります。
これらの状況を踏まえ、先ほど申し上げた将来の人口や暮らしの
在り方も見据え、日常生活を支える地域公共交通の構築を進める
とともに、市民の皆様、市内事業者各位、さらには、あらゆる分野
の人、物、時間、空間を最大限に活用し、持続できる地域をつくり
上げていまいらなければならないと考えておりますので、御理解、
御協力を賜りますようお願い申し上げます。
次に、産・学・官、特に香川高専や地元企業とのDXやAIの取組
につきましては、香川高等専門学校とは、これまでも学・官連携に
基づき、様々な取組を実施してきておりますが、地元企業の革新
やDXを支援するため、さらに連携強化を進めていきたいと考えて
おります。
現在、将来的な香川高専の学生の起業にもつなげていくことを
目指し、香川高専が抱える学生が地域と接点を持てておらず、
地域に入り込めていないという課題を解決するため、まずは、
高専生に実際に地域に出てもらう機会をつくりながらアイデア
ソンを実施することを検討しておりますが、学生がキャンパスの
外で経験を重ね、学生が持つ知識や技術を課題解決に生かせる
よう取組を進めていきたいと考えており、そういった取組の先で
実際に起業してもらうことができれば、地元企業の進歩、イノベー
ションにもつながっていくものと考えております。
なお、地元企業に対するDX支援としては、今年度からリスキ
リング事業をはじめ、技術的な研修だけでなく、地元企業の優良
事例を聞く機会の提供を通じて、経営者の意識改革や社員の
DXマインドの醸成とスキルの向上を目指しております。
DXやAIの分野については、日々進化を続けておりますので、
市内に高専があるという優位性を十分に生かし、地元企業に
支援をしてまいりたいと考えております。
次に、脱炭素経営認定制度とは、市内の中小企業の皆様に
中長期的な支援を行うことで、脱炭素経営を推進し、市域全体
の企業の価値向上を目指すものであります。自社のCO2排出量
を算定し、2030年度までの取組や削減目標値を設定した削減計画
を策定、市へ認定申請していただき、市は計画内容を審査し、適切
であると認めた場合には認定証を交付いたします。
また、削減計画の達成状況によって、市が表彰することにより、
企業価値の向上や宣伝効果にもつながると考えております。
一方、三豊市独自の脱炭素ですが、温室効果ガスを削減していく
だけでなく、本市の豊かな自然を守りながら、吸収量を増やしていく
ことです。
豊かな生物多様性は人類存続の基盤であり、その上に社会があり、
さらにその上に経済が成り立っていかなければなりません。
現在、進行中のものを申し上げますと、本市の海域においては、
藻場の再生について実証が行われております。
実現できれば、豊かな海を現在から将来へ引き継ぐことができる
ことだけでなく、海藻はCO2を吸収します。これらの取組を進めて
いき、海だけでなく、陸地においても検討してまいります。
削減と吸収、そして自然を守ることを同時に進めていくことによって、
新たな価値を生み出していきたいと考えております。
●意見2
1点だけ、病院です。
公立邑智病院、三豊総合病院で視察した会派の議員に無理言って
私、資料頂いたんですが、ここの石原名誉医院長が邑智病院を時々
訪ねて、病院というものは、職員が楽しく働ける職場になれば、自然
に患者に優しい優良な病院になる!と言い続け、風通しのよい職場、
明るい雰囲気の快適な職場を皆でつくり上げて、地域住民に満足
していただく病院になっているそうです。
私はこの職員が楽しく働ける職場にするというのが一番に大事だと
思いますので、それだけ申して次に行きます。
以上、明日に続く・・・。
会派「清風会」は2時間枠ですので、私と三谷幹事長で手分けして。
私の部分を公開します。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
清風会の代表質問を2人でさせていただきます。
さて、本日は主権者教育の一環として、12月定例会の高校生に続き、
市内の中学生が傍聴に来ていただきました。
中学生の皆さん、おはようございます。
少し難しい用語も出てきますが、市政、議会へ少しでも関心を持って
いただければ幸いです。
さて、私にとって議員になってから50回目の質問となりました。
ここも節目であります。
代表質問ですから、市長の施政方針に沿って、時間枠の中でできる
だけお聞きしたいと思いますので、当局の皆様も簡潔明瞭な答弁を
お願いいたします。
まず初めに、首長、市議とも残任期1年を切りました。来年1月1日
には本市誕生20年目の節目を迎えるこの令和7年度第2次総合計画
後期基本計画における四つの重点プロジェクトがありますが、この
具体的な中身は2問目以降でお聞きしていきます。
その上で、健康、教育、三豊市独自の脱炭素など、多くの施策や事業、
またメニューの中で、山下市長の総仕上げのこの1年には何を優先
して取り組んでいくのでしょうか。
人口減少に対する危機感、地方創生2.0に関連して、山下市長の
本市の未来に向けたまちづくりの政治姿勢と施政方針のキーワード
でもある進歩とは、これ、昨年は選択肢でしたが、本年の進歩とは
具体的に何なのか。
施政方針にあるように、「革新や刷新が行われず、日本が進歩を
忘れていた」と書かれておりますが、ここは全くに同感であります。
世界全体の流れは、我々が感じているより驚異的な速さで進歩して
います。
気がついたら世界に、社会に取り残されているのです。
それでは、いつかの時代と同じ繰り返しになります。
まさに失われた30年です。全くそのとおりであるがゆえの進歩だと
思いましたが、それで合っているのでしょうか。
また、結びにある『戦艦大和ノ最期』の臼淵 磐大尉が士官たちに
語った言葉、山下市長の一つの指針となっていると書かれております。
私なりに理解するに、失われた30年で日本は進歩を忘れてしまい、
まず施政方針の節目とは、まさに今年は太平洋戦争が終わり80年目
の節目であり、この節目に先人の言葉を通して、私たちが改めて当事
者に寄り添い、自分事として捉え、未来につながるための重要な機会
を私たちは先人から、先人たちが歩んできた苦難や成功の歴史から
学び、未来へつなげ、子供たちから高齢者まで、皆が夢と希望を持ち
続けられる社会、豊かな生活を目指し、改めて日本、また本市を前に
進め続けられなければならないという思いの中で、まさに、
「One MITOYO~心つながる豊かさ実感都市~」を目指すという
理解なのかなと私は思いますが、その理解でよいのかお聞きしたいと
思いますので、よろしくお願いいたします。
●答弁1
清風会、浜口議員の御質問にお答え申し上げます前に、高瀬中学校
の皆さん、本当にようこそお越しいただきました。
なかなか難しい言葉もいっぱいあると思います。
その中で、一つお願いがあります。
皆さんで興味を持った言葉、一つでいいので覚えて帰って、それを調べる
ということをしていただけたらなと思います。
この質問でもよく出てきます、施政方針って何だろう。
そういうことを考えていただけたら、何か皆さんの今後のプラスになると
思います。
この場では、本当に市の大切なことを話し合っております。
ぜひそういうことをやっていただけたらと思います。
それでは、浜口議員の御質問にお答えいたします。
回答の順番が前後して申し訳ございませんが、まず2点目の市長の
本市、未来に向けた持続可能なまちづくりの政治姿勢と施政方針の
キーワードである進歩とはとの御質問ですが、本市はその誕生以来、
人口減少が続いており、その傾向は今後も続いていくものと予測
されております。
なので、大変厳しい危機感を持つ状況でございます。
しかしながら、そういった中にあっても、若者、女性にも選ばれる町、
高齢者も含めて、誰もが安心して住み続けられる町を実現し、10年後
も20年後も未来に向けて持続的に発展する本市を市民の皆様とつくり
上げていきたいと考えております。
そのときに重要なことが進歩であります。
社会や環境などが大きく変化する中で、これまでどおりのやり方を
続けるだけでは、守りたいものも守れなくなってしまいます。
例えば、本市の基幹産業である農業につきましても、農業生産者は
減り、耕作放棄地は増えておりますが、これまでどおりのやり方を
続けるだけでは、その傾向を変えることができないと思ったからこそ、
新たな取組として薬用栽培や有機栽培に取り組んできたのであり、
さらにスマート農業というテクノロジーを加え、強化を図っていきたい
と考えております。
このように、進歩とは単にデジタル化を進めるという話ではなく、
これまでもこうやってきたのだから、それを続ければよいと思考を
停止するのではなく、社会や環境の変化に合わせて柔軟に対応
する考え方を持ち、必要なら失敗を恐れず新しいものを取り入れ、
よりよい方向に、現状より一歩でも前に進めていくことだと考えて
おります。
それが既存の考え方を変えることもあれば、既存の手法を変える
こともあるのだと思います。
変えるべきは変える。変えないものは変えない。
そういった取組を積み重ねていくことによって、三豊市を持続的に
発展していく。
市民の皆さんの暮らしを守っていきたいと考えております。
次に、1点目の市長の総仕上げのこの1年には、何を優先して
取り組んでいくのかとの御質問ですが、令和7年度は合併特例債
の発行期限を迎えますので、大型建設事業をしっかりやりきること
が重要だと考えております。
その上で、施政方針に記載させていただいたスマート農業、地元
企業及び地元経済の革新やDXへの支援、放課後改革、国際バカ
ロレア教育など、進歩のための取組につきましては、今後の本市の
ため、いずれも重要な取組だと考えておりますので、しっかりと取り
組んでまいりたいと考えております。
最後に、3点目の結びにある『戦艦大和ノ最期』の臼淵大尉が士官
たちに語った言葉の意味を聞きたいとの御質問ですが、これは議員
が御指摘いただいたように、非常に私の考えの部分に近いものを
御示唆していただいたと思っております。
最初に申し上げましたように、節目というのは、議員御指摘のとおり、
この施政方針にも書かせていただきました。
先人の苦難や成功に学んで、未来へつないでいくという意味で、この
言葉を使わせていただきました。
これは引用でございますので、基本的に私がその言葉に対しての
解釈を添えるということは差し控えさせていただきたいと思います。
これはなぜかというと、臼淵大尉が本当に自分の死を前にして発した
言葉です。
その臼淵大尉の言葉自体の意味というのは、臼淵大尉の本人しか
分からない言葉でございますので、それを私がああだこうだと解釈
するよりも、皆さんがこの80年目の節目に自分事として何かを感じて
いただける、そういったことを望んで書かせていただきました。
そして、施政方針の中にも書かせていただきましたけれども、その
意味という部分では、本当に日本が戦後同じことを繰り返している
のではないのか。
失われた30年で何を失ったのか。そういったものをもう一度振り返る。
これはまさに節目のことであるというふうに考えております。
そういった意味では非常に御指摘の部分、私の考え方に近いもので
あると思っております。
ここの部分に関しては感謝申し上げたいと思います。
ですので、そういった意味では、皆さんも、できれば様々な節目に
おいて、今後もいろいろな形での自分たちの考え、自分が感じた
ものというものをこれから大事にして、そして前に進んでいく。
その原動力、進歩というものにつながっていく。
それを我々としては一緒に議員各位の皆様と進めてまいりたいと
思い、ここに書かせていただきました。戦後80年、我々が本当にもう
一度考えなきゃいけないもの、そういったものをここに、議会の中に、
三豊市議会の中に、私としては残しておきたいという思いがまず
ありました。
●質問2
大変すばらしいお考えをお聞きしまして、ありがとうございます。
次に、「みとよでスマイル~持続と豊かさ~」、四つの重点プロ
ジェクトの詳細をお聞きしていきます。
特に今回思いましたのは、この「みとよでスマイル~持続と豊かさ~」、
防災、健康福祉、インフラ、産業の充実といいますか、重点施策が多い
です。
施政方針の9ページ以上が割かれておりますが、この中で、防災全般
は同僚議員がお聞きしますので、私からは緊急防災・減災事業費の
対象事業が拡充されるとともに、特別交付税措置の制度の拡充に
ついてのみお聞きします。
画面を切り替えてください。
南海トラフ大地震に備え、緊急防災・減災事業費を活用する予定が
あるのかをお聞きいたします。
私の代表質問はいつもなんですが、地方財政対策から、総務省が
出しているところからの抜粋が多いんですが、緊急防災・減災事業債
というのは充当率です。
充当率100%かつ地方交付税措置率70%で、簡単に言いますと、
7割補助と同様の財源的な有利さがあります。
この緊防債、短く言ってあれなんですが、緊防債は過疎債の次に
有利な起債だと私は思いますが、これを有効に活用する予定がある
のかをお聞きいたします。
それと、本市も能登半島地震と同じく、詫間、仁尾両町で最大震度
7が予想される地域があります。
その上で、能登半島地震では、輪島市と珠洲市が市内の建物被害
を調べた結果、両市とも建物の3割以上が全壊でありました。
住宅の耐震診断と耐震対策、ちゅうちょしている市民を促進する
具体施策があるのかをお聞きします。
画面を切り替えてください。
特に、写真の最大震度7が予想される地域、赤い部分ですが、この
地域には優先して取り組むべきだと考えます。
どのようにお考えでしょうか。
また、みとよ市民病院を地域に根差した病院とするため、経営改善
に取り組んでいますが、十分な成果が出ていないということです。
それゆえ、今回の補正で一般会計から長期借入金2億3,000万が
計上されておりますが、全力で取り組んだ結果がこうなのか、これ
以上はどうしていくのか、市長の判断が必要です。
書かれているように、公立病院の経営状況はどこも厳しいところ
ばかりです。
コロナ以降、赤字経営がほとんどでありますが、私は「住民ニーズを
踏まえ」というところ、ここが一番重要だと感じます。
というのも、お正月に市民の方からお電話いただきましたけど、
行きたいと電話したら、どこの病院にかかっているのか、病気の
状況とか現在の状態をさんざん聞かれた挙げ句に、最後は先生
がいませんからと言われました。
それなら最初に言ってほしかったとか、ベッドが空いていませんと
強い口調で電話口で言われたとか、先生や看護師から少しきつい
言葉で言われましたなどの意見を多々お聞きしております。
最後は、本当に市民のための病院なんですかと言われる方がいます。
これ、本当にサービスの類いで、住民ニーズを捉え、市民病院は
駄目だという評判が広がりかねません。
一番に改善するべきであると思いますが、どのようにお考えでしょうか。
次に、三豊市の玄関口、また顔となるJR高瀬駅はどのように
考えているのかもお聞きいたします。
JR四国は人手不足などにより、高瀬駅2024年3月中旬から無人化
されております。
JRも民間企業です。
利用者観点から、なるべく早い整備をJR四国と協議いただきたい
のはもちろん、議会運営委員会で訪れたJR浜田駅には待合所に
自習スペースがありました。
これ、市の教育委員会が整備したそうですが、JR高瀬駅や詫間駅
にも欲しい。
それよりも駅の整備とともに、三豊市役所のある高瀬駅でICカード
が利用できるようにしてほしいと私は切に思いますが、どうでしょうか。
また、公共設置施設についても具体的な部分は同僚議員がお聞き
します。
清風会では、防災と公共施設再編は非常に重要だと感じますので、
2人から質問をしますが、私からは公共施設等適正管理推進事業債
についてお聞きします。
画面を切り替えてください。
総務省は、集約化、複合化を推進させるために、起債の充当を見直し
て、例えば施設の整備を行い、施設を統合する場合に、除却事業は
起債対象になっていましたが、交付税措置率の50%がありません
でした。
ただの除却はただの借金でしかできなかったのですが、機能統合
する除却であれば、50%の交付税措置する有利な起債が使える
ようになっております。
施設の整備は行わず、機能を統合する場合も同じで、もちろん、
公共施設等総合管理計画の進捗度を確認して、計画的に予算措置
されているかという確認はあります。
また、複数団体による公共施設の集約化、複合化に係る特別交付
税措置の創設もできました。
特別交付税措置が今回、この地方財政対策の中でたくさん出てきて
いるんですよ。
特別交付税をうまく取れれば私はいいかなと非常に思うんですが、
どうでしょうか。
また、昨年、交通システム事業団MiLAISが設立され、この事業団
の目標は何か、また地域公共交通をどうしていくのか、産・学・官、
香川高専や地元企業、スタートアップ企業の支援やDX、AIにはどの
ように取り組んでいくのか、市長の先ほどの答弁の中にもありました。
また、脱炭素経営認定制度とは何か、三豊市独自の脱炭素について
はどう取り組んでいるのか、いくのかをお聞きいたします。
●答弁2
浜口議員の御質問にお答えいたします。
高瀬中学2年3組B班。ようこそいらっしゃいました。
引き続き、議会を見ていてください。
それでは、浜口議員の御質問にお答え申し上げます。
質問が多岐にわたりますので、少し長くなりますことをお許しください。
南海トラフでは、令和7年1月1日現在、海溝型地震の30年以内の
発生確率が80%程度と評価され、大きな数値になっているのは、
地震発生が切迫していることを示しております。
南海トラフ地震が発生すれば、甚大な被害を及ぼす可能性が
あるため、日頃から耐震補強や家具の固定などの対策を講じること
が重要です。
緊急防災・減災事業債を活用する予定につきましては、全国的に
緊急に実施する必要性が高く、即効性のある防災減災のための
地方単独事業等が緊急防災・減災事業債の対象となっており、
これまでも防災センターの建設や防災行政無線更新事業などで
活用しております。
充当率100%で、元利償還金の70%を地方交付税措置される有利
な財源であり、対象事業も拡充されてきておりますので、消防施設
や防災資機材の更新など整備を進めております。
次に、耐震対策にちゅうちょしている市民への具体策につきまして
は、ちゅうちょする理由としては、高額な改修費用、耐震対策への
疑問、手続が分からない、未耐震住宅の所有者に高齢世帯が多い
ことなどが考えられます。
引き続き、無料相談会や地域の防災訓練などの機会を捉えて、
低コスト工法の紹介や補助制度の丁寧な周知等に努めてまいり
ます。
また、市内でも最大震度が高い地域等を耐震化重点エリアに
設定し、住民の耐震化を進めるため、香川県と連携して戸別訪問
を実施しました。
また、震度7が想定される自治会の防災研修会へ参加し、建物
被害を減少する啓発を行いました。
なお、令和6年度の本市における民間住宅耐震対策支援事業
については、能登半島地震や南海トラフ地震臨時情報の発表など
を背景として、市民の危機意識が高まり、耐震診断は、前年度比
の約6倍となる64件、簡易改修等を含む耐震改修工事は3倍の
30件と大幅に増加いたしました。これにとどまることなく、市民の
耐震対策に対する機運が高まっているこの機を逃さずに取り組ん
でまいりたいと考えております。
次に、みとよ市民病院の方向性につきましては、議員御案内の
とおり、令和5年度に三豊市公立病院経営強化プランを策定し、
経営改善に取り組んでおります。
市民の皆様からの御意見も賜りながら進めておりますが、公立
病院の経営状況は全国的にも厳しいものがあると考えております。
施政方針でも触れさせていただきましたが、公立病院の役割は、
収益だけで語れるものではありませんが、現下の状況改善は
間違いなく大きな課題であります。
いずれにいたしましても、病院職員一人一人が現在の厳しい
経営状況を認識した上で、各部署が具体的な行動計画を策定し、
安定した経営状態のもとで、市民の皆様が求めている安全で
良質な医療を継続的に提供していける病院、また、職員の意識
改革を進めるとともに、患者ファーストに努め、選ばれる病院と
なるよう取り組んでまいります。
次に、JR高瀬駅の整備についてでございます。
令和7年度中の完成を目指し、JR四国と共同で計画を進めて
おります。
整備の主な内容としては、これまでに特に要望の声が多く寄せ
られていたトイレについて、どなたも安全かつ衛生的に利用できる
よう整備するとともに、駅利用者の滞在空間や市民が集える
パブリックスペース、そして駐輪場を建設いたします。
また、駅前広場においては、交通結節点としての機能を強化
するため、コミュニティバスの乗り入れができるロータリーを新設
し、鉄道とバス、両公共交通の乗り継ぎのシームレス化を図る
ほか、敷地内における車両や歩行者の安全性確保も考慮して
設計を進めております。
御質問の改札における交通系ICカードの対応につきましては、
これまでも市民からの要望もありましたが、JR四国からは導入
には多額の初期投資、将来の更新費用を要するため、当面の間、
ICカードの利用可能駅の拡大は見送っている。四国内のお客様
にはチケットアプリの利用を推進しているとのことでした。
いずれにいたしましても、今回の駅舎建て替えを契機に、本市の
玄関口として、皆様に快適に御利用いただける駅になることは
もちろんのこと、改善と新たな機能の付加により、人の流れや
交流を生み出す拠点となるよう整備してまいります。
次に、公共施設等適正管理推進事業債の利活用につきまして
は、議員御案内のとおり、総務省より発表されました令和7年度
地方財政対策の概要によると、公共施設等適正管理推進事業債
につきましては、公共施設等総合管理計画等に基づいて実施する
公共施設の集約化、複合化等に伴う施設の除却事業が対象に
追加されることとなりました。
これまで有利な合併特例債を活用し、事業を実施してまいりました
が、特例債終了後には、公共施設等適正管理推進事業債を活用
してまいりたいと考えております。
また、公共施設の除却債については、交付税措置の対象では
ありませんが、今回追加されることで、公共施設を解体する必要
がある場合においても、条件付ではありますが、有効活用できる
起債であると考えております。
市にとって一番有利な条件で事業実施ができるよう努めてまいり
たいと考えております。
次に、交通システム事業団MiLAISの目標、また、地域公共交通
につきましては、一般社団法人三豊交通システム事業団MiLAIS
については、昨年7月29日に設立され、その目標としては、人口減少
や人口構造の変化、さらにはライフスタイルの多様化の影響で移動
困難者が増え、交通、移動ニーズの高度化が進む中で、本市の
地域公共交通計画の基本理念である全ての人が「行きたいときに
行きたいところへ行けるまち」を享受し、持続するまちで豊かに幸せ
に暮らし続けられるよう、地域におけるモビリティに関する課題解決
を目指すこととしております。
具体的には、市内交通事業者や地域の皆様のハブとなりながら、
あらゆる移動手段の確保に努めてまいります。
本市の運転免許証自主返納者数は、過去10年間で申し上げます
と3,604人、年間平均約360人の方が自ら移動することを断念し、
誰かに頼らなければ行きたいところへ行くことができない状況と
なっております。
このような中で、日常生活の最も基盤となるエリアでのファースト
ワンマイル、ラストワンマイルの課題も解決しなければなりません。
過去の御質問でもお答え申し上げましたように、詫間町、大浜地域
でこれらワンマイル解決に向けた移動サービスの事業が地域の
皆さんや事業者の御協力を頂きながら形になってまいりましたので、
これをモデルとなるようさらに進めてまいりたいと思います。
さらに、高齢化に伴う移動困難者の増加の一方、生産年齢人口
の減少の影響は、運転士を含む働き手不足にも及んでいます。
国立社会保障・人口問題研究所の人口推計によれば、2050年の
生産年齢人口は、現在の約3万人弱から約1万9,000人と、およそ
37%の減少が予測されており、社会全体の働き手の確保が極めて
困難な時代が到来することとなります。
これらの状況を踏まえ、先ほど申し上げた将来の人口や暮らしの
在り方も見据え、日常生活を支える地域公共交通の構築を進める
とともに、市民の皆様、市内事業者各位、さらには、あらゆる分野
の人、物、時間、空間を最大限に活用し、持続できる地域をつくり
上げていまいらなければならないと考えておりますので、御理解、
御協力を賜りますようお願い申し上げます。
次に、産・学・官、特に香川高専や地元企業とのDXやAIの取組
につきましては、香川高等専門学校とは、これまでも学・官連携に
基づき、様々な取組を実施してきておりますが、地元企業の革新
やDXを支援するため、さらに連携強化を進めていきたいと考えて
おります。
現在、将来的な香川高専の学生の起業にもつなげていくことを
目指し、香川高専が抱える学生が地域と接点を持てておらず、
地域に入り込めていないという課題を解決するため、まずは、
高専生に実際に地域に出てもらう機会をつくりながらアイデア
ソンを実施することを検討しておりますが、学生がキャンパスの
外で経験を重ね、学生が持つ知識や技術を課題解決に生かせる
よう取組を進めていきたいと考えており、そういった取組の先で
実際に起業してもらうことができれば、地元企業の進歩、イノベー
ションにもつながっていくものと考えております。
なお、地元企業に対するDX支援としては、今年度からリスキ
リング事業をはじめ、技術的な研修だけでなく、地元企業の優良
事例を聞く機会の提供を通じて、経営者の意識改革や社員の
DXマインドの醸成とスキルの向上を目指しております。
DXやAIの分野については、日々進化を続けておりますので、
市内に高専があるという優位性を十分に生かし、地元企業に
支援をしてまいりたいと考えております。
次に、脱炭素経営認定制度とは、市内の中小企業の皆様に
中長期的な支援を行うことで、脱炭素経営を推進し、市域全体
の企業の価値向上を目指すものであります。自社のCO2排出量
を算定し、2030年度までの取組や削減目標値を設定した削減計画
を策定、市へ認定申請していただき、市は計画内容を審査し、適切
であると認めた場合には認定証を交付いたします。
また、削減計画の達成状況によって、市が表彰することにより、
企業価値の向上や宣伝効果にもつながると考えております。
一方、三豊市独自の脱炭素ですが、温室効果ガスを削減していく
だけでなく、本市の豊かな自然を守りながら、吸収量を増やしていく
ことです。
豊かな生物多様性は人類存続の基盤であり、その上に社会があり、
さらにその上に経済が成り立っていかなければなりません。
現在、進行中のものを申し上げますと、本市の海域においては、
藻場の再生について実証が行われております。
実現できれば、豊かな海を現在から将来へ引き継ぐことができる
ことだけでなく、海藻はCO2を吸収します。これらの取組を進めて
いき、海だけでなく、陸地においても検討してまいります。
削減と吸収、そして自然を守ることを同時に進めていくことによって、
新たな価値を生み出していきたいと考えております。
●意見2
1点だけ、病院です。
公立邑智病院、三豊総合病院で視察した会派の議員に無理言って
私、資料頂いたんですが、ここの石原名誉医院長が邑智病院を時々
訪ねて、病院というものは、職員が楽しく働ける職場になれば、自然
に患者に優しい優良な病院になる!と言い続け、風通しのよい職場、
明るい雰囲気の快適な職場を皆でつくり上げて、地域住民に満足
していただく病院になっているそうです。
私はこの職員が楽しく働ける職場にするというのが一番に大事だと
思いますので、それだけ申して次に行きます。
以上、明日に続く・・・。
Posted by はまぐちふどうさん at 09:03│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。