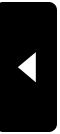2024年12月28日
私の一般質問(その1)水産業の振興
私の49回目の「一般質問」は以下の2問でした。
1.水産業振興について
本市の水産業では、漁獲量の低下と魚価の低迷、後継者不足さらには
燃料費などの高騰により経営環境が厳しくなっているが、どのような振興
策を講じて、支援を行っていくのか。
その上で陸上養殖の可能性についても検討しているのか、を聞く。
また環境についても海水温の上昇、「海が変わった」という点での海底の
砂地やアマモの減少について、特に「藻場」の再生事業については、試行
的な段階の中で、本市の取組支援の現状を聞きたい。
2.子育て支援について
2023年4月に、こども家庭庁が発足し、同年12月には、若い世代の将来
展望を描けない状況や子育てをされている方の生活や子育ての悩みを
受け止めて、「こども未来戦略」が策定されている。
こども家庭庁HP上には「こども未来戦略MAP」も公開されているが、主な
施策である
(1)子育て世帯の家計を応援(住宅支援)
(2)すべてのこどもと子育てを応援(伴走型相談支援、こども誰でも通園
制度)
(3)共働き・共育てを応援(男性育休取得推進)
などの取り組みについて、MAP上の財政支援措置の本市の取組状況、
今後の方針を聞く。
その上で、自治体のこども政策の縦割りを一元化したり、こども子育て
支援センター(仮称)の整備方針、就学前施設の在り方や今後の整備
方針、保育士の処遇改善なども聞きたい。
1問目から公開します。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
初めに、水産業振興についてお聞きをいたします。
令和6年の施政方針にありました本市の水産業においては、漁獲量の
低下と魚価の低迷、後継者不足、さらには燃料費などの高騰により、
経営環境が本当に年々厳しくなっております。
どのような振興策を講じて支援を行っていくのかをお聞きいたします。
その上で、施政方針に書かれている陸上養殖の可能性についても
検討しているのか、検討したのかもお聞きしたいと思います。
漁獲量の低下については、その背景に、温暖化による海水温の上昇
やプランクトンの減少など、生態系の影響が最も危惧されております。
要は環境についてですが、海水温の上昇で海が変わったという点での、
海底の砂地やアマモの減少について、特に海草や海藻が群生する藻場
の再生を起点に瀬戸内海の保全を目指す産・官・学プロジェクトがつい
最近立ち上がり、11月6日に詫間町の荘内半島で調査が行われております。
瀬戸内渚フォーラムという名のプロジェクトですが、東京の海洋環境を研究
するベンチャー企業が企画し、この会社が中心となって、企業、団体、大学、
また自治体などが参画し、本市詫間町の企業がメインで参画をしております。
自治体では三原市が参画しておりますが、この事業についても試行的な
段階の中で、本市の取組支援ができると考えますが、当局の考えをお聞き
いたしますのでよろしくお願いいたします。
●答弁1(山下昭史市長)
近年、瀬戸内の漁業を取り巻く環境は、議員御指摘のとおり、資源の減少
や漁業従事者の高齢化、後継者問題に加え、原油価格の高騰や魚価の
低迷など非常に厳しい状況であります。
昨年11月1日を基準日として実施した漁業センサスの速報が今年8月に公表
されておりますが、香川県全体の漁業経営体は970で、5年前と比べて264
経営体、率にして21.4%減少しています。本市においても66から50経営体へ、
率にして県全体を上回る24.2%減少しており、販売額についても同様の傾向
が見られるところであります。
現在、本市の漁業は、令和2年8月に、市内4漁協のうち3漁協が合併して
発足した三豊市漁業協同組合と詫間漁業協同組合を中心としてその振興が
図られているところであります。御質問の市独自の水産振興支援についてで
ございますが、これまで平成21年に設置いたしました三豊市漁業振興基金を
財源として、市内の漁業組合等が行います漁業近代化施設整備、担い手対策、
水産物販売促進事業などの取組について支援しているところです。
昨年度の実績といたしましては、漁港設備整備など8件の事業に対して支援を
させていただいております。
また、市内の各漁協からの放流魚種の要望を踏まえ、キジハタ、マダコ等の
種苗を沿岸漁場に放流することで、市独自での栽培漁業に係る水産資源の
維持などの支援にも取り組んでいるところであります。
続きまして、陸上養殖の可能性を検討しているのかについてですが、近年、
水産物に対する世界的な需要の急速な高まりを背景に、陸上養殖は、気候
など外的要因に左右されない供給の安定化と海洋資源の持続可能な生産
方式として注目されています。
対象種によっては、既に事業化されているものもありますが、まだまだ実証
段階のものも多く、コスト面や技術面での課題が多くある状況のようです。
陸上養殖は技術の発展により、一口で陸上養殖といっても様々な形態が
あるようです。
例えば、海水を利用せず魚を育てる技術や、地下海水を引込み、魚の品種
改良で成長を促す技術などがあります。
実際、本市でも、民間企業が地元企業と連携して陸上養殖を検討したよう
ですが、海水成分の問題で断念したと聞いております。
ただ、現在の瀬戸内海の環境の変化、これに伴う魚種の変化と漁獲量の
減少は本市の漁業に多大な影響を与えています。
こうした中で、陸上養殖は新たな漁業の選択肢の一つとして有効であると
考えます。
農業を含めた第一次産業が直面する危機に対しては、本市も専門機関や
民間企業と連携して取り組んでまいります。
最後に、藻場の再生作業についてでございますが、議員御紹介のとおり、
近年、海水の栄養不足が指摘されている瀬戸内海の保全を目指す産・官・
学のプロジェクト、瀬戸内渚フォーラムがスタートしています。香川、岡山、
広島などの各県を中心に、趣旨に賛同した民間企業や団体、行政が参画
し、海の生態系を支える藻場の再生を起点として、豊かな海の保全活動に
連携して取り組むものです。
このプロジェクトに本市も参加しております。
プロジェクトは3か年計画で、既に1年目として、三豊市内においても現地
調査を実施しております。
海の砂漠化とも言われる磯焼けの危機を回避し、豊かな海の復活は、
漁業振興はもちろんのこと、海藻は光合成をする際にCO2を吸収し、温暖
化の抑制にもなり、脱炭素にも関わってきます。
このブルーカーボンの観点からも、藻場の減少は逆に温暖化を進めてしま
うことにもなりかねません。
藻場の再生による豊かな海の復活と脱炭素というテーマにおいては、瀬戸
内渚フォーラムは私も期待をしているところであります。
いずれにいたしましても、重要なのは、本来の瀬戸内海の豊かさを取り
戻すことであります。
このために、引き続き行政として部局を越えた連携を行い、協力できる限り
のことは進めていく考えであります。
●再質問1
ありがとうございます。画面を切り替えてください。
瀬戸内渚フォーラムの3か年計画で、瀬戸内海の5か所で藻場調査が実施
されております。
今、市長も言っていただきましたが、瀬戸内渚フォーラムのプロジェクトに
参加をしているというのを聞いて安心いたしました。
次の画面をお願いします。活動予定域が玉野市胸上、瀬戸内市牛窓、尾道、
三原、三豊市となっております。三原市とは連携して自治体として参画して
おりますので、いろいろ情報交流もしていただきたいところでございます。
また、陸上養殖についても、農業を含めた一次産業が復活しないといけません。
市長の言われるよう専門機関や民間企業との連携を応援したいところであり
ます。
まずは、水産業振興から再質問いたします。
漁協の現状、先ほど答弁もありましたが、三豊市内では3漁協が合併した
三豊市漁業協同組合は、令和5年の組合数が125名で、正組合員59名、
准組合員が66名だそうですが、令和2年8月1日の合併時には160名の
組合員がいました。
2年間で22%以上も減っております。
単一でのたくま漁業協同組合は組合員数58名で、直近の正組合員数が
25名、准組合員数が33名で、正組合員が20名以下になると合併しない
といけないそうであります。
漁業関係者にもお話を伺ってきましたけど、やはり合併の検討もしないと
いけない、そこの部分は県または市が指導、指南してほしいとおっしゃって
いました。
その辺り、非常にデリケートではございますが、今後御検討も頂きたいと
思います。
その上で、やはり担い手不足、後継者不足の中で、新規の漁師希望は
香川漁業塾で学んでいただく、言わばがっつり系が多く、やはり週末漁師
や兼業の漁師といいますか、ライトなところから漁師を体験、経験してもら
うことが重要であります。
例えば大人であれば漁師体験もして、子供であれば中学生の職場体験
も危なくないところから経験してもらいたい。
詫間中学校は職場体験は漁業はありません。
広く漁業を知っていただく必要があるかと思います。
地域の移住者が中心となって漁業の親子体験をやられているようで、ここ
は敬意を表しますが、継続するためにも、当局が県や漁協と協力して、
関与、サポートがもっとできるところかと思います。
いろいろなことをやっているのは分かっているんですが、もっとやっぱり
やらないと、組合数、漁師の数が減っていくということなので、その辺り
どのようにお考えでしょうか、お聞きいたします。
次に、水産業の基盤の確立という点では、やはり養殖業での安定的
収入が必要になるかと思いますが、カキの養殖も後継者不足やその年
の気候に左右されますし、過去にはノリの養殖も盛んでしたが、今、
三豊市内にはありません。
これも生育不良や色落ちに左右されたり、機械などが高額で、瀬戸内海
でもほとんどが縮小しておりますが、今、詫間漁協ではヒジキの養殖が
試験的に行われようとしております。ロープ一本でできる養殖であり、
高知の会社と連携して今治市でも取り組まれているようで、私の実家の
下でも行われるみたいですが、これ一つ試験的にやろうとしても、くい
打ちなどでも県の許可申請から占有許可が必要となり、1平米当たり
60円の費用がかかります。
来年度拡大して、広く試験養殖を行うとすれば、もっとお金がかかると、
この辺りが試験養殖なんですから、減免措置とか、お金は試験養殖時
には要らないから、市から出してほしい。
私はこの辺りこそ漁業振興基金が使われるべきだと思いますし、漁業
の振興が大切やと言いながら、漁師がもうかっていないのに新しいこと
をやるにはお金はきっちり払ってくださいという点は、私は矛盾している
と思いますが、どうでしょうか。
また、夏でも身やせしにくく、環境に優しい、その上通年出荷が可能な
3倍体カキが検討されています。
3倍体カキは、生殖機能を抑制して育成された卵を産まないカキであり、
産卵にエネルギーを使わず、成長のみに使えるため、大きく育つ上に、
産卵して痩せ細ることがなく、年間を通して安定した身入りとなります。
また、これは遺伝子組換えではありません。
カキのほかにはニジマスやサーモンなどの養殖も全国で行われている
ようですが、これは養殖海域にもともといるカキと交雑個体を残しにくい
ことを意味し、地域固有特性の消失やこれに伴う特定疾病の感染拡大
を防ぐことにつながることから、SDGsで提唱されている海の豊かさを
守ろうという目標達成にも大きく貢献するようで、これらも試験的に研究
をしているそうであります。
そこを当局は県とも連携して、応援サポートしていくべきだと思います。
どうでしょうか、再質問をいたします。
●答弁2(大矢哲也農政部長)
最初に、漁協の合併に関してでございます。
これは組合ですので、自主的な活動により合意形成が図られ、実現
されるというような認識でございますが、市といたしましても、令和2年の
三豊市漁業協同組合が誕生した際の経験もございます。
より身近な行政として、その役割をしっかり果たしてまいりたいと考えて
ございます。
次に、漁業体験についてでございますけれども、こうした活動を通して、
漁業や瀬戸内海の資源への興味、理解を深めてもらうと同時に、自然
や食など豊かな学びにも寄与する水産振興に非常に有意義な取組で
あると考えます。市といたしましても、こうした取組が一層広がるよう
環境づくりを模索してまいりたいと思います。
次に、漁協が導入を検討し進めているヒジキや3倍体カキの新しい
取組、これを応援すべきではないかという御意見でございます。
こうした新たな取組に対しましては、市独自の漁業振興基金を財源と
した産地形成支援事業の活用も可能でございますので、早急に関係
機関と連携して対応をしてまいりたいと思います。
●再質問2
環境についてなんですが、海水温の上昇で海が変わったという点での
エビデンスがあります。
燧灘の水温が災害クラスに上昇しているそうであります。世界の海面の
平均気温が2023年3月以降、過去最高を記録したまま下がらない状態
が続いていますが、これが影響している可能性が高いということです。
また、窒素やリン、カリウムなどの天然素材がバランスよく継続して溶け
出す海域肥料を三豊市漁協もまいているようですが、海がきれいになり
過ぎているとの声もよくお聞きします。
海が変わったという点での安定的収入につながるべく、陸上養殖の
可能性も、本当に私も応援したいと思いますが、SDGs未来都市、第2
期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、世界中のサンゴ礁の
観察、研究分析、廃プラのごみの活動をしているタラ財団と連携して、
瀬戸内の環境保全に努め、市民の環境に対する意識啓発を図ると
いう点で、本市のSDGs未来都市、目標計画は理解しますが、やはり
瀬戸内渚フォーラムに参画するんですから、藻場の再生、SDGsで
提唱されている海の豊かさを守ろうという上記にプラスして、藻場の
調査から群生までを三豊市から発信して、豊かな海を守り広げて
ほしいと切に思っております。
私が子供の頃、40年以上前ですが、シャコとかイカナゴ、アサリなど
の貝類が今はいなくなって、今はタコやワタリガニも少ない。
アイゴ、これが藻を食べる魚として繁殖しています。
取って食べてほしいんですということですが、私もこのアイゴはよく知って
いるんですけど、とげがあって危険なんですが、身はおいしい魚です。
何とマグロが瀬戸内海でとれる時代になっています。
市長答弁にあった、重要なのは本来の瀬戸内海の豊かさを取り戻すと
いう点です。
豊かな、かつていた魚介類をこの三豊市から復活、発信させるべきで
あると考えますし、この辺りの調査研究もしてほしいところです。
特に、ワタリガニ、私ども荘内半島ではガネと言いますけど、私の亡く
なったおじもガネ網をやっていたんですが、ワタリガニも少ない中、先日
市長とお話していた中で、ワタリガニの試験的養殖ができないかなと
言っていましたけど、私は何からでも取り組むべきだと考えております
が、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁3(大矢哲也農政部長)
藻場の調査から群生までを三豊市から発信し、広げてはどうかといった
ことにつきましては、現在、県の海域レベルにおいて、栄養塩の管理や
モニタリング、藻場の種まきなどが行われているところでございますが、
議員御案内のとおり、三豊市漁協でも独自に藻場の回復に向け、仁尾
町蔦嶋周辺でアマモ再生事業に取り組んでいるところでございます。
こうした取組に関しましては、答えがすぐに出るという性質のものでは
ございませんが、引き続き地元漁協の声を聞きながら、県など関係
機関と連携して前に進めてまいります。
次に、ワタリガニの試験養殖に取り組んでいくべきではとのことでござ
いますけれども、気候変動に伴い、海水温の上昇や磯焼けの拡大など、
いろいろな形で漁場の環境に変化が広がっております。
時代とともに変化する海に対しましては、議員御指摘のきれいな海から
豊かな海への取組、また試験養殖といった新たなチャレンジができる
環境づくりを進めることが、本市水産振興となるものと考えております
ので、今後とも地元漁協と連携し、こうした取組に関しましてはできる
限りの対応を行ってまいります。
●再質問3
市長からブルーカーボンの答弁がありました。
森林などが吸収するCO2をグリーンカーボンと呼ぶのに対して、海藻
などの海の植物によって海中や海底に吸収・埋没されるCO2のことを
ブルーカーボンと呼びます。
ブルーカーボンとは、海中、海面付近にある生態系によって吸収・貯留
をされた炭素のことでありますが、陸地にある森林などが吸収・貯留した
炭素のグリーンカーボンと区別するために呼び分けがされております。
温暖化対策と海の豊かさを取り戻すこと、私たちの直面する課題の中
では、この二つは最も最重要課題の二つと言えますが、この二つの課題
の両方に効く取組がブルーカーボンなんですから、ESGも関係して、この
辺り、ブルーカーボンは採算がとれないと言われております中、山下市長
の大変好きなところですし、熱海でも藻場が減少していることを知り、地元
の皆さんと協力しながら藻場の再生を中心としたブルーカーボンプロジェ
クトが進められています。
ブルーカーボンプロジェクトは地元に小さな循環をつくるという意味で、
地域循環共生圏の取組でもありますが、本市も率先して取り組んで
みてはどうですか、最後に質問をいたします。
●答弁4(米谷明洋市民環境部長)
浜口議員のブルーカーボンにつきましての再質問にお答え申し上げます。
グリーンカーボン、ブルーカーボンは、自然豊かな三豊市にとってはCO2
の吸収を進めていく上で欠かせない分野であると認識をしております。
グリーンカーボンやブルーカーボン、そして脱炭素につきましては、行政
だけでは前へ進めることはできませんので、議員御紹介の熱海のブルー
カーボンプロジェクト推進協議会のような組織を立ち上げて推進力を高め
ていくことも、十分検討をしていかなければなりません。
現在は、先ほど申し上げました瀬戸内渚フォーラムが本市の中において
活動を展開をしておりますので、こちらについて協力していきながら、さら
なる高みについて意見を交わしていきたいと思っております。
そして、将来的にはその活動が自然保護や生物多様性につながって、地域
循環、また自然資源の活用にもつながるよう模索しながら進めていきたいと
思っております。
●再質問4
ブルーカーボンについて、今の件について市長答弁があればお願いしたい
ところです。
●答弁5(山下昭史市長)
浜口議員の再質問にお答えいたします。
ブルーカーボンの答弁というよりも、今回のこの議論において、やっぱり
我々は思わなきゃいけないのは、ブルーカーボンをやればいいのと、漁業
関係を何とかしろという部分で、何か別のように捉えがちなんですけど、
実は全てがつながっているということを、我々も含めて、また市民の皆さん
にも御理解いただけたらなと思います。
ブルーカーボンの取組は、すなわち藻場を再生することであったりとか、
藻場がそのままCO2の固定化をするというところを御理解いただいて、
藻場ができれば小魚も育つ、海の揺り籠と言われた瀬戸内海が今は揺り
籠ではなくなっているということ、小魚が隠れる場所、育つ場所、産卵でき
る場所というのがなくなっている。
そこを守ることによって基本的には、漁師さんが生計を保つ漁獲量である
とか魚種がよみがえってくるという流れであります。
一方で、粟島で取り組んでいるタラ財団の活動も、マイクロプラスチック
をなくすということであります。
だから、我々としては再生の部分と、そしてもうこれ以上海の生態系を
壊さないということ、これも同時にやっていかなきゃいけないということ
なので、全ての部分が密接につながっているんだということを我々は
分かった上で、行政の取組としても、本当に部局を超えた取組として
やっていかなきゃいけないなと。
それがすなわちはもう我々の生活そのものであるということだと思って
おります。
以上です。
●ありがとうございました。次の質問に行きます。

純粋に海が変わっています。
特に今年の夏の暑さで、水温も30℃以上になって、藻場や
魚も結構いなくなっていますね。
瀬戸内海と漁師を守る施策を考えていかないといけない!
私ができる範囲で考え、言い続けて、実行したいと思います。
1.水産業振興について
本市の水産業では、漁獲量の低下と魚価の低迷、後継者不足さらには
燃料費などの高騰により経営環境が厳しくなっているが、どのような振興
策を講じて、支援を行っていくのか。
その上で陸上養殖の可能性についても検討しているのか、を聞く。
また環境についても海水温の上昇、「海が変わった」という点での海底の
砂地やアマモの減少について、特に「藻場」の再生事業については、試行
的な段階の中で、本市の取組支援の現状を聞きたい。
2.子育て支援について
2023年4月に、こども家庭庁が発足し、同年12月には、若い世代の将来
展望を描けない状況や子育てをされている方の生活や子育ての悩みを
受け止めて、「こども未来戦略」が策定されている。
こども家庭庁HP上には「こども未来戦略MAP」も公開されているが、主な
施策である
(1)子育て世帯の家計を応援(住宅支援)
(2)すべてのこどもと子育てを応援(伴走型相談支援、こども誰でも通園
制度)
(3)共働き・共育てを応援(男性育休取得推進)
などの取り組みについて、MAP上の財政支援措置の本市の取組状況、
今後の方針を聞く。
その上で、自治体のこども政策の縦割りを一元化したり、こども子育て
支援センター(仮称)の整備方針、就学前施設の在り方や今後の整備
方針、保育士の処遇改善なども聞きたい。
1問目から公開します。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
初めに、水産業振興についてお聞きをいたします。
令和6年の施政方針にありました本市の水産業においては、漁獲量の
低下と魚価の低迷、後継者不足、さらには燃料費などの高騰により、
経営環境が本当に年々厳しくなっております。
どのような振興策を講じて支援を行っていくのかをお聞きいたします。
その上で、施政方針に書かれている陸上養殖の可能性についても
検討しているのか、検討したのかもお聞きしたいと思います。
漁獲量の低下については、その背景に、温暖化による海水温の上昇
やプランクトンの減少など、生態系の影響が最も危惧されております。
要は環境についてですが、海水温の上昇で海が変わったという点での、
海底の砂地やアマモの減少について、特に海草や海藻が群生する藻場
の再生を起点に瀬戸内海の保全を目指す産・官・学プロジェクトがつい
最近立ち上がり、11月6日に詫間町の荘内半島で調査が行われております。
瀬戸内渚フォーラムという名のプロジェクトですが、東京の海洋環境を研究
するベンチャー企業が企画し、この会社が中心となって、企業、団体、大学、
また自治体などが参画し、本市詫間町の企業がメインで参画をしております。
自治体では三原市が参画しておりますが、この事業についても試行的な
段階の中で、本市の取組支援ができると考えますが、当局の考えをお聞き
いたしますのでよろしくお願いいたします。
●答弁1(山下昭史市長)
近年、瀬戸内の漁業を取り巻く環境は、議員御指摘のとおり、資源の減少
や漁業従事者の高齢化、後継者問題に加え、原油価格の高騰や魚価の
低迷など非常に厳しい状況であります。
昨年11月1日を基準日として実施した漁業センサスの速報が今年8月に公表
されておりますが、香川県全体の漁業経営体は970で、5年前と比べて264
経営体、率にして21.4%減少しています。本市においても66から50経営体へ、
率にして県全体を上回る24.2%減少しており、販売額についても同様の傾向
が見られるところであります。
現在、本市の漁業は、令和2年8月に、市内4漁協のうち3漁協が合併して
発足した三豊市漁業協同組合と詫間漁業協同組合を中心としてその振興が
図られているところであります。御質問の市独自の水産振興支援についてで
ございますが、これまで平成21年に設置いたしました三豊市漁業振興基金を
財源として、市内の漁業組合等が行います漁業近代化施設整備、担い手対策、
水産物販売促進事業などの取組について支援しているところです。
昨年度の実績といたしましては、漁港設備整備など8件の事業に対して支援を
させていただいております。
また、市内の各漁協からの放流魚種の要望を踏まえ、キジハタ、マダコ等の
種苗を沿岸漁場に放流することで、市独自での栽培漁業に係る水産資源の
維持などの支援にも取り組んでいるところであります。
続きまして、陸上養殖の可能性を検討しているのかについてですが、近年、
水産物に対する世界的な需要の急速な高まりを背景に、陸上養殖は、気候
など外的要因に左右されない供給の安定化と海洋資源の持続可能な生産
方式として注目されています。
対象種によっては、既に事業化されているものもありますが、まだまだ実証
段階のものも多く、コスト面や技術面での課題が多くある状況のようです。
陸上養殖は技術の発展により、一口で陸上養殖といっても様々な形態が
あるようです。
例えば、海水を利用せず魚を育てる技術や、地下海水を引込み、魚の品種
改良で成長を促す技術などがあります。
実際、本市でも、民間企業が地元企業と連携して陸上養殖を検討したよう
ですが、海水成分の問題で断念したと聞いております。
ただ、現在の瀬戸内海の環境の変化、これに伴う魚種の変化と漁獲量の
減少は本市の漁業に多大な影響を与えています。
こうした中で、陸上養殖は新たな漁業の選択肢の一つとして有効であると
考えます。
農業を含めた第一次産業が直面する危機に対しては、本市も専門機関や
民間企業と連携して取り組んでまいります。
最後に、藻場の再生作業についてでございますが、議員御紹介のとおり、
近年、海水の栄養不足が指摘されている瀬戸内海の保全を目指す産・官・
学のプロジェクト、瀬戸内渚フォーラムがスタートしています。香川、岡山、
広島などの各県を中心に、趣旨に賛同した民間企業や団体、行政が参画
し、海の生態系を支える藻場の再生を起点として、豊かな海の保全活動に
連携して取り組むものです。
このプロジェクトに本市も参加しております。
プロジェクトは3か年計画で、既に1年目として、三豊市内においても現地
調査を実施しております。
海の砂漠化とも言われる磯焼けの危機を回避し、豊かな海の復活は、
漁業振興はもちろんのこと、海藻は光合成をする際にCO2を吸収し、温暖
化の抑制にもなり、脱炭素にも関わってきます。
このブルーカーボンの観点からも、藻場の減少は逆に温暖化を進めてしま
うことにもなりかねません。
藻場の再生による豊かな海の復活と脱炭素というテーマにおいては、瀬戸
内渚フォーラムは私も期待をしているところであります。
いずれにいたしましても、重要なのは、本来の瀬戸内海の豊かさを取り
戻すことであります。
このために、引き続き行政として部局を越えた連携を行い、協力できる限り
のことは進めていく考えであります。
●再質問1
ありがとうございます。画面を切り替えてください。
瀬戸内渚フォーラムの3か年計画で、瀬戸内海の5か所で藻場調査が実施
されております。
今、市長も言っていただきましたが、瀬戸内渚フォーラムのプロジェクトに
参加をしているというのを聞いて安心いたしました。
次の画面をお願いします。活動予定域が玉野市胸上、瀬戸内市牛窓、尾道、
三原、三豊市となっております。三原市とは連携して自治体として参画して
おりますので、いろいろ情報交流もしていただきたいところでございます。
また、陸上養殖についても、農業を含めた一次産業が復活しないといけません。
市長の言われるよう専門機関や民間企業との連携を応援したいところであり
ます。
まずは、水産業振興から再質問いたします。
漁協の現状、先ほど答弁もありましたが、三豊市内では3漁協が合併した
三豊市漁業協同組合は、令和5年の組合数が125名で、正組合員59名、
准組合員が66名だそうですが、令和2年8月1日の合併時には160名の
組合員がいました。
2年間で22%以上も減っております。
単一でのたくま漁業協同組合は組合員数58名で、直近の正組合員数が
25名、准組合員数が33名で、正組合員が20名以下になると合併しない
といけないそうであります。
漁業関係者にもお話を伺ってきましたけど、やはり合併の検討もしないと
いけない、そこの部分は県または市が指導、指南してほしいとおっしゃって
いました。
その辺り、非常にデリケートではございますが、今後御検討も頂きたいと
思います。
その上で、やはり担い手不足、後継者不足の中で、新規の漁師希望は
香川漁業塾で学んでいただく、言わばがっつり系が多く、やはり週末漁師
や兼業の漁師といいますか、ライトなところから漁師を体験、経験してもら
うことが重要であります。
例えば大人であれば漁師体験もして、子供であれば中学生の職場体験
も危なくないところから経験してもらいたい。
詫間中学校は職場体験は漁業はありません。
広く漁業を知っていただく必要があるかと思います。
地域の移住者が中心となって漁業の親子体験をやられているようで、ここ
は敬意を表しますが、継続するためにも、当局が県や漁協と協力して、
関与、サポートがもっとできるところかと思います。
いろいろなことをやっているのは分かっているんですが、もっとやっぱり
やらないと、組合数、漁師の数が減っていくということなので、その辺り
どのようにお考えでしょうか、お聞きいたします。
次に、水産業の基盤の確立という点では、やはり養殖業での安定的
収入が必要になるかと思いますが、カキの養殖も後継者不足やその年
の気候に左右されますし、過去にはノリの養殖も盛んでしたが、今、
三豊市内にはありません。
これも生育不良や色落ちに左右されたり、機械などが高額で、瀬戸内海
でもほとんどが縮小しておりますが、今、詫間漁協ではヒジキの養殖が
試験的に行われようとしております。ロープ一本でできる養殖であり、
高知の会社と連携して今治市でも取り組まれているようで、私の実家の
下でも行われるみたいですが、これ一つ試験的にやろうとしても、くい
打ちなどでも県の許可申請から占有許可が必要となり、1平米当たり
60円の費用がかかります。
来年度拡大して、広く試験養殖を行うとすれば、もっとお金がかかると、
この辺りが試験養殖なんですから、減免措置とか、お金は試験養殖時
には要らないから、市から出してほしい。
私はこの辺りこそ漁業振興基金が使われるべきだと思いますし、漁業
の振興が大切やと言いながら、漁師がもうかっていないのに新しいこと
をやるにはお金はきっちり払ってくださいという点は、私は矛盾している
と思いますが、どうでしょうか。
また、夏でも身やせしにくく、環境に優しい、その上通年出荷が可能な
3倍体カキが検討されています。
3倍体カキは、生殖機能を抑制して育成された卵を産まないカキであり、
産卵にエネルギーを使わず、成長のみに使えるため、大きく育つ上に、
産卵して痩せ細ることがなく、年間を通して安定した身入りとなります。
また、これは遺伝子組換えではありません。
カキのほかにはニジマスやサーモンなどの養殖も全国で行われている
ようですが、これは養殖海域にもともといるカキと交雑個体を残しにくい
ことを意味し、地域固有特性の消失やこれに伴う特定疾病の感染拡大
を防ぐことにつながることから、SDGsで提唱されている海の豊かさを
守ろうという目標達成にも大きく貢献するようで、これらも試験的に研究
をしているそうであります。
そこを当局は県とも連携して、応援サポートしていくべきだと思います。
どうでしょうか、再質問をいたします。
●答弁2(大矢哲也農政部長)
最初に、漁協の合併に関してでございます。
これは組合ですので、自主的な活動により合意形成が図られ、実現
されるというような認識でございますが、市といたしましても、令和2年の
三豊市漁業協同組合が誕生した際の経験もございます。
より身近な行政として、その役割をしっかり果たしてまいりたいと考えて
ございます。
次に、漁業体験についてでございますけれども、こうした活動を通して、
漁業や瀬戸内海の資源への興味、理解を深めてもらうと同時に、自然
や食など豊かな学びにも寄与する水産振興に非常に有意義な取組で
あると考えます。市といたしましても、こうした取組が一層広がるよう
環境づくりを模索してまいりたいと思います。
次に、漁協が導入を検討し進めているヒジキや3倍体カキの新しい
取組、これを応援すべきではないかという御意見でございます。
こうした新たな取組に対しましては、市独自の漁業振興基金を財源と
した産地形成支援事業の活用も可能でございますので、早急に関係
機関と連携して対応をしてまいりたいと思います。
●再質問2
環境についてなんですが、海水温の上昇で海が変わったという点での
エビデンスがあります。
燧灘の水温が災害クラスに上昇しているそうであります。世界の海面の
平均気温が2023年3月以降、過去最高を記録したまま下がらない状態
が続いていますが、これが影響している可能性が高いということです。
また、窒素やリン、カリウムなどの天然素材がバランスよく継続して溶け
出す海域肥料を三豊市漁協もまいているようですが、海がきれいになり
過ぎているとの声もよくお聞きします。
海が変わったという点での安定的収入につながるべく、陸上養殖の
可能性も、本当に私も応援したいと思いますが、SDGs未来都市、第2
期三豊市まち・ひと・しごと創生総合戦略の中で、世界中のサンゴ礁の
観察、研究分析、廃プラのごみの活動をしているタラ財団と連携して、
瀬戸内の環境保全に努め、市民の環境に対する意識啓発を図ると
いう点で、本市のSDGs未来都市、目標計画は理解しますが、やはり
瀬戸内渚フォーラムに参画するんですから、藻場の再生、SDGsで
提唱されている海の豊かさを守ろうという上記にプラスして、藻場の
調査から群生までを三豊市から発信して、豊かな海を守り広げて
ほしいと切に思っております。
私が子供の頃、40年以上前ですが、シャコとかイカナゴ、アサリなど
の貝類が今はいなくなって、今はタコやワタリガニも少ない。
アイゴ、これが藻を食べる魚として繁殖しています。
取って食べてほしいんですということですが、私もこのアイゴはよく知って
いるんですけど、とげがあって危険なんですが、身はおいしい魚です。
何とマグロが瀬戸内海でとれる時代になっています。
市長答弁にあった、重要なのは本来の瀬戸内海の豊かさを取り戻すと
いう点です。
豊かな、かつていた魚介類をこの三豊市から復活、発信させるべきで
あると考えますし、この辺りの調査研究もしてほしいところです。
特に、ワタリガニ、私ども荘内半島ではガネと言いますけど、私の亡く
なったおじもガネ網をやっていたんですが、ワタリガニも少ない中、先日
市長とお話していた中で、ワタリガニの試験的養殖ができないかなと
言っていましたけど、私は何からでも取り組むべきだと考えております
が、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁3(大矢哲也農政部長)
藻場の調査から群生までを三豊市から発信し、広げてはどうかといった
ことにつきましては、現在、県の海域レベルにおいて、栄養塩の管理や
モニタリング、藻場の種まきなどが行われているところでございますが、
議員御案内のとおり、三豊市漁協でも独自に藻場の回復に向け、仁尾
町蔦嶋周辺でアマモ再生事業に取り組んでいるところでございます。
こうした取組に関しましては、答えがすぐに出るという性質のものでは
ございませんが、引き続き地元漁協の声を聞きながら、県など関係
機関と連携して前に進めてまいります。
次に、ワタリガニの試験養殖に取り組んでいくべきではとのことでござ
いますけれども、気候変動に伴い、海水温の上昇や磯焼けの拡大など、
いろいろな形で漁場の環境に変化が広がっております。
時代とともに変化する海に対しましては、議員御指摘のきれいな海から
豊かな海への取組、また試験養殖といった新たなチャレンジができる
環境づくりを進めることが、本市水産振興となるものと考えております
ので、今後とも地元漁協と連携し、こうした取組に関しましてはできる
限りの対応を行ってまいります。
●再質問3
市長からブルーカーボンの答弁がありました。
森林などが吸収するCO2をグリーンカーボンと呼ぶのに対して、海藻
などの海の植物によって海中や海底に吸収・埋没されるCO2のことを
ブルーカーボンと呼びます。
ブルーカーボンとは、海中、海面付近にある生態系によって吸収・貯留
をされた炭素のことでありますが、陸地にある森林などが吸収・貯留した
炭素のグリーンカーボンと区別するために呼び分けがされております。
温暖化対策と海の豊かさを取り戻すこと、私たちの直面する課題の中
では、この二つは最も最重要課題の二つと言えますが、この二つの課題
の両方に効く取組がブルーカーボンなんですから、ESGも関係して、この
辺り、ブルーカーボンは採算がとれないと言われております中、山下市長
の大変好きなところですし、熱海でも藻場が減少していることを知り、地元
の皆さんと協力しながら藻場の再生を中心としたブルーカーボンプロジェ
クトが進められています。
ブルーカーボンプロジェクトは地元に小さな循環をつくるという意味で、
地域循環共生圏の取組でもありますが、本市も率先して取り組んで
みてはどうですか、最後に質問をいたします。
●答弁4(米谷明洋市民環境部長)
浜口議員のブルーカーボンにつきましての再質問にお答え申し上げます。
グリーンカーボン、ブルーカーボンは、自然豊かな三豊市にとってはCO2
の吸収を進めていく上で欠かせない分野であると認識をしております。
グリーンカーボンやブルーカーボン、そして脱炭素につきましては、行政
だけでは前へ進めることはできませんので、議員御紹介の熱海のブルー
カーボンプロジェクト推進協議会のような組織を立ち上げて推進力を高め
ていくことも、十分検討をしていかなければなりません。
現在は、先ほど申し上げました瀬戸内渚フォーラムが本市の中において
活動を展開をしておりますので、こちらについて協力していきながら、さら
なる高みについて意見を交わしていきたいと思っております。
そして、将来的にはその活動が自然保護や生物多様性につながって、地域
循環、また自然資源の活用にもつながるよう模索しながら進めていきたいと
思っております。
●再質問4
ブルーカーボンについて、今の件について市長答弁があればお願いしたい
ところです。
●答弁5(山下昭史市長)
浜口議員の再質問にお答えいたします。
ブルーカーボンの答弁というよりも、今回のこの議論において、やっぱり
我々は思わなきゃいけないのは、ブルーカーボンをやればいいのと、漁業
関係を何とかしろという部分で、何か別のように捉えがちなんですけど、
実は全てがつながっているということを、我々も含めて、また市民の皆さん
にも御理解いただけたらなと思います。
ブルーカーボンの取組は、すなわち藻場を再生することであったりとか、
藻場がそのままCO2の固定化をするというところを御理解いただいて、
藻場ができれば小魚も育つ、海の揺り籠と言われた瀬戸内海が今は揺り
籠ではなくなっているということ、小魚が隠れる場所、育つ場所、産卵でき
る場所というのがなくなっている。
そこを守ることによって基本的には、漁師さんが生計を保つ漁獲量である
とか魚種がよみがえってくるという流れであります。
一方で、粟島で取り組んでいるタラ財団の活動も、マイクロプラスチック
をなくすということであります。
だから、我々としては再生の部分と、そしてもうこれ以上海の生態系を
壊さないということ、これも同時にやっていかなきゃいけないということ
なので、全ての部分が密接につながっているんだということを我々は
分かった上で、行政の取組としても、本当に部局を超えた取組として
やっていかなきゃいけないなと。
それがすなわちはもう我々の生活そのものであるということだと思って
おります。
以上です。
●ありがとうございました。次の質問に行きます。
純粋に海が変わっています。
特に今年の夏の暑さで、水温も30℃以上になって、藻場や
魚も結構いなくなっていますね。
瀬戸内海と漁師を守る施策を考えていかないといけない!
私ができる範囲で考え、言い続けて、実行したいと思います。
Posted by はまぐちふどうさん at 13:49│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。