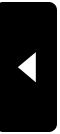2024年10月29日
私の一般質問R6/9(その1)
私の48回目の一般質問を公開します。
以前と違って、数年前から動画も公開されています。
私の一般質問の動画はこちら
今回は、粟島の離島振興、能登半島で考えさせられた防災関係、
市民から指摘のあったナラ枯れの3問です。
1.離島振興と観光施策について
来年度の瀬戸内芸術祭を見据え、粟島の島民の声として、島の空き家
対策や道端の草刈り、樹木伐採、またルポール粟島が今後継続されて
いくのか、など心配の声を聞く。
島の振興と観光施策などについては、「第3次観光基本計画」の策定を
見据え、どのように考えているのか。
また、改正離島振興法及び、今年度の離島振興対策予算についても
当局の考えを聞く。
2.防災対策について
宮崎県での地震を受けて、南海トラフ地震の想定震源域で大規模地震
への注意を呼びかける臨時情報が発表された。
いつ大規模地震が起きてもおかしくないこと、近年の大型台風やゲリラ
豪雨を常に意識し、ふだんから備えを進める上で、改めて、
(1)補難所の充足率
(2)備蓄品の確保
(3)要配慮者などへの対応など
災害対策基本法の改正により、十分な備えが出来ているのか?
また、コストをかけずにできる倒木被害防止や河道内の樹木の伐採、
河川・側溝などの浚渫は、災害に備えて行うべきであると思うが、どの
ように考えているのか。
3.ナラ枯れ被害について
荘内半島の山々でナラ枯れ被害があるのでは?と市民の指摘を
受けた。市民周知と対策方法など考えているのか。
写真は粟島から見た「高見島」です 。
。

1.離島振興と観光施策について
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
通告に従いまして一般質問させていただきますので、よろしくお願い
します。
来年度の瀬戸内芸術祭を控えて、島の空き家対策や道端の草刈り、
樹木伐採などが高齢化してできない、生活としての来年度のガソリン
運搬、これについては同僚議員の答弁がありましたが、今ほとんどの
島民が御高齢で、直近8月1日現在では住基ベースで147名、106世帯、
もちろん現住人口はもっと少ないとは思いますが、粟島の島民の生活
が厳しくなっております。
私もお盆に粟島に行ってきて、島民の皆さんのお声を聞いてまいり
ました。
そのときに、ル・ポール粟島が今後継続されていくのか、心配の声も
お聞きしております。
島の振興を考えるに、漁師も高齢化で少なくなって、やはり観光施策
を充実していくべきであることを痛感いたしました。
もちろん島民は観光について否定的な方もいるかとは思いますが、
私は本市にある二つの有人離島については、瀬戸内芸術祭とリンク
して、観光を前面に打ち出していくべきで、第三次観光基本計画の
策定を見据えた場合に、どのように島の立ち位置を考えているのか
をお聞きしたいと思います。
その上で、改正離島振興法、今年度の離島振興対策予算について、
どのように利活用していくのかも併せてお聞きしたいと思いますので、
簡潔明瞭な答弁をよろしくお願いいたします。
●答弁(山下昭史市長)
議員御案内のとおり、本年度は市の新しい産業である観光をさらに
成長させるべく、第三次観光基本計画の策定を進めているところです。
本市の魅力を再定義し、その魅力をブラッシュアップしながら、行政、
事業者、産業団体等がその役割を担い、互いに連携することで、持続
可能な成長の好循環が生まれ、三豊市独自の観光の姿を描くことを
目標に、現在、策定委員会において議論を行っております。
本市の魅力は第1に美しい自然であり、海、山、川、島の多様な自然
環境がコンパクトに集まっている立地は、観光客に大きくアピールする
べきであると考えております。
特に、議員御質問の本市の二つの有人離島には人を魅了する豊富な
コンテンツを有しています。
瀬戸内国際芸術祭、漂流郵便局を代表とする現代アートを堪能できる
粟島、神秘に満ちた大楠や天空の花畑と言われる絶景が楽しめる
志々島は、本市が誇る観光資源です。
それぞれ魅力あふれるコンテンツを有効に活用しながら、昔ながらの
島の暮らしと観光を両立させ、持続可能な観光振興となるような計画
策定を進めているところであります。
持続可能な観光というところでは、観光が市内経済を豊かにする、
言い換えればもうかる観光、観光の産業化という視点も大変重要です。
例えば、粟島を目的に三豊市を訪れた観光客が粟島を起点に市内を
周遊し、滞在時間が延長され、最終的に市内に宿泊することで、高い
経済効果が生まれます。
今後は観光スポットからの次の観光スポットへの周遊性、また観光
スポットでの市民との交流や体験コンテンツを掛け合わせることによる
魅力的な観光地域づくりに取り組み、市内での1人当たりの平均観光
消費額を伸ばす必要があると考えております。
観光基本法の策定はまだ始まったばかりですが、観光に関連する
各分野より選定した計画策定委員の皆様には活発な議論を頂きながら、
観光の産業化に向け、第三次観光基本計画を今年度中に策定して
まいります。
その際、議員御質問の有人島である粟島、志々島も含めた本市の
魅力が十分発揮できるよう取り組んでまいります。
次に、離島振興対策予算についての御質問ですが、本年度は粟島
芸術家村事業で必要な施設の維持管理経費とタラとの協定に基づく
海洋環境ポート事業が主な予算となっております。
海洋環境ポート事業は、財源として国の離島活性化交付金を活用した
事業でございますが、昨年度までの瀬戸内国際芸術祭や粟島芸術家
村事業などの開催につきましても、この交付金を活用したものであります。
このように、本市では国の離島活性化のための交付金を積極的に
活用しながら、様々な離島振興事業を実施してまいりましたが、この
交付金については、離島振興法の改正に伴い、令和5年度から補助
メニューが拡充されています。
特にハード事業では、新たに離島広域活性化事業が創設され、交流
施設の整備費なども交付金の対象に追加されてきます。
本年度はこれらのメニューを活用した事業は予定しておりませんが、
今後も国の交付金を有効に活用しながら、島民の皆様の日常生活に
必要な環境の維持や島への交流促進につながる取組を積極的に
進めてまいりたいと考えています。
また、来年度以降につきましては、瀬戸内芸術祭と大阪万博が開か
れることから、万博から瀬戸内海、特に粟島も含めた離島への誘客
など、瀬戸内海を面的に捉えた周遊観光などへの取組も行いたいと
思います。
そして、瀬戸内海の観光資源としての価値の向上、漁業関係者など
我々の生活に身近で生物の多様性の宝庫である瀬戸内海の持つ
すばらしい環境を未来へつなげる取組を行ってまいりたいと考えて
おりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
●再質問1
もうかる観光、観光の産業化というのは本当に非常に重要なところ
ですが、令和4年に離島振興法の一部を改正する法律が施行されました。
その中で、離島に関する配慮規定が充実し、医療、交通通信、教育
などについては、特別の配慮となっています。
要は格上げがされているんです。
その中で、令和2年度には粟島スマートアイランド推進事業、令和4年
度には粟島スマートアイランド推進プロジェクトNextの実証実験が
行われてきました。
まず、ここの検証も行っているかとは思いますが、どうでしょうか。
一般財源がかかってないから大丈夫ということではなくて、要は離島
における遠隔医療体制の強化に向けた健康管理システムの構築と、
本土と遜色ない物流体制の確立による島民の生活の利便性の向上
に実際つながったのか効果検証する必要があるかと思いますが、
どうだったんでしょうか。
それと私、令和5年に勉強した部分から質問いたしますけど、令和5年
度離島振興関係予算では、市長答弁にありましたように、離島広域活性
化事業が新設されております。
デジタル技術等新技術活用促進事業、小規模離島等生活環境改善事業
が拡充され、スマートアイランドの事業が実証から実装ができるようになっ
ております。
そこがベースでのグリーンスローモビリティ事業の実装だったかと思い
ますが、その上で、離島広域活性化事業では、定住促進住宅整備事業、
定住誘引施設等整備事業、これは既存施設の改修等ができておるん
ですが、その上に新築にも交付金が出るようになりました。
ようは、シェアオフィス等の整備は、改修プラス新築に交付金が出るよう
になっております。
また、定住基盤強化事業などの基盤整備事業が総合的に推進され、
離島の振興を図ることができるようになりました。
特に、定住基盤強化事業では、土砂災害特別警戒区域内での住宅
改修、建て替えの上限が離島では541万円と大幅に上がっております。
ちなみに、本土での回収のみは336万円までなんですが、このあたりの
支援策は使えないのかなと私は思いました。
この離島活性化交付金事業は、離島の自立的発展を促進して、島民の
生活安定、福祉向上を図るとともに、地域間交流を促進し、無居住離島
の増加及び人口の著しい減少を防止するために、ソフト事業を支援する
枠組みとして、既存の離島活性化交付金の支援対象事業が拡充をされ
ていますのに、市長からは、メニューを活用した事業が予定されていない
と答弁もありましたけど、これらのメニューこそ本市の移動のためにうまく
利活用してほしいと思います。
その上で、企業誘致等促進、交流促進事業として、関係人口の拡大、
創出のために、離島における地域情報の発信、PR映像やパンフレット
の作成などにも使えたりと、これはデジ田のベーシックインフラのような
交付金対象が多いと思うんですが、こちらは実態がありますから、
グリーンスローモビリティの導入だけでなく、これら多くのメニューを離島
に利活用していくべきであると私は思います。
そのあたりをどのようにお考えなのか、再質問をいたします。
●答弁1(立石慎一政策部長)
まず、粟島で行ったスマートアイランド実証事業が現在どのように生か
されているかという御質問ですが、実証については、令和2年度と令和
4年度の2度行っております。
令和2年度は移動、医療、物流という三つのテーマで実証をしたものです。
まず、移動についてはグリーンスローモビリティによる島内の移動に関
しての実証でございまして、令和2年度実証以降も、運行日やダイヤ等の
試行錯誤を繰り返しながら実証を継続した結果、令和5年10月に本格
運行へ移行することができております。
次に、医療については、オンラインでの診察、服薬指導を行うものです
が、現在、粟島診療所では、この実施を生かして、オンライン診療を行う
準備が整えられております。
今後、荒天で医師が粟島に渡ることができないなど、様々な場面に
応じてオンライン診療を行ってまいりたいと考えております。
最後に、物流につきましては、ドローンによる薬の配送というものに
チャレンジをした結果、参画したベンチャー企業により、粟島へのドロ
ーンの定期航路が開設をされました。
しかし、残念ながら、現在は当該サービスについては終了をしております。
令和4年度は、令和2年度の成果を踏まえて、医療、物流に関する実証
を行っております。
1回目同様、オンラインでの診療、服薬指導を実施し、医薬品を当該の
薬局から粟島住民に手渡すまでの手順と物資の流れを確認しました。
配送ではドローンに代わり、遠隔操作の無人船舶を使用し、遠隔医療
から島民宅の物資の流れを一気通貫で行うことに成功しております。
しかしながら、コスト面や荒天時の運行などの不安定さなどの課題も
見えてきましたので、社会実装にはまだまだこれは時間がかかるもの
ではないかと考えているところです。
次に、離島広域活性化事業の定住基盤強化事業を活用しないのか
という御質問を頂きましたが、この事業については、令和5年度に新設
された離島振興の補助メニューであり、新たに土砂災害特別警戒区域
内の住宅改修や建物の費用に補助金が充てられるものが追加をされ
ております。
議員御指摘のとおり、いわゆる土砂災害のレッドゾーンにお住まいの
方の住宅を災害から守るために、外壁の補強の改修であったり、住宅
の建て替えも補助対象とされております。
新しくできた制度のため、国土交通省に事業内容を確認したところ、
対象となる事業費の23%に当たる額の2分の1を国が補助し、国の
補助金以上を市町村が負担する、国と市町村が負担した残りの部分
は、住宅所有者が負担する制度となっております。
国土交通省の説明では、現在までこの制度を活用した事例は全国
でもないとのことでしたが、制度の活用については、今後も研究をして
まいりたいと考えております。
このほか令和5年度より離島活性化のための交付金のメニューが
拡充をされております。
来年度は瀬戸内国際芸術祭の開催に合わせたパンフレットなど、
交付金を活用して作成をする予定にしておりますが、今後一層の
離島振興を図っていくためにも、この交付金は有効に活用をして
まいりたいと考えております。
●再質問2
もうかる観光の産業化、本当に非常に重要なところで、何度も言います
けど、待ちに待った粟島海洋記念館の耐震改修、私たち詫間の人間は
海員学校と呼んでおりましたが、登録有形文化財である粟島海洋記念館
建造群は、現存する日本最古の海員学校の校舎として瀬戸内国際芸術
祭では会場の中心拠点としてにぎわいを見せていましたが、こんなに遅く
になって、やっと耐震改修が始まりました。
また、この改修が令和9年3月完成と、次回の瀬戸芸や大阪万博には
間に合わず、粟島の観光シンボルがなかなか県と連携が取れずに、
着工が遅くなって島民も落胆しております。
この原因も知る必要があるかと思いますが、やはり散策しますと、上新田
から下新田、また西浜までも空き家や廃屋が多いですし、明らかに活気
がありません。
ゲストハウスも売りに出ている始末ですし、これ以上にル・ポール粟島が
なくなることだけは避けてほしいと思っています。
そんな中でも、地域の皆さんが助け合って草刈りや樹木伐採、また
島民以外の皆様のボランティアに支えられながら、登山道の整備、助け
合っての生活をしております。まさに地域の皆様が助け合ってゆったり
とした生活が展開されている。先日、認知症カフェも盛況であるという
お話もお聞きをしました。
離島の地域振興を考えるに、過疎法に対応した過疎対策が過去から
行われてきて、2000年までの過疎地域活性化特別措置法から、2010
年まで自立促進、持続可能性が叫ばれて、今は過疎地域持続的発展
特別措置法で、必要人口の維持のための縮充促進がメインに叫ばれて
きました。
縮充というのは縮小と充実から構成される言葉ですが、この縮充とは、
地域を持続させるために必要な最低限の人口を維持するとともに、
人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりということです。
私、以前も質問しましたが、要は粟島でもどこでもそうなんですが、
同僚議員も発言ありましたけど、今後担い手がいなくなってきています。
団塊の世代以降が激減して、ほとんどの方が60歳以上で、地域維持
のための人材確保が困難な中、地域が細くなり過ぎて、行政で何でも
やってほしい。その上で、行政も細くなっていますからなかなか対応が
できない。
ましてやハード整備も限界があるのかなと私は思いますが、地域は
誰が支えるのか、やはり地域における互助による支えが必要で、
地域を持続させるために必要な最低限の人口を維持するとともに、
人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりを市がサポートして
いくべきであります。
まさに粟島が三豊市の10年先を走っている気がします中で、
暮らしのものさしづくり、縁づくり事業が全国の過疎自治体で活発化
をしております。
行政機関や他地域の住民が積極的に関わりを持ち、居住者のQOL、
クオリティーオブライフ、生活の質を維持するとともに、無住化までに
実施すべき集落保全活動を積極的に行っていく主体的行動が必要な
気がします。
そのあたり、行政がどのように関わっていくのかをお聞きをいたします。
●答弁2(立石慎一政策部長)
本市では、その誕生以来、市民の主体なまちづくり活動が促進を
され、これまで行政が担ってきた公共サービスの一部を市民自らの
手によって実施することとともに、希薄化が進む地域社会の互助、
共助機能の強化につなげてきております。
また、令和4年度からは地域の共助によるサービスで暮らしを支え、
ウェルビーイング向上やベーシックインフラ構想にも取り組んでおります。
このように、本市においては議員御指摘の互助や共助の取組を
進めてまいりましたが、コロナ禍によって疲弊した地域コミュニティー
においては、共助の取組の重要性は増しているものと考えており、
また、粟島や志々島のような離島であればなおさらであると考えて
おります。
今後、共助の取組を活性化していくためには、共助の領域で活躍
できるプレイヤーをつくっていくことが重要だと考えておりますので、
自治会活動やNPO活動など市民の主体的なまちづくり活動の支援
や地域おこし協力隊や地域活性化起業人などの意欲ある外部人材
の受入れ、民間事業者による共助サービス創出を喚起するための
取組などを推進してまいりたいと考えております。
●再質問3
愛媛県の高井神島というところがありまして、2022年は5世帯7人
しか住んでいませんが、港周辺の民家や公共施設に施された大
規模な漫画アートを展開しております。
これに全国から人が来ているそうなんです。
数か月前なんですが、NHK、Eテレで「ハルさんの休日」という番組、
財田の古民家カフェが紹介されました。私も数回訪れたことがあります。
ここはおせっかい大歓迎、みんなの居場所づくり、人と人とのつながり
を大切にされている場所となっていました。まさに幸福度が高い、
過疎地域で人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりが実現を
されていることを感じました。
粟島も同じことが実現されているし、されないといけません。
地域の経済循環を支援するために、ローカル10,000プロジェクトの
地方単独事業に対する特別交付税措置が創設され、地方への
人の流れの創出、拡大を加速するために、先ほどお話ありました
地域活性化起業人制度に社員の副業型が追加され、また、地域
おこし協力隊に係る特別交付税措置が拡充されており、本市も
導入予定とお聞きをしております。
この古民家カフェの運営は地域おこし協力隊第1号の石井優香
さんです。
ここに来て、国も地域を支える人を重要視している気がします。
同僚議員の質問もありましたけど、本当に集落支援員も導入すべき
ですよ。
このあたり、まちづくり推進隊が担っていくこともできると私は
個人的には思います。
石井さんは香川県地域おこし協力隊OBOGネットワーク組織、
かがわごとが設立され、その理事として、自治体側の協力隊導入
サポートや現役協力隊のサポートを行ってくれています。
私、お聞きしました。やはり、人と人とのつながりというのが非常
に重視されている中で、
「One MITOYO~心つながる豊かさ実感都市~」
三豊の構築を推進していくべきで、過疎地域で人口が減っても
豊かに暮らし続ける仕組みづくりを粟島発で実現して、持続
可能な生活をお接待の心から観光へとつなげていくべきだと私は
考えます。どのようにお考えでしょうか。最後に質問いたします。
●答弁3(立石慎一政策部長)
議員から、粟島における人口が減っても豊かに暮らし続ける
仕組みづくりについては、様々な取組を御紹介いただきましたが、
その一つの取組である地域おこし協力隊につきましては、現在、
産業政策課におきまして1名の方を登用し、粟島もフィールドの
一つに観光事業の活性化、本市の魅力の情報発信等に係る
業務に携わっていただいております。
観光分野につきましては、外部からの視点や独自のノウハウを
持つ地域おこし協力隊や地域活性化起業人といった外部人材の
活用は有効だと考えておりますので、積極的に活用していきたい
と考えております。
来年度につきましては、瀬戸内国際芸術祭の開催も予定されて
おりますので、例えば、新たに地域おこし協力隊を登用し、最終的
には本市全体をフィールドに観光分野で活用していただくことを
念頭に置きながら、その足がかりとして、来年度、粟島の活性化の
ために充塡して活動していただくことは、一つの可能性として十分
に考える余地があるものだと考えておりますので、検討してまいり
たいと思います。
これまで粟島ではまちづくり推進隊の皆様にも活動を頂いており
ますが、今後はさらに多くの皆様による活動を喚起して、共助の
取組を活性化できるよう取り組んでまいります。
ながながと、ダラダラと質問する点、反省しきりですね。
後で読み返すとわかります。
それでも・・・いろんな事調査・研究して発言しております。
その点はご評価いただきたいかと・・・皆様、反省点は真摯に
次回に活かしますっ!
以前と違って、数年前から動画も公開されています。
私の一般質問の動画はこちら
今回は、粟島の離島振興、能登半島で考えさせられた防災関係、
市民から指摘のあったナラ枯れの3問です。
1.離島振興と観光施策について
来年度の瀬戸内芸術祭を見据え、粟島の島民の声として、島の空き家
対策や道端の草刈り、樹木伐採、またルポール粟島が今後継続されて
いくのか、など心配の声を聞く。
島の振興と観光施策などについては、「第3次観光基本計画」の策定を
見据え、どのように考えているのか。
また、改正離島振興法及び、今年度の離島振興対策予算についても
当局の考えを聞く。
2.防災対策について
宮崎県での地震を受けて、南海トラフ地震の想定震源域で大規模地震
への注意を呼びかける臨時情報が発表された。
いつ大規模地震が起きてもおかしくないこと、近年の大型台風やゲリラ
豪雨を常に意識し、ふだんから備えを進める上で、改めて、
(1)補難所の充足率
(2)備蓄品の確保
(3)要配慮者などへの対応など
災害対策基本法の改正により、十分な備えが出来ているのか?
また、コストをかけずにできる倒木被害防止や河道内の樹木の伐採、
河川・側溝などの浚渫は、災害に備えて行うべきであると思うが、どの
ように考えているのか。
3.ナラ枯れ被害について
荘内半島の山々でナラ枯れ被害があるのでは?と市民の指摘を
受けた。市民周知と対策方法など考えているのか。
写真は粟島から見た「高見島」です
 。
。1.離島振興と観光施策について
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
通告に従いまして一般質問させていただきますので、よろしくお願い
します。
来年度の瀬戸内芸術祭を控えて、島の空き家対策や道端の草刈り、
樹木伐採などが高齢化してできない、生活としての来年度のガソリン
運搬、これについては同僚議員の答弁がありましたが、今ほとんどの
島民が御高齢で、直近8月1日現在では住基ベースで147名、106世帯、
もちろん現住人口はもっと少ないとは思いますが、粟島の島民の生活
が厳しくなっております。
私もお盆に粟島に行ってきて、島民の皆さんのお声を聞いてまいり
ました。
そのときに、ル・ポール粟島が今後継続されていくのか、心配の声も
お聞きしております。
島の振興を考えるに、漁師も高齢化で少なくなって、やはり観光施策
を充実していくべきであることを痛感いたしました。
もちろん島民は観光について否定的な方もいるかとは思いますが、
私は本市にある二つの有人離島については、瀬戸内芸術祭とリンク
して、観光を前面に打ち出していくべきで、第三次観光基本計画の
策定を見据えた場合に、どのように島の立ち位置を考えているのか
をお聞きしたいと思います。
その上で、改正離島振興法、今年度の離島振興対策予算について、
どのように利活用していくのかも併せてお聞きしたいと思いますので、
簡潔明瞭な答弁をよろしくお願いいたします。
●答弁(山下昭史市長)
議員御案内のとおり、本年度は市の新しい産業である観光をさらに
成長させるべく、第三次観光基本計画の策定を進めているところです。
本市の魅力を再定義し、その魅力をブラッシュアップしながら、行政、
事業者、産業団体等がその役割を担い、互いに連携することで、持続
可能な成長の好循環が生まれ、三豊市独自の観光の姿を描くことを
目標に、現在、策定委員会において議論を行っております。
本市の魅力は第1に美しい自然であり、海、山、川、島の多様な自然
環境がコンパクトに集まっている立地は、観光客に大きくアピールする
べきであると考えております。
特に、議員御質問の本市の二つの有人離島には人を魅了する豊富な
コンテンツを有しています。
瀬戸内国際芸術祭、漂流郵便局を代表とする現代アートを堪能できる
粟島、神秘に満ちた大楠や天空の花畑と言われる絶景が楽しめる
志々島は、本市が誇る観光資源です。
それぞれ魅力あふれるコンテンツを有効に活用しながら、昔ながらの
島の暮らしと観光を両立させ、持続可能な観光振興となるような計画
策定を進めているところであります。
持続可能な観光というところでは、観光が市内経済を豊かにする、
言い換えればもうかる観光、観光の産業化という視点も大変重要です。
例えば、粟島を目的に三豊市を訪れた観光客が粟島を起点に市内を
周遊し、滞在時間が延長され、最終的に市内に宿泊することで、高い
経済効果が生まれます。
今後は観光スポットからの次の観光スポットへの周遊性、また観光
スポットでの市民との交流や体験コンテンツを掛け合わせることによる
魅力的な観光地域づくりに取り組み、市内での1人当たりの平均観光
消費額を伸ばす必要があると考えております。
観光基本法の策定はまだ始まったばかりですが、観光に関連する
各分野より選定した計画策定委員の皆様には活発な議論を頂きながら、
観光の産業化に向け、第三次観光基本計画を今年度中に策定して
まいります。
その際、議員御質問の有人島である粟島、志々島も含めた本市の
魅力が十分発揮できるよう取り組んでまいります。
次に、離島振興対策予算についての御質問ですが、本年度は粟島
芸術家村事業で必要な施設の維持管理経費とタラとの協定に基づく
海洋環境ポート事業が主な予算となっております。
海洋環境ポート事業は、財源として国の離島活性化交付金を活用した
事業でございますが、昨年度までの瀬戸内国際芸術祭や粟島芸術家
村事業などの開催につきましても、この交付金を活用したものであります。
このように、本市では国の離島活性化のための交付金を積極的に
活用しながら、様々な離島振興事業を実施してまいりましたが、この
交付金については、離島振興法の改正に伴い、令和5年度から補助
メニューが拡充されています。
特にハード事業では、新たに離島広域活性化事業が創設され、交流
施設の整備費なども交付金の対象に追加されてきます。
本年度はこれらのメニューを活用した事業は予定しておりませんが、
今後も国の交付金を有効に活用しながら、島民の皆様の日常生活に
必要な環境の維持や島への交流促進につながる取組を積極的に
進めてまいりたいと考えています。
また、来年度以降につきましては、瀬戸内芸術祭と大阪万博が開か
れることから、万博から瀬戸内海、特に粟島も含めた離島への誘客
など、瀬戸内海を面的に捉えた周遊観光などへの取組も行いたいと
思います。
そして、瀬戸内海の観光資源としての価値の向上、漁業関係者など
我々の生活に身近で生物の多様性の宝庫である瀬戸内海の持つ
すばらしい環境を未来へつなげる取組を行ってまいりたいと考えて
おりますので、御理解賜りますようお願い申し上げます。
●再質問1
もうかる観光、観光の産業化というのは本当に非常に重要なところ
ですが、令和4年に離島振興法の一部を改正する法律が施行されました。
その中で、離島に関する配慮規定が充実し、医療、交通通信、教育
などについては、特別の配慮となっています。
要は格上げがされているんです。
その中で、令和2年度には粟島スマートアイランド推進事業、令和4年
度には粟島スマートアイランド推進プロジェクトNextの実証実験が
行われてきました。
まず、ここの検証も行っているかとは思いますが、どうでしょうか。
一般財源がかかってないから大丈夫ということではなくて、要は離島
における遠隔医療体制の強化に向けた健康管理システムの構築と、
本土と遜色ない物流体制の確立による島民の生活の利便性の向上
に実際つながったのか効果検証する必要があるかと思いますが、
どうだったんでしょうか。
それと私、令和5年に勉強した部分から質問いたしますけど、令和5年
度離島振興関係予算では、市長答弁にありましたように、離島広域活性
化事業が新設されております。
デジタル技術等新技術活用促進事業、小規模離島等生活環境改善事業
が拡充され、スマートアイランドの事業が実証から実装ができるようになっ
ております。
そこがベースでのグリーンスローモビリティ事業の実装だったかと思い
ますが、その上で、離島広域活性化事業では、定住促進住宅整備事業、
定住誘引施設等整備事業、これは既存施設の改修等ができておるん
ですが、その上に新築にも交付金が出るようになりました。
ようは、シェアオフィス等の整備は、改修プラス新築に交付金が出るよう
になっております。
また、定住基盤強化事業などの基盤整備事業が総合的に推進され、
離島の振興を図ることができるようになりました。
特に、定住基盤強化事業では、土砂災害特別警戒区域内での住宅
改修、建て替えの上限が離島では541万円と大幅に上がっております。
ちなみに、本土での回収のみは336万円までなんですが、このあたりの
支援策は使えないのかなと私は思いました。
この離島活性化交付金事業は、離島の自立的発展を促進して、島民の
生活安定、福祉向上を図るとともに、地域間交流を促進し、無居住離島
の増加及び人口の著しい減少を防止するために、ソフト事業を支援する
枠組みとして、既存の離島活性化交付金の支援対象事業が拡充をされ
ていますのに、市長からは、メニューを活用した事業が予定されていない
と答弁もありましたけど、これらのメニューこそ本市の移動のためにうまく
利活用してほしいと思います。
その上で、企業誘致等促進、交流促進事業として、関係人口の拡大、
創出のために、離島における地域情報の発信、PR映像やパンフレット
の作成などにも使えたりと、これはデジ田のベーシックインフラのような
交付金対象が多いと思うんですが、こちらは実態がありますから、
グリーンスローモビリティの導入だけでなく、これら多くのメニューを離島
に利活用していくべきであると私は思います。
そのあたりをどのようにお考えなのか、再質問をいたします。
●答弁1(立石慎一政策部長)
まず、粟島で行ったスマートアイランド実証事業が現在どのように生か
されているかという御質問ですが、実証については、令和2年度と令和
4年度の2度行っております。
令和2年度は移動、医療、物流という三つのテーマで実証をしたものです。
まず、移動についてはグリーンスローモビリティによる島内の移動に関
しての実証でございまして、令和2年度実証以降も、運行日やダイヤ等の
試行錯誤を繰り返しながら実証を継続した結果、令和5年10月に本格
運行へ移行することができております。
次に、医療については、オンラインでの診察、服薬指導を行うものです
が、現在、粟島診療所では、この実施を生かして、オンライン診療を行う
準備が整えられております。
今後、荒天で医師が粟島に渡ることができないなど、様々な場面に
応じてオンライン診療を行ってまいりたいと考えております。
最後に、物流につきましては、ドローンによる薬の配送というものに
チャレンジをした結果、参画したベンチャー企業により、粟島へのドロ
ーンの定期航路が開設をされました。
しかし、残念ながら、現在は当該サービスについては終了をしております。
令和4年度は、令和2年度の成果を踏まえて、医療、物流に関する実証
を行っております。
1回目同様、オンラインでの診療、服薬指導を実施し、医薬品を当該の
薬局から粟島住民に手渡すまでの手順と物資の流れを確認しました。
配送ではドローンに代わり、遠隔操作の無人船舶を使用し、遠隔医療
から島民宅の物資の流れを一気通貫で行うことに成功しております。
しかしながら、コスト面や荒天時の運行などの不安定さなどの課題も
見えてきましたので、社会実装にはまだまだこれは時間がかかるもの
ではないかと考えているところです。
次に、離島広域活性化事業の定住基盤強化事業を活用しないのか
という御質問を頂きましたが、この事業については、令和5年度に新設
された離島振興の補助メニューであり、新たに土砂災害特別警戒区域
内の住宅改修や建物の費用に補助金が充てられるものが追加をされ
ております。
議員御指摘のとおり、いわゆる土砂災害のレッドゾーンにお住まいの
方の住宅を災害から守るために、外壁の補強の改修であったり、住宅
の建て替えも補助対象とされております。
新しくできた制度のため、国土交通省に事業内容を確認したところ、
対象となる事業費の23%に当たる額の2分の1を国が補助し、国の
補助金以上を市町村が負担する、国と市町村が負担した残りの部分
は、住宅所有者が負担する制度となっております。
国土交通省の説明では、現在までこの制度を活用した事例は全国
でもないとのことでしたが、制度の活用については、今後も研究をして
まいりたいと考えております。
このほか令和5年度より離島活性化のための交付金のメニューが
拡充をされております。
来年度は瀬戸内国際芸術祭の開催に合わせたパンフレットなど、
交付金を活用して作成をする予定にしておりますが、今後一層の
離島振興を図っていくためにも、この交付金は有効に活用をして
まいりたいと考えております。
●再質問2
もうかる観光の産業化、本当に非常に重要なところで、何度も言います
けど、待ちに待った粟島海洋記念館の耐震改修、私たち詫間の人間は
海員学校と呼んでおりましたが、登録有形文化財である粟島海洋記念館
建造群は、現存する日本最古の海員学校の校舎として瀬戸内国際芸術
祭では会場の中心拠点としてにぎわいを見せていましたが、こんなに遅く
になって、やっと耐震改修が始まりました。
また、この改修が令和9年3月完成と、次回の瀬戸芸や大阪万博には
間に合わず、粟島の観光シンボルがなかなか県と連携が取れずに、
着工が遅くなって島民も落胆しております。
この原因も知る必要があるかと思いますが、やはり散策しますと、上新田
から下新田、また西浜までも空き家や廃屋が多いですし、明らかに活気
がありません。
ゲストハウスも売りに出ている始末ですし、これ以上にル・ポール粟島が
なくなることだけは避けてほしいと思っています。
そんな中でも、地域の皆さんが助け合って草刈りや樹木伐採、また
島民以外の皆様のボランティアに支えられながら、登山道の整備、助け
合っての生活をしております。まさに地域の皆様が助け合ってゆったり
とした生活が展開されている。先日、認知症カフェも盛況であるという
お話もお聞きをしました。
離島の地域振興を考えるに、過疎法に対応した過疎対策が過去から
行われてきて、2000年までの過疎地域活性化特別措置法から、2010
年まで自立促進、持続可能性が叫ばれて、今は過疎地域持続的発展
特別措置法で、必要人口の維持のための縮充促進がメインに叫ばれて
きました。
縮充というのは縮小と充実から構成される言葉ですが、この縮充とは、
地域を持続させるために必要な最低限の人口を維持するとともに、
人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりということです。
私、以前も質問しましたが、要は粟島でもどこでもそうなんですが、
同僚議員も発言ありましたけど、今後担い手がいなくなってきています。
団塊の世代以降が激減して、ほとんどの方が60歳以上で、地域維持
のための人材確保が困難な中、地域が細くなり過ぎて、行政で何でも
やってほしい。その上で、行政も細くなっていますからなかなか対応が
できない。
ましてやハード整備も限界があるのかなと私は思いますが、地域は
誰が支えるのか、やはり地域における互助による支えが必要で、
地域を持続させるために必要な最低限の人口を維持するとともに、
人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりを市がサポートして
いくべきであります。
まさに粟島が三豊市の10年先を走っている気がします中で、
暮らしのものさしづくり、縁づくり事業が全国の過疎自治体で活発化
をしております。
行政機関や他地域の住民が積極的に関わりを持ち、居住者のQOL、
クオリティーオブライフ、生活の質を維持するとともに、無住化までに
実施すべき集落保全活動を積極的に行っていく主体的行動が必要な
気がします。
そのあたり、行政がどのように関わっていくのかをお聞きをいたします。
●答弁2(立石慎一政策部長)
本市では、その誕生以来、市民の主体なまちづくり活動が促進を
され、これまで行政が担ってきた公共サービスの一部を市民自らの
手によって実施することとともに、希薄化が進む地域社会の互助、
共助機能の強化につなげてきております。
また、令和4年度からは地域の共助によるサービスで暮らしを支え、
ウェルビーイング向上やベーシックインフラ構想にも取り組んでおります。
このように、本市においては議員御指摘の互助や共助の取組を
進めてまいりましたが、コロナ禍によって疲弊した地域コミュニティー
においては、共助の取組の重要性は増しているものと考えており、
また、粟島や志々島のような離島であればなおさらであると考えて
おります。
今後、共助の取組を活性化していくためには、共助の領域で活躍
できるプレイヤーをつくっていくことが重要だと考えておりますので、
自治会活動やNPO活動など市民の主体的なまちづくり活動の支援
や地域おこし協力隊や地域活性化起業人などの意欲ある外部人材
の受入れ、民間事業者による共助サービス創出を喚起するための
取組などを推進してまいりたいと考えております。
●再質問3
愛媛県の高井神島というところがありまして、2022年は5世帯7人
しか住んでいませんが、港周辺の民家や公共施設に施された大
規模な漫画アートを展開しております。
これに全国から人が来ているそうなんです。
数か月前なんですが、NHK、Eテレで「ハルさんの休日」という番組、
財田の古民家カフェが紹介されました。私も数回訪れたことがあります。
ここはおせっかい大歓迎、みんなの居場所づくり、人と人とのつながり
を大切にされている場所となっていました。まさに幸福度が高い、
過疎地域で人口が減っても豊かに暮らし続ける仕組みづくりが実現を
されていることを感じました。
粟島も同じことが実現されているし、されないといけません。
地域の経済循環を支援するために、ローカル10,000プロジェクトの
地方単独事業に対する特別交付税措置が創設され、地方への
人の流れの創出、拡大を加速するために、先ほどお話ありました
地域活性化起業人制度に社員の副業型が追加され、また、地域
おこし協力隊に係る特別交付税措置が拡充されており、本市も
導入予定とお聞きをしております。
この古民家カフェの運営は地域おこし協力隊第1号の石井優香
さんです。
ここに来て、国も地域を支える人を重要視している気がします。
同僚議員の質問もありましたけど、本当に集落支援員も導入すべき
ですよ。
このあたり、まちづくり推進隊が担っていくこともできると私は
個人的には思います。
石井さんは香川県地域おこし協力隊OBOGネットワーク組織、
かがわごとが設立され、その理事として、自治体側の協力隊導入
サポートや現役協力隊のサポートを行ってくれています。
私、お聞きしました。やはり、人と人とのつながりというのが非常
に重視されている中で、
「One MITOYO~心つながる豊かさ実感都市~」
三豊の構築を推進していくべきで、過疎地域で人口が減っても
豊かに暮らし続ける仕組みづくりを粟島発で実現して、持続
可能な生活をお接待の心から観光へとつなげていくべきだと私は
考えます。どのようにお考えでしょうか。最後に質問いたします。
●答弁3(立石慎一政策部長)
議員から、粟島における人口が減っても豊かに暮らし続ける
仕組みづくりについては、様々な取組を御紹介いただきましたが、
その一つの取組である地域おこし協力隊につきましては、現在、
産業政策課におきまして1名の方を登用し、粟島もフィールドの
一つに観光事業の活性化、本市の魅力の情報発信等に係る
業務に携わっていただいております。
観光分野につきましては、外部からの視点や独自のノウハウを
持つ地域おこし協力隊や地域活性化起業人といった外部人材の
活用は有効だと考えておりますので、積極的に活用していきたい
と考えております。
来年度につきましては、瀬戸内国際芸術祭の開催も予定されて
おりますので、例えば、新たに地域おこし協力隊を登用し、最終的
には本市全体をフィールドに観光分野で活用していただくことを
念頭に置きながら、その足がかりとして、来年度、粟島の活性化の
ために充塡して活動していただくことは、一つの可能性として十分
に考える余地があるものだと考えておりますので、検討してまいり
たいと思います。
これまで粟島ではまちづくり推進隊の皆様にも活動を頂いており
ますが、今後はさらに多くの皆様による活動を喚起して、共助の
取組を活性化できるよう取り組んでまいります。
ながながと、ダラダラと質問する点、反省しきりですね。
後で読み返すとわかります。
それでも・・・いろんな事調査・研究して発言しております。
その点はご評価いただきたいかと・・・皆様、反省点は真摯に
次回に活かしますっ!
Posted by はまぐちふどうさん at 08:04│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。