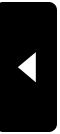2024年11月10日
私の一般質問R6/6(その1)
6月議会の私の一般質問を、ブログで書いてないような気がして。
以下の2問でした。
動画はコチラ
1.地域公共交通全般について
今春の組織変更により、政策部地域戦略課内に
「交通システム事業団設立準備室」
が新設された。
人口構造の変化に伴い、担い手不足などの移動に関する将来不安
が生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素である「移動」を確保
する必要がある、とのことだが今後の具体的な設立計画・方針と地域
公共交通全般の現状などについて聞く。
(1)民間活力の反映とは、三豊市地域公共交通計画との整合性
(2)財政面も含めスピード感のある持続的で新しいチャレンジとは
(3)移動に関するモデル地域は設定するのか
(4)コミュニティバスなど、既存の取り組みの検証、市民ニーズの把握は
しているのか
2.住宅の耐震対策などについて
能登半島地震において、多くの木造住宅の被害が甚大であった。
施政方針において、珠洲市は「明日の三豊市」と言う山下市長には、
本市の耐震診断と耐震対策を一層促進、啓発する必要があると考える。
補助事業を強化するためにどのような取り組みや市民周知をしていくのか、
また旧耐震基準だけでなく、1981年6月以降2000年5月以前の新耐震
基準住宅の耐震性能が不足しているという可能性が認識されている中、
現状を把握して、民間危険ブロック塀も含めた補助金の拡充について
検討・導入していかないのか。
とにかく最近は、多くの分野で質問するように心がけています。
後は「教育委員会」と「子育て支援」などが残るかなぁ、とか思っています
が、私みたいなのが「教育」を語れませんから、今勉強しております 。
。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。通告に従いまして一般質問をさせて
いただきますので、よろしくお願いします。
初めに、地域公共交通全般についてお聞きいたします。
今週の組織改正により、政策部地域戦略課内に交通システム事
業団設立準備室が新設されました。
新設理由として、人口構造の変化に伴い、担い手不足等の移動に
関する将来不安が生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素
である移動を確保する必要があるとのことですが、本市では三豊市
地域公共交通計画も策定がされており、基本理念「行きたいときに
行きたいところへ行けるまち」が設定されております。
本市の地域公共交通といえば、既存のJR鉄道の2線6駅、市コミ
ュニティバス、民間タクシー、汽船といった公共交通から、新たな
移動である詫間・仁尾エリアでの民間企業が運営する乗り合い
オンデマンド交通mobiさん、令和5年10月より本格運行へ移行
した粟島でのグリーンスローモビリティ、財田町にて実証中の乗合
タクシー、これについては令和6年度も継続運行がされており、
まさに新たな移動が生まれてきておりますが、
(1)今回、新たに設立される三豊市交通システム事業団が担うで
あろう民間活力の反映とは。三豊市地域公共交通計画との整合性。
(2)財政面も含め、スピード感のある持続的で新しいチャレンジとは何か。
(3)移動に関するモデル地域は設定するのか。
(4)コミュニティバスなど、既存の取組の検証、市民ニーズの把握は
しているのか。
以上4点を中心に、今後の具体的な地域公共交通についての現状と、
今後の計画方針と提案も含めた全般についてお聞きをいたしますので、
簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。
●答弁1(山下昭史市長)
議員御質問にありましたとおり、今年度の組織改正により、政策部
地域戦略課内に交通システム事業団設立準備室が新設となりました。
人口構造の変化に伴い、担い手不足等の移動に関する将来不安が
生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素である移動を確保して
いく必要があります。
このため、民間活力を反映させること、また、財政面も含め、スピード
感のある持続的で新しいチャレンジを行うことを目的として、交通シス
テム事業団の設立をしたいと考えております。
まず、1点目の民間活力の反映とはの部分でございますが、全国的
にも人口減少や人口構造の変化に伴うドライバー不足、また、働き方
改革による路線バスの減便は報道されているとおりです。
三豊市でも、4月の市内交通事業者への調査で、10社中8社がドラ
イバー不足であるとの回答であり、その8社では、現状に対してドライ
バーの必要数は、平均で3人の不足、多いところでは5人の不足との
回答が2社ありました。
また、現有ドライバーの年齢層につきましても、10社の現ドライバーの
うち55%が60歳以上で運行されている現状でありました。
一方で、これらドライバー不足などの交通移動が直面している課題は、
昨年10月に施行された地域公共交通活性化再生法で掲げられている
とおり、交通事業者の経営努力のみでは避けられないものであるため、
自動運転やMaaSなどデジタル技術を実装する交通DX、車両電動化
や再エネ、地産地消など交通GX、そして官民共創、交通事業者間共
創、多分野共創の三つの共創、共に創るほうですけれども、すなわち、
地域の関係者の連携と協働を通じて、利便性、持続可能性、生産性
を高める地域公共交通のリ・デザインを進める必要性を強く感じて
おります。
このことからも、地域で頑張ってくださっている地域交通事業者と共に、
あらゆる民間活力の支援も頂きながら、持続する地域公共交通を
見据えたいと考えます。
また、三豊市地域公共交通計画との整合性につきましては、まさに
計画の基本理念である「行きたいときに行きたいところへ行けるまち」
を事業団のコンセプトとして持ち、人や物といった地域の資源を最大限
活用し、必要に応じては、先端技術や新しいモビリティサービスにも
挑戦しながら、ニーズに応じた交通ネットワークの整備を目指してまい
りたいと思います。
次に、2点目の財政面も含め、スピード感のある持続的で新しいチャ
レンジとはの部分でございますが、これら全てを行政のみで補完して
いくのではなく、様々な共創の下、人、物、金など資源を有益に掛け
合わせることで、持続可能となるシステムにチャレンジしていきたいと
考えています。
まずは、慢性的な人手不足の中、また、人口構造の変化を見据えると、
自動運転については必ず視野に入れていく必要があると考えており、
三豊市では、国土交通省の自動運転社会実装推進事業に応募して
おりました。そして、このたび、6月6日に採択の通知がございました。
三豊市では、最新技術を取り入れた自動運転の実証運行をすること
により、地域の交通課題の解決を図れる将来へとなるようチャレンジ
してまいります。
次に、3点目の移動に関するモデル地域は設定するのかの部分で
ございます。
これまでにも半径2キロの地域生活圏構想は申し上げてきたとおり
です。
このたび、大浜地域では、地域の拠点となる施設、機能の整備や
民間事業者の進出も徐々に整ってきております。
今後、この大浜をモデル地域として、生活における交通移動の課題
解決を検討していきたいと考えております。
次に、4点目の御質問、コミュニティバスなど既存の取組の検証、
市民ニーズの把握はしているのかの部分でございますが、既存
事業であるコミュニティバス、粟島グリーンスローモビリティ、乗合
タクシーなどの事業について、その取組の検証、市民ニーズの
把握につきましては、日々利用者や事業者の声を反映できるよう
努力はしておりますが、前述のとおり、ドライバー不足のため、
金銭的な面だけでは解決できない問題も多々あることは事実です。
先日開催された地域公共交通活性化協議会の場においても、
交通移動サービスの内容が市民にしっかり行き渡っていないので
はないかとの御意見も頂戴したところであり、今後はさらに市民に
寄り添いながら、交通行政の課題を解決できるよう、「行きたいとき
に行きたいところへ行けるまち」の確立を目指して、交通事業団を
核としてチャレンジしてまいります。
●再質問1
まず、交通システム事業団については、7月に設立して、財政面を
含め、スピード感のある持続的で新しいチャレンジを行っていきたい。
よく分かりました。
地域公共交通のリ・デザイン、再構築も進めていく、モデル地域も
詫間町大浜地域でという答弁、また、自動運転社会実装推進事業の
採択もすばらしいことだと思います。
その上で、まず、4番目のコミュニティバスなど既存の取組の検証、
市民ニーズの把握についてお聞きをいたします。
私のところへも利用者の声が届いているんですが、例えば荘内線の
西回りですが、地域交流館荘内が終点であれば、既存の大浜バス停
まで約500メートルといいますか数百メートルあります。
されど数百メートルでありまして、今まで乗り継ぎのバス停、大浜の
バス停には、地域の拠点であるクリニックや郵便局があります。
今までは普通に利用ができていた高齢者が地域交流館荘内から
歩いてクリニックや、年金支給日になって郵便局を利用しないといけ
ない状況に、バスが行かなくなって不便になっているという地域の声
をたくさんお聞きをしております。
また、コミュニティバスは、日中はさほど利用がないから大型のバン
のような車がいいのではないかとか、バス停にベンチを設置して
ほしいなど、利用者からの意見、要望、また、コミュニティバスの運転
手からは、県道や市道を樹木が塞いでいる。木や竹が覆いかぶさって
いるよと。
JR駅のバス停に違法駐車がされている。車両の老朽化がひどく、
代車といいますか予備車が足りないのではないかなど、事業者から
の声も頂いておりますが、このような声、当局は把握して対応、対策
を取っているのか。現場確認やデータをしっかり分析すれば早急な
対応ができるはずだと思うんですが。
私はこの利用者側、利用者のニーズが把握されていない原因の
一つに、本市では地域公共交通計画が作成されていて、地域公共
交通活性化協議会の委員が選定され、私ここに委員の名簿もあり
ますけど、市民ニーズが反映されていない理由に、利用者がメン
バーの委員の中にいないんですよ。
市民の代表として、自治会連合会の方、財田の方がおりますが、
コミュニティバスは利用されていない方だとお聞きをしております。
自家用車で移動していると。
協議会のメンバーは、私、令和3年第3回定例会の一般質問の
答弁で、交通事業者、利用者、市民の代表、学識経験者、道路管理
者など関係者としたいとの答弁が執行部からあったんですけど、
交通事業者の中には、経営者以外に運転手や公共交通ネット
ワークをつくるパートナー、利用者では、高齢者だけではない、車に
乗らない方、移住者とか高専生とか高校生とか、市民の代表より、
実際に乗っている人や沿線に立地する商店や企業、行政でも観光
交流局とか警察、運輸局などの関係者が目的を共有して本音で
議論ができる協議会が必要なのではないかと質問をさせていた
だきました。
もちろん警察や運輸局、大型スーパーの店長などは入っているんで
すけど、肝心の利用者、それもコミュニティバスの利用者が全くいない
点、ここが一番大きな問題であって、利用者の声が反映できていない
協議会だから、市民ニーズが反映されていないのかなと感じております。
全国でも、地域公共交通活性化協議会にコミュニティバスの利用者
が入っていないというところは、本当、私、調べたんですけど、珍しい
ようなんですけど、この辺りの協議会のメンバーの選定、選考も再度
考えていくべきかと思いますが、再質問をさせていただきます。
●答弁2(立石慎一政策部長)
まず、本年度のダイヤ改正により、荘内線の西回りの終点が変更に
なり、地域交流館荘内となったとの御指摘につきましては、4月の
ダイヤ改正時に地域交流館荘内の開設に伴い、乗り継ぎ地点を
大浜バス停から地域交流館荘内バス停へ変更したことから、西回り
線の終点からの病院や郵便局までの移動が不便になったものと
解しております。
御指摘を受けまして、次回の改正に合わせて最終地点を延伸する
のか、もしくは、さきの答弁で申し上げましたけれども、移動に関する
モデル地域として現在当該地域を想定しておりますので、その中で
ラストワンマイル対策として何らかの別の手段でおつなぎするのか
を検討しております。
しかしながら、いずれも一定の手続が必要になることから、しばらく
の間、御不便をおかけすることになりますが、御容赦いただきたく
存じます。
また、次に、コミュニティバスに対する様々な御要望や現状の
問題点などの把握について、当市の地域公共交通活性化協議会
の委員にバスの利用者がいないため、内容を把握できていない
のではとの御指摘についてですが、三豊市地域公共交通活性化
協議会の委員につきましては、設置根拠法令である地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律に基づき、
1、地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体、
2、関係する公共交通事業者等道路管理者、港湾管理者、その他
地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者、
3、関係する公安委員会、地域公共交通の利用者、学識経験者、
その他の当該地方公共団体が必要と認める者
の規定に基づき任命をさせていただいており、このうちの地域公共
交通の利用者、いわゆる市民の代表団体である市自治会連合会の
代表者、また、老人クラブ連合会の代表者のお二方に参画を頂いて
おります。
一方、これらの委員による審議で移動困難者の声を反映した審議、
管理ができているのかの御質問ですが、当然のことながら、審議に
対しての各議案は、活性化協議会の委員に頂く御意見はもとより、
交通担当者が日々の業務の中で、市民、御利用者、運行事業者
からお伺いした移動に関する課題や要望等を踏まえ、市民にとって
よりよい移動サービスと公共交通環境となるよう調整した上で、
委員各位に御審議を頂いております。
いずれにいたしましても、今後の地域公共交通活性化協議会の
委員改選の際には、バス利用者様の委員選定の検討をいたします。
また、頂きました御要望を踏まえ、運行事業者や関係機関との協議
を行いながら、三豊市交通システム事業団においては、多様な視点
を持ち、共創による活力や効果的なアイデア、サービスを模索しな
がら、市民の地域移動交通の利便性を目指してまいりたいと思います。
今後も引き続き、移動に困難を感じている方の声をお伺いしながら、
よりよい地域公共交通を整備してまいりたいと考えております。

●再質問2
ありがとうございます。市民の代表、各種団体の代表、いるということ
ですが、そこは実際のバス利用者を入れていただけるようにお願いを
申し上げます。
地域交通のリ・デザインについてもお聞きをいたします。
国土交通省が2022年度地域交通のリ・デザインに関する有識者提言
を公表して、それらを受けて、交通政策審議会の部会が地域公共交通
のリ・デザインの中間取りまとめを行って、サービスの低下と利用者の
減少という負の連鎖を正面から捉え、一歩踏み込んだ提言をしております。
アフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」有識者検討会の
構成員名簿では、地域公共団体のヒアリング対象として、山下昭史
市長もメンバーで出席されたこともあり、大変よく御存じかと思います。
これは、簡単に言えば、地域公共交通をリ・デザインという形で再構築
をしていくべきという提言で、先ほど答弁にありました交通DX・GX、
三つの共創、地域の関係者の連携と協働を通じて、利便性、持続可能
性、生産性を高めていきたい、そういう国土交通省の目指す提言に
沿っていくという点は、国交省から全国的に同じ提言があるわけです
から、粛々とお願いをしたいと思います。
2023年4月には、地域公共交通活性化再生法の一部改正も行われて
おります。
関西大学経済学部の宇都宮浄人教授の寄稿を読ませていただきまし
たが、ポイントは、中間取りまとめの中で繰り返し出てくる地域経営に
おける連携強化であります。
まちづくり、地域づくりと交通との連携が進んでいないという全国の
自治体の問題の一つが本市にもあるように思います。
1990年代から交通とまちづくりの連携の可能性が議論され、取り組ま
れてきましたけど、今なお連携が進んでいないということについて、
今回の中間取りまとめでは、関係者の意識や、地域全体をコーディ
ネートできる人材の不足等を一つの原因と認めて、官民事業者、分野
間の共創を進めていこうという方針が結局は出されております。
共創というのは、「共に創造する」の「創」ですけど、企業があらゆる
利害関係者、ステークホルダーと協働しながら新しい価値を創造していく
こと。
ステークホルダーには、企業、自治体、消費者とか利用者などが含まれ
ます。
まさにここが重要だと感じております中、本市ではmobiさん、ここが頑張
られているのに、エリアが拡大しない理由、コミュニティバス、タクシー
事業者などとも協働が進んでいるとは到底思えませんし、その辺りの
協働、連携を交通システム事業団が担えるのか、担ってくれるのかが
一番に私は聞きたいところであります。
つい先日にはmobiの若い社長さんともお話を伺いましたが、リ・デザ
インを目指す官民の共創としてのデータも持っていますし、交通事業者
間の共創は、共同経営でタクシー事業者との垣根を越えたサービス
展開、また、他分野を含めた共創では、介護や教育など様々な分野と
垣根を越えた事業連携を近いうちに取り組みたいと話されていました。
地域公共交通の様々な役割、教育、観光、健康、まちづくりをミックス
させる移動をどうしていくのか、彼が真剣に考えていただいていること
がお話を聞いて本当に分かりました。
もちろん民間企業の事業ですから、市費の投入はできませんが、
2022年、2023年度とも国交省の共創モデル実証プロジェクトの採択
は受けていて、三豊市=mobiということが検索でも出てきますし、
ここが全国的に私は知名度も上がっているような気がします。
ただ、高専生の通学支援にはなっていますが、高齢者の通院、買物
などのお出かけ支援までは拡大がされていないようで、私もJR詫間
駅の朝の様子も見てまいりましたが、非常に高専生がたくさん利用
しております。
この辺り、先進的に地域交通に取り組んでいる事業者の声を聞いて、
リ・デザイン再構築を早急にするべきだと考えますが、どのように
お考えがあるのかを再質問いたします。
●答弁3(立石慎一政策部長)
地域公共交通のリ・デザインについてですが、議員御発言のとおり、
国土交通省は、令和2年度、地域交通のリ・デザインに関する有識者
提言を公表いたしました。地域公共交通の再構築とは、交通DX、
交通GX、三つの共創を柱に、地域の関係者の連携と協働を通じて、
地域公共交通の利便性、生産性、持続可能性を高めることにあります。
本市の詫間・仁尾地域で、いわゆるサブスクタクシーとして運行を
開始した暮らしの交通株式会社mobi様に関しましては、地域の事業
者様の共同出資により事業を始められ、国土交通省の共創モデル
実証モデルも活用されながら、地域の新しい交通サービスとして運行
を続けられております。
これにより、運行エリア内である香川高専の学生さんはかなり利用
されているとお聞きしており、これまでコミュニティバスのみが通学
手段であった学生さんも選択肢が増えたことで分散され、雨天時の
コミュニティバスの乗りこぼしなどの解消が得られている状況です。
しかしながら、一方で、議員御発言のとおり、高齢者の方々の御
利用に関してはまだまだ拡大されていないという現状ですが、一方
で、市民の高齢者の方からnobiについてどのような仕組みなのか、
月額定額制やエリアについてお問合せがあることもあり、関心が
高いことも事実です。
そのほかにも当市の公共交通の機関であるコミュニティバスは、
市内複数の交通事業者の皆様によって運行されており、同様に
タクシー事業者、バス事業者様におきましても、これまで本市の
地域の移動交通は支えていただいております。
これらの事業者の皆様においては、厳しい社会状況の中、経営を
続けていただき、地域公共交通を支えてくださっていることに感謝
を申し上げたいと思います。
さて、三豊市として、多極分散型のまちづくりを目指していく中で、
コミュニティバスは公共交通の機関ではありますが、それだけでは
補えない課題がございます。議員御指摘のとおり、地域公共交通
の再構築については、これから公共交通を考えていく上で、共創、
協働しながら新しい価値を創造していくことが重要であり、それこそ
が今後設立予定の三豊市交通システム事業団の目指していく
ところであると考えております。
さきの答弁でも申し上げましたとおり、人口構造の変化に伴う移動
困難者の増加、また、ドライバー不足、燃料高騰の問題など、地域
が抱える移動に係る課題は日増しに大きくなっております。
だからこそ交通事業者、市民の皆様と共に、地域総動員で持続可能
な地域交通の再構築に向けた取組をスピード感を持って進めて
まいりたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りたいと存じます。
●再質問3
私、今回、地域公共交通全般を調査研究、勉強していまして分かった
ことがあるんですけど、地方の交通問題の本質として、全国的に公共
交通に関しては、新型コロナウイルス感染拡大で利用者が減少して
存続の危機に陥っている路線が少なくなく、特に地方では顕著で
あります。
しかし、鉄道に関わる一部のメディアを除いて、世論はそのことを
あまり大きな問題と捉えていません。
これは、地方の住民は、本市も含めてその大半が運転免許と自家用車
を保有して、日常の足として活用しており、交通問題で特に困っていない
ためなのかなということであります。
本市においても、私たち議員しかり、当局の皆さんも、ほとんどが自家
用車で庁舎に通勤する移動であって、ほとんどの方が地域公共交通
は利用していないように思います。
仮にコミュニティバスやタクシー事業者が撤退しても、ふだんから使って
いない人には関係ないです。
遠方から来る人はいても、自ら自家用車を運転して迎えに行けばいいし、
保護者が毎日駅や学校に送迎する家庭、高齢者を病院やクリニックへ
家族が送迎するケースも多く、これがほとんどかもしれません。
それゆえ協議会に利用者が入っていない理由もこの辺りにあるのかな
と思います、私は。
2021年に実施された都市交通特性調査の結果を見ると、地方都市圏
における公共交通の分担率は、平日で6%、休日で3%と、3大都市圏
の平日27%、休日16%とはかけ離れており、結局、地方部では9割以上
の方が自転車か徒歩、二輪車、自動車での移動だそうです。
先日SNSで、香川県の運転免許保有率を令和6年1月1日現在で計算
されている方がおりまして、高松70.6%、丸亀72.1%、軒並み70%前半
の中で、本市は76.3%であるよと教えていただきました。
18歳以上の免許保有率は、令和5年度当初ベースで、私が計算して
みましたが、間違っているかもしれませんけど、85%ぐらいかなと思います。
本市もその上に自転車、徒歩、二輪車利用を入れれば9割の方が困って
いないということになるのかなと個人的に感じております。
18歳になれば免許を取得するのが当たり前。高齢者は免許返納しよう
と思うが返納できない。
返納したら命取られたんと同じやが、通院にも買物にも行けんようになる
がという声をたくさんお聞きしております。
このことが地方の交通問題の本質であって、地方部では、自動車で移動
している限りにおいては、交通に関する問題意識は生じにくく、ある意味
では快適な生活が実現している。交通弱者である高校生や高齢者など、
何らかの事情で自動車を運転できない人のことがなおざりにされている
現状があります。
流通経済大学の板谷教授の寄稿を読ませていただいたんですけど、
まさしく私、そのとおりだと思いました。
地方部では依存した交通体系になっているために、自動車を運転でき
ない住民が大きな不利益を被っており、このままでは長期的に地方の
衰退につながることが危惧されるものの、住民の大半は危機感を感じて
おらず、本市もコミュニティバスは特別交付税措置があるから走らせら
れているという現状があるように思います。この状況への対策として、
何よりも住民の意識改革が必要であり、ビジネスモデルを転換する
必要があって、リ・デザインという再構築、官民交通事業者、他分野の
共創という形での成功事例をつくる。これが本市で実現されれば、
本当にすばらしいことだと感じますが、ドライバー不足が顕著な中では、
ここは一旦リセットして考えないといけない時期に来ているのかなと
思います。
ローカルベーシックインフラの構築も、一旦データ連携基盤から離れて
考えていくべきではないか。
ベーシックインフラから一旦離れてできること、やれることがあるのでは
ないかなとも感じております。
例えば、本市の65歳からの福祉タクシーの利用もデータ分析する必要が
あります。先ほど言いましたように、本市の運転免許証保有率が高いし、
地方では9割以上の方が自転車とか徒歩、二輪車、自動車での移動
ですから、免許返納する人というのは限界があると思いますが、
そこにこだわる必要があるのかとも考えております。
健康福祉部長にもこの点についてお考えがあれば答弁をお願いしたい
ところです。
様々な移動のデータを分析して、スピード感を持って様々なことを
やっていく必要が、昨日の同僚議員の質問にもありましたけど、それ
だったら地域公共交通をリセットして、ドライバー不足だったら、なお
さら高校生とか高齢者などに特化して再構築をしていくこと。
高齢者に限っては、例えば免許返納者だけでなくて、例えば80歳とか
一定の高齢者に達した方には、以前のように全員福祉タクシー券を
配付して、まずはタクシーやバスを使っていただき、地域の公共交通
を知って利用していただいてから次の利用につなげていくということは
すぐにできますし、データも取れるかと私は思います。
このような点はどのようにお考えでしょうか、再質問いたします。
●答弁4(田中昌和健康福祉部長)
福祉タクシー事業につきましては、高齢者の交通手段の確保及び
経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的に事業
を開始いたしましたが、令和元年度からは、交通事故の減少を図る
ため、高齢ドライバーの運転免許証の自主返納を支援することも
加えた事業となった経緯がございます。
議員御案内のとおり、本市のような地方部においては、高齢者の
移動手段が徒歩や自転車のほかには、二輪車や自動車での移動が
ほとんどであり、免許返納にも限界があることは認識しておりますが、
福祉タクシー事業だけでは高齢者の日々の交通手段の根本的な
解決は難しいと考えております。
また、議員御提案の高齢者全員への福祉タクシー券の配付に
ついては、これまでの事業の経過や財政的な面からも拡充は
難しいと考えております。
また、福祉タクシー利用のデータ分析につきましては、現状の
福祉タクシー券は紙ベースのため、データ収集及び分析は現状
では困難であると考えておりますので、御理解賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
●再質問5
そういう答弁を頂けると思っていなかったので、これについては、
また別途やりたいと思います。これは話すると長いので。
次に、新しい共有の形、過疎地のライドシェアを提案したいと思います。
ライドシェアとは、移動の手段である車と、それを運転するドライバーを
シェアリングする新しい移動の形です。
スマートフォンアプリなどで配車を依頼して、タクシーのように利用する
形式が一般的なライドシェアの仕組みとなっております。
海外ではウーバー社などが有名ですが、ドライバー不足を解消する
べく、規制緩和していくライドシェア、これは都市型ライドシェアであり
まして、最近、そうではない過疎地のライドシェアが脚光を浴びており
ます。
過疎地のライドシェアは、十分な運転能力はあるものの、職業ドライバー
になることが難しい潜在的ドライバーを活用して、具体例として、平日
にも空き時間がある学生や、休日に副業をしたいサラリーマンなどが
配車アプリを通じて、移動を提供する人と移動したい人をマッチング
させればスタートできるというものであります。
フルタイムで職業ドライバーになることが難しい地域住民の方々が
ドライバーの担い手になっていただくことが過疎地ライドシェアの
ポイントで、路線バスの維持に苦心している自治体にとって、公共
交通を維持する切り札となるかもしれないものです。
北海道をはじめ、全国でも導入が進んでおります。既存の路線バス
と異なり、決められた路線やダイヤがないために、運行台数や時間帯
の柔軟な調整によって住民の方々のニーズに応えることが可能であり、
潜在的ドライバーと遊休車両を過疎地ライドシェアアプリがマッチング
するものであり、これらも検討していくべきではないのかなと提案を
させていただきますけど、これもmobi、ライドシェア、乗合タクシーなど、
様々な選択肢があって、地域との協働を考えて、公共交通を担っていく
べきであると考えます。どのようにお考えでしょうか。
●答弁6(立石慎一政策部長)
ライドシェアは、日本版ライドシェアと呼ばれるものと、議員御発言の
過疎地でのライドシェア、いわゆる自治体ライドシェアの二つに区分を
されております。
日本版ライドシェアについては、昨今の報道でも取り扱われており
ますとおり、本年4月には東京、神奈川県、愛知県、京都府の一部
地域がその運行対象となり、5月からは札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、
神戸、広島、福岡の8地域において、区域ごとにタクシーが不足する
時間帯のみ運行が認められ、料金はタクシーと同額での運用が
行われております。
一方、御質問の自治体ライドシェアにつきましては、日本版のそれ
以前から各地において、道路運送法の自家用有償旅客運送の一つ
として、過疎地などの公共交通空白地にて認められております。
現在、その運行主体を民間や地域団体に拡大する動きもあるようです。
これらの一部解禁や拡大に向けた動きの背景としては、御案内の
とおり、深刻なドライバー不足に起因するものであり、信用補償調査
企業の調査では、この10年でタクシー・ハイヤー事業者において、
ドライバーなどの従業員が半減した事業者は全国で14.5%、香川県
においてはその平均をはるかに超える、全国で2番目に減少率が
高い29%の事業者が半減したとの結果が出ております。
このライドシェアについての市の考え方はとの御質問でございます
が、本市が抱える課題も全国と同様であり、ドライバー不足は深刻さ
を増しております。
ライドシェアは、これらを担っていただける市民のドライバーの方々や
地域交通事業者の皆様の御協力が整い、初めてスタートラインに立つ
ものでございます。議員御発言の地域の公共交通リ・デザイン実現
会議取りまとめ報告書にもありますとおり、地域のあらゆる輸送資源
を総動員し、当該資源を地域の関係者で効率的に確保し運行すること
で、持続可能な地域交通を確保していく必要があると感じております。
このようなことから、今後、移動交通に係る課題を地域全体の課題と
して捉え、地域全体で確保に向けて検討をしてまいりたいと考えております。
●再質問6
やはり国土交通省の提唱するリ・デザインに関する制度について、最後に
またお聞きをしますけど、本市では交通DXで自動運転はやります。
MaaSも取り組みます。交通GXではEVバスもやっています。
ただ、これは全国どこでもできる施策であって、本市が独自で何をやるのか、
何ができるのかが重要になるかと感じております。
三つの共創、官民、交通事業者間、他分野の共創を考えれば、ここに
父母ヶ浜や紫雲出山の観光、介護や、特に教育、スクールバスや放課後
改革など移動と共創することができるのは理解できます。
JR詫間駅は、高専生のbomi利用がありますが、JRの高瀬駅が新しく
なるとしても、ここを交通の拠点とするにはデータが必要です。JR四国
との詳細な協議も必要かと感じます。
私は特に介護のほうで島根県大田市の井田いきいきタクシーという
事例を調べました。
高齢者の移動目的は何か、ずばり通院と買物だけではなく、サブスクで
乗り放題をすると趣味や娯楽が多くなり、楽しみの移動で外出すること
が確認できたそうです。
実際に利用者へのヒアリングからは、毎週誘い合って温泉に行くとか、
友人宅におしゃべりに行く利用者が数多く存在して、今後はこのような
交通サービスで介護予防効果の分析を行うことで、交通に係る経費
以上の健康寿命増進による経費削減効果を詳細に算出することが
可能となっているようです。
やはり福祉も交通と協働、共創していくべきなんですよ。田中部長、
私はそう思いますけど。
もちろんここはベーシックインフラにつながる部分かと思いますが、
特定企業だけでなくコミュニティバスの沿線には多くの民間企業が
ありますし、応援いただく個人も募っていくべきであります。
ベーシックインフラのような大きなデータ連携基盤の活用もいいん
ですが、本市の高齢者や高校生などの声を聞いて意見を反映して、
エビデンスを取ることで、今すぐできる地域公共交通対策、スピード
感を持ってやることが多々あるはずであります。
私は、今言いました多くのすばらしい企業とか、多くの民間企業
や各種団体を広域で巻き込んで、広域の地域公共交通も考えて
支援していくべきだと考えておりますが、この交通システム事業団、
具体的な目標を挙げて、いつまでにやるのか、具現化して取り組ん
でいく、成功事例が全国的にない中で本市が成功事例をつくって
いくぐらいの意気込みが欲しいと思います。
本市独自の新しい事業としての地域公共交通の再構築のお考えを
最後に市長に発言をお願いいたします。
●答弁7(山下昭史市長)
1点、先ほどの福祉のお問合せ、質問に対しての答弁ですが、
やっていないわけではなくて、ダイハツと一緒にやっています共同
送迎、これも福祉でありますので、福祉タクシーのチケットに関して
の部分では部長が答弁したとおりなんですけれども、福祉分野に
おける取組というのはやっておりますし、共同送迎における段階的
な目的は、議員が御質問されていましたような、いわゆる買物支援
とかというのはフェーズによって、今度、そういった部分を含めて
まいりますので、そういった点ではミックスしていくということは御理
解いただけたらと思います。
それを前提にいたしまして、先ほどの公共交通の地域課題の解消
を目指しまして、三豊市では様々なMaaSへの実証や取組を行って
まいりました。
その中の一つに粟島グリーンスローモビリティがありますけれども、
この利用者の声としては、特に用じゃなくても友達と一緒にドライブ
がてらに乗るとか、ドライバーとの世間話が癒やされるなど、まさに
生活のため、何か目的のための移動というだけでなく、外出機会の
創出、楽しめる移動という御利用もされているようです。
また、財田乗合タクシーの実証におきましても、地域のイベント時の
タクシー御利用が突出して多いんです。
行きたいものに参加できることで、いつまでも地域になじみ、幸福感
を持つことができるということ。健康寿命増進につながることがまさに
期待できると考えております。
しかしながら、一方で、これまでの答弁にもありましたように、人口
構造の変化、担い手不足等の移動に関する将来不安がある中で、
地域の交通課題はより深刻化されております。
これに対し、三豊市では、交通DXである自動運転に取り組みまして、
今だからこそ、遅れをとらず、新技術の活用により、地方の交通課題
を打破できるようなチャレンジに取り組みたいと考えております。
自動運転のチャレンジは今からではありますが、こういった取組を
得て、新たな技術や地域の多くの人や物に資源を最大限活用しな
がら、行政だけでなく、民間の活力、他分野を含めた共創による交通
サービスを模索していきたいと思っておりまして、
「行きたいときに行きたいところへ行けるまち」
を目指していくための交通システム事業団であります。これは7月を
設立目標にしております。
そういった意味では、地域の皆様の連携協働による利便性の高い
持続可能な公共交通を目指してまいりたいと思います。
もう一点、広域に関してですけれども、議員御指摘のとおりでして、
生活圏というのは基本的に行政区域とは必ずしも一致しておりません。
琴平に近い高瀬町の人は琴平での買物とかが多かったりしますし、
財田町の人もそうです。また一方で、豊中の人が観音寺のほうに
買物に行く、この生活圏に応じた取り組み方というのが必要だと
思います。
公共交通という言葉自体がミックスという中では、今後意味を違えて
くるのかなと思っておりますし、先ほど言いました観光、父母ヶ浜に
来られる方も、観光用の乗り物ではなくて、市民生活と一緒に利用
できるようなもの、そういったものも必要です。
一番問題になっているのは2次交通でありまして、高松空港から
こちら三豊に来る人が交通手段がないとか、そういった部分も含めて
考えるときに、これは三豊市だけの交通システムではなくて、コミュ
ニティバスは既に琴平町に行ったり、三豊総合病院に行ったりして、
善通寺も行ったりしておりますので、そういった延長線で考えると
いうことが今後重要であると思いますし、そういった議員御指摘の
部分に関しては、当然、交通事業団が中心となって取り組んでいく
ものと考えております。
以上、結構いろいろ言わせていただいた、1問目でした。
大浜地域のことをどうしても発言してしまいます。
皆さん、いろんな意見をいただき、嬉しい限りです。
それと福祉タクシー券の一定年齢への配布は・・・言い続けます。
エビデンスがあるので ・・・。
・・・。
以下の2問でした。
動画はコチラ
1.地域公共交通全般について
今春の組織変更により、政策部地域戦略課内に
「交通システム事業団設立準備室」
が新設された。
人口構造の変化に伴い、担い手不足などの移動に関する将来不安
が生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素である「移動」を確保
する必要がある、とのことだが今後の具体的な設立計画・方針と地域
公共交通全般の現状などについて聞く。
(1)民間活力の反映とは、三豊市地域公共交通計画との整合性
(2)財政面も含めスピード感のある持続的で新しいチャレンジとは
(3)移動に関するモデル地域は設定するのか
(4)コミュニティバスなど、既存の取り組みの検証、市民ニーズの把握は
しているのか
2.住宅の耐震対策などについて
能登半島地震において、多くの木造住宅の被害が甚大であった。
施政方針において、珠洲市は「明日の三豊市」と言う山下市長には、
本市の耐震診断と耐震対策を一層促進、啓発する必要があると考える。
補助事業を強化するためにどのような取り組みや市民周知をしていくのか、
また旧耐震基準だけでなく、1981年6月以降2000年5月以前の新耐震
基準住宅の耐震性能が不足しているという可能性が認識されている中、
現状を把握して、民間危険ブロック塀も含めた補助金の拡充について
検討・導入していかないのか。
とにかく最近は、多くの分野で質問するように心がけています。
後は「教育委員会」と「子育て支援」などが残るかなぁ、とか思っています
が、私みたいなのが「教育」を語れませんから、今勉強しております
 。
。●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。通告に従いまして一般質問をさせて
いただきますので、よろしくお願いします。
初めに、地域公共交通全般についてお聞きいたします。
今週の組織改正により、政策部地域戦略課内に交通システム事
業団設立準備室が新設されました。
新設理由として、人口構造の変化に伴い、担い手不足等の移動に
関する将来不安が生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素
である移動を確保する必要があるとのことですが、本市では三豊市
地域公共交通計画も策定がされており、基本理念「行きたいときに
行きたいところへ行けるまち」が設定されております。
本市の地域公共交通といえば、既存のJR鉄道の2線6駅、市コミ
ュニティバス、民間タクシー、汽船といった公共交通から、新たな
移動である詫間・仁尾エリアでの民間企業が運営する乗り合い
オンデマンド交通mobiさん、令和5年10月より本格運行へ移行
した粟島でのグリーンスローモビリティ、財田町にて実証中の乗合
タクシー、これについては令和6年度も継続運行がされており、
まさに新たな移動が生まれてきておりますが、
(1)今回、新たに設立される三豊市交通システム事業団が担うで
あろう民間活力の反映とは。三豊市地域公共交通計画との整合性。
(2)財政面も含め、スピード感のある持続的で新しいチャレンジとは何か。
(3)移動に関するモデル地域は設定するのか。
(4)コミュニティバスなど、既存の取組の検証、市民ニーズの把握は
しているのか。
以上4点を中心に、今後の具体的な地域公共交通についての現状と、
今後の計画方針と提案も含めた全般についてお聞きをいたしますので、
簡潔明瞭な答弁をお願いいたします。
●答弁1(山下昭史市長)
議員御質問にありましたとおり、今年度の組織改正により、政策部
地域戦略課内に交通システム事業団設立準備室が新設となりました。
人口構造の変化に伴い、担い手不足等の移動に関する将来不安が
生じる中で、市民の暮らしを支える重要な要素である移動を確保して
いく必要があります。
このため、民間活力を反映させること、また、財政面も含め、スピード
感のある持続的で新しいチャレンジを行うことを目的として、交通シス
テム事業団の設立をしたいと考えております。
まず、1点目の民間活力の反映とはの部分でございますが、全国的
にも人口減少や人口構造の変化に伴うドライバー不足、また、働き方
改革による路線バスの減便は報道されているとおりです。
三豊市でも、4月の市内交通事業者への調査で、10社中8社がドラ
イバー不足であるとの回答であり、その8社では、現状に対してドライ
バーの必要数は、平均で3人の不足、多いところでは5人の不足との
回答が2社ありました。
また、現有ドライバーの年齢層につきましても、10社の現ドライバーの
うち55%が60歳以上で運行されている現状でありました。
一方で、これらドライバー不足などの交通移動が直面している課題は、
昨年10月に施行された地域公共交通活性化再生法で掲げられている
とおり、交通事業者の経営努力のみでは避けられないものであるため、
自動運転やMaaSなどデジタル技術を実装する交通DX、車両電動化
や再エネ、地産地消など交通GX、そして官民共創、交通事業者間共
創、多分野共創の三つの共創、共に創るほうですけれども、すなわち、
地域の関係者の連携と協働を通じて、利便性、持続可能性、生産性
を高める地域公共交通のリ・デザインを進める必要性を強く感じて
おります。
このことからも、地域で頑張ってくださっている地域交通事業者と共に、
あらゆる民間活力の支援も頂きながら、持続する地域公共交通を
見据えたいと考えます。
また、三豊市地域公共交通計画との整合性につきましては、まさに
計画の基本理念である「行きたいときに行きたいところへ行けるまち」
を事業団のコンセプトとして持ち、人や物といった地域の資源を最大限
活用し、必要に応じては、先端技術や新しいモビリティサービスにも
挑戦しながら、ニーズに応じた交通ネットワークの整備を目指してまい
りたいと思います。
次に、2点目の財政面も含め、スピード感のある持続的で新しいチャ
レンジとはの部分でございますが、これら全てを行政のみで補完して
いくのではなく、様々な共創の下、人、物、金など資源を有益に掛け
合わせることで、持続可能となるシステムにチャレンジしていきたいと
考えています。
まずは、慢性的な人手不足の中、また、人口構造の変化を見据えると、
自動運転については必ず視野に入れていく必要があると考えており、
三豊市では、国土交通省の自動運転社会実装推進事業に応募して
おりました。そして、このたび、6月6日に採択の通知がございました。
三豊市では、最新技術を取り入れた自動運転の実証運行をすること
により、地域の交通課題の解決を図れる将来へとなるようチャレンジ
してまいります。
次に、3点目の移動に関するモデル地域は設定するのかの部分で
ございます。
これまでにも半径2キロの地域生活圏構想は申し上げてきたとおり
です。
このたび、大浜地域では、地域の拠点となる施設、機能の整備や
民間事業者の進出も徐々に整ってきております。
今後、この大浜をモデル地域として、生活における交通移動の課題
解決を検討していきたいと考えております。
次に、4点目の御質問、コミュニティバスなど既存の取組の検証、
市民ニーズの把握はしているのかの部分でございますが、既存
事業であるコミュニティバス、粟島グリーンスローモビリティ、乗合
タクシーなどの事業について、その取組の検証、市民ニーズの
把握につきましては、日々利用者や事業者の声を反映できるよう
努力はしておりますが、前述のとおり、ドライバー不足のため、
金銭的な面だけでは解決できない問題も多々あることは事実です。
先日開催された地域公共交通活性化協議会の場においても、
交通移動サービスの内容が市民にしっかり行き渡っていないので
はないかとの御意見も頂戴したところであり、今後はさらに市民に
寄り添いながら、交通行政の課題を解決できるよう、「行きたいとき
に行きたいところへ行けるまち」の確立を目指して、交通事業団を
核としてチャレンジしてまいります。
●再質問1
まず、交通システム事業団については、7月に設立して、財政面を
含め、スピード感のある持続的で新しいチャレンジを行っていきたい。
よく分かりました。
地域公共交通のリ・デザイン、再構築も進めていく、モデル地域も
詫間町大浜地域でという答弁、また、自動運転社会実装推進事業の
採択もすばらしいことだと思います。
その上で、まず、4番目のコミュニティバスなど既存の取組の検証、
市民ニーズの把握についてお聞きをいたします。
私のところへも利用者の声が届いているんですが、例えば荘内線の
西回りですが、地域交流館荘内が終点であれば、既存の大浜バス停
まで約500メートルといいますか数百メートルあります。
されど数百メートルでありまして、今まで乗り継ぎのバス停、大浜の
バス停には、地域の拠点であるクリニックや郵便局があります。
今までは普通に利用ができていた高齢者が地域交流館荘内から
歩いてクリニックや、年金支給日になって郵便局を利用しないといけ
ない状況に、バスが行かなくなって不便になっているという地域の声
をたくさんお聞きをしております。
また、コミュニティバスは、日中はさほど利用がないから大型のバン
のような車がいいのではないかとか、バス停にベンチを設置して
ほしいなど、利用者からの意見、要望、また、コミュニティバスの運転
手からは、県道や市道を樹木が塞いでいる。木や竹が覆いかぶさって
いるよと。
JR駅のバス停に違法駐車がされている。車両の老朽化がひどく、
代車といいますか予備車が足りないのではないかなど、事業者から
の声も頂いておりますが、このような声、当局は把握して対応、対策
を取っているのか。現場確認やデータをしっかり分析すれば早急な
対応ができるはずだと思うんですが。
私はこの利用者側、利用者のニーズが把握されていない原因の
一つに、本市では地域公共交通計画が作成されていて、地域公共
交通活性化協議会の委員が選定され、私ここに委員の名簿もあり
ますけど、市民ニーズが反映されていない理由に、利用者がメン
バーの委員の中にいないんですよ。
市民の代表として、自治会連合会の方、財田の方がおりますが、
コミュニティバスは利用されていない方だとお聞きをしております。
自家用車で移動していると。
協議会のメンバーは、私、令和3年第3回定例会の一般質問の
答弁で、交通事業者、利用者、市民の代表、学識経験者、道路管理
者など関係者としたいとの答弁が執行部からあったんですけど、
交通事業者の中には、経営者以外に運転手や公共交通ネット
ワークをつくるパートナー、利用者では、高齢者だけではない、車に
乗らない方、移住者とか高専生とか高校生とか、市民の代表より、
実際に乗っている人や沿線に立地する商店や企業、行政でも観光
交流局とか警察、運輸局などの関係者が目的を共有して本音で
議論ができる協議会が必要なのではないかと質問をさせていた
だきました。
もちろん警察や運輸局、大型スーパーの店長などは入っているんで
すけど、肝心の利用者、それもコミュニティバスの利用者が全くいない
点、ここが一番大きな問題であって、利用者の声が反映できていない
協議会だから、市民ニーズが反映されていないのかなと感じております。
全国でも、地域公共交通活性化協議会にコミュニティバスの利用者
が入っていないというところは、本当、私、調べたんですけど、珍しい
ようなんですけど、この辺りの協議会のメンバーの選定、選考も再度
考えていくべきかと思いますが、再質問をさせていただきます。
●答弁2(立石慎一政策部長)
まず、本年度のダイヤ改正により、荘内線の西回りの終点が変更に
なり、地域交流館荘内となったとの御指摘につきましては、4月の
ダイヤ改正時に地域交流館荘内の開設に伴い、乗り継ぎ地点を
大浜バス停から地域交流館荘内バス停へ変更したことから、西回り
線の終点からの病院や郵便局までの移動が不便になったものと
解しております。
御指摘を受けまして、次回の改正に合わせて最終地点を延伸する
のか、もしくは、さきの答弁で申し上げましたけれども、移動に関する
モデル地域として現在当該地域を想定しておりますので、その中で
ラストワンマイル対策として何らかの別の手段でおつなぎするのか
を検討しております。
しかしながら、いずれも一定の手続が必要になることから、しばらく
の間、御不便をおかけすることになりますが、御容赦いただきたく
存じます。
また、次に、コミュニティバスに対する様々な御要望や現状の
問題点などの把握について、当市の地域公共交通活性化協議会
の委員にバスの利用者がいないため、内容を把握できていない
のではとの御指摘についてですが、三豊市地域公共交通活性化
協議会の委員につきましては、設置根拠法令である地域公共交通
の活性化及び再生に関する法律に基づき、
1、地域公共交通計画を作成しようとする地方公共団体、
2、関係する公共交通事業者等道路管理者、港湾管理者、その他
地域公共交通計画に定めようとする事業を実施すると見込まれる者、
3、関係する公安委員会、地域公共交通の利用者、学識経験者、
その他の当該地方公共団体が必要と認める者
の規定に基づき任命をさせていただいており、このうちの地域公共
交通の利用者、いわゆる市民の代表団体である市自治会連合会の
代表者、また、老人クラブ連合会の代表者のお二方に参画を頂いて
おります。
一方、これらの委員による審議で移動困難者の声を反映した審議、
管理ができているのかの御質問ですが、当然のことながら、審議に
対しての各議案は、活性化協議会の委員に頂く御意見はもとより、
交通担当者が日々の業務の中で、市民、御利用者、運行事業者
からお伺いした移動に関する課題や要望等を踏まえ、市民にとって
よりよい移動サービスと公共交通環境となるよう調整した上で、
委員各位に御審議を頂いております。
いずれにいたしましても、今後の地域公共交通活性化協議会の
委員改選の際には、バス利用者様の委員選定の検討をいたします。
また、頂きました御要望を踏まえ、運行事業者や関係機関との協議
を行いながら、三豊市交通システム事業団においては、多様な視点
を持ち、共創による活力や効果的なアイデア、サービスを模索しな
がら、市民の地域移動交通の利便性を目指してまいりたいと思います。
今後も引き続き、移動に困難を感じている方の声をお伺いしながら、
よりよい地域公共交通を整備してまいりたいと考えております。
●再質問2
ありがとうございます。市民の代表、各種団体の代表、いるということ
ですが、そこは実際のバス利用者を入れていただけるようにお願いを
申し上げます。
地域交通のリ・デザインについてもお聞きをいたします。
国土交通省が2022年度地域交通のリ・デザインに関する有識者提言
を公表して、それらを受けて、交通政策審議会の部会が地域公共交通
のリ・デザインの中間取りまとめを行って、サービスの低下と利用者の
減少という負の連鎖を正面から捉え、一歩踏み込んだ提言をしております。
アフターコロナに向けた地域交通の「リ・デザイン」有識者検討会の
構成員名簿では、地域公共団体のヒアリング対象として、山下昭史
市長もメンバーで出席されたこともあり、大変よく御存じかと思います。
これは、簡単に言えば、地域公共交通をリ・デザインという形で再構築
をしていくべきという提言で、先ほど答弁にありました交通DX・GX、
三つの共創、地域の関係者の連携と協働を通じて、利便性、持続可能
性、生産性を高めていきたい、そういう国土交通省の目指す提言に
沿っていくという点は、国交省から全国的に同じ提言があるわけです
から、粛々とお願いをしたいと思います。
2023年4月には、地域公共交通活性化再生法の一部改正も行われて
おります。
関西大学経済学部の宇都宮浄人教授の寄稿を読ませていただきまし
たが、ポイントは、中間取りまとめの中で繰り返し出てくる地域経営に
おける連携強化であります。
まちづくり、地域づくりと交通との連携が進んでいないという全国の
自治体の問題の一つが本市にもあるように思います。
1990年代から交通とまちづくりの連携の可能性が議論され、取り組ま
れてきましたけど、今なお連携が進んでいないということについて、
今回の中間取りまとめでは、関係者の意識や、地域全体をコーディ
ネートできる人材の不足等を一つの原因と認めて、官民事業者、分野
間の共創を進めていこうという方針が結局は出されております。
共創というのは、「共に創造する」の「創」ですけど、企業があらゆる
利害関係者、ステークホルダーと協働しながら新しい価値を創造していく
こと。
ステークホルダーには、企業、自治体、消費者とか利用者などが含まれ
ます。
まさにここが重要だと感じております中、本市ではmobiさん、ここが頑張
られているのに、エリアが拡大しない理由、コミュニティバス、タクシー
事業者などとも協働が進んでいるとは到底思えませんし、その辺りの
協働、連携を交通システム事業団が担えるのか、担ってくれるのかが
一番に私は聞きたいところであります。
つい先日にはmobiの若い社長さんともお話を伺いましたが、リ・デザ
インを目指す官民の共創としてのデータも持っていますし、交通事業者
間の共創は、共同経営でタクシー事業者との垣根を越えたサービス
展開、また、他分野を含めた共創では、介護や教育など様々な分野と
垣根を越えた事業連携を近いうちに取り組みたいと話されていました。
地域公共交通の様々な役割、教育、観光、健康、まちづくりをミックス
させる移動をどうしていくのか、彼が真剣に考えていただいていること
がお話を聞いて本当に分かりました。
もちろん民間企業の事業ですから、市費の投入はできませんが、
2022年、2023年度とも国交省の共創モデル実証プロジェクトの採択
は受けていて、三豊市=mobiということが検索でも出てきますし、
ここが全国的に私は知名度も上がっているような気がします。
ただ、高専生の通学支援にはなっていますが、高齢者の通院、買物
などのお出かけ支援までは拡大がされていないようで、私もJR詫間
駅の朝の様子も見てまいりましたが、非常に高専生がたくさん利用
しております。
この辺り、先進的に地域交通に取り組んでいる事業者の声を聞いて、
リ・デザイン再構築を早急にするべきだと考えますが、どのように
お考えがあるのかを再質問いたします。
●答弁3(立石慎一政策部長)
地域公共交通のリ・デザインについてですが、議員御発言のとおり、
国土交通省は、令和2年度、地域交通のリ・デザインに関する有識者
提言を公表いたしました。地域公共交通の再構築とは、交通DX、
交通GX、三つの共創を柱に、地域の関係者の連携と協働を通じて、
地域公共交通の利便性、生産性、持続可能性を高めることにあります。
本市の詫間・仁尾地域で、いわゆるサブスクタクシーとして運行を
開始した暮らしの交通株式会社mobi様に関しましては、地域の事業
者様の共同出資により事業を始められ、国土交通省の共創モデル
実証モデルも活用されながら、地域の新しい交通サービスとして運行
を続けられております。
これにより、運行エリア内である香川高専の学生さんはかなり利用
されているとお聞きしており、これまでコミュニティバスのみが通学
手段であった学生さんも選択肢が増えたことで分散され、雨天時の
コミュニティバスの乗りこぼしなどの解消が得られている状況です。
しかしながら、一方で、議員御発言のとおり、高齢者の方々の御
利用に関してはまだまだ拡大されていないという現状ですが、一方
で、市民の高齢者の方からnobiについてどのような仕組みなのか、
月額定額制やエリアについてお問合せがあることもあり、関心が
高いことも事実です。
そのほかにも当市の公共交通の機関であるコミュニティバスは、
市内複数の交通事業者の皆様によって運行されており、同様に
タクシー事業者、バス事業者様におきましても、これまで本市の
地域の移動交通は支えていただいております。
これらの事業者の皆様においては、厳しい社会状況の中、経営を
続けていただき、地域公共交通を支えてくださっていることに感謝
を申し上げたいと思います。
さて、三豊市として、多極分散型のまちづくりを目指していく中で、
コミュニティバスは公共交通の機関ではありますが、それだけでは
補えない課題がございます。議員御指摘のとおり、地域公共交通
の再構築については、これから公共交通を考えていく上で、共創、
協働しながら新しい価値を創造していくことが重要であり、それこそ
が今後設立予定の三豊市交通システム事業団の目指していく
ところであると考えております。
さきの答弁でも申し上げましたとおり、人口構造の変化に伴う移動
困難者の増加、また、ドライバー不足、燃料高騰の問題など、地域
が抱える移動に係る課題は日増しに大きくなっております。
だからこそ交通事業者、市民の皆様と共に、地域総動員で持続可能
な地域交通の再構築に向けた取組をスピード感を持って進めて
まいりたいと考えておりますので、御理解と御協力を賜りたいと存じます。
●再質問3
私、今回、地域公共交通全般を調査研究、勉強していまして分かった
ことがあるんですけど、地方の交通問題の本質として、全国的に公共
交通に関しては、新型コロナウイルス感染拡大で利用者が減少して
存続の危機に陥っている路線が少なくなく、特に地方では顕著で
あります。
しかし、鉄道に関わる一部のメディアを除いて、世論はそのことを
あまり大きな問題と捉えていません。
これは、地方の住民は、本市も含めてその大半が運転免許と自家用車
を保有して、日常の足として活用しており、交通問題で特に困っていない
ためなのかなということであります。
本市においても、私たち議員しかり、当局の皆さんも、ほとんどが自家
用車で庁舎に通勤する移動であって、ほとんどの方が地域公共交通
は利用していないように思います。
仮にコミュニティバスやタクシー事業者が撤退しても、ふだんから使って
いない人には関係ないです。
遠方から来る人はいても、自ら自家用車を運転して迎えに行けばいいし、
保護者が毎日駅や学校に送迎する家庭、高齢者を病院やクリニックへ
家族が送迎するケースも多く、これがほとんどかもしれません。
それゆえ協議会に利用者が入っていない理由もこの辺りにあるのかな
と思います、私は。
2021年に実施された都市交通特性調査の結果を見ると、地方都市圏
における公共交通の分担率は、平日で6%、休日で3%と、3大都市圏
の平日27%、休日16%とはかけ離れており、結局、地方部では9割以上
の方が自転車か徒歩、二輪車、自動車での移動だそうです。
先日SNSで、香川県の運転免許保有率を令和6年1月1日現在で計算
されている方がおりまして、高松70.6%、丸亀72.1%、軒並み70%前半
の中で、本市は76.3%であるよと教えていただきました。
18歳以上の免許保有率は、令和5年度当初ベースで、私が計算して
みましたが、間違っているかもしれませんけど、85%ぐらいかなと思います。
本市もその上に自転車、徒歩、二輪車利用を入れれば9割の方が困って
いないということになるのかなと個人的に感じております。
18歳になれば免許を取得するのが当たり前。高齢者は免許返納しよう
と思うが返納できない。
返納したら命取られたんと同じやが、通院にも買物にも行けんようになる
がという声をたくさんお聞きしております。
このことが地方の交通問題の本質であって、地方部では、自動車で移動
している限りにおいては、交通に関する問題意識は生じにくく、ある意味
では快適な生活が実現している。交通弱者である高校生や高齢者など、
何らかの事情で自動車を運転できない人のことがなおざりにされている
現状があります。
流通経済大学の板谷教授の寄稿を読ませていただいたんですけど、
まさしく私、そのとおりだと思いました。
地方部では依存した交通体系になっているために、自動車を運転でき
ない住民が大きな不利益を被っており、このままでは長期的に地方の
衰退につながることが危惧されるものの、住民の大半は危機感を感じて
おらず、本市もコミュニティバスは特別交付税措置があるから走らせら
れているという現状があるように思います。この状況への対策として、
何よりも住民の意識改革が必要であり、ビジネスモデルを転換する
必要があって、リ・デザインという再構築、官民交通事業者、他分野の
共創という形での成功事例をつくる。これが本市で実現されれば、
本当にすばらしいことだと感じますが、ドライバー不足が顕著な中では、
ここは一旦リセットして考えないといけない時期に来ているのかなと
思います。
ローカルベーシックインフラの構築も、一旦データ連携基盤から離れて
考えていくべきではないか。
ベーシックインフラから一旦離れてできること、やれることがあるのでは
ないかなとも感じております。
例えば、本市の65歳からの福祉タクシーの利用もデータ分析する必要が
あります。先ほど言いましたように、本市の運転免許証保有率が高いし、
地方では9割以上の方が自転車とか徒歩、二輪車、自動車での移動
ですから、免許返納する人というのは限界があると思いますが、
そこにこだわる必要があるのかとも考えております。
健康福祉部長にもこの点についてお考えがあれば答弁をお願いしたい
ところです。
様々な移動のデータを分析して、スピード感を持って様々なことを
やっていく必要が、昨日の同僚議員の質問にもありましたけど、それ
だったら地域公共交通をリセットして、ドライバー不足だったら、なお
さら高校生とか高齢者などに特化して再構築をしていくこと。
高齢者に限っては、例えば免許返納者だけでなくて、例えば80歳とか
一定の高齢者に達した方には、以前のように全員福祉タクシー券を
配付して、まずはタクシーやバスを使っていただき、地域の公共交通
を知って利用していただいてから次の利用につなげていくということは
すぐにできますし、データも取れるかと私は思います。
このような点はどのようにお考えでしょうか、再質問いたします。
●答弁4(田中昌和健康福祉部長)
福祉タクシー事業につきましては、高齢者の交通手段の確保及び
経済的負担の軽減を図り、福祉の増進に寄与することを目的に事業
を開始いたしましたが、令和元年度からは、交通事故の減少を図る
ため、高齢ドライバーの運転免許証の自主返納を支援することも
加えた事業となった経緯がございます。
議員御案内のとおり、本市のような地方部においては、高齢者の
移動手段が徒歩や自転車のほかには、二輪車や自動車での移動が
ほとんどであり、免許返納にも限界があることは認識しておりますが、
福祉タクシー事業だけでは高齢者の日々の交通手段の根本的な
解決は難しいと考えております。
また、議員御提案の高齢者全員への福祉タクシー券の配付に
ついては、これまでの事業の経過や財政的な面からも拡充は
難しいと考えております。
また、福祉タクシー利用のデータ分析につきましては、現状の
福祉タクシー券は紙ベースのため、データ収集及び分析は現状
では困難であると考えておりますので、御理解賜りますようよろしく
お願い申し上げます。
●再質問5
そういう答弁を頂けると思っていなかったので、これについては、
また別途やりたいと思います。これは話すると長いので。
次に、新しい共有の形、過疎地のライドシェアを提案したいと思います。
ライドシェアとは、移動の手段である車と、それを運転するドライバーを
シェアリングする新しい移動の形です。
スマートフォンアプリなどで配車を依頼して、タクシーのように利用する
形式が一般的なライドシェアの仕組みとなっております。
海外ではウーバー社などが有名ですが、ドライバー不足を解消する
べく、規制緩和していくライドシェア、これは都市型ライドシェアであり
まして、最近、そうではない過疎地のライドシェアが脚光を浴びており
ます。
過疎地のライドシェアは、十分な運転能力はあるものの、職業ドライバー
になることが難しい潜在的ドライバーを活用して、具体例として、平日
にも空き時間がある学生や、休日に副業をしたいサラリーマンなどが
配車アプリを通じて、移動を提供する人と移動したい人をマッチング
させればスタートできるというものであります。
フルタイムで職業ドライバーになることが難しい地域住民の方々が
ドライバーの担い手になっていただくことが過疎地ライドシェアの
ポイントで、路線バスの維持に苦心している自治体にとって、公共
交通を維持する切り札となるかもしれないものです。
北海道をはじめ、全国でも導入が進んでおります。既存の路線バス
と異なり、決められた路線やダイヤがないために、運行台数や時間帯
の柔軟な調整によって住民の方々のニーズに応えることが可能であり、
潜在的ドライバーと遊休車両を過疎地ライドシェアアプリがマッチング
するものであり、これらも検討していくべきではないのかなと提案を
させていただきますけど、これもmobi、ライドシェア、乗合タクシーなど、
様々な選択肢があって、地域との協働を考えて、公共交通を担っていく
べきであると考えます。どのようにお考えでしょうか。
●答弁6(立石慎一政策部長)
ライドシェアは、日本版ライドシェアと呼ばれるものと、議員御発言の
過疎地でのライドシェア、いわゆる自治体ライドシェアの二つに区分を
されております。
日本版ライドシェアについては、昨今の報道でも取り扱われており
ますとおり、本年4月には東京、神奈川県、愛知県、京都府の一部
地域がその運行対象となり、5月からは札幌、仙台、埼玉、千葉、大阪、
神戸、広島、福岡の8地域において、区域ごとにタクシーが不足する
時間帯のみ運行が認められ、料金はタクシーと同額での運用が
行われております。
一方、御質問の自治体ライドシェアにつきましては、日本版のそれ
以前から各地において、道路運送法の自家用有償旅客運送の一つ
として、過疎地などの公共交通空白地にて認められております。
現在、その運行主体を民間や地域団体に拡大する動きもあるようです。
これらの一部解禁や拡大に向けた動きの背景としては、御案内の
とおり、深刻なドライバー不足に起因するものであり、信用補償調査
企業の調査では、この10年でタクシー・ハイヤー事業者において、
ドライバーなどの従業員が半減した事業者は全国で14.5%、香川県
においてはその平均をはるかに超える、全国で2番目に減少率が
高い29%の事業者が半減したとの結果が出ております。
このライドシェアについての市の考え方はとの御質問でございます
が、本市が抱える課題も全国と同様であり、ドライバー不足は深刻さ
を増しております。
ライドシェアは、これらを担っていただける市民のドライバーの方々や
地域交通事業者の皆様の御協力が整い、初めてスタートラインに立つ
ものでございます。議員御発言の地域の公共交通リ・デザイン実現
会議取りまとめ報告書にもありますとおり、地域のあらゆる輸送資源
を総動員し、当該資源を地域の関係者で効率的に確保し運行すること
で、持続可能な地域交通を確保していく必要があると感じております。
このようなことから、今後、移動交通に係る課題を地域全体の課題と
して捉え、地域全体で確保に向けて検討をしてまいりたいと考えております。
●再質問6
やはり国土交通省の提唱するリ・デザインに関する制度について、最後に
またお聞きをしますけど、本市では交通DXで自動運転はやります。
MaaSも取り組みます。交通GXではEVバスもやっています。
ただ、これは全国どこでもできる施策であって、本市が独自で何をやるのか、
何ができるのかが重要になるかと感じております。
三つの共創、官民、交通事業者間、他分野の共創を考えれば、ここに
父母ヶ浜や紫雲出山の観光、介護や、特に教育、スクールバスや放課後
改革など移動と共創することができるのは理解できます。
JR詫間駅は、高専生のbomi利用がありますが、JRの高瀬駅が新しく
なるとしても、ここを交通の拠点とするにはデータが必要です。JR四国
との詳細な協議も必要かと感じます。
私は特に介護のほうで島根県大田市の井田いきいきタクシーという
事例を調べました。
高齢者の移動目的は何か、ずばり通院と買物だけではなく、サブスクで
乗り放題をすると趣味や娯楽が多くなり、楽しみの移動で外出すること
が確認できたそうです。
実際に利用者へのヒアリングからは、毎週誘い合って温泉に行くとか、
友人宅におしゃべりに行く利用者が数多く存在して、今後はこのような
交通サービスで介護予防効果の分析を行うことで、交通に係る経費
以上の健康寿命増進による経費削減効果を詳細に算出することが
可能となっているようです。
やはり福祉も交通と協働、共創していくべきなんですよ。田中部長、
私はそう思いますけど。
もちろんここはベーシックインフラにつながる部分かと思いますが、
特定企業だけでなくコミュニティバスの沿線には多くの民間企業が
ありますし、応援いただく個人も募っていくべきであります。
ベーシックインフラのような大きなデータ連携基盤の活用もいいん
ですが、本市の高齢者や高校生などの声を聞いて意見を反映して、
エビデンスを取ることで、今すぐできる地域公共交通対策、スピード
感を持ってやることが多々あるはずであります。
私は、今言いました多くのすばらしい企業とか、多くの民間企業
や各種団体を広域で巻き込んで、広域の地域公共交通も考えて
支援していくべきだと考えておりますが、この交通システム事業団、
具体的な目標を挙げて、いつまでにやるのか、具現化して取り組ん
でいく、成功事例が全国的にない中で本市が成功事例をつくって
いくぐらいの意気込みが欲しいと思います。
本市独自の新しい事業としての地域公共交通の再構築のお考えを
最後に市長に発言をお願いいたします。
●答弁7(山下昭史市長)
1点、先ほどの福祉のお問合せ、質問に対しての答弁ですが、
やっていないわけではなくて、ダイハツと一緒にやっています共同
送迎、これも福祉でありますので、福祉タクシーのチケットに関して
の部分では部長が答弁したとおりなんですけれども、福祉分野に
おける取組というのはやっておりますし、共同送迎における段階的
な目的は、議員が御質問されていましたような、いわゆる買物支援
とかというのはフェーズによって、今度、そういった部分を含めて
まいりますので、そういった点ではミックスしていくということは御理
解いただけたらと思います。
それを前提にいたしまして、先ほどの公共交通の地域課題の解消
を目指しまして、三豊市では様々なMaaSへの実証や取組を行って
まいりました。
その中の一つに粟島グリーンスローモビリティがありますけれども、
この利用者の声としては、特に用じゃなくても友達と一緒にドライブ
がてらに乗るとか、ドライバーとの世間話が癒やされるなど、まさに
生活のため、何か目的のための移動というだけでなく、外出機会の
創出、楽しめる移動という御利用もされているようです。
また、財田乗合タクシーの実証におきましても、地域のイベント時の
タクシー御利用が突出して多いんです。
行きたいものに参加できることで、いつまでも地域になじみ、幸福感
を持つことができるということ。健康寿命増進につながることがまさに
期待できると考えております。
しかしながら、一方で、これまでの答弁にもありましたように、人口
構造の変化、担い手不足等の移動に関する将来不安がある中で、
地域の交通課題はより深刻化されております。
これに対し、三豊市では、交通DXである自動運転に取り組みまして、
今だからこそ、遅れをとらず、新技術の活用により、地方の交通課題
を打破できるようなチャレンジに取り組みたいと考えております。
自動運転のチャレンジは今からではありますが、こういった取組を
得て、新たな技術や地域の多くの人や物に資源を最大限活用しな
がら、行政だけでなく、民間の活力、他分野を含めた共創による交通
サービスを模索していきたいと思っておりまして、
「行きたいときに行きたいところへ行けるまち」
を目指していくための交通システム事業団であります。これは7月を
設立目標にしております。
そういった意味では、地域の皆様の連携協働による利便性の高い
持続可能な公共交通を目指してまいりたいと思います。
もう一点、広域に関してですけれども、議員御指摘のとおりでして、
生活圏というのは基本的に行政区域とは必ずしも一致しておりません。
琴平に近い高瀬町の人は琴平での買物とかが多かったりしますし、
財田町の人もそうです。また一方で、豊中の人が観音寺のほうに
買物に行く、この生活圏に応じた取り組み方というのが必要だと
思います。
公共交通という言葉自体がミックスという中では、今後意味を違えて
くるのかなと思っておりますし、先ほど言いました観光、父母ヶ浜に
来られる方も、観光用の乗り物ではなくて、市民生活と一緒に利用
できるようなもの、そういったものも必要です。
一番問題になっているのは2次交通でありまして、高松空港から
こちら三豊に来る人が交通手段がないとか、そういった部分も含めて
考えるときに、これは三豊市だけの交通システムではなくて、コミュ
ニティバスは既に琴平町に行ったり、三豊総合病院に行ったりして、
善通寺も行ったりしておりますので、そういった延長線で考えると
いうことが今後重要であると思いますし、そういった議員御指摘の
部分に関しては、当然、交通事業団が中心となって取り組んでいく
ものと考えております。
以上、結構いろいろ言わせていただいた、1問目でした。
大浜地域のことをどうしても発言してしまいます。
皆さん、いろんな意見をいただき、嬉しい限りです。
それと福祉タクシー券の一定年齢への配布は・・・言い続けます。
エビデンスがあるので
 ・・・。
・・・。Posted by はまぐちふどうさん at 09:08│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。