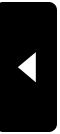2024年12月29日
私の一般質問(その2)子育て支援
私の「一般質問」の2問目は久しぶりの子育て支援の質問でした。
保護者の皆様、NPO関係者、保育所関係者の皆様に貴重なご意見
をお聞きして・・・結構なボリュームとなりました。
まさに、「あれも、これも聞きたいし、財源も考えないとおかしいでしょ!」
の私スタイルの質問でした、はい 。(早口は直したい!)
。(早口は直したい!)
でも「いつも良く調べてますねぇー。」とお褒めの言葉もいただきます。
これが私の質問スタイルだし、調査・研究の結果なんですが、純粋に
褒められると嬉しい 。
。
●質問
次に、子育て支援全般についてお聞きします。
私も久々の子育て関係の質問ですから、張り切っていますので、結構な
ボリュームがありますから、簡潔・明瞭な答弁をお願いします。
2023年4月にこども家庭庁が発足し、同年12月には、若い世代の将来
展望を描けない状況や、子育てをされている方の生活や子育ての悩み
を受け止めて、こども未来戦略が策定されております。
画面の切替えをお願いします。これは総額3.6兆円です。
こども家庭庁のホームページ上にこども未来戦略マップ、これが公開
されておりますが、主な施策である、
1、子育て世帯の家計を応援、住宅支援、
2、全ての子供と子育てを応援、伴走型相談支援、子供誰でも通園制度、
3、共働き・共育てを応援、男性育児休暇取得促進
など、非常によくできております中、このマップ上での財政支援措置の
本市の取組状況、今後の方針を聞きたいと思います。
今、私が言ったところが私が一番気になるところです。
その上で、自治体のこども政策の縦割りの一元化、子ども子育て支援
センター(仮称)の整備方針、就学前施設の在り方や今後の整備方針、
保育士の処遇改善など全般をお聞きいたしますので、よろしくお願い
いたします。

●答弁1(田中昌和健康福祉部長)
議員御案内のとおり、国においては、昨年4月にこども家庭庁が発足
し、同年12月にはこども未来戦略が策定され、こども大綱が目指す
「こどもまんなか社会」の実現に向け、様々なこども施策の取組が取り
まとめられたところでございます。
このほか、児童福祉法や子ども・子育て支援法の一部改正も行われる
など、国を上げて少子化対策なども含め、子供の未来を守る施策に
取り組んでいく覚悟が示されたものと考えております。
こども未来戦略マップに掲げられている主な施策の本市の取組状況
につきましては、まず、一つ目の柱である子育て世帯の家計を応援に
ついてのうち、住宅支援については、市営住宅の申込み要件において、
未就学児がいる子育て世帯の収入要件を緩和しております。
そのほかの家計を応援する財政支援としましては、この10月から児童
手当の抜本的拡充が行われ、対象が高校生年代まで延長されるととも
に、所得制限の撤廃や支給回数の増加など、子育て世帯への経済的
支援が拡充されたほか、ひとり親家庭に対する児童扶養手当の拡充も
実施されております。
次に、二つ目の柱である全ての子供と子育てを応援についてのうち、
伴走型相談支援については、本市では児童福祉法の改正に先立ち、
平成31年度に子育て世代包括支援センター「なないろ」を設置し、令和
2年度からは、それまで就学前であった対象を18歳まで拡充することで、
妊娠期から18歳までの子供や子育て世代に対する切れ目のない支援
に取り組んできたところですが、今般の児童福祉法の改正により、本年
4月からは子ども家庭センター「なないろ」として、母子保健と児童福祉
を一体化し、子育て世帯に対する相談支援体制を拡充・強化したところ
でございます。
財政支援としましては、出産・子育て応援交付金や産後ケアの無償化
などを実施しております。
また、こども誰でも通園制度については、本市においては令和8年度
からの実施に向けて準備を進めているところでございます。
三つ目の柱であります共働き・共育てを応援についてのうち、男性
育休取得推進については、男女共同参画の取組として、経営者向け
の女性活躍推進セミナーを開催しているほか、出産前から父親が育児
に積極的に関わるきっかけづくりとして、パパママ教室や妊娠8か月
相談を開催しており、父親の育児参加の意義や家庭内での役割分担
などについて学ぶことで、父親の積極的な育児参加を促すとともに、
共育ての意識づけを促進しております。
今年度、本市においては、子育て支援施策の最上位計画であります
三豊すくすく子育てサポートプランⅡが終期を迎えることから、現在
本市の子育て支援施策の新たな指針となる三豊市こども計画(仮称)
の策定に取り組んでいるところであります。
今後、県計画における各種施策の評価や、今回計画策定に向けて
実施しました就学前児童及び小学生保護者、子供、若者へのニーズ
調査結果、新たに取り組むべき施策や課題などを踏まえ、本市が子
育てしやすい、こどもまんなかのまちの実現に向けた計画策定に取り
組むとともに、引き続き各種こども政策に積極的に取り組んでまいり
たいと考えております。
●再質問1
画面を切り替えてください。
簡潔明瞭にお願いしたいんですけど、まず、子育て世帯の家計を応援、
住宅支援からですが、若いお母さん方のお声を聞きました。その中で、
この2番、ちょっと見にくいんですけど、子育てにはお金がかかると、
子供が小学生になったときに給食費が無償になったらいいとか、保育
所に入れて働かないと大変なんですと、やはり家計の心配な声をお聞
きしております。
その中で住宅支援の負担は非常に大きいかと思います。
国の住まいの支援はフラット35の金利負担が軽くなるとか、子育て
エコホーム支援事業等々あるんですけど、やはり市としての支援が
欲しいところなんです。
40歳未満の若者定住促進、地域経済活性化補助金がなくなった現在、
本市には三豊市結婚新生活支援事業補助金があるみたいですが、
新築住宅補助金は夫婦ともに29歳以下でマックス60万円、夫婦いずれ
か30から39歳で30万円と、明らかに以前の100万円の補助金のほうが
魅力なんです。
また、この制度は昨年からのスタートで、リフォームが1件のみ、今年は
住宅賃借費用の問合せが数件あるようですが、入り口で支援した後、
ここの制度の拡充をいま一度お願いしたいところです。
要は過去のエビデンスから、子育て世帯の移住・定住につながっている
のか。これは地域戦略課と横串で検証したのかを政策部長にお聞き
したいところであります。
新築ができないのなら、子育て世帯によるリフォームや増築など、
新築住宅は今高いですから、やはりアパートの入り口で支援して、そこ
に継続して住んでもらわないけませんから、今こそ子育て世帯の独自
の住宅支援を考えていただきたいと思います。
次に、全てのこどもと子育てを応援、伴走型相談支援、こども誰でも
通園制度については、NPO法人、私、視察させていただきましたが、
本当に若いお母さん方の相談に乗って、一緒になっての相談業務、
とてもよくやってくれています。
そんな中で、利用者支援相談業務は、来年度から18歳までの拡大
がされますけど、相談できる環境整備ができているのか。
また、保健師が何でも相談してくださいと言われるけど、保健師に
相談するまでもないところ、ここの相談支援をNPOが担ってくれて
いることを当局が理解されていますか。
例えばデリケートな部分の相談を、大きくしたくないという相談が
あった場合に、市に上げて解決してくれるのか。
この相談情報が拡散すると広場に行きたくなくなるという点も危惧
されていましたし、それでも市に情報を上げてくれるところは評価
するが、上げてくれないところは評価されないなど、いろいろNPO
の人たちもデリケートな相談の配慮をしつつやっている現状を私も
現場を見て聞いて確認をしましたけど、まず、部長や担当課長は
NPO法人の視察をされたことがあるんですか。
現場で一緒になって子育て中の保護者や事業者の声を聞いた
ことがあるのか。
午前中、同僚議員も発言ありましたけど、まずは現場を見ていた
だきたいんですよ。
その辺り、机上だけでなく、現場を確認していただきたいと思い
ますが、どうでしょうか。
また、こども誰でも通園制度、これは親が働いていなくても、
未就学児の子供を保育所に預けることができる制度なんですが、
行政の支援が届きにくい親子が孤立して、虐待などにつながる
ことを防ぐ狙いがあります。
理念はいいと思いますが、泣き叫ぶ子をいきなり預けられるのか、
実務的にどうやるのか。
どのように導入していって、課題は何があって、どう解消・解決して
いく予定なのかもお聞きしたいと思います。
先ほどのこども未来マップ、切り替えます。
この男性育休取得促進なんですが、中小企業の育休にインセン
ティブがありますとありますが、まずは私はここは市役所の職員
が率先するべきだと思います。
三豊市役所における男性職員の育児休暇取得状況を関係部局
に問い合わせたところ、令和5年度で取得可能職員数7人のうち
4人が取得率57.1%、令和6年11月25日時点では、取得可能職員
数6人のうち3人が取得、取得率は50%ということなんですが、その
取得日数は最長でも1か月以上半年未満で、令和5年度で1名、
令和6年度で2名となっており、1年といった長期にわたって取得して
いる職員は誰もおりません。
市は、令和4年10月に三豊市職員の育児休業等に関する条例を
改正して、男性職員の育児休業取得促進を行っていますけど、この
実績を踏まえると、形だけのアリバイづくりのような気がして、本当に
男性職員の育児休業促進を行っていると思えません。
その辺り、どのように考えているのかをお聞きいたします。
●答弁2(立石慎一政策部長)
まず、冒頭のほうでありました住宅の新築に関する補助を、またもう
一度事業としてできないかといったあたりの御質問を頂いたと思うん
ですが、やはり人口減少が進む三豊市においては、特に若年層の
減少率が高くなっておりまして、若者に定住していただくこと、また
移住していただくことが本当に三豊市の人口減少に歯止めをかける
ためにも重要な施策ではないかと考えております。
そういった考えにつきましては、政策部のみならず、全ての部署に
おいて、子育て世帯に満足いただけるようなまちづくりをするという
ことを考えて、施策を取り組んでいかなければならないと考えております。
議員御質問の子育て世帯への住宅支援施策については、人口減少
に歯止めをかけるためにも効果の高い取組でありますので、市の財政
事情が厳しいことはありますけども、全庁的に何ができるかなどを横串
で全庁内で検討し、また何かできることを検討してまいりたいと考えて
おります。
●答弁2(田中昌和健康福祉部長)
浜口議員の再質問のうち、まず伴走型相談支援についての御質問に
お答え申し上げます。
まず、18歳まで相談が拡充されることついての環境整備についてなん
ですけども、まず環境整備に当たりましては、現状、どういった環境整備
になっているかにつきましては、まずは、先ほど議員がおっしゃいました
とおり、現場をしっかり確認した上で、できる体制ができているかを確認
した上で、事業者と一緒に環境づくりに努めていく必要があると考えて
おります。
したがいまして、先ほど議員からお話ありましたが、現場の確認について
は、子育て支援課の課長については、現場を確認したり、あるいは現場
からの声を十分聞いているところではございますけれども、私はまだ
ちょっと十分その辺り、現場の確認ができておりませんので、今後、
できるだけ現場に出向いて、そういった事業者の声についても把握して
、一緒に考えていきたいと思っております。
続きまして、誰でも通園制度につきましては、先ほどの委員から御紹介
ありましたように、これは来年、令和8年度から導入される制度でござい
ます。
現在、本市におきましては、もう既に実施されているような自治体の事例
も情報収集しているところでございますけども、やはり初めてお子さんを
預けるという状況になりますので、その場合にはやっぱり新たな人材を
確保をしていく必要があるというような課題も見えてございます。
そういう観点もございますので、今後とも令和8年度の実施に向けまして、
他市の情報も収集しながら、取り組んでいける体制をつくってまいりたい
と考えております。
●答弁2(宮崎洋一総務部長)
私からは、市職員の育休の取得について御答弁させていただきたいと
思います。
議員御指摘ありましたとおり、本市において1年といった長期の育児
休業を取得している職員はおりませんけれども、育児休業取得は申請
制度であり、申請された期間については市として認めておるというところ
でございます。
また、令和4年10月、本市の条例を改正させていただきました際、男性
職員を対象といたしまして育休研修を実施し、周知に努めてはまいった
ところであります。
そしてこども未来戦略マップの男性職員の育休取得推進のためのイン
センティブにつきましても、育児休業となった職員は、基本的に給与
支給が停止されますが、月額給与の6割の額が市町村職員共済組合
から育児休業手当金として支給されます。
一定のインセンティブ制度も活用し対応しておるところでありますけども、
議員御指摘のとおり、安心して長期にわたって育児休業を取得する男性
職員を増やし、市役所が率先して取り組んでいく状況、これは市内の
企業の皆さんにも知っていただくということをもちまして、男性職員の育児
休業取得者数の増加につなげていくことが非常に重要であると考えて
おります。
●再質問2
次に、市内保育所の指定管理料についてお聞きいたします。
高瀬南部保育所と松崎保育所の関係です。東京の民間事業者に指定
管理しておりますけど、高瀬南部は令和30年度、約1億5,700万円、
松崎保育所が約1億1,700万円の指定管理料で、決算ベースで合計
2億7,400万円でした。
これが直近の令和6年度では、高瀬南部保育所が2億2,700万円、
松崎保育所が1億9,500万円の指定管理料で、合計が4億2,200万円
です。
実に約1.8倍以上に金額が膨れております。
これは人件費の見直し、賃金のベースアップ所与によるものであったり、
会計年度任用職員の導入により職員給与の大幅な見直しによるもの
だそうですが、すごい指定管理料だと私は思うんですよ。
内訳があるのかなとも思います。
というのも、こども家庭庁の中で保育所の公定価格試算というものが
ありまして、私も市内の事業者の方に教えていただいたんですが、公定
価格とは、分かりやすく説明すると、子供1人当たりの教育・保育に必要
となる費用のことであります。
この金額は国が定めた基準をもとに算定されており、保育所や認定こど
も園などの保育施設を運営するに当たって大事なものですが、高瀬南部
保育所の規模で計算すると、年間運営費額が令和4年度ベースで
1億680万円だそうで、令和4年度の高瀬南部保育所の2億710万円とは
1億円の開きがあります。といいますか乖離があります。
単純計算なんですが、この開きが非常に大きいかと思います。
事業の棚卸しをする時期に、この指定管理料といいますか、事業者が
悪いのではなくて、ほかの民間事業者とのバランスも鑑みて、保育所の
指定管理自体を見直すべき、考え直すべき時期に来ていると思いますが、
どうでしょうか。あと二、三年ありますけど、これはお考えください。
それと、やはり公立と民間といいますか、公私間の格差是正をしないと
いけない気がします。
これは2点あって、まずは民間保育所運営補助事業、観音寺市や善通寺
市には、園児数や保育日数により、民間の保育事業者への市の単独
補助金があります。これはやはり必要な気がします。
それとオムツ回収補助金です。
県の2分の1補助事業になって、公立保育所が回収されますが、民間
保育所にはないところで、自治体が全て平等に補助をするべきであると
思いますが、やはり子育て・保育行政にはお金は投入して、公私の是正
をお願いしたいと思います。
その上で、三原じゅん子こども政策担当大臣が2024年度の保育士の
給与を前年度から10.7%引き上げると明らかにされましたけど、公私
平等に処遇改善がやれるのか。保育幼稚園課では、民間保育所の
職員給与の額自体も把握されているはずですから、この辺りどのように
お考えなのかを再質問いたします。
●答弁3(田中昌和健康福祉部長)
まず、指定管理料が高いということにつきましてですが、まず、現在
市内には八つの公立保育所がございまして、そのうち、先ほど議員
から御紹介ありました高瀬南部保育所と松崎保育所の二つの保育所
において指定管理制度を導入しております。
議員御指摘の指定管理料が民間の保育所より運営費用で高い数字
になることは十分認識をしております。
そういう中で、今後どのように取り組むかということなんですけども、
今後の業者選定におきましては、2年後に契約期間の満了を迎える
ということがありまして、次年度には選定方法を決定する必要がある
とは考えております。
今後の方向性については、例えば公設民営方式とか、民営化の可能
性も含めて、幅広い選択肢を視野に入れつつ、最適な運営方法を
検討していく必要があるとは考えております。
加えまして、委託料の適正化は重要な課題とは認識しておりますので、
コスト削減と質の維持を両立するために、今後、指定管理期間の終了
に向けた準備を進める中で、市民や保護者、保育関係者の声を丁寧
に伺いながら、最適な方策を講じてまいりたいと思いますので、御理解
と御協力賜りますようよろしくお願いいたします。
続きまして、保育所における官民格差の是正についてですが、まず、
本市のほうでは、全ての子供たちが安心して質の高い保育を受けられ
る環境を整備することを最優先課題としております。
その中で公立保育所と民間保育所との間に、運営体制や待遇の面で
一定の差が生じていることについては認識しており、これが保育全体
の質に影響を与えないよう努める必要があると考えております。
議員から御指摘ありましたように、現在、本市では、民間保育所に
対する運営補助は行っておりませんが、市の職員研修に民間保育所
の方に参加いただいたり、そういうことによりまして、官民問わず保育
の質を向上させる取組を進めております。
こうした取組を通じまして、現場で働く保育士の方々が互いに学び合い、
スキルを高める機会を今後も提供してまいりたいと考えております。
また、本市の財政は厳しい状況ではありますけれども、限られた財源
の中で、保育環境の質を維持・向上しながら官民格差の是正に取り組
むためには、既存の事業の見直しや効率化、さらには国や補助、県から
の補助金交付金の活用も含めて財源を活用する必要がありまして、
具体的には、例えば使用済み紙おむつの処分補助、これにつきまして
は、民間保育所の運営費負担の軽減の観点からも、県の補助制度を
最大限活用しながら、市の負担を抑えつつ、効果的な支援を検討した
いと考えております。
最後に、民間の、先ほど大臣が10%引き上げるという発言がござい
ますけれども、それにつきましては、国の動向を見ながら、本市につき
ましても適正に対応できるよう考えてまいりたいと考えております。
●再質問4
次は、自治体のこども政策の縦割りの一元化です。
教育委員会と市長部局にまたがっているこども政策を一元化する
自治体が増えておりますので、教育委員会にまとめる例と市長部局
にまとめる例がありますが、市長部局にまとめて成功しているところ
では、やはり兵庫県の明石市であります。
今こそ地方自治体のこども政策は縦割りの中で再編をすべきであるか
と思います。
全国ではこれを一緒にしているところはまだ1割程度らしいですが、
本市で生まれた子供さんが、令和5年暫定出生数が二百七十数名で、
令和4年度、これは確定で287人、ここから魔の300人以下出生数に
なっていますけど、これだけ少子化になると、本当にこども政策の一元
化を検討していくべきであると思います。
どうでしょうかというのが1問。
もう一点はこども家庭センター(仮称)についての整備です。
私が所属している教育民生常任委員会の所管事務調査事項である
にもかかわらず、白紙であって、何も決まっていません。
これはどうなんでしょうか。
市長から代表質問のときに、三豊市子ども・子育て支援センター機能
等検討委員会から、いろんなことがあって、具体的なビジョンがまだ
お示しできていない状況であると代表質問で答弁がありましたが、
やはり、合併特例債の発行期限内でのセンターの施設整備が難しく
なったことを踏まえて、財源確保等も含めていろいろ検討しているん
でしょうか。
いつビジョンを示していただけるんでしょうか、お聞きいたします。
●答弁5(田中昌和健康福祉部長)
浜口議員の再質問にお答え申し上げます。
まず、こども政策の一元化につきましてですが、本市におきましては、
平成27年度から開始されました子ども・子育て支援新制度に対応する
ため、平成26年4月から幼稚園保育所への入園・入所業務を子育て
支援課に集約しまして、平成30年4月には保育幼稚園課を新設し、幼稚
園の手続や施設管理に関する業務を市長部局へ集約することで、就学
前の教育・保育に関する業務の一元化を進めてきたところでございます。
しかしながら、幼稚園に関する事務のうち、職員の服務や研修、保健
衛生に関することなどは教育委員会事務局学校教育課が所管しており
まして、議員御指摘のとおり、現状は市長部局と教育委員会事務局の
両部局が担当業務を遂行しているところでございます。
このため対外的には縦割り行政と捉えられる1面もあると思いますが、
日頃から両者間で情報共有を図るとともに、一部の業務については連携
して取り組んでいるところでありまして、窓口業務においては、現在の
ところ大きな支障は生じていない状況でございます。
こども政策の一元化は、縦割り行政の解消のみならず、こども政策を
推進するための体制強化にもつながるものと考えておりますので、今後
も議員から御案内ありました他市の先進事例も参考に調査・研究をして
まいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い
します。
続きまして、子ども・子育て支援センターの整備につきましての御質問
にお答え申し上げます。
三豊市子ども・子育て支援センター(仮称)につきましては、本庁舎周辺
整備の一環としまして、子育て支援機能と児童発達支援センター機能を
併せ持つ施設として整備する方向で検討を進めてきたところでございます
が、建設場所等の課題が解決しないまま、当初想定していた合併特例債
を活用した期限内での整備がかなわなくなったことを受けまして、検討が
中断していたところでございます。
しかしながら、子育て世代が集い、交流し、抱える不安や悩みを気軽に
相談でき適切な支援につなぐことができる子育て拠点の整備が本市の
子育て支援に必要である考えに変わりはございません。
このため、現在課題となっている建設場所、事業所、財源確保策等に
ついては、改めて庁内関係部署と連携しながら検討を始めたところで
あり、できるだけ早期に整備の実現の可能性を見いだしていきたいと
考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
●再質問6
子育て支援センター(仮称)については、合併特例債がないならば、こども
家庭庁になって子ども・子育て支援事業債というのがありますよ。
これは交付税措置率、施設新築は30%ですけど、ハード整備に使える起債
なんです。
これは機能強化プランを伴う施設の改修の場合は50%です。
返すときに半分見てくれるというのは非常に大きいですから、これは検討
しないかんと思うんですよ。
というのは、やはり財源の話をしてしまいますが、さっきのこども未来戦略
マップもそうですけど、手厚い財源措置となっているのは事実なんです。
こども家庭庁の手厚い財源措置もしてきたのかをお聞きいたします。
こども・子育て政策に係る地方単独事業ソフトの推進では、地方財政
計画の一般行政経費単独が1,000億円増額されて普通交付税で措置
されるようになっています。
たくさんのメニューがあるんですよ。
幼稚園保育所の独自の処遇改善や配置改善、こどもの居場所づくり、
産前産後ケアや伴走型支援の充実、いろいろ検討されたんですか。
また、普通交付税の算定に当たって地方団体が実施するこども・子育て
政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る基準財政需要額に、
これは御存じだと思いますが、18歳以下人口とする新たなこども・子育て
費が創設されておりますから、人口に占める18歳以下人口の割合が
小さい団体にも配慮した補正措置が講じられているようですけど、
ハード事業とかソフト事業、財源がないんやったら、いろんなメニューを
取ってきたらいいと思うんです。
その辺りどのように活用は検討したんですか、お聞きしたいと思います。
●答弁7(立石慎一政策部長)
浜口議員の再質問にお答えいたします。
議員が御指摘の指定された普通交付税算定におけるこども・子育て費
については、直近の国勢調査における18歳以下の人口が9,542人であっ
たため、平成6年度は約23億5,000万円が基準財政需要額に算定を
されております。
一方、子供の社会福祉や保健衛生費、その他教育に要した費用は、
詳細は確認できておりませんが、恐らく基準財政需要額として算定され
た額を上回る額を支出しているものと思われます。
今回、国が新たに財政措置をした地方独自の子育て支援分に関して
は、どの程度基準財政需要額が算定されているかは分かりかねるところ
ですけども、三豊市では今年度から、保育園児に対する保育士の人数
を1年早く増員するなどの市単独事業の取組も行っております。
基準財政需要額として算定されているとはいえ、そのまま普通交付税
として頂けるものではなく、次年度以降も算定されることが約束されて
いるものではないので、財政事情も考慮せず地方単独事業を拡充する
べきものではないと考えますが、こども未来戦略を掲げている施策に
ついては、限られた財源を有効に活用しつつ、取り組んでまいりたいと
考えております。
●丸戸研二議長
理事者の答弁は終わりました。残り10秒ですが、再質問ございますか。
●最後の発言!
子供たちへの未来への先行投資、どんどんやるべきだと思いますので、
よろしくお願いします!!!
1時間ジャストで終了しましたー。
私も子育てして、PTAにも関わらせていただきましたので、子育て
支援の質問は、「力」が入りましたー。
反省しつつ、次の質問に繋げたいと思います。
「一般質問」については以上です・・・今年は議長終わって、4回、
様々な分野で質問させていただきました。
「一般質問は議員の通信簿」
を心がけ、来年も毎回質問!で頑張る所存です。
皆様、よろしくお願い申し上げます。
ご意見はコメント欄か hama2103@gmail.com まで
お願いします。
保護者の皆様、NPO関係者、保育所関係者の皆様に貴重なご意見
をお聞きして・・・結構なボリュームとなりました。
まさに、「あれも、これも聞きたいし、財源も考えないとおかしいでしょ!」
の私スタイルの質問でした、はい
 。(早口は直したい!)
。(早口は直したい!)でも「いつも良く調べてますねぇー。」とお褒めの言葉もいただきます。
これが私の質問スタイルだし、調査・研究の結果なんですが、純粋に
褒められると嬉しい
 。
。●質問
次に、子育て支援全般についてお聞きします。
私も久々の子育て関係の質問ですから、張り切っていますので、結構な
ボリュームがありますから、簡潔・明瞭な答弁をお願いします。
2023年4月にこども家庭庁が発足し、同年12月には、若い世代の将来
展望を描けない状況や、子育てをされている方の生活や子育ての悩み
を受け止めて、こども未来戦略が策定されております。
画面の切替えをお願いします。これは総額3.6兆円です。
こども家庭庁のホームページ上にこども未来戦略マップ、これが公開
されておりますが、主な施策である、
1、子育て世帯の家計を応援、住宅支援、
2、全ての子供と子育てを応援、伴走型相談支援、子供誰でも通園制度、
3、共働き・共育てを応援、男性育児休暇取得促進
など、非常によくできております中、このマップ上での財政支援措置の
本市の取組状況、今後の方針を聞きたいと思います。
今、私が言ったところが私が一番気になるところです。
その上で、自治体のこども政策の縦割りの一元化、子ども子育て支援
センター(仮称)の整備方針、就学前施設の在り方や今後の整備方針、
保育士の処遇改善など全般をお聞きいたしますので、よろしくお願い
いたします。
●答弁1(田中昌和健康福祉部長)
議員御案内のとおり、国においては、昨年4月にこども家庭庁が発足
し、同年12月にはこども未来戦略が策定され、こども大綱が目指す
「こどもまんなか社会」の実現に向け、様々なこども施策の取組が取り
まとめられたところでございます。
このほか、児童福祉法や子ども・子育て支援法の一部改正も行われる
など、国を上げて少子化対策なども含め、子供の未来を守る施策に
取り組んでいく覚悟が示されたものと考えております。
こども未来戦略マップに掲げられている主な施策の本市の取組状況
につきましては、まず、一つ目の柱である子育て世帯の家計を応援に
ついてのうち、住宅支援については、市営住宅の申込み要件において、
未就学児がいる子育て世帯の収入要件を緩和しております。
そのほかの家計を応援する財政支援としましては、この10月から児童
手当の抜本的拡充が行われ、対象が高校生年代まで延長されるととも
に、所得制限の撤廃や支給回数の増加など、子育て世帯への経済的
支援が拡充されたほか、ひとり親家庭に対する児童扶養手当の拡充も
実施されております。
次に、二つ目の柱である全ての子供と子育てを応援についてのうち、
伴走型相談支援については、本市では児童福祉法の改正に先立ち、
平成31年度に子育て世代包括支援センター「なないろ」を設置し、令和
2年度からは、それまで就学前であった対象を18歳まで拡充することで、
妊娠期から18歳までの子供や子育て世代に対する切れ目のない支援
に取り組んできたところですが、今般の児童福祉法の改正により、本年
4月からは子ども家庭センター「なないろ」として、母子保健と児童福祉
を一体化し、子育て世帯に対する相談支援体制を拡充・強化したところ
でございます。
財政支援としましては、出産・子育て応援交付金や産後ケアの無償化
などを実施しております。
また、こども誰でも通園制度については、本市においては令和8年度
からの実施に向けて準備を進めているところでございます。
三つ目の柱であります共働き・共育てを応援についてのうち、男性
育休取得推進については、男女共同参画の取組として、経営者向け
の女性活躍推進セミナーを開催しているほか、出産前から父親が育児
に積極的に関わるきっかけづくりとして、パパママ教室や妊娠8か月
相談を開催しており、父親の育児参加の意義や家庭内での役割分担
などについて学ぶことで、父親の積極的な育児参加を促すとともに、
共育ての意識づけを促進しております。
今年度、本市においては、子育て支援施策の最上位計画であります
三豊すくすく子育てサポートプランⅡが終期を迎えることから、現在
本市の子育て支援施策の新たな指針となる三豊市こども計画(仮称)
の策定に取り組んでいるところであります。
今後、県計画における各種施策の評価や、今回計画策定に向けて
実施しました就学前児童及び小学生保護者、子供、若者へのニーズ
調査結果、新たに取り組むべき施策や課題などを踏まえ、本市が子
育てしやすい、こどもまんなかのまちの実現に向けた計画策定に取り
組むとともに、引き続き各種こども政策に積極的に取り組んでまいり
たいと考えております。
●再質問1
画面を切り替えてください。
簡潔明瞭にお願いしたいんですけど、まず、子育て世帯の家計を応援、
住宅支援からですが、若いお母さん方のお声を聞きました。その中で、
この2番、ちょっと見にくいんですけど、子育てにはお金がかかると、
子供が小学生になったときに給食費が無償になったらいいとか、保育
所に入れて働かないと大変なんですと、やはり家計の心配な声をお聞
きしております。
その中で住宅支援の負担は非常に大きいかと思います。
国の住まいの支援はフラット35の金利負担が軽くなるとか、子育て
エコホーム支援事業等々あるんですけど、やはり市としての支援が
欲しいところなんです。
40歳未満の若者定住促進、地域経済活性化補助金がなくなった現在、
本市には三豊市結婚新生活支援事業補助金があるみたいですが、
新築住宅補助金は夫婦ともに29歳以下でマックス60万円、夫婦いずれ
か30から39歳で30万円と、明らかに以前の100万円の補助金のほうが
魅力なんです。
また、この制度は昨年からのスタートで、リフォームが1件のみ、今年は
住宅賃借費用の問合せが数件あるようですが、入り口で支援した後、
ここの制度の拡充をいま一度お願いしたいところです。
要は過去のエビデンスから、子育て世帯の移住・定住につながっている
のか。これは地域戦略課と横串で検証したのかを政策部長にお聞き
したいところであります。
新築ができないのなら、子育て世帯によるリフォームや増築など、
新築住宅は今高いですから、やはりアパートの入り口で支援して、そこ
に継続して住んでもらわないけませんから、今こそ子育て世帯の独自
の住宅支援を考えていただきたいと思います。
次に、全てのこどもと子育てを応援、伴走型相談支援、こども誰でも
通園制度については、NPO法人、私、視察させていただきましたが、
本当に若いお母さん方の相談に乗って、一緒になっての相談業務、
とてもよくやってくれています。
そんな中で、利用者支援相談業務は、来年度から18歳までの拡大
がされますけど、相談できる環境整備ができているのか。
また、保健師が何でも相談してくださいと言われるけど、保健師に
相談するまでもないところ、ここの相談支援をNPOが担ってくれて
いることを当局が理解されていますか。
例えばデリケートな部分の相談を、大きくしたくないという相談が
あった場合に、市に上げて解決してくれるのか。
この相談情報が拡散すると広場に行きたくなくなるという点も危惧
されていましたし、それでも市に情報を上げてくれるところは評価
するが、上げてくれないところは評価されないなど、いろいろNPO
の人たちもデリケートな相談の配慮をしつつやっている現状を私も
現場を見て聞いて確認をしましたけど、まず、部長や担当課長は
NPO法人の視察をされたことがあるんですか。
現場で一緒になって子育て中の保護者や事業者の声を聞いた
ことがあるのか。
午前中、同僚議員も発言ありましたけど、まずは現場を見ていた
だきたいんですよ。
その辺り、机上だけでなく、現場を確認していただきたいと思い
ますが、どうでしょうか。
また、こども誰でも通園制度、これは親が働いていなくても、
未就学児の子供を保育所に預けることができる制度なんですが、
行政の支援が届きにくい親子が孤立して、虐待などにつながる
ことを防ぐ狙いがあります。
理念はいいと思いますが、泣き叫ぶ子をいきなり預けられるのか、
実務的にどうやるのか。
どのように導入していって、課題は何があって、どう解消・解決して
いく予定なのかもお聞きしたいと思います。
先ほどのこども未来マップ、切り替えます。
この男性育休取得促進なんですが、中小企業の育休にインセン
ティブがありますとありますが、まずは私はここは市役所の職員
が率先するべきだと思います。
三豊市役所における男性職員の育児休暇取得状況を関係部局
に問い合わせたところ、令和5年度で取得可能職員数7人のうち
4人が取得率57.1%、令和6年11月25日時点では、取得可能職員
数6人のうち3人が取得、取得率は50%ということなんですが、その
取得日数は最長でも1か月以上半年未満で、令和5年度で1名、
令和6年度で2名となっており、1年といった長期にわたって取得して
いる職員は誰もおりません。
市は、令和4年10月に三豊市職員の育児休業等に関する条例を
改正して、男性職員の育児休業取得促進を行っていますけど、この
実績を踏まえると、形だけのアリバイづくりのような気がして、本当に
男性職員の育児休業促進を行っていると思えません。
その辺り、どのように考えているのかをお聞きいたします。
●答弁2(立石慎一政策部長)
まず、冒頭のほうでありました住宅の新築に関する補助を、またもう
一度事業としてできないかといったあたりの御質問を頂いたと思うん
ですが、やはり人口減少が進む三豊市においては、特に若年層の
減少率が高くなっておりまして、若者に定住していただくこと、また
移住していただくことが本当に三豊市の人口減少に歯止めをかける
ためにも重要な施策ではないかと考えております。
そういった考えにつきましては、政策部のみならず、全ての部署に
おいて、子育て世帯に満足いただけるようなまちづくりをするという
ことを考えて、施策を取り組んでいかなければならないと考えております。
議員御質問の子育て世帯への住宅支援施策については、人口減少
に歯止めをかけるためにも効果の高い取組でありますので、市の財政
事情が厳しいことはありますけども、全庁的に何ができるかなどを横串
で全庁内で検討し、また何かできることを検討してまいりたいと考えて
おります。
●答弁2(田中昌和健康福祉部長)
浜口議員の再質問のうち、まず伴走型相談支援についての御質問に
お答え申し上げます。
まず、18歳まで相談が拡充されることついての環境整備についてなん
ですけども、まず環境整備に当たりましては、現状、どういった環境整備
になっているかにつきましては、まずは、先ほど議員がおっしゃいました
とおり、現場をしっかり確認した上で、できる体制ができているかを確認
した上で、事業者と一緒に環境づくりに努めていく必要があると考えて
おります。
したがいまして、先ほど議員からお話ありましたが、現場の確認について
は、子育て支援課の課長については、現場を確認したり、あるいは現場
からの声を十分聞いているところではございますけれども、私はまだ
ちょっと十分その辺り、現場の確認ができておりませんので、今後、
できるだけ現場に出向いて、そういった事業者の声についても把握して
、一緒に考えていきたいと思っております。
続きまして、誰でも通園制度につきましては、先ほどの委員から御紹介
ありましたように、これは来年、令和8年度から導入される制度でござい
ます。
現在、本市におきましては、もう既に実施されているような自治体の事例
も情報収集しているところでございますけども、やはり初めてお子さんを
預けるという状況になりますので、その場合にはやっぱり新たな人材を
確保をしていく必要があるというような課題も見えてございます。
そういう観点もございますので、今後とも令和8年度の実施に向けまして、
他市の情報も収集しながら、取り組んでいける体制をつくってまいりたい
と考えております。
●答弁2(宮崎洋一総務部長)
私からは、市職員の育休の取得について御答弁させていただきたいと
思います。
議員御指摘ありましたとおり、本市において1年といった長期の育児
休業を取得している職員はおりませんけれども、育児休業取得は申請
制度であり、申請された期間については市として認めておるというところ
でございます。
また、令和4年10月、本市の条例を改正させていただきました際、男性
職員を対象といたしまして育休研修を実施し、周知に努めてはまいった
ところであります。
そしてこども未来戦略マップの男性職員の育休取得推進のためのイン
センティブにつきましても、育児休業となった職員は、基本的に給与
支給が停止されますが、月額給与の6割の額が市町村職員共済組合
から育児休業手当金として支給されます。
一定のインセンティブ制度も活用し対応しておるところでありますけども、
議員御指摘のとおり、安心して長期にわたって育児休業を取得する男性
職員を増やし、市役所が率先して取り組んでいく状況、これは市内の
企業の皆さんにも知っていただくということをもちまして、男性職員の育児
休業取得者数の増加につなげていくことが非常に重要であると考えて
おります。
●再質問2
次に、市内保育所の指定管理料についてお聞きいたします。
高瀬南部保育所と松崎保育所の関係です。東京の民間事業者に指定
管理しておりますけど、高瀬南部は令和30年度、約1億5,700万円、
松崎保育所が約1億1,700万円の指定管理料で、決算ベースで合計
2億7,400万円でした。
これが直近の令和6年度では、高瀬南部保育所が2億2,700万円、
松崎保育所が1億9,500万円の指定管理料で、合計が4億2,200万円
です。
実に約1.8倍以上に金額が膨れております。
これは人件費の見直し、賃金のベースアップ所与によるものであったり、
会計年度任用職員の導入により職員給与の大幅な見直しによるもの
だそうですが、すごい指定管理料だと私は思うんですよ。
内訳があるのかなとも思います。
というのも、こども家庭庁の中で保育所の公定価格試算というものが
ありまして、私も市内の事業者の方に教えていただいたんですが、公定
価格とは、分かりやすく説明すると、子供1人当たりの教育・保育に必要
となる費用のことであります。
この金額は国が定めた基準をもとに算定されており、保育所や認定こど
も園などの保育施設を運営するに当たって大事なものですが、高瀬南部
保育所の規模で計算すると、年間運営費額が令和4年度ベースで
1億680万円だそうで、令和4年度の高瀬南部保育所の2億710万円とは
1億円の開きがあります。といいますか乖離があります。
単純計算なんですが、この開きが非常に大きいかと思います。
事業の棚卸しをする時期に、この指定管理料といいますか、事業者が
悪いのではなくて、ほかの民間事業者とのバランスも鑑みて、保育所の
指定管理自体を見直すべき、考え直すべき時期に来ていると思いますが、
どうでしょうか。あと二、三年ありますけど、これはお考えください。
それと、やはり公立と民間といいますか、公私間の格差是正をしないと
いけない気がします。
これは2点あって、まずは民間保育所運営補助事業、観音寺市や善通寺
市には、園児数や保育日数により、民間の保育事業者への市の単独
補助金があります。これはやはり必要な気がします。
それとオムツ回収補助金です。
県の2分の1補助事業になって、公立保育所が回収されますが、民間
保育所にはないところで、自治体が全て平等に補助をするべきであると
思いますが、やはり子育て・保育行政にはお金は投入して、公私の是正
をお願いしたいと思います。
その上で、三原じゅん子こども政策担当大臣が2024年度の保育士の
給与を前年度から10.7%引き上げると明らかにされましたけど、公私
平等に処遇改善がやれるのか。保育幼稚園課では、民間保育所の
職員給与の額自体も把握されているはずですから、この辺りどのように
お考えなのかを再質問いたします。
●答弁3(田中昌和健康福祉部長)
まず、指定管理料が高いということにつきましてですが、まず、現在
市内には八つの公立保育所がございまして、そのうち、先ほど議員
から御紹介ありました高瀬南部保育所と松崎保育所の二つの保育所
において指定管理制度を導入しております。
議員御指摘の指定管理料が民間の保育所より運営費用で高い数字
になることは十分認識をしております。
そういう中で、今後どのように取り組むかということなんですけども、
今後の業者選定におきましては、2年後に契約期間の満了を迎える
ということがありまして、次年度には選定方法を決定する必要がある
とは考えております。
今後の方向性については、例えば公設民営方式とか、民営化の可能
性も含めて、幅広い選択肢を視野に入れつつ、最適な運営方法を
検討していく必要があるとは考えております。
加えまして、委託料の適正化は重要な課題とは認識しておりますので、
コスト削減と質の維持を両立するために、今後、指定管理期間の終了
に向けた準備を進める中で、市民や保護者、保育関係者の声を丁寧
に伺いながら、最適な方策を講じてまいりたいと思いますので、御理解
と御協力賜りますようよろしくお願いいたします。
続きまして、保育所における官民格差の是正についてですが、まず、
本市のほうでは、全ての子供たちが安心して質の高い保育を受けられ
る環境を整備することを最優先課題としております。
その中で公立保育所と民間保育所との間に、運営体制や待遇の面で
一定の差が生じていることについては認識しており、これが保育全体
の質に影響を与えないよう努める必要があると考えております。
議員から御指摘ありましたように、現在、本市では、民間保育所に
対する運営補助は行っておりませんが、市の職員研修に民間保育所
の方に参加いただいたり、そういうことによりまして、官民問わず保育
の質を向上させる取組を進めております。
こうした取組を通じまして、現場で働く保育士の方々が互いに学び合い、
スキルを高める機会を今後も提供してまいりたいと考えております。
また、本市の財政は厳しい状況ではありますけれども、限られた財源
の中で、保育環境の質を維持・向上しながら官民格差の是正に取り組
むためには、既存の事業の見直しや効率化、さらには国や補助、県から
の補助金交付金の活用も含めて財源を活用する必要がありまして、
具体的には、例えば使用済み紙おむつの処分補助、これにつきまして
は、民間保育所の運営費負担の軽減の観点からも、県の補助制度を
最大限活用しながら、市の負担を抑えつつ、効果的な支援を検討した
いと考えております。
最後に、民間の、先ほど大臣が10%引き上げるという発言がござい
ますけれども、それにつきましては、国の動向を見ながら、本市につき
ましても適正に対応できるよう考えてまいりたいと考えております。
●再質問4
次は、自治体のこども政策の縦割りの一元化です。
教育委員会と市長部局にまたがっているこども政策を一元化する
自治体が増えておりますので、教育委員会にまとめる例と市長部局
にまとめる例がありますが、市長部局にまとめて成功しているところ
では、やはり兵庫県の明石市であります。
今こそ地方自治体のこども政策は縦割りの中で再編をすべきであるか
と思います。
全国ではこれを一緒にしているところはまだ1割程度らしいですが、
本市で生まれた子供さんが、令和5年暫定出生数が二百七十数名で、
令和4年度、これは確定で287人、ここから魔の300人以下出生数に
なっていますけど、これだけ少子化になると、本当にこども政策の一元
化を検討していくべきであると思います。
どうでしょうかというのが1問。
もう一点はこども家庭センター(仮称)についての整備です。
私が所属している教育民生常任委員会の所管事務調査事項である
にもかかわらず、白紙であって、何も決まっていません。
これはどうなんでしょうか。
市長から代表質問のときに、三豊市子ども・子育て支援センター機能
等検討委員会から、いろんなことがあって、具体的なビジョンがまだ
お示しできていない状況であると代表質問で答弁がありましたが、
やはり、合併特例債の発行期限内でのセンターの施設整備が難しく
なったことを踏まえて、財源確保等も含めていろいろ検討しているん
でしょうか。
いつビジョンを示していただけるんでしょうか、お聞きいたします。
●答弁5(田中昌和健康福祉部長)
浜口議員の再質問にお答え申し上げます。
まず、こども政策の一元化につきましてですが、本市におきましては、
平成27年度から開始されました子ども・子育て支援新制度に対応する
ため、平成26年4月から幼稚園保育所への入園・入所業務を子育て
支援課に集約しまして、平成30年4月には保育幼稚園課を新設し、幼稚
園の手続や施設管理に関する業務を市長部局へ集約することで、就学
前の教育・保育に関する業務の一元化を進めてきたところでございます。
しかしながら、幼稚園に関する事務のうち、職員の服務や研修、保健
衛生に関することなどは教育委員会事務局学校教育課が所管しており
まして、議員御指摘のとおり、現状は市長部局と教育委員会事務局の
両部局が担当業務を遂行しているところでございます。
このため対外的には縦割り行政と捉えられる1面もあると思いますが、
日頃から両者間で情報共有を図るとともに、一部の業務については連携
して取り組んでいるところでありまして、窓口業務においては、現在の
ところ大きな支障は生じていない状況でございます。
こども政策の一元化は、縦割り行政の解消のみならず、こども政策を
推進するための体制強化にもつながるものと考えておりますので、今後
も議員から御案内ありました他市の先進事例も参考に調査・研究をして
まいりたいと考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い
します。
続きまして、子ども・子育て支援センターの整備につきましての御質問
にお答え申し上げます。
三豊市子ども・子育て支援センター(仮称)につきましては、本庁舎周辺
整備の一環としまして、子育て支援機能と児童発達支援センター機能を
併せ持つ施設として整備する方向で検討を進めてきたところでございます
が、建設場所等の課題が解決しないまま、当初想定していた合併特例債
を活用した期限内での整備がかなわなくなったことを受けまして、検討が
中断していたところでございます。
しかしながら、子育て世代が集い、交流し、抱える不安や悩みを気軽に
相談でき適切な支援につなぐことができる子育て拠点の整備が本市の
子育て支援に必要である考えに変わりはございません。
このため、現在課題となっている建設場所、事業所、財源確保策等に
ついては、改めて庁内関係部署と連携しながら検討を始めたところで
あり、できるだけ早期に整備の実現の可能性を見いだしていきたいと
考えておりますので、御理解賜りますようよろしくお願い申し上げます。
●再質問6
子育て支援センター(仮称)については、合併特例債がないならば、こども
家庭庁になって子ども・子育て支援事業債というのがありますよ。
これは交付税措置率、施設新築は30%ですけど、ハード整備に使える起債
なんです。
これは機能強化プランを伴う施設の改修の場合は50%です。
返すときに半分見てくれるというのは非常に大きいですから、これは検討
しないかんと思うんですよ。
というのは、やはり財源の話をしてしまいますが、さっきのこども未来戦略
マップもそうですけど、手厚い財源措置となっているのは事実なんです。
こども家庭庁の手厚い財源措置もしてきたのかをお聞きいたします。
こども・子育て政策に係る地方単独事業ソフトの推進では、地方財政
計画の一般行政経費単独が1,000億円増額されて普通交付税で措置
されるようになっています。
たくさんのメニューがあるんですよ。
幼稚園保育所の独自の処遇改善や配置改善、こどもの居場所づくり、
産前産後ケアや伴走型支援の充実、いろいろ検討されたんですか。
また、普通交付税の算定に当たって地方団体が実施するこども・子育て
政策の全体像を示し、こども・子育て政策に係る基準財政需要額に、
これは御存じだと思いますが、18歳以下人口とする新たなこども・子育て
費が創設されておりますから、人口に占める18歳以下人口の割合が
小さい団体にも配慮した補正措置が講じられているようですけど、
ハード事業とかソフト事業、財源がないんやったら、いろんなメニューを
取ってきたらいいと思うんです。
その辺りどのように活用は検討したんですか、お聞きしたいと思います。
●答弁7(立石慎一政策部長)
浜口議員の再質問にお答えいたします。
議員が御指摘の指定された普通交付税算定におけるこども・子育て費
については、直近の国勢調査における18歳以下の人口が9,542人であっ
たため、平成6年度は約23億5,000万円が基準財政需要額に算定を
されております。
一方、子供の社会福祉や保健衛生費、その他教育に要した費用は、
詳細は確認できておりませんが、恐らく基準財政需要額として算定され
た額を上回る額を支出しているものと思われます。
今回、国が新たに財政措置をした地方独自の子育て支援分に関して
は、どの程度基準財政需要額が算定されているかは分かりかねるところ
ですけども、三豊市では今年度から、保育園児に対する保育士の人数
を1年早く増員するなどの市単独事業の取組も行っております。
基準財政需要額として算定されているとはいえ、そのまま普通交付税
として頂けるものではなく、次年度以降も算定されることが約束されて
いるものではないので、財政事情も考慮せず地方単独事業を拡充する
べきものではないと考えますが、こども未来戦略を掲げている施策に
ついては、限られた財源を有効に活用しつつ、取り組んでまいりたいと
考えております。
●丸戸研二議長
理事者の答弁は終わりました。残り10秒ですが、再質問ございますか。
●最後の発言!
子供たちへの未来への先行投資、どんどんやるべきだと思いますので、
よろしくお願いします!!!
1時間ジャストで終了しましたー。
私も子育てして、PTAにも関わらせていただきましたので、子育て
支援の質問は、「力」が入りましたー。
反省しつつ、次の質問に繋げたいと思います。
「一般質問」については以上です・・・今年は議長終わって、4回、
様々な分野で質問させていただきました。
「一般質問は議員の通信簿」
を心がけ、来年も毎回質問!で頑張る所存です。
皆様、よろしくお願い申し上げます。
ご意見はコメント欄か hama2103@gmail.com まで
お願いします。
Posted by はまぐちふどうさん at 13:16│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。