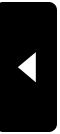2019年12月13日
全国農業新聞の記事に感動・・・
今年、「全国農業新聞」をHさんに言われて、購読していますが・・・。
一度「所有者不明農地」の「一般質問」しただけで、私自身、あまり読むところ
少ないのです。
それでも「農業」はとても弱い分野で、少しづつでも勉強を続けていく中で、
12月6日(金)の新聞記事に、とても感激する記事を見つけましたのでご紹介
します。
(全国農業新聞より掲載)
今、各地で最後に残った学校が消えていこうとしてます。
財政難を背景に、文科省が改めて統廃合を地方自治体に迫っているのです。
地方自治体側でも、人口減少の中で思い切った再編成を進めようとする動きも
見られます。
教育委員会の中には上からの圧力を背景に、統廃合を自らの「手柄」にする
ような役職者も一部に見られます。
しかし、田園回帰の時代が期待されている中、本当にそれでよいのでしょうか。
定住は地域の総合力の勝負です。
いくら農業分野で担い手確保を頑張ったとしても、近くに通える学校が無くなれ
ば、子育て世代の意欲は鈍ることでしょう。
また、本当にところ、学校の統廃合を進めれば進めるほど、地元に定住する、
あるいは帰ってくる子供は増えるのでしょうか。
むしろ、子供たちを故郷から遠ざけ、追いやる方向に働くことは確実です。
財政難を理由にするところもありますが、先生方の給料は市町村が負担しなくて
よいのです(だからこそ、国は統廃合に躍起になるのですが)。
一つの小学校があれば標準額で1千万円を超える交付税が市町村に渡り、
たいていの費用は十分賄えます。
一方、先生の職場を減らせば、地域全体の貴重な所得源が自治体から奪われ
ます。
少人数では部活動などが難しいという声もありますが、教職員の超過勤務が
問題となる中、今こそヨーロッパ的な総合型地域スポーツクラブへの進化を図る
べきでしょう。
大勢でもまれる必要があると説く人もいますが、むしろ「落ちこぼれ」をつくる弊害
が大きいと思います。
私が訪ねてきた多くの小規模校でも、一人一人の活躍の場を丁寧につくる素晴
らしい教育が行われていました。私自身の子供も、複式学級の小学校で丹念に
育てていただき、感謝しています。
世の中、「大きければ良い」という成長志向がいまだに幅を利かせています。
しかし、今からは、自然や仲間と共生しながら循環型社会を創る時代でしょう。
美しい山、川、野、海に抱かれた小さな学校の灯火(ともしび)を地域住民と共に
守り、未来につなげたいと心から願っています。
持続可能な地域社会総合研究所所長 藤山 浩氏の掲載記事より
なんか、涙 が出てきそうになりまして・・・全くその通りかと思いました。
が出てきそうになりまして・・・全くその通りかと思いました。
大浜小学校も閉校し、跡地利用で問題が出ております。

それゆえ、本市でも学校の統廃合が進んでおりますが、財政的には良いけども、
子ども達の心身を形成する「温かな思いやりのある子供」を育てるには、果たして
この施策が正しかったのかどうかはわかりません。
いろいろ考えさせられております、わたし。
本市の「曽保小学校」・・・頑張っていただきたいと思います。
一度「所有者不明農地」の「一般質問」しただけで、私自身、あまり読むところ
少ないのです。
それでも「農業」はとても弱い分野で、少しづつでも勉強を続けていく中で、
12月6日(金)の新聞記事に、とても感激する記事を見つけましたのでご紹介
します。
(全国農業新聞より掲載)
今、各地で最後に残った学校が消えていこうとしてます。
財政難を背景に、文科省が改めて統廃合を地方自治体に迫っているのです。
地方自治体側でも、人口減少の中で思い切った再編成を進めようとする動きも
見られます。
教育委員会の中には上からの圧力を背景に、統廃合を自らの「手柄」にする
ような役職者も一部に見られます。
しかし、田園回帰の時代が期待されている中、本当にそれでよいのでしょうか。
定住は地域の総合力の勝負です。
いくら農業分野で担い手確保を頑張ったとしても、近くに通える学校が無くなれ
ば、子育て世代の意欲は鈍ることでしょう。
また、本当にところ、学校の統廃合を進めれば進めるほど、地元に定住する、
あるいは帰ってくる子供は増えるのでしょうか。
むしろ、子供たちを故郷から遠ざけ、追いやる方向に働くことは確実です。
財政難を理由にするところもありますが、先生方の給料は市町村が負担しなくて
よいのです(だからこそ、国は統廃合に躍起になるのですが)。
一つの小学校があれば標準額で1千万円を超える交付税が市町村に渡り、
たいていの費用は十分賄えます。
一方、先生の職場を減らせば、地域全体の貴重な所得源が自治体から奪われ
ます。
少人数では部活動などが難しいという声もありますが、教職員の超過勤務が
問題となる中、今こそヨーロッパ的な総合型地域スポーツクラブへの進化を図る
べきでしょう。
大勢でもまれる必要があると説く人もいますが、むしろ「落ちこぼれ」をつくる弊害
が大きいと思います。
私が訪ねてきた多くの小規模校でも、一人一人の活躍の場を丁寧につくる素晴
らしい教育が行われていました。私自身の子供も、複式学級の小学校で丹念に
育てていただき、感謝しています。
世の中、「大きければ良い」という成長志向がいまだに幅を利かせています。
しかし、今からは、自然や仲間と共生しながら循環型社会を創る時代でしょう。
美しい山、川、野、海に抱かれた小さな学校の灯火(ともしび)を地域住民と共に
守り、未来につなげたいと心から願っています。
持続可能な地域社会総合研究所所長 藤山 浩氏の掲載記事より
なんか、涙
 が出てきそうになりまして・・・全くその通りかと思いました。
が出てきそうになりまして・・・全くその通りかと思いました。大浜小学校も閉校し、跡地利用で問題が出ております。

それゆえ、本市でも学校の統廃合が進んでおりますが、財政的には良いけども、
子ども達の心身を形成する「温かな思いやりのある子供」を育てるには、果たして
この施策が正しかったのかどうかはわかりません。
いろいろ考えさせられております、わたし。
本市の「曽保小学校」・・・頑張っていただきたいと思います。
Posted by はまぐちふどうさん at 07:28│Comments(0)
│その他
コメントは管理者承認が必要となります。