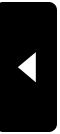2019年04月13日
H30行政視察報告(所有者不明土地)
地方議員研究会(大阪) 1月11日(金)
●土地所有者不明問題と今後の動向
榎並 利博氏(株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員)
◎所感
所有者不明土地の定義であるが、非常に広い定義で、所有者台帳が長い間、
更新されていない土地ということである。
この所有者台帳とは、一番典型的なのは登記簿である。
あと農地の場合には農地台帳等もあるが、実は法的な土地台帳は、日本
ではこの他にも存在する、が、全部の台帳を横串に刺しているのは不動産の
登記簿だけで、あとは個別のそれぞれの法律に沿って分かれている。
そのうち土地登記簿は、登記簿を見ても真実の所有者がそこに書いてある
わけではなく、日本では登記が義務化されているわけでもない。
不動産売買で土地を買えば所有権は動くが、実は今の登記制度ができて、
もう百何十年たっている訳であり、相続登記で相続などが起きると自然に
所有権は移るが、登記を必ずしているわけではないため、どんどんその
真実の所有者と登記簿の名義人が離れてきている。
また、所有者は特定できるが、現実の所在が不明というケースが、よくある
パターンである。
それから、登記名義人が死亡し、その相続人が多数いるというケースも多く
あり、これも相続が2回ぐらい繰り返されると、間違いなく相続人が100人
ぐらいになる。昔の登記所での実務の取り扱いでは、「誰々、ほか4名」など
の書き方でも登記を受け付けていたが、真実の所有者が、ほか何名では
わからないので、そうすると収用しようにも対応しようない状態となっている。
これが「所有者不明土地の問題」である。
市としても固定資産税の徴収の面で将来的に、大問題となるであろう、
対策を考えるべき時期に直面している。
国も所有者不明土地の利用円滑化法特別措置法を成立させている。
これは、すでにある所有者不明の土地を解消し、企業や自治体が活用できる
ようにする仕組みづくりで、18年の通常国会では所有者不明の土地を企業や
市町村が公園や駐車場といった公共目的に使えるようにするものである。
所有者と自治体や企業が合意すれば土地の売却などによる利活用は今でも
可能であるが、それでも、買い手がつかなかったり管理が難しかったりして、
所有者が放置してしまう土地が多いがゆえ、国や自治体などが、こうした土地
の受け皿として機能できるかも課題となっており、今の日本の土地流通の
一番の問題点をこのセミナーで学ばせていただき、とても勉強になった。
以上、簡単ですが報告を終わります。
この辺りももっと勉強したい分野です。
(自身の得意分野「家業」にも繋がる部分ですから。)
●土地所有者不明問題と今後の動向
榎並 利博氏(株式会社富士通総研 経済研究所 主席研究員)
◎所感
所有者不明土地の定義であるが、非常に広い定義で、所有者台帳が長い間、
更新されていない土地ということである。
この所有者台帳とは、一番典型的なのは登記簿である。
あと農地の場合には農地台帳等もあるが、実は法的な土地台帳は、日本
ではこの他にも存在する、が、全部の台帳を横串に刺しているのは不動産の
登記簿だけで、あとは個別のそれぞれの法律に沿って分かれている。
そのうち土地登記簿は、登記簿を見ても真実の所有者がそこに書いてある
わけではなく、日本では登記が義務化されているわけでもない。
不動産売買で土地を買えば所有権は動くが、実は今の登記制度ができて、
もう百何十年たっている訳であり、相続登記で相続などが起きると自然に
所有権は移るが、登記を必ずしているわけではないため、どんどんその
真実の所有者と登記簿の名義人が離れてきている。
また、所有者は特定できるが、現実の所在が不明というケースが、よくある
パターンである。
それから、登記名義人が死亡し、その相続人が多数いるというケースも多く
あり、これも相続が2回ぐらい繰り返されると、間違いなく相続人が100人
ぐらいになる。昔の登記所での実務の取り扱いでは、「誰々、ほか4名」など
の書き方でも登記を受け付けていたが、真実の所有者が、ほか何名では
わからないので、そうすると収用しようにも対応しようない状態となっている。
これが「所有者不明土地の問題」である。
市としても固定資産税の徴収の面で将来的に、大問題となるであろう、
対策を考えるべき時期に直面している。
国も所有者不明土地の利用円滑化法特別措置法を成立させている。
これは、すでにある所有者不明の土地を解消し、企業や自治体が活用できる
ようにする仕組みづくりで、18年の通常国会では所有者不明の土地を企業や
市町村が公園や駐車場といった公共目的に使えるようにするものである。
所有者と自治体や企業が合意すれば土地の売却などによる利活用は今でも
可能であるが、それでも、買い手がつかなかったり管理が難しかったりして、
所有者が放置してしまう土地が多いがゆえ、国や自治体などが、こうした土地
の受け皿として機能できるかも課題となっており、今の日本の土地流通の
一番の問題点をこのセミナーで学ばせていただき、とても勉強になった。
以上、簡単ですが報告を終わります。
この辺りももっと勉強したい分野です。
(自身の得意分野「家業」にも繋がる部分ですから。)
Posted by はまぐちふどうさん at 18:35│Comments(0)
│視察研修