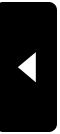2019年10月05日
私の一般質問その2(所有者不明土地)
私の一般質問は、「家業」から、最近気になる点を。
2.所有者不明土地の現状と対策について
2018年11月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法
「表題部所有者不明 土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が
成立した。
全国的に空き地が増加している中で「所有者不明土地」も年々増加している
ことが問題となっており、本市においても様々な「空き家対策」は展開がされて
いる中で、所有者不明土地の問題も当局としてできる限り先手を打って解決に
動かねばならない問題であると考える。
そこで、「所有者不明土地」の当局の現状把握と対策についてを聞く。
●質問1
次に、所有者不明土地についてお聞きいたします。
2018年11月、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法、
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が成立して
おります。
全国的に空き地が増加しており、空き地には所有者が明確な空き地と所有者
が不明な空き地の2種類があり、所有者不明土地が年々増加していることが
問題となっておりますので質問をいたします。
過去には同僚議員からの質問もありましたが、一部法整備がされてきており
ますので、そのあたりから質問をしたいと思います。
一般財団法人国土計画協会の中に設けられている所有者不明土地問題
研究会の推計によれば、2018年時点における全国の所有者不明土地の
面積は約410万ヘクタールで、九州の面積とほぼ同じ、所有者不明率は国の
20.1%と言われております。
そして、このまま何も手を打たずに放置しておくと、所有者不明土地は2040年
までに合計720万ヘクタールにまで拡大する見通しが打ち出されております。
なぜ登記名義人が不明になってしまうのかを考えれば、相続未登記が起こる
ことが理由であります。
土地の持ち主が死亡すると相続が発生し、通常は土地の相続が発生した時点
で相続人が相続登記を行い、登記簿上の名義人が変更されますが、現状、
土地の相続登記については義務づけがされていないこともあり、相続登記を
行わない事例がふえております。
余談ですけど、空き家対策も同じことで、空き家はあっても相続登記をしない
まま放置がされており、本市の空き家対策は空き家バンクや危険家屋の除去、
自治会での見守りなど、有効な施策は出されているものの、相続登記がされて
いないケースはどうあがいても現在の法律では対応できませんので、これ以上
の空き家対策も難しい現状もあろうかと思います。
相続登記を行わない理由はいろいろ考えられますが、例えば子供さんが本市
から東京、大阪に出て生活をしている場合、両親が亡くなって、地方の土地、
特に山林や農地を引き継ぐことになったとしても、もはや使わない価値のない
土地になっているので、登記をする際にかかる登録免許税、固定資産税、
維持管理費などのコストを負担したくないという意識があり、相続登記を
しないまま放置しているケースも多々あるようです。
現在、本市においては若い人の流れをつくる移住定住の促進といった目標の
ためのさまざまな施策を展開中ですが、この所有者不明土地の問題も行政と
してできる限り先手を打って解決に動かねばならない問題であると考えます。
そこで、まず、この所有者不明土地の問題について、当局はどのように認識
して対応しようとしているのか、また、現状把握と対策について、まず、以下の
点について質問をいたします。
固定資産税にかかわる所有者不明の土地の現状として、表題部所有者不明
土地が本市の何%であるのか、また、課税されている土地は本市全体の何%
で、法定免税点未満の土地は何%あるのか、また、その内訳と公示送達と
なっているものは何通あるのかなどについてまずお聞きをいたしますので、
よろしくお願いします。
●答弁1(小野守一市民環境部長)
浜口議員御指摘の所有者不明土地問題については、近年全国的に人口減少、
少子高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口移動を背景とした
土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が増加しているところです。
しかしながら、個人情報保護や守秘義務等の制約があり、対応については遅々
として進んでいないのが現状です。
そのような中、今回一連の法律の成立により、市の組織内部あるいは法務局等
機関が所有者の探索を実施するに当たって、市に対し情報の提供を求めること
ができるようになりました。
市税務課としては、このような場合は探索に必要な限度で情報提供することに
なります。
さて、三豊市の現状として、所有者不明土地の数字的な状況について御説明
申し上げます。
三豊市内には35万筆を超える筆数があります。
課税されている土地は市全体の67.5%、法定免税点未満の土地は全体の
4.7%となっています。
また、税務課で保有しているデータのうち、表題部所有者に当たる欄が正規に
記録できていない土地は5,000筆にのぼり、全体の1.4%となっています。
なお、地目別に見ると、宅地が560筆、田畑が1,700筆、その他が2,750筆と
なっています。
また、本年4月に発送した平成31年度の当初納税通知書の送付件数は
約3万通で、宛先不明等で返送されたものを含む公示送達は38件です。
●質問2
所有者がわからないために土地を利用できないという問題を解消するため
に、関係省庁でも対応が進められてきました。
先ほど言いましたが、国交省国土審議会土地政策分科会特別部会に
おいて、平成29年9月より検討を行い、平成30年6月6日、所有者不明土地
の利用の円滑化などに関する特別措置法、所有者不明法が成立し、平成
30年11月に一部が施行され、令和元年6月1日に全面的に施行がされて
おります。
このときの所有者不明のポイントは、所有者の探索方法が明確化したこと、
現在の所有者を探すために市区町村に戸籍や住民票の提出を求めること
ができるようになりました。
また、所有者が不明の土地を円滑に利用できるようにしたこと、探索の結果、
所有者がわからなかった土地を公共事業での利用の手続が簡単になったり、
地域住民のための施設を最大10年間設置することが可能になったりして
おります。
特に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みでは、反対する権利者が
おらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地において
公共事業における収用手続の合理化、円滑化として所有権の取得、
国・都道府県知事が認定した事業について、収用委員会にかわり
都道府県知事が裁定するのと、地域福祉増進事業の創設、利用権の
設定として、地域住民などの福祉利便の増進に資する事業について、
都府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、上限
10年間の利用権の設定、所有者があらわれて明け渡しを求めた場合は、
期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能なんですが、
こういうことか構築されまして、このようなことができるようになってきて
おりますので、特に公共事業における収用手続が簡単になったことへの
対応などを考えられているのかをまず再質問、一ついたします。
それと、所有者不明土地について、問題の解消を後押しするために成立
した新法が、先ほど言いました表題部所有者不明土地の登記及び管理
の適正化に関する法律であります。
権利関係の明確化や適正な利用を促進するのが狙いで、所有者不明
土地の登記の適正化を図るため、登記機関に所有者の探索のために
必要となる調査権限を与え、所有者等探索委員制度が創設され、所有者
の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設け
られております。
また、所有者の対策を行った結果、所有者を特定することができなかった
所有者不明土地について、その適切な管理を図るための措置として、
裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられて
おります。
この裁判所が選任した管理者による管理が可能となったことにより、これ
によって該当する所有者不明土地について、草木の伐採が可能になり、
これまでは所有者が不明だったため、誰の許可を得て伐採すればよい
のかわからず、山林などが荒廃するおそれがあった土地が、裁判所が
選任した管理者にその管理が任されれば、それに歯どめをかけて災害
などを未然に防ぐための施策を講じることができるようになる可能性が
高まっております。
また、適正な管理の中には、裁判所が選任した管理者が一定の条件の
もとに自身の判断によってその土地を売却するという行為も含まれて
おります。
この場合の売却代金は、所有者があらわれたときに返金できるように
するため供託して、供託金が時効を迎えるまでに所有者が供託金の
引き出しを求めてこなかった場合は、供託金が国庫帰属するという
仕組みとなっております。
ただ、今回の法整備によって売却などが可能になる土地は全国で1%
程度にとどまると言われており、本市でも先ほど5,000筆で1.4%との
答弁がありました。これは表題部所有者不明土地とは旧台帳制度化に
おける所有者欄の氏名、住所の変則的な記載があるもののみで、
所有者の登記、権利部ですね、ここがない不動産について、登記簿の
表題部に記録がされるもので、これは明治時代からある先ほどのその他
に含まれる墓地とか山林とか原野などなのかなと私は推測をしております。
そのために、実効性のある制度の構築が喫緊の課題となる中、令和元年
6月14日、所有者不明土地等対策推進のための関係閣僚会議において、
新たな基本方針及び工程表が閣議決定をされております。
国交省は、6月1日に全面施行された所有者不明土地の円滑な施行に
ついて、今後は地方整備局ごとに、地方公共団体法務局などと連携して
設置した地方協議会を通じた地方公共団体の支援やモデル事業による
先進事例支援などにより、制度の活用を推進していくようであります。
その上で2020年までに土地基本法が改正されまして、この新土地基本法に
基づく新たな総合的土地政策を提示するために、土地政策の再構築に
向けた検討が進められていくというふうになっており、少しずつではあります
が、着実にその表題部以外の所有者不明土地を取り巻く制度の動向に
引き続き注視をしていく必要があります。
要は、所有者不明土地の直接的な発生原因が相続なので、今後は相続時
の不動産登記の義務化とか、登記簿や固定資産台帳、農地台帳などの
共通化、さらに今後は地方の売れない土地が相続時に土地の所有権が
放棄できるような制度も検討されていくかもしれません。
今回調査していて、このあたりは数年先に国の制度ができるまでは、少しまだ
ブランクがあるということがわかりましたので、本市としては相続登記の必要
性についてもっと市民に周知する必要がありますし、相続登記の必要性に
ついて記載した啓発のチラシを配布したり、固定資産税の納税通知書の中に
今入れています「住宅をお持ちの皆様へ」と空き家バンク関係のチラシの中
にも相続登記の啓発と記載したりすることや、相談する窓口などの対応が
できるかとも思います。
今月号の広報では、未登記家屋の所有者が変わったとき、売買、相続、贈与
など変更したときは、名義人変更届出書を提出してくださいと小さく書かれて
いますが、今後の届出書を提出しないケースも予想されますし、このあたりの
現在できる検討策というのはどう考えておりますでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(正田尚記建設経済部長)
まず初めに、公共事業における所有者不明土地の収用手続について御説明を
させていただきます。
今回施行された所有者不明土地の利用円滑化に関する特別措置法の中で、
反対する所有者、地益権者、抵当権者がおらず、なおかつ建築物等がなく、
現に利用されていない所有者不明土地については、事業認定した公共事業に
ついて、土地収用法の特例により県知事に裁定を申請し、審理手続を省略、
権利取得裁決、明け渡し裁決を一本化することができるようになり、所有者
不明土地の収用手続に要する期間が約3分の1短縮、約10カ月の短縮する
ことができるようになりました。
また、今回、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行
以後、この土地収用法の特例に該当し、事業認定を受けて市道、河川等の
工事をしている事例は、現在のところは三豊市ではございません。
しかし、今後、所有者不明土地がふえ、特例に該当する案件が出てくる可能性
が高くなると思われますので、この特例を活用することになった場合に備え、
手続等について準備をしていく必要があると思っております。
●答弁2(小野守一市民環境部長)
まず、固定資産税については、納税義務の継承について説明いたします。
納税義務者が死亡した場合、市役所ではさまざまな手続をしていただく中で、
次の納税義務者についても遅滞なく手続ができるよう窓口にて説明をしている
ところです。
直接手続ができない場合でも、郵便等により手続の勧奨を実施しています。
ただ、相続登記についての説明は法務局での手続が必要である旨の案内は
しておりますが、積極的にできていないのが現状だと考えております。
これを機に、窓口での説明の際に、法務局作成の相続登記啓発チラシを配布
して勧奨に努め、また、御指導いただいております関係課との調整の上、市と
してできる限り取り組んでまいりたいと考えております。
●質問3
それでは、所有者不明農地についてもお聞きをいたします。
昨年11月、改正農業経営基盤強化促進法が施行され、所有者不明農地の
利用を促す制度の創設も行われております。
共有者の過半が不明な農地でも、農業委員会による探索や工事などの手続を
踏めば、農地中間管理機構を通して最長20年の賃借が可能となっております。
動かしようがなかった農地に流動化の道を開く新制度に対し、現場の関心が
高いようで、早速鹿児島県の喜界町では、全国に先駆けて喜界町農業委員会
がこの運用に乗り出し、探索を終了して、ことし1月に6カ月間の公示を開始、
他の共有者からの異議がなければ農業委員会の総会で承認された後、
利用権の設定が実現して、改正基盤法の活用、全国第1号が誕生する予定
であります。
要は、本改正により相続未登記農地であっても、全ての相続人を調べること
なく、簡易な手続で最長20年間、農地中間管理機構経由で借りることが可能
となっております。
相続未登記やそのおそれのある農地は、全国の約2割、93.4ヘクタールと言
われております。
多くは実際に耕作されてはいますが、離農後に貸し付けできなければ、多くの
遊休農地を生みますし、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要する
ことにより、地域において担い手への集積、集約化が進まないなど、問題に
なっています。
この制度はその前に手を打つものでありますが、この新制度では農業委員会
が鍵を握ると思います。
この制度を検討するのも一つの手段であると思いますが、所有者不明農地に
ついて、この新制度へのお考え、検討されているか、相談などはあるのか、
農地が相続未登記にならないような対策があるのかについても再質問を
いたします。
●答弁3(正田尚記建設経済部長)
所有者不明農地についてですが、本市においても所有者が不明となっている
相続未登記農地には、課税情報、土地登記簿謄本、戸籍謄本などから相続人
を探索し、過半の同意を得た上で、農業経営基盤強化促進法に基づき農地
中間管理機構へ利用権設定を行っています。
今回、鹿児島県喜界町農業委員会の事例のように、共有者不明農地等に
ついて2分の1以上の共有者を確知することができない場合には、6カ月間の
公示を経て、最長20年以内の利用権設定を行うことが可能ですが、現在の
ところ、本市においては2分の1以上の共有者が確知できなかった事例は
発生しておりません。
しかしながら、今後、喜界町と同様な事例が発生した場合の手続等については、
事前に準備を進めておく必要があると思っております。
所有者不明農地の所有権の移転や利用権の設定には多大の時間と労力を
要することから、相続登記の義務化など、関係法令の整備に向けて、国・県等
に強く要望してまいりたいと考えております。
●最後にお願い発言
事例はないということですが、ありがとうございます。
農地については、今、最長20年の長期の賃借が可能になったとはいえ、
いずれは所有権移転まで踏み込んだ制度も求められるかと思います。
利用権の設定期間が終われば、また一から手続する必要があり、相続
未登記の根本的な解決にはつながりませんので、やはり全般的に相続
未登記とならないような対策、市民や本市内の農地など、固定資産税を
払っている方などへの周知が必要ですから、ぜひこれらの対策を再度
お願いして質問を終わります。ありがとうございました。
不動産業に関わる、結構な得意分野は、いろいろ調べられました・・・。
それでも「一般質問」、まだまだだと感じます・・・日々精進したいと思います。
2.所有者不明土地の現状と対策について
2018年11月「所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法」が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法
「表題部所有者不明 土地の登記及び管理の適正化に関する法律」が
成立した。
全国的に空き地が増加している中で「所有者不明土地」も年々増加している
ことが問題となっており、本市においても様々な「空き家対策」は展開がされて
いる中で、所有者不明土地の問題も当局としてできる限り先手を打って解決に
動かねばならない問題であると考える。
そこで、「所有者不明土地」の当局の現状把握と対策についてを聞く。
●質問1
次に、所有者不明土地についてお聞きいたします。
2018年11月、所有者不明土地の利用の円滑化に関する特別措置法が
施行され、2019年5月には所有者不明土地問題の解消を後押しする新法、
表題部所有者不明土地の登記及び管理の適正化に関する法律が成立して
おります。
全国的に空き地が増加しており、空き地には所有者が明確な空き地と所有者
が不明な空き地の2種類があり、所有者不明土地が年々増加していることが
問題となっておりますので質問をいたします。
過去には同僚議員からの質問もありましたが、一部法整備がされてきており
ますので、そのあたりから質問をしたいと思います。
一般財団法人国土計画協会の中に設けられている所有者不明土地問題
研究会の推計によれば、2018年時点における全国の所有者不明土地の
面積は約410万ヘクタールで、九州の面積とほぼ同じ、所有者不明率は国の
20.1%と言われております。
そして、このまま何も手を打たずに放置しておくと、所有者不明土地は2040年
までに合計720万ヘクタールにまで拡大する見通しが打ち出されております。
なぜ登記名義人が不明になってしまうのかを考えれば、相続未登記が起こる
ことが理由であります。
土地の持ち主が死亡すると相続が発生し、通常は土地の相続が発生した時点
で相続人が相続登記を行い、登記簿上の名義人が変更されますが、現状、
土地の相続登記については義務づけがされていないこともあり、相続登記を
行わない事例がふえております。
余談ですけど、空き家対策も同じことで、空き家はあっても相続登記をしない
まま放置がされており、本市の空き家対策は空き家バンクや危険家屋の除去、
自治会での見守りなど、有効な施策は出されているものの、相続登記がされて
いないケースはどうあがいても現在の法律では対応できませんので、これ以上
の空き家対策も難しい現状もあろうかと思います。
相続登記を行わない理由はいろいろ考えられますが、例えば子供さんが本市
から東京、大阪に出て生活をしている場合、両親が亡くなって、地方の土地、
特に山林や農地を引き継ぐことになったとしても、もはや使わない価値のない
土地になっているので、登記をする際にかかる登録免許税、固定資産税、
維持管理費などのコストを負担したくないという意識があり、相続登記を
しないまま放置しているケースも多々あるようです。
現在、本市においては若い人の流れをつくる移住定住の促進といった目標の
ためのさまざまな施策を展開中ですが、この所有者不明土地の問題も行政と
してできる限り先手を打って解決に動かねばならない問題であると考えます。
そこで、まず、この所有者不明土地の問題について、当局はどのように認識
して対応しようとしているのか、また、現状把握と対策について、まず、以下の
点について質問をいたします。
固定資産税にかかわる所有者不明の土地の現状として、表題部所有者不明
土地が本市の何%であるのか、また、課税されている土地は本市全体の何%
で、法定免税点未満の土地は何%あるのか、また、その内訳と公示送達と
なっているものは何通あるのかなどについてまずお聞きをいたしますので、
よろしくお願いします。
●答弁1(小野守一市民環境部長)
浜口議員御指摘の所有者不明土地問題については、近年全国的に人口減少、
少子高齢化に伴う土地利用ニーズの低下や都市部への人口移動を背景とした
土地の所有意識の希薄化等により、所有者不明土地が増加しているところです。
しかしながら、個人情報保護や守秘義務等の制約があり、対応については遅々
として進んでいないのが現状です。
そのような中、今回一連の法律の成立により、市の組織内部あるいは法務局等
機関が所有者の探索を実施するに当たって、市に対し情報の提供を求めること
ができるようになりました。
市税務課としては、このような場合は探索に必要な限度で情報提供することに
なります。
さて、三豊市の現状として、所有者不明土地の数字的な状況について御説明
申し上げます。
三豊市内には35万筆を超える筆数があります。
課税されている土地は市全体の67.5%、法定免税点未満の土地は全体の
4.7%となっています。
また、税務課で保有しているデータのうち、表題部所有者に当たる欄が正規に
記録できていない土地は5,000筆にのぼり、全体の1.4%となっています。
なお、地目別に見ると、宅地が560筆、田畑が1,700筆、その他が2,750筆と
なっています。
また、本年4月に発送した平成31年度の当初納税通知書の送付件数は
約3万通で、宛先不明等で返送されたものを含む公示送達は38件です。
●質問2
所有者がわからないために土地を利用できないという問題を解消するため
に、関係省庁でも対応が進められてきました。
先ほど言いましたが、国交省国土審議会土地政策分科会特別部会に
おいて、平成29年9月より検討を行い、平成30年6月6日、所有者不明土地
の利用の円滑化などに関する特別措置法、所有者不明法が成立し、平成
30年11月に一部が施行され、令和元年6月1日に全面的に施行がされて
おります。
このときの所有者不明のポイントは、所有者の探索方法が明確化したこと、
現在の所有者を探すために市区町村に戸籍や住民票の提出を求めること
ができるようになりました。
また、所有者が不明の土地を円滑に利用できるようにしたこと、探索の結果、
所有者がわからなかった土地を公共事業での利用の手続が簡単になったり、
地域住民のための施設を最大10年間設置することが可能になったりして
おります。
特に、所有者不明土地を円滑に利用する仕組みでは、反対する権利者が
おらず、建築物がなく、現に利用されていない所有者不明土地において
公共事業における収用手続の合理化、円滑化として所有権の取得、
国・都道府県知事が認定した事業について、収用委員会にかわり
都道府県知事が裁定するのと、地域福祉増進事業の創設、利用権の
設定として、地域住民などの福祉利便の増進に資する事業について、
都府県知事が公益性を確認し、一定期間の公告に付した上で、上限
10年間の利用権の設定、所有者があらわれて明け渡しを求めた場合は、
期間終了後に原状回復、異議がない場合は延長可能なんですが、
こういうことか構築されまして、このようなことができるようになってきて
おりますので、特に公共事業における収用手続が簡単になったことへの
対応などを考えられているのかをまず再質問、一ついたします。
それと、所有者不明土地について、問題の解消を後押しするために成立
した新法が、先ほど言いました表題部所有者不明土地の登記及び管理
の適正化に関する法律であります。
権利関係の明確化や適正な利用を促進するのが狙いで、所有者不明
土地の登記の適正化を図るため、登記機関に所有者の探索のために
必要となる調査権限を与え、所有者等探索委員制度が創設され、所有者
の探索の結果を登記に反映させるための不動産登記法の特例が設け
られております。
また、所有者の対策を行った結果、所有者を特定することができなかった
所有者不明土地について、その適切な管理を図るための措置として、
裁判所の選任した管理者による管理を可能とする制度が設けられて
おります。
この裁判所が選任した管理者による管理が可能となったことにより、これ
によって該当する所有者不明土地について、草木の伐採が可能になり、
これまでは所有者が不明だったため、誰の許可を得て伐採すればよい
のかわからず、山林などが荒廃するおそれがあった土地が、裁判所が
選任した管理者にその管理が任されれば、それに歯どめをかけて災害
などを未然に防ぐための施策を講じることができるようになる可能性が
高まっております。
また、適正な管理の中には、裁判所が選任した管理者が一定の条件の
もとに自身の判断によってその土地を売却するという行為も含まれて
おります。
この場合の売却代金は、所有者があらわれたときに返金できるように
するため供託して、供託金が時効を迎えるまでに所有者が供託金の
引き出しを求めてこなかった場合は、供託金が国庫帰属するという
仕組みとなっております。
ただ、今回の法整備によって売却などが可能になる土地は全国で1%
程度にとどまると言われており、本市でも先ほど5,000筆で1.4%との
答弁がありました。これは表題部所有者不明土地とは旧台帳制度化に
おける所有者欄の氏名、住所の変則的な記載があるもののみで、
所有者の登記、権利部ですね、ここがない不動産について、登記簿の
表題部に記録がされるもので、これは明治時代からある先ほどのその他
に含まれる墓地とか山林とか原野などなのかなと私は推測をしております。
そのために、実効性のある制度の構築が喫緊の課題となる中、令和元年
6月14日、所有者不明土地等対策推進のための関係閣僚会議において、
新たな基本方針及び工程表が閣議決定をされております。
国交省は、6月1日に全面施行された所有者不明土地の円滑な施行に
ついて、今後は地方整備局ごとに、地方公共団体法務局などと連携して
設置した地方協議会を通じた地方公共団体の支援やモデル事業による
先進事例支援などにより、制度の活用を推進していくようであります。
その上で2020年までに土地基本法が改正されまして、この新土地基本法に
基づく新たな総合的土地政策を提示するために、土地政策の再構築に
向けた検討が進められていくというふうになっており、少しずつではあります
が、着実にその表題部以外の所有者不明土地を取り巻く制度の動向に
引き続き注視をしていく必要があります。
要は、所有者不明土地の直接的な発生原因が相続なので、今後は相続時
の不動産登記の義務化とか、登記簿や固定資産台帳、農地台帳などの
共通化、さらに今後は地方の売れない土地が相続時に土地の所有権が
放棄できるような制度も検討されていくかもしれません。
今回調査していて、このあたりは数年先に国の制度ができるまでは、少しまだ
ブランクがあるということがわかりましたので、本市としては相続登記の必要
性についてもっと市民に周知する必要がありますし、相続登記の必要性に
ついて記載した啓発のチラシを配布したり、固定資産税の納税通知書の中に
今入れています「住宅をお持ちの皆様へ」と空き家バンク関係のチラシの中
にも相続登記の啓発と記載したりすることや、相談する窓口などの対応が
できるかとも思います。
今月号の広報では、未登記家屋の所有者が変わったとき、売買、相続、贈与
など変更したときは、名義人変更届出書を提出してくださいと小さく書かれて
いますが、今後の届出書を提出しないケースも予想されますし、このあたりの
現在できる検討策というのはどう考えておりますでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(正田尚記建設経済部長)
まず初めに、公共事業における所有者不明土地の収用手続について御説明を
させていただきます。
今回施行された所有者不明土地の利用円滑化に関する特別措置法の中で、
反対する所有者、地益権者、抵当権者がおらず、なおかつ建築物等がなく、
現に利用されていない所有者不明土地については、事業認定した公共事業に
ついて、土地収用法の特例により県知事に裁定を申請し、審理手続を省略、
権利取得裁決、明け渡し裁決を一本化することができるようになり、所有者
不明土地の収用手続に要する期間が約3分の1短縮、約10カ月の短縮する
ことができるようになりました。
また、今回、所有者不明土地の利用の円滑化等に関する特別措置法の施行
以後、この土地収用法の特例に該当し、事業認定を受けて市道、河川等の
工事をしている事例は、現在のところは三豊市ではございません。
しかし、今後、所有者不明土地がふえ、特例に該当する案件が出てくる可能性
が高くなると思われますので、この特例を活用することになった場合に備え、
手続等について準備をしていく必要があると思っております。
●答弁2(小野守一市民環境部長)
まず、固定資産税については、納税義務の継承について説明いたします。
納税義務者が死亡した場合、市役所ではさまざまな手続をしていただく中で、
次の納税義務者についても遅滞なく手続ができるよう窓口にて説明をしている
ところです。
直接手続ができない場合でも、郵便等により手続の勧奨を実施しています。
ただ、相続登記についての説明は法務局での手続が必要である旨の案内は
しておりますが、積極的にできていないのが現状だと考えております。
これを機に、窓口での説明の際に、法務局作成の相続登記啓発チラシを配布
して勧奨に努め、また、御指導いただいております関係課との調整の上、市と
してできる限り取り組んでまいりたいと考えております。
●質問3
それでは、所有者不明農地についてもお聞きをいたします。
昨年11月、改正農業経営基盤強化促進法が施行され、所有者不明農地の
利用を促す制度の創設も行われております。
共有者の過半が不明な農地でも、農業委員会による探索や工事などの手続を
踏めば、農地中間管理機構を通して最長20年の賃借が可能となっております。
動かしようがなかった農地に流動化の道を開く新制度に対し、現場の関心が
高いようで、早速鹿児島県の喜界町では、全国に先駆けて喜界町農業委員会
がこの運用に乗り出し、探索を終了して、ことし1月に6カ月間の公示を開始、
他の共有者からの異議がなければ農業委員会の総会で承認された後、
利用権の設定が実現して、改正基盤法の活用、全国第1号が誕生する予定
であります。
要は、本改正により相続未登記農地であっても、全ての相続人を調べること
なく、簡易な手続で最長20年間、農地中間管理機構経由で借りることが可能
となっております。
相続未登記やそのおそれのある農地は、全国の約2割、93.4ヘクタールと言
われております。
多くは実際に耕作されてはいますが、離農後に貸し付けできなければ、多くの
遊休農地を生みますし、多数に及ぶ相続人の探索に多大なコストを要する
ことにより、地域において担い手への集積、集約化が進まないなど、問題に
なっています。
この制度はその前に手を打つものでありますが、この新制度では農業委員会
が鍵を握ると思います。
この制度を検討するのも一つの手段であると思いますが、所有者不明農地に
ついて、この新制度へのお考え、検討されているか、相談などはあるのか、
農地が相続未登記にならないような対策があるのかについても再質問を
いたします。
●答弁3(正田尚記建設経済部長)
所有者不明農地についてですが、本市においても所有者が不明となっている
相続未登記農地には、課税情報、土地登記簿謄本、戸籍謄本などから相続人
を探索し、過半の同意を得た上で、農業経営基盤強化促進法に基づき農地
中間管理機構へ利用権設定を行っています。
今回、鹿児島県喜界町農業委員会の事例のように、共有者不明農地等に
ついて2分の1以上の共有者を確知することができない場合には、6カ月間の
公示を経て、最長20年以内の利用権設定を行うことが可能ですが、現在の
ところ、本市においては2分の1以上の共有者が確知できなかった事例は
発生しておりません。
しかしながら、今後、喜界町と同様な事例が発生した場合の手続等については、
事前に準備を進めておく必要があると思っております。
所有者不明農地の所有権の移転や利用権の設定には多大の時間と労力を
要することから、相続登記の義務化など、関係法令の整備に向けて、国・県等
に強く要望してまいりたいと考えております。
●最後にお願い発言
事例はないということですが、ありがとうございます。
農地については、今、最長20年の長期の賃借が可能になったとはいえ、
いずれは所有権移転まで踏み込んだ制度も求められるかと思います。
利用権の設定期間が終われば、また一から手続する必要があり、相続
未登記の根本的な解決にはつながりませんので、やはり全般的に相続
未登記とならないような対策、市民や本市内の農地など、固定資産税を
払っている方などへの周知が必要ですから、ぜひこれらの対策を再度
お願いして質問を終わります。ありがとうございました。
不動産業に関わる、結構な得意分野は、いろいろ調べられました・・・。
それでも「一般質問」、まだまだだと感じます・・・日々精進したいと思います。
Posted by はまぐちふどうさん at 07:46│Comments(0)
│一般質問
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。