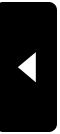2020年11月26日
京都でセミナーその1(議員定数)
11月10日(火)に、地方議員総合研究所セミナー(京都)へ。
遅くなりましたが、ご報告致します。
他3人の議員と一緒に、コロナで躊躇しましたが学ばせていただきました。
10:00~13:00
「適正な議員定数の決定手法を考える」
場所 京都テルサ
講師 廣瀬和彦 氏
(地方議員総合研究所代表取締役・全国市議会議長会法制参事)
全国から50名以上の、町議・市議・県議さん達が参加。(オンライン講義も!)
いろいろ京都の美味しいモノやお土産モノの話しを時々入れてのお話し、
また多くのデータを使っての講義がとても分かりやすかったです。

適正な議員定数の決定手法を考える
(議員定数)
1.議員定数削減は議会改革ではない。
2.類似団体の議会を参考として議員定数を決定することの無意味さ
3.住民の議会に対する無関心と議員定数への理解の欠如
4.議員定数の意義と地方自治法における規定の変貌
5.議員定数にあたっての留意点
(1)人口比例方式が採用されてきた理由
(2)監視機能への影響
(3)意見反映への影響
(4)所管委員会の判断
6.定数減少にかかる問題点と委員会審査
(1)議会費との関係
(2)監視機能への影響
(3)意見反映への影響
(4)所管委員会の判断
7.議員定数算定方式
(1)6つの基準に基づく定数算定方式
(2)選挙区と1票の格差
8.議員定数改正が与える影響を統計的に判断
(1)財政への影響
(2)政策立案への影響
(3)監視機能への影響
議員定数とは議会議員の総定数をいう。
議員定数の最大数 → 制約なし
議員定数の最小数 → 3人
市区議会議員定数の推移として、人口5~10万未満は22.7人(H23)から
20.5人(H30)となっており年々減少傾向にある。
対して議員報酬の推移、人口5~10万未満は38.5万円(H23)から39.2万円
(H30)に上がっている状況。
市区議会議員定数・報酬状況として2008~2018年、議員定数減&議員報酬
変化なしが一番多い365区市であり、次いで議員定数減&議員報酬増が
150自治体と続いている。
例えば市民に対してアンケートをとる自治体もあるが、実際アンケート内容と
して議会議員の仕事内容がわかっていない、マスコミの悪いイメ-ジ?から
市議の仕事内容までを理解できていない市民が多い。議員の仕事内容が
理解できている人にならアンケートはOKであるが、そのような人はほとんど
いないと思われる。
また前述のように、議員定数減と議員報酬増はセットでしか通らない。
本来なら議員定数は議員定数で、議員報酬は議員報酬で、別々に考えて
議論されるべき。
また自治体の議会費を増加しないような考慮もすべきである。
選挙制度の現状として、政令市以外の市町村は「大選挙区制・単記投票制」
である。
平成の大合併から地方議会議員数は
定数 64,712人(H10) → 34,130人(H26)
議員数 63,140人(H10) → 33,438人(H26)に減少をした。
特に町村議員数は40,559人(H10)から11,249人(H26)に減少したが、
市区議会議員は19,744人(H10)から24,640人(H18)に一旦増加し、
平成の大合併などを経て19,576人(H26)と、平成10年頃とほぼ横ばい
の状況となっている。
その間、統一地方選の投票率は下がる一方である。
(市区町村議選47.33%(H27))
昨今は統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選者数の割合が、
都道府県議会議員選挙で21.9%(H27)、町村議会議員選挙で21.8%(H27)
となり、2割以上が無投票、市議会議員選挙でも3.6%(H27)となっており、
議員のなり手不足が大きな問題となっている。
平成23年には地方自治法上、議会制度の自由度を高め、議会機能を充実・
強化させる見地から法定上限制度はもはや不要であるとして議員定数が
廃止され、市議会議員定数の法定上限の撤廃がなされた。
高知県大川村では人口400人の村で村議会を廃止し、「町村総会」の設置
検討が開始された。
議会の議員が住民の声を反映するものである以上、住民の数が多くなれば
多くなる程、それに比例して住民の意見の種類も多くなると考えられるから、
これを議会に反映させるべき任務を担う議員の数も多くする必要がある、と
いう議員定数と人口比例方式の意見も多い。
地方公共団体との組織全体の均衡状況を考えれば、
H22とH25年を単純に比較すれば、議員報酬総額は-9.5%、市町村長
給与総額は-8.2%、職員給総額-9.2%、一般職員総数―3.9%、平均
議員数―6.2%である。
議員報酬総額、平均議員数は職員給総額や一般職員総数より削減が
行われている(データから顕著に分かる)。
これらにより全国的に議会費は経費削減し、努力がされていることが
分かった?
また議会改革は議会の充実・強化のために行う改革であり、議員定数や
議員報酬は議会改革でなない。
これらをメインに議論することで議員のモチベーションが下がり、例えば
定数削減や報酬削減に取り組んでも、仕事内容を知らない市民からは
「まだまだだ!」という声があり、行き過ぎた過敏な対応となる場合がある。
定数や報酬も、将来的な考慮で10~15年くらいのスパンで見直しで考えて
いくべきであろう。
議会の権能を発揮する議員定数における視点
①議事機関としての権能
②立法機関としての権能発揮
③監視機関としての権能発揮
議会事務局の補佐体制として人口5~10万未満の市は議員数平均20.5人で
事務局員職員数は平均5.9人である。これは都道府県事務局職員数に比べて
圧倒的に少ない。町村では議会事務局未設置の自治体もある。
議員定数に関するアンケート調査をした自治体も多く、議員数の認知として、
あなたの住む市の議員数を知っているか?
知らないと答えた市民、明石市70.0%、鳥取市46.5%、多摩市63.5%。
議員数に対する評価として、多いと答えた市民が、明石市42.3%、浜田市
98.3%、鳥取市59.0%など、議員数すら知らないのに、多いと感じるのは
何故???という現状。
結局、住民意見として、市議さん達が何をしているのかわからない、という
アンケートでの意見が多く見受けられた。
市決算に占める議会費の割合として、議会費割合0.62%(H24)が0.55(H28)
に。
基本、どんどん減っているが、議会の絶対費が減るのは仕方ないが、絶対費
ではなく構成割合を減らすべきではない。
また一般市の議会費割合の平均は0.78%である。
二元代表制の一翼を担う議会費を減らすのはどうなのか?
個々の議員の知識や情報を積み上げていくための委員会研修や議員派遣は
増額をも検討すべきではないのか?
また最後にデータから議員定数改正が与える影響として、議員定数を削減しても
増やしても、地方財政への影響がない、コストの削減を提唱するのは意味がない
事を学べ、とても勉強になりました。
議員定数の算定方式
①常任委員会数方式
②人口比例方式
③住民自治協議会方式(または小学校区方式)
④議会費固定化方式
⑤類似都市との費会方式(人口規模・財政状況)
⑥面積・人口方式
この中では常任委員会の数(議論ができる6~7人)×常任委員会数で、議長分を
プラスすることもあり、が議員総数となる方式。
人口段階5~10万は1常任委員会あたりの常任委員会平均人数7.5人で
常任委員会の平均数3.2、
1委員会から算定した議員定数は24.0人であるが、H30平均議員定数は20.5人
であって、現状でも少ない?
また市役所組織の所管部の数も重要で、だいたい所管部毎の常任委員会数が
妥当という考え・・・本市は各所管部(2部組織)毎に1つの常任委員会となる。
●総務常任委員会
・政策部
・総務部
●教育民生常任委員会
・教育委員会
・健康福祉部
●市民建設常任委員会
・市民部
・建設経済部
富山県黒部市では、4部で各常任委員会を設置
●総務企画部
●市民生活部
●産業経済部
●都市建設部
余談になるが、このような思い切った組織内部の再編も必要かと感じた。
個人的には・・・
特に本市は3常任委員会で議論のできる7人×3で21人+議長=22人は妥当?
なのかな、という風に感じた。
これは類似団体との比較ではなく、真剣に議論していく必要があるような気が
しました。
◎最後に
議会の意志決定、多くの住民代表の意見を吸い上げる意図、様々な住民の意見
を反映し、機能するため、意志決定機関としての議会の中での議論を行うため
には、ある程度の議員定数は必要である。
(近隣市議会や類似団体との比較方式はあてにならない?と学べた。)
特にそれゆえ議員間討議の必要性を議会で議論すべきであり、本会議の中での
議員間討議を活発に行うべきである。
多くの資料やデータから検証をすれば、今の議員定数は決して多すぎるという事
はない?
やはり議会での審議や議論の中で、住民全体の利益を考えて活動できる議員
定数となっているのかが重要であり、議員定数や議員報酬の横並びは無意味
である。
昔は地域代表の顔役、世話役が名誉職として議員をしていたが、現状はサラリー
マン的な動き、定例議会での一般質問や代表質問の作成、議案審議の他に、
住民要望の相談や取次ぎ、会派における協議、定例議会以外の常任委員会
(本市での調査会)や特別委員会での議論、行政視察や議員個人の視察や
セミナー、会派での視察、広報活動など、活動範囲が一昔前と比べて非常に
拡大した仕事量にはなっており、それに見合う報酬も必要ではある?と考え
られる。
議員定数については納得しない住民に理解していただく努力が必要で、適切な
議員定数の中で活動していく事が最も重要となる。
(この辺り、議員定数削減は、データから意味が無いと言っても市民受けは
しますが。)
それよりも選挙でなぜ無投票になるのか?
この現実を変えるべく議員のなり手不足の解消を考えるべきであって、報酬を
上げてもなり手不足の解消にはならないと考える?
プラスアルファの効果的な手法はないが、議員が議会の仕事にやりがいを
感じるようになるべき、数を握ったら正論とか、役職などの人事権を握った方が
正論、だという考え方ではなくて、政策的な議論を行って、議会の活性化を図り、
議会活動、議員活動を充実したものにしていくことが重要である。
そのためにもある程度の議員定数は必要?だというような内容の廣瀬先生に
セミナー、であったと感じました。
とても参考になりましたが、やはり市民に納得いただけるデータや理由が必要
であり、議員定数を減らせばよい!という、近隣議会や類似議会がしている、
コストが下がる、という点は根拠のない理由である事が理解できましたので、
この辺りは本当に勉強になったと思いました。
(何度も言いますが、それでも定数減は市民受けしますよね。)
それも市議の仕事が理解してない人達は特に賛同してくる、というセミナーで
ありました。
ただ、それでも私の個人的な考えは・・・実は今の定数の議論があるとすれば、
議員定数の削減は、「賛成」の立場なのです。
これについては様々な意見がありますので、今後は三豊市議会でも議論が
されていくでしょうし、私もその時のために理論武装もしつつ・・・とても参考と
なるセミナーとなりました。
午後につづく・・・。
遅くなりましたが、ご報告致します。
他3人の議員と一緒に、コロナで躊躇しましたが学ばせていただきました。
10:00~13:00
「適正な議員定数の決定手法を考える」
場所 京都テルサ
講師 廣瀬和彦 氏
(地方議員総合研究所代表取締役・全国市議会議長会法制参事)
全国から50名以上の、町議・市議・県議さん達が参加。(オンライン講義も!)
いろいろ京都の美味しいモノやお土産モノの話しを時々入れてのお話し、
また多くのデータを使っての講義がとても分かりやすかったです。

適正な議員定数の決定手法を考える
(議員定数)
1.議員定数削減は議会改革ではない。
2.類似団体の議会を参考として議員定数を決定することの無意味さ
3.住民の議会に対する無関心と議員定数への理解の欠如
4.議員定数の意義と地方自治法における規定の変貌
5.議員定数にあたっての留意点
(1)人口比例方式が採用されてきた理由
(2)監視機能への影響
(3)意見反映への影響
(4)所管委員会の判断
6.定数減少にかかる問題点と委員会審査
(1)議会費との関係
(2)監視機能への影響
(3)意見反映への影響
(4)所管委員会の判断
7.議員定数算定方式
(1)6つの基準に基づく定数算定方式
(2)選挙区と1票の格差
8.議員定数改正が与える影響を統計的に判断
(1)財政への影響
(2)政策立案への影響
(3)監視機能への影響
議員定数とは議会議員の総定数をいう。
議員定数の最大数 → 制約なし
議員定数の最小数 → 3人
市区議会議員定数の推移として、人口5~10万未満は22.7人(H23)から
20.5人(H30)となっており年々減少傾向にある。
対して議員報酬の推移、人口5~10万未満は38.5万円(H23)から39.2万円
(H30)に上がっている状況。
市区議会議員定数・報酬状況として2008~2018年、議員定数減&議員報酬
変化なしが一番多い365区市であり、次いで議員定数減&議員報酬増が
150自治体と続いている。
例えば市民に対してアンケートをとる自治体もあるが、実際アンケート内容と
して議会議員の仕事内容がわかっていない、マスコミの悪いイメ-ジ?から
市議の仕事内容までを理解できていない市民が多い。議員の仕事内容が
理解できている人にならアンケートはOKであるが、そのような人はほとんど
いないと思われる。
また前述のように、議員定数減と議員報酬増はセットでしか通らない。
本来なら議員定数は議員定数で、議員報酬は議員報酬で、別々に考えて
議論されるべき。
また自治体の議会費を増加しないような考慮もすべきである。
選挙制度の現状として、政令市以外の市町村は「大選挙区制・単記投票制」
である。
平成の大合併から地方議会議員数は
定数 64,712人(H10) → 34,130人(H26)
議員数 63,140人(H10) → 33,438人(H26)に減少をした。
特に町村議員数は40,559人(H10)から11,249人(H26)に減少したが、
市区議会議員は19,744人(H10)から24,640人(H18)に一旦増加し、
平成の大合併などを経て19,576人(H26)と、平成10年頃とほぼ横ばい
の状況となっている。
その間、統一地方選の投票率は下がる一方である。
(市区町村議選47.33%(H27))
昨今は統一地方選挙における改選定数に占める無投票当選者数の割合が、
都道府県議会議員選挙で21.9%(H27)、町村議会議員選挙で21.8%(H27)
となり、2割以上が無投票、市議会議員選挙でも3.6%(H27)となっており、
議員のなり手不足が大きな問題となっている。
平成23年には地方自治法上、議会制度の自由度を高め、議会機能を充実・
強化させる見地から法定上限制度はもはや不要であるとして議員定数が
廃止され、市議会議員定数の法定上限の撤廃がなされた。
高知県大川村では人口400人の村で村議会を廃止し、「町村総会」の設置
検討が開始された。
議会の議員が住民の声を反映するものである以上、住民の数が多くなれば
多くなる程、それに比例して住民の意見の種類も多くなると考えられるから、
これを議会に反映させるべき任務を担う議員の数も多くする必要がある、と
いう議員定数と人口比例方式の意見も多い。
地方公共団体との組織全体の均衡状況を考えれば、
H22とH25年を単純に比較すれば、議員報酬総額は-9.5%、市町村長
給与総額は-8.2%、職員給総額-9.2%、一般職員総数―3.9%、平均
議員数―6.2%である。
議員報酬総額、平均議員数は職員給総額や一般職員総数より削減が
行われている(データから顕著に分かる)。
これらにより全国的に議会費は経費削減し、努力がされていることが
分かった?
また議会改革は議会の充実・強化のために行う改革であり、議員定数や
議員報酬は議会改革でなない。
これらをメインに議論することで議員のモチベーションが下がり、例えば
定数削減や報酬削減に取り組んでも、仕事内容を知らない市民からは
「まだまだだ!」という声があり、行き過ぎた過敏な対応となる場合がある。
定数や報酬も、将来的な考慮で10~15年くらいのスパンで見直しで考えて
いくべきであろう。
議会の権能を発揮する議員定数における視点
①議事機関としての権能
②立法機関としての権能発揮
③監視機関としての権能発揮
議会事務局の補佐体制として人口5~10万未満の市は議員数平均20.5人で
事務局員職員数は平均5.9人である。これは都道府県事務局職員数に比べて
圧倒的に少ない。町村では議会事務局未設置の自治体もある。
議員定数に関するアンケート調査をした自治体も多く、議員数の認知として、
あなたの住む市の議員数を知っているか?
知らないと答えた市民、明石市70.0%、鳥取市46.5%、多摩市63.5%。
議員数に対する評価として、多いと答えた市民が、明石市42.3%、浜田市
98.3%、鳥取市59.0%など、議員数すら知らないのに、多いと感じるのは
何故???という現状。
結局、住民意見として、市議さん達が何をしているのかわからない、という
アンケートでの意見が多く見受けられた。
市決算に占める議会費の割合として、議会費割合0.62%(H24)が0.55(H28)
に。
基本、どんどん減っているが、議会の絶対費が減るのは仕方ないが、絶対費
ではなく構成割合を減らすべきではない。
また一般市の議会費割合の平均は0.78%である。
二元代表制の一翼を担う議会費を減らすのはどうなのか?
個々の議員の知識や情報を積み上げていくための委員会研修や議員派遣は
増額をも検討すべきではないのか?
また最後にデータから議員定数改正が与える影響として、議員定数を削減しても
増やしても、地方財政への影響がない、コストの削減を提唱するのは意味がない
事を学べ、とても勉強になりました。
議員定数の算定方式
①常任委員会数方式
②人口比例方式
③住民自治協議会方式(または小学校区方式)
④議会費固定化方式
⑤類似都市との費会方式(人口規模・財政状況)
⑥面積・人口方式
この中では常任委員会の数(議論ができる6~7人)×常任委員会数で、議長分を
プラスすることもあり、が議員総数となる方式。
人口段階5~10万は1常任委員会あたりの常任委員会平均人数7.5人で
常任委員会の平均数3.2、
1委員会から算定した議員定数は24.0人であるが、H30平均議員定数は20.5人
であって、現状でも少ない?
また市役所組織の所管部の数も重要で、だいたい所管部毎の常任委員会数が
妥当という考え・・・本市は各所管部(2部組織)毎に1つの常任委員会となる。
●総務常任委員会
・政策部
・総務部
●教育民生常任委員会
・教育委員会
・健康福祉部
●市民建設常任委員会
・市民部
・建設経済部
富山県黒部市では、4部で各常任委員会を設置
●総務企画部
●市民生活部
●産業経済部
●都市建設部
余談になるが、このような思い切った組織内部の再編も必要かと感じた。
個人的には・・・
特に本市は3常任委員会で議論のできる7人×3で21人+議長=22人は妥当?
なのかな、という風に感じた。
これは類似団体との比較ではなく、真剣に議論していく必要があるような気が
しました。
◎最後に
議会の意志決定、多くの住民代表の意見を吸い上げる意図、様々な住民の意見
を反映し、機能するため、意志決定機関としての議会の中での議論を行うため
には、ある程度の議員定数は必要である。
(近隣市議会や類似団体との比較方式はあてにならない?と学べた。)
特にそれゆえ議員間討議の必要性を議会で議論すべきであり、本会議の中での
議員間討議を活発に行うべきである。
多くの資料やデータから検証をすれば、今の議員定数は決して多すぎるという事
はない?
やはり議会での審議や議論の中で、住民全体の利益を考えて活動できる議員
定数となっているのかが重要であり、議員定数や議員報酬の横並びは無意味
である。
昔は地域代表の顔役、世話役が名誉職として議員をしていたが、現状はサラリー
マン的な動き、定例議会での一般質問や代表質問の作成、議案審議の他に、
住民要望の相談や取次ぎ、会派における協議、定例議会以外の常任委員会
(本市での調査会)や特別委員会での議論、行政視察や議員個人の視察や
セミナー、会派での視察、広報活動など、活動範囲が一昔前と比べて非常に
拡大した仕事量にはなっており、それに見合う報酬も必要ではある?と考え
られる。
議員定数については納得しない住民に理解していただく努力が必要で、適切な
議員定数の中で活動していく事が最も重要となる。
(この辺り、議員定数削減は、データから意味が無いと言っても市民受けは
しますが。)
それよりも選挙でなぜ無投票になるのか?
この現実を変えるべく議員のなり手不足の解消を考えるべきであって、報酬を
上げてもなり手不足の解消にはならないと考える?
プラスアルファの効果的な手法はないが、議員が議会の仕事にやりがいを
感じるようになるべき、数を握ったら正論とか、役職などの人事権を握った方が
正論、だという考え方ではなくて、政策的な議論を行って、議会の活性化を図り、
議会活動、議員活動を充実したものにしていくことが重要である。
そのためにもある程度の議員定数は必要?だというような内容の廣瀬先生に
セミナー、であったと感じました。
とても参考になりましたが、やはり市民に納得いただけるデータや理由が必要
であり、議員定数を減らせばよい!という、近隣議会や類似議会がしている、
コストが下がる、という点は根拠のない理由である事が理解できましたので、
この辺りは本当に勉強になったと思いました。
(何度も言いますが、それでも定数減は市民受けしますよね。)
それも市議の仕事が理解してない人達は特に賛同してくる、というセミナーで
ありました。
ただ、それでも私の個人的な考えは・・・実は今の定数の議論があるとすれば、
議員定数の削減は、「賛成」の立場なのです。
これについては様々な意見がありますので、今後は三豊市議会でも議論が
されていくでしょうし、私もその時のために理論武装もしつつ・・・とても参考と
なるセミナーとなりました。
午後につづく・・・。
Posted by はまぐちふどうさん at 07:46│Comments(0)
│視察研修
コメントは管理者承認が必要となります。