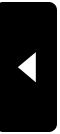2019年11月09日
東京視察研修(第15回地域医療セミナー)
11月1日(木)
ほぼ毎年参加しております「地域医療政策セミナー」。
今年は三豊市議会は私のみの参加でしたが、毎年お会いします高松市議会
の方々とお会いできました。
行きは、9時50分発の「高松空港」 → 「羽田空港」の飛行機です。
11時15分に到着し、移動して軽く昼食をとり、「赤坂見附」へ。
全国自治体病院経営都市議会協議会主催
「第15回地域医療政策セミナー」
午後1時~4時40分 都市センターホテル

●「“患者流出>流入”医療圏におけるイノベーション
~目指すべき方向の明確化とPFIの活用~」
八尾市立病院 総長 星田 四朗 氏
(八尾市立病院)
積極的な救急患者の受入れに努め、「断らない救急」への取組を進める。
「病院・診療所・薬局連携ネットワークシステム」により、薬局と病名や検査値等
の診療情報を共有するなど、病院連携の一助としてシステムを活用し、地域医療
に貢献している。平成30年度自治体立優良病院表彰(総務大臣表彰)を受賞した。
八尾市は、大阪府中河内地域に位置する市。中核市に指定されている人口
266,593人、市域面積41.72㎢、世帯数124,514世帯の市である。
八尾市立病院は病床数380床で、21の診療科目を持つ。
平成16年に病院新築移転し、PFI事業を開始した。病院事業収支は平成23年度
決算で新病院開院後初めて単年度黒字を達成し、以降8年連続で黒字決算である。
平成30年6月21日に表彰式が行われ、総務大臣から「平成30年度自治体立
優良病院表彰」を受けた。
この表彰は、経営努力がなされた結果、経営の健全性が確保されていること
及び地域医療の確保に重要な役割を果たしているなどの一定の基準を満たし
た自治体立の病院を、総務大臣が表彰するもので、これまで148病院が表彰
を受けてきたが、大阪府立の公立病院としては当院が初めての受賞となった。
特に最新の高度医療機器を整備しており、放射線治療機器(リニアック)は
一番高い7億円など、とても驚いたが医療機器の更新が地域医療の確保に
繋がっている点、とても参考になった。
元々病院のある中河内二次医療圏は、大阪府内に大学病院は5施設あるが、
中河内二次医療圏にはなく、鉄道網が大阪市を中心に放射状に展開され、
例えば八尾市中心部(近鉄八尾駅周辺)からは、大阪市内の医療機関
(大阪日赤等)への方がアクセスが良く、患者の流出がひどかった医療圏で
ある。また救急に強い民間病院も存在している。
そのため八尾市立病院には進むべき方向を明確化した病院経営で、
○1.急性期医療
・これまで流出していた患者を八尾市内で診療。
→ 市立病院として充実した医療で貢献
→ 市民に選ばれる病院へ
・総合入院体制加算の届け出を目標に体制整備・診療実績を積み上げた。
また循環器急性疾患への取り組みとして、循環器内科の診療体制を充実し、
実績に基づいた医療機器を整備した。生活習慣病としての一面で、糖尿病
センター設置を政策的に進めた。
○2.政策医療
・周産期医療
八尾市の政策医療であり、重点的に取り組みを行ってきた。産婦人科では
39床の産婦人科病棟で産婦人科医7~8人がおり、年間700~800の分娩を
行っている。
小児科では、特定入院料算定病棟を設置し、中河内医療圏小児救急輪番制
(火・土)を実施している。しかし予防医学の充実・少子化傾向は年々進み、
小児医療の提供体制を確保しつつ、急性期疾患対応を拡充した。
(一般病棟を増床し、小児科病棟を減床)周産期医療を重視しつつ、地域の
医療情勢に柔軟に対応している。
・地域医療(地域医療連携室)
地域医療支援病院の承認を受け、
→ 紹介・逆紹介の活性化(地域医療連携室を中心に・・・一番患者は来るところ)
→ 救急搬送患者の積極的な受入れ
救急医療は八尾市の政策医療で、その充実は長年の懸案であり、近年最も
力を入れている分野の一つである。
新病院開設時(平成16年5月)に地域医療連携室を設置し、2階中央受付フロア
に大きな窓口を設け「かかりつけ医との連携・機能分化」を大きくアピールした。
・地域医療(地域医療支援病院)
新病院開院当時の当院にとっては、地域医療支援病院はハードルが高すぎて
「雲の上の存在」であったが、平成21年度頃から公立病院でも承認を受ける病院
が出始めたことで、承認要件に対する現状を確認。平成22年夏から、未達成項目
の達成目標を設置し、チャレンジを開始。平成24年11月に承認となった。
・地域医療(地域医療支援病院:広報)
前方連携はPFI事業の協力企業が担当しているが、紹介状受付業務だけでなく
「広報担当者」を配置した積極的な地域連携を実施。
→ 患者向け・地域医療機関向け広報誌の作成・配布、診療報酬PR、イベントPR、
患者からの申し入れへの対応 等
・地域医療(救急医療)
地域医療のもう1つの柱である救急医療について、平成30年4月に就任した救急
診療科部長による「断らない救急」方針の浸透。
・しかし、ICU・急性期病棟とも満床状態が多く、入院が必要な場合は他院への転送
が多くなる。
しかし、「まず診てくれる」ことから救急隊との信頼関係が良化傾向になっている。
3.がん治療
「がん診療の推進」「チーム医療の強化」
→がん相談支援センター設置(平成20年2月)
→大阪府がん診療拠点病院(平成21年4月)
→チーム医療推進委員会設置(平成21年6月)
→大阪府立成人病センターより、呼吸器外科医を招聘(平成23年4月)
→大阪府立成人病センターより、放射線治療の専門医を招聘(平成26年4月)など
がんの年間手術件数は増加(平成23年度:800件 → 平成30年度:1,200件弱)
様々な取り組みの結果、平成27年4月から国指定の「地域がん診療連携拠点
病院」に。
2人に1人ががんになる時代に合わせて政策的に進める。
経営を考えるには「DPCを理解する」
・DPCは全国の病院から集めたビッグデータをもとに、標準的な治療内容・医療資源・
在院日数をもとにコード分類・標準設定としたもの。
毎月数字のチエックして、ドクターと医事課責任者のサポートをいただいている。
PFIを活用した病院経営
PFIとはPPP(公民連携)の一種で、公共事業を民間の資金と経営能力・技術力を
活用し実施する手法の1つである。
平成30年3月現在、日本国内で666件のPFI事業案件があり、病院では13件の
PFI事業が運営されている。
八尾市立病院は建築は市が従来の公共事業として行い、施設の維持管理と医療
関連サービス等の運営をPFI事業として行っているのが特徴の1つ。
SPCとして「八尾医療PFI株式会社」が設立されていた。
八尾市立病院の維持管理・運営事業のみを行う目的で設立された株式会社である。
八尾市立病院PFI事業の特徴として運営形態は
公共
医療サービス(医療のコア業務)
人事・経理・予算管理等(事務管理のコア業務)
民間
ファシリティマネジメント
病院運営業務(政令8業務)
その他病院運営業務
病院事務局は「企画運営課」1課体制(人事・経理・企画運営係)。
医事課、施設管理課、用度課等の機能はPFI事業者(協力企業)が主体となった運用
としている。また適切なモニタリングも行われているようであった。
◎所感
運営型のPFIも勉強になったが、大都市の大病院だからできる事なのではないか?
本市の予定されているような市立病院規模では、やはり「全適」を考える必要がある
と思われた。
特に前半の、八尾市立病院の進むべき方向を明確化した病院経営はたいへん参考
になり、本市の市立病院も、今後の方向性を考える上で、ソフト面での充実や、より
患者に沿った経営など、考えさせられたセミナーとなった。
●「超高齢社会に求められる地域医療のかたち」
医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長 佐々木 淳 氏
(医療法人社団悠翔会)
在宅医療に特化した医療法人で、「機能強化型在宅療養支援診療所」を東京
近郊に12ヵ所展開。365日×24時間体制で、約4000人の患者の在宅療養を
支援する。
「患者のニーズを最優先」に、すべての患者にベストの診療サービスを提供できる
よう、既存の概念や前例に捕らわれることなく理想の在宅医療を追求している。
健康寿命と平均寿命の推移から、歳をとれば、だれもが要介護、認知症になる。
それゆえ
(1)衰弱していく身体と上手に付き合う
(2)最期まで自分の人生を生き切る
ことが重要となる。
薬と転倒リスクは関係性があり、転倒の40%が薬剤関連である。特に薬が5種類
を超えると転倒リスクは急激に上昇する。特に高血圧。糖尿病・高脂血症に対する
厳格な治療は死亡のリスクを高める。
高齢者は入院がリスクであり、
リロケーションダメージ
環境変化によるストレス過緊張・適応障害・医原性サルコペニア
床上安静・食事制限による廃用症候群と低栄養の進行。
ようは1日の入院で1年歳をとる、と考えても良い。
帰ってくると要支援・要介護になっている現状。
在宅高齢者の緊急入院は肺炎と骨折で50%。入退院を繰り返しながら
要介護→寝たきり→死亡する。
「防ぐ」+「備える」
一次予防:潜在的リスクの管理
二次予防:早期発見・早期治療
三次予防:早期退院
ACP:アドバンスケアプランニング
肺炎も骨折も原因は同じ(低栄養・筋量減少・筋脆弱性)
→「食べる」が基本。高齢者の標準体重は成人と違う!
歳とともに少しずつ太ろう! (低栄養は死亡のリスクが4倍に)
ターゲットは健康寿命(怖いのは病気よりも衰弱!)塩分制限は必要?
→ (必要ない)
過剰よりも不足が問題で、いろんな栄養素を食べて、低栄養にならないこと。
在宅高齢者の平均BMI18.1であり、60%の高齢者が痩せている!
加齢に伴い筋量が減少。(1年で1%減少する)
「健康的な食事」では運動しても筋肉は戻ってこない。
ようは健康寿命が終わっている人は太った方が良い、しっかり栄養とって
しっかり運動して太れば良い。
不摂生は健康寿命が終わった人の特権である。健康寿命が終わってない人は、
「健康な人生をより長く」健康寿命が終わっている人は「残る人生をより楽しく」
が基本
健康寿命まだの人 健康寿命終わった人
・食べ過ぎない ・しっかり食べる
・太らない ・体重を増やす
・喫煙×飲酒× ・喫煙◎飲酒◎
・血圧しっかり下げる ・血圧は下げ過ぎない
・血糖しっかり下げる ・血糖は下げ過ぎない・
・脂質しっかり下げる ・脂質は下げない
・薬をちゃんと飲む ・薬はできるだけ少なく
(動脈硬化・メタボ対策)(低栄養・フレイル対策)
人生の最終段階とは?
本当は家でいたいのに日本は77.3%が病院死で、諸外国のような施設・集合
住宅死で看取れていない現状。納得できる最期を迎えるために
1.治らないという現実を受容する。
2.最期まで生活や人生を諦めない
3.苦痛の緩和は確実に
人生の最期の下り坂は自分で選べるように。看取りは医療ではないケアである。
在宅医療のKPI
①急変への対応
②入院を減らす
③自宅で看取る
在宅医療を地域全体で。
高齢者福祉の三原則
・人生(生活)の継続性
・自己決定の尊重
・残存機能(できること)の活用
・残存機能(できないこと)の確認
・ケアプランを作成・提供
・ケアプランに基づく生活援助
たくさんの人に支えられているという認識が重要。
友人がいないと死亡率が2.5倍
孤独と孤立とは違う
「生きがい」がある人は長生き
「人生の目的」があると要介護になりにくい
「人生の目的」は認知症の進行を抑制する。
社会とのつながりが寿命を決める・・・病気になっても高齢になっても最期まで
安心して暮らし続けられる地域(新しい家族関係、他世代交流、新しい役割)を
構築すれば、日本は全く違う国になる・・・とても参考になりました。
(あくまでも佐々木先生の考え?だと想いますが、いろいろ同感できる部分も
多々ありまして、とても参考になりました。)
終わったら、もう夕暮れでした。
ホテル宿泊でで、駅に向かって歩くと・・・某外資系保険会社のビル。

その昔、火災があった「ホテル・ニュージャパン」の跡地に建ってるビルです。
歴史の変化を感じます・・・夕暮れのビルを見ながら、思いました・・・。
それと同時に「永康病院」について、いろいろ考えてしまいましたが、
今回も、「政務活動費」でしっかり勉強をさせていただきました。
ありがとうございました。
ほぼ毎年参加しております「地域医療政策セミナー」。
今年は三豊市議会は私のみの参加でしたが、毎年お会いします高松市議会
の方々とお会いできました。
行きは、9時50分発の「高松空港」 → 「羽田空港」の飛行機です。
11時15分に到着し、移動して軽く昼食をとり、「赤坂見附」へ。
全国自治体病院経営都市議会協議会主催
「第15回地域医療政策セミナー」
午後1時~4時40分 都市センターホテル

●「“患者流出>流入”医療圏におけるイノベーション
~目指すべき方向の明確化とPFIの活用~」
八尾市立病院 総長 星田 四朗 氏
(八尾市立病院)
積極的な救急患者の受入れに努め、「断らない救急」への取組を進める。
「病院・診療所・薬局連携ネットワークシステム」により、薬局と病名や検査値等
の診療情報を共有するなど、病院連携の一助としてシステムを活用し、地域医療
に貢献している。平成30年度自治体立優良病院表彰(総務大臣表彰)を受賞した。
八尾市は、大阪府中河内地域に位置する市。中核市に指定されている人口
266,593人、市域面積41.72㎢、世帯数124,514世帯の市である。
八尾市立病院は病床数380床で、21の診療科目を持つ。
平成16年に病院新築移転し、PFI事業を開始した。病院事業収支は平成23年度
決算で新病院開院後初めて単年度黒字を達成し、以降8年連続で黒字決算である。
平成30年6月21日に表彰式が行われ、総務大臣から「平成30年度自治体立
優良病院表彰」を受けた。
この表彰は、経営努力がなされた結果、経営の健全性が確保されていること
及び地域医療の確保に重要な役割を果たしているなどの一定の基準を満たし
た自治体立の病院を、総務大臣が表彰するもので、これまで148病院が表彰
を受けてきたが、大阪府立の公立病院としては当院が初めての受賞となった。
特に最新の高度医療機器を整備しており、放射線治療機器(リニアック)は
一番高い7億円など、とても驚いたが医療機器の更新が地域医療の確保に
繋がっている点、とても参考になった。
元々病院のある中河内二次医療圏は、大阪府内に大学病院は5施設あるが、
中河内二次医療圏にはなく、鉄道網が大阪市を中心に放射状に展開され、
例えば八尾市中心部(近鉄八尾駅周辺)からは、大阪市内の医療機関
(大阪日赤等)への方がアクセスが良く、患者の流出がひどかった医療圏で
ある。また救急に強い民間病院も存在している。
そのため八尾市立病院には進むべき方向を明確化した病院経営で、
○1.急性期医療
・これまで流出していた患者を八尾市内で診療。
→ 市立病院として充実した医療で貢献
→ 市民に選ばれる病院へ
・総合入院体制加算の届け出を目標に体制整備・診療実績を積み上げた。
また循環器急性疾患への取り組みとして、循環器内科の診療体制を充実し、
実績に基づいた医療機器を整備した。生活習慣病としての一面で、糖尿病
センター設置を政策的に進めた。
○2.政策医療
・周産期医療
八尾市の政策医療であり、重点的に取り組みを行ってきた。産婦人科では
39床の産婦人科病棟で産婦人科医7~8人がおり、年間700~800の分娩を
行っている。
小児科では、特定入院料算定病棟を設置し、中河内医療圏小児救急輪番制
(火・土)を実施している。しかし予防医学の充実・少子化傾向は年々進み、
小児医療の提供体制を確保しつつ、急性期疾患対応を拡充した。
(一般病棟を増床し、小児科病棟を減床)周産期医療を重視しつつ、地域の
医療情勢に柔軟に対応している。
・地域医療(地域医療連携室)
地域医療支援病院の承認を受け、
→ 紹介・逆紹介の活性化(地域医療連携室を中心に・・・一番患者は来るところ)
→ 救急搬送患者の積極的な受入れ
救急医療は八尾市の政策医療で、その充実は長年の懸案であり、近年最も
力を入れている分野の一つである。
新病院開設時(平成16年5月)に地域医療連携室を設置し、2階中央受付フロア
に大きな窓口を設け「かかりつけ医との連携・機能分化」を大きくアピールした。
・地域医療(地域医療支援病院)
新病院開院当時の当院にとっては、地域医療支援病院はハードルが高すぎて
「雲の上の存在」であったが、平成21年度頃から公立病院でも承認を受ける病院
が出始めたことで、承認要件に対する現状を確認。平成22年夏から、未達成項目
の達成目標を設置し、チャレンジを開始。平成24年11月に承認となった。
・地域医療(地域医療支援病院:広報)
前方連携はPFI事業の協力企業が担当しているが、紹介状受付業務だけでなく
「広報担当者」を配置した積極的な地域連携を実施。
→ 患者向け・地域医療機関向け広報誌の作成・配布、診療報酬PR、イベントPR、
患者からの申し入れへの対応 等
・地域医療(救急医療)
地域医療のもう1つの柱である救急医療について、平成30年4月に就任した救急
診療科部長による「断らない救急」方針の浸透。
・しかし、ICU・急性期病棟とも満床状態が多く、入院が必要な場合は他院への転送
が多くなる。
しかし、「まず診てくれる」ことから救急隊との信頼関係が良化傾向になっている。
3.がん治療
「がん診療の推進」「チーム医療の強化」
→がん相談支援センター設置(平成20年2月)
→大阪府がん診療拠点病院(平成21年4月)
→チーム医療推進委員会設置(平成21年6月)
→大阪府立成人病センターより、呼吸器外科医を招聘(平成23年4月)
→大阪府立成人病センターより、放射線治療の専門医を招聘(平成26年4月)など
がんの年間手術件数は増加(平成23年度:800件 → 平成30年度:1,200件弱)
様々な取り組みの結果、平成27年4月から国指定の「地域がん診療連携拠点
病院」に。
2人に1人ががんになる時代に合わせて政策的に進める。
経営を考えるには「DPCを理解する」
・DPCは全国の病院から集めたビッグデータをもとに、標準的な治療内容・医療資源・
在院日数をもとにコード分類・標準設定としたもの。
毎月数字のチエックして、ドクターと医事課責任者のサポートをいただいている。
PFIを活用した病院経営
PFIとはPPP(公民連携)の一種で、公共事業を民間の資金と経営能力・技術力を
活用し実施する手法の1つである。
平成30年3月現在、日本国内で666件のPFI事業案件があり、病院では13件の
PFI事業が運営されている。
八尾市立病院は建築は市が従来の公共事業として行い、施設の維持管理と医療
関連サービス等の運営をPFI事業として行っているのが特徴の1つ。
SPCとして「八尾医療PFI株式会社」が設立されていた。
八尾市立病院の維持管理・運営事業のみを行う目的で設立された株式会社である。
八尾市立病院PFI事業の特徴として運営形態は
公共
医療サービス(医療のコア業務)
人事・経理・予算管理等(事務管理のコア業務)
民間
ファシリティマネジメント
病院運営業務(政令8業務)
その他病院運営業務
病院事務局は「企画運営課」1課体制(人事・経理・企画運営係)。
医事課、施設管理課、用度課等の機能はPFI事業者(協力企業)が主体となった運用
としている。また適切なモニタリングも行われているようであった。
◎所感
運営型のPFIも勉強になったが、大都市の大病院だからできる事なのではないか?
本市の予定されているような市立病院規模では、やはり「全適」を考える必要がある
と思われた。
特に前半の、八尾市立病院の進むべき方向を明確化した病院経営はたいへん参考
になり、本市の市立病院も、今後の方向性を考える上で、ソフト面での充実や、より
患者に沿った経営など、考えさせられたセミナーとなった。
●「超高齢社会に求められる地域医療のかたち」
医療法人社団悠翔会 理事長・診療部長 佐々木 淳 氏
(医療法人社団悠翔会)
在宅医療に特化した医療法人で、「機能強化型在宅療養支援診療所」を東京
近郊に12ヵ所展開。365日×24時間体制で、約4000人の患者の在宅療養を
支援する。
「患者のニーズを最優先」に、すべての患者にベストの診療サービスを提供できる
よう、既存の概念や前例に捕らわれることなく理想の在宅医療を追求している。
健康寿命と平均寿命の推移から、歳をとれば、だれもが要介護、認知症になる。
それゆえ
(1)衰弱していく身体と上手に付き合う
(2)最期まで自分の人生を生き切る
ことが重要となる。
薬と転倒リスクは関係性があり、転倒の40%が薬剤関連である。特に薬が5種類
を超えると転倒リスクは急激に上昇する。特に高血圧。糖尿病・高脂血症に対する
厳格な治療は死亡のリスクを高める。
高齢者は入院がリスクであり、
リロケーションダメージ
環境変化によるストレス過緊張・適応障害・医原性サルコペニア
床上安静・食事制限による廃用症候群と低栄養の進行。
ようは1日の入院で1年歳をとる、と考えても良い。
帰ってくると要支援・要介護になっている現状。
在宅高齢者の緊急入院は肺炎と骨折で50%。入退院を繰り返しながら
要介護→寝たきり→死亡する。
「防ぐ」+「備える」
一次予防:潜在的リスクの管理
二次予防:早期発見・早期治療
三次予防:早期退院
ACP:アドバンスケアプランニング
肺炎も骨折も原因は同じ(低栄養・筋量減少・筋脆弱性)
→「食べる」が基本。高齢者の標準体重は成人と違う!
歳とともに少しずつ太ろう! (低栄養は死亡のリスクが4倍に)
ターゲットは健康寿命(怖いのは病気よりも衰弱!)塩分制限は必要?
→ (必要ない)
過剰よりも不足が問題で、いろんな栄養素を食べて、低栄養にならないこと。
在宅高齢者の平均BMI18.1であり、60%の高齢者が痩せている!
加齢に伴い筋量が減少。(1年で1%減少する)
「健康的な食事」では運動しても筋肉は戻ってこない。
ようは健康寿命が終わっている人は太った方が良い、しっかり栄養とって
しっかり運動して太れば良い。
不摂生は健康寿命が終わった人の特権である。健康寿命が終わってない人は、
「健康な人生をより長く」健康寿命が終わっている人は「残る人生をより楽しく」
が基本
健康寿命まだの人 健康寿命終わった人
・食べ過ぎない ・しっかり食べる
・太らない ・体重を増やす
・喫煙×飲酒× ・喫煙◎飲酒◎
・血圧しっかり下げる ・血圧は下げ過ぎない
・血糖しっかり下げる ・血糖は下げ過ぎない・
・脂質しっかり下げる ・脂質は下げない
・薬をちゃんと飲む ・薬はできるだけ少なく
(動脈硬化・メタボ対策)(低栄養・フレイル対策)
人生の最終段階とは?
本当は家でいたいのに日本は77.3%が病院死で、諸外国のような施設・集合
住宅死で看取れていない現状。納得できる最期を迎えるために
1.治らないという現実を受容する。
2.最期まで生活や人生を諦めない
3.苦痛の緩和は確実に
人生の最期の下り坂は自分で選べるように。看取りは医療ではないケアである。
在宅医療のKPI
①急変への対応
②入院を減らす
③自宅で看取る
在宅医療を地域全体で。
高齢者福祉の三原則
・人生(生活)の継続性
・自己決定の尊重
・残存機能(できること)の活用
・残存機能(できないこと)の確認
・ケアプランを作成・提供
・ケアプランに基づく生活援助
たくさんの人に支えられているという認識が重要。
友人がいないと死亡率が2.5倍
孤独と孤立とは違う
「生きがい」がある人は長生き
「人生の目的」があると要介護になりにくい
「人生の目的」は認知症の進行を抑制する。
社会とのつながりが寿命を決める・・・病気になっても高齢になっても最期まで
安心して暮らし続けられる地域(新しい家族関係、他世代交流、新しい役割)を
構築すれば、日本は全く違う国になる・・・とても参考になりました。
(あくまでも佐々木先生の考え?だと想いますが、いろいろ同感できる部分も
多々ありまして、とても参考になりました。)
終わったら、もう夕暮れでした。
ホテル宿泊でで、駅に向かって歩くと・・・某外資系保険会社のビル。

その昔、火災があった「ホテル・ニュージャパン」の跡地に建ってるビルです。
歴史の変化を感じます・・・夕暮れのビルを見ながら、思いました・・・。
それと同時に「永康病院」について、いろいろ考えてしまいましたが、
今回も、「政務活動費」でしっかり勉強をさせていただきました。
ありがとうございました。
Posted by はまぐちふどうさん at 09:44│Comments(0)
│視察研修
※会員のみコメントを受け付けております、ログインが必要です。