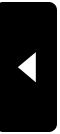2021年10月03日
私の一般質問R3/9(その1)
9月定例議会の報告は、いつもながら私の一般質問から。
1.給付型奨学金制度について
今年度からスタートした「三豊市奨学金支給制度」については、本市独自の
施策として、問い合わせや相談も多いと聞く。
申請書提出期限が終了した現在の申請状況などを含めた現状を聞く。
また市民ニーズが高ければ、今後はどのような拡充策などが検討されている
のかを聞きたい。
2.旧大浜小学校跡地利用について
旧大浜小学校跡地については旧大浜幼稚園跡地での大浜地区コミュニティ
センター(仮称)の建設が急がれると思うが、今後のスケジュールを聞く。
また先日の台風被害や長雨などの自然災害を考えるに、大浜地域での
新たな避難所の整備も必要であると考える。
公有財産処分等事務取扱マニュアルに基づく処分フローによらない、当面の
旧大浜小学校校舎の利活用などは考えられないのか。
またこの地域の一体的な、学校跡地を核とした「小さな拠点」整備を希望する
が、その辺りの検討がされていくのか当局の整備方針を聞きたい。
の2問でした。
高校生の子どもを持つシングルマザーで頑張っている同級生からの質問と、
2問目は、校舎を解体して欲しくない、利活用できないのか?という大浜の
地域の方からのご意見をいただいての質問でした。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
通告に従いまして一般質問をさせていただきますので、よろしくお願い
します。
初めに、三豊市給付型奨学金制度についてお聞きいたします。
本市では、これまでも就学の意欲を持ちながら、家庭の経済的な理由に
より就学困難な人に対し、貸与型奨学金制度による貸付けを行ってきて
おりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が深刻な中、
これから大学や短大、専修学校への進学を志す学生たちが夢や希望を
持ち、成長できる社会の実現に向けた取組の施策の一つとして、新たに
三豊市独自の給付型奨学金制度がスタートしようとしております。
6月1日からはこの受付が開始されましたが、この三豊市給付型奨学金
制度については、本市独自の施策として非常に問合せや相談が多いと
お聞きをしております。
この事業においてはふるさと納税が財源となっておりますが、5月末には
この事業に対して匿名の方から現金100万円の御寄附も頂き、本当に
ありがたく思いますが、申請者期限が終了し、現在の申請状況などを
含めた現状をお聞きいたします。
私自身、ちょうど私どもの子供世代でありますので、保護者からの問合せ
もあるのですが、市民ニーズが高ければ、今後はどのような拡充策が
検討されているかもお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁(山下昭史市長)
三豊市奨学金支給制度は三豊市独自の施策であり、コロナ禍などに
よる家庭の事情により就学を諦めることなく、意欲ある学生たちが夢の
実現に専念できるよう、今年度新たに創設したものです。
制度開始に当たりましては、1人でも多くの対象者にこの制度を知って
いただくため、広報紙や防災行政無線、市のホームページ掲載だけで
なく、対象者である三豊市出身の子供たちがこの春まで在籍していた
坂出以西の全ての公立・私立高校に職員がお伺いして説明するなど、
制度の周知に努めたところであります。
その結果、募集を開始しました6月以降、対象者本人やその保護者、
親族の方から、また、県内の自治体や高等学校、報道機関も含め
129件の問合せがあるなど、本制度への関心の高さを肌で感じたところ
であります。
これら問合せの内容につきましては、主に制度や申請要件、申請書の
書き方に関するものがほとんどでありましたが、中には、家族に対象者
はいないが、ニュースを見てよい取組だと思うとの激励の言葉もあったと
聞いております。
このような反響の中、7月末の申請締切時には63名もの申請があり、
速やかに教育委員による選考会議を開催、委員各位の公平・公正な
視点での選考をもって合否を決定し、8月31日に選考結果の通知書を
発送したところであります。
そして、現在は支給決定となった20名に対し、今月末までに給付できる
よう手続を進めている状況であります。
議員御質問の当制度の拡充策につきましては、まずは現役学生たち
の生活の実態を把握するため、昨年度より新型コロナウイルスの影響
をじかに受けている現2年生を含む現役学生を対象にニーズ調査を
実施した結果、回答者139人中73人、約53%が「学生生活で困っている」
との回答がありました。
また、「在学生を対象とした新たな給付型奨学金制度があれば利用したい
か」の問いには、64%が「利用したい」と回答。そして、利用したい主な
理由として親の収入や学生本人のアルバイト収入の激減が挙げられ、
コロナ禍の収束が見えない中での不安かつ不安定な生活実態が読み
取れる結果となっております。
三豊市といたしましては、この結果を受け、将来を担う当市出身の現役
学生たちが経済的な理由で道半ばで夢を諦めることなく学びを継続できる
環境を実現するため、現行の新入学生に現役学生をも対象に加えること、
さらに新入学生につきましても当該年の3月に高校を卒業された方以外の
新1年生、すなわち浪人されて大学、短大及び専門学校に進学された方も
対象に含めた給付型奨学金制度に拡充したいと考えております。
●再質問
今年度入学の現役学生以外への拡充、特に、文部科学省の調査では、
コロナ禍で昨年度後期について全国の大学生の約6割が「授業の大部分を
オンラインで受けた」と回答しており、対面授業が受けられる普通の大学生活
が送れない、また大学で友達ができにくいなどの状況も報告が書かれており
ます。
それでも普通に授業料やアパートなどでの賃料は発生しておりますので、
やはり対象層の拡充、浪人生の進学も含めての対応も予定されていると、
とてもすばらしい取組でありますし、ぜひ応援をしたいと思います。
それと、やはり昨今は格差社会でも教育格差が叫ばれております。
格差とは、所得、資産、教育などにおいて生じた一定レベルの差が社会的な
階層化をもたらしている状況であり、階層化とは、当事者が選択性を持てない、
あるいは著しく制約を受ける身分的な一定の段階層的に位置することを余儀
なくされる状況を意味します。
自治体では、こうした格差社会の状態を地域内で認識して是正する取組が
必要で、地域内の格差状態を放置すれば地域力が劣化し、地域の持続性を
も担保することが難しくなります。
特にコロナ禍が長期化する中で、全国的に地域住民の生活などをめぐって
社会の格差が一段と拡大しているように感じます。
特に子育て世代で所得が減少している現状があり、足元での日常生活に
とどまらず、将来的にも負の連鎖による深刻な影響など、暗い影を落とし
始めております。
給付型奨学金でも20名は助かりますが、その他の皆さんも深刻な影響が
ある方もいると考えます。
それゆえ、金融機関の教育ローンなどの選択肢も出るかと思いますが、教育
ローンの利子補給などでの支援ができないでしょうか。
子育て世帯に対する経済的負担の軽減などを目的として、県や市などが金融
機関の教育ローンの利用者に対して、その利子の一部または全部に相当する
金額を給付する制度を設けている自治体があります。近隣では高松市が導入
しておりますが、市内に支店のある金融機関の融資を受けた資金に係る約定
利子、今年度支払った利子の合計金額のうち、年利1%相当の限度額2万円
の利子補給の制度を導入しております。
利子補給であれば財政負担も少ないですし、やはり給付型5万円とは別枠に
入学料や授業料は国公立でも数十万円かかっております。
施設整備費などの学校納付金の負担も含めれば、教育ローンに頼らざるを
得ないという方もおられると思います。
高松市の場合は、前年の世帯の合計所得金額が500万円以下で市税の滞納
がない方を対象としておりますが、この辺りのプラスでの導入を検討してもいい
かなと思うのですが、どうでしょうか。再質問をいたします。
○議長(為広員史君) ただいまの再質問に対し、理事者の答弁を求めます。
●答弁(西川昌幸教育部長)
議員御案内のとおり、教育ローンの利子補給制度は、子育て世代に対する
経済的負担の軽減等を目的として、県や市町、さらには大学などが教育ローン
利用者に対しその利子の一部または全額を給付する制度であり、県内では
高松市が導入いたしております。
子供の教育費は、ある地方銀行の試算によりますと、幼稚園から大学まで
全て国公立の学校に通うとすると約790万円、全て私立の学校に通うとする
と約2,290万円が必要とされており、これに交通費や家賃、生活費を加えると
膨大な金額となりますことから、家庭の状況によりましては、これを工面する
ため教育ローンや奨学金を利用せざるを得ないのが現状であると認識いた
しております。
三豊市教育委員会といたしましては、教育格差が叫ばれる中、これを是正
するための万策を打つことの必要性、重要性は認識いたしておりますが、先
ほど申し上げました現行の給付型奨学金制度の拡充により現役学生も対象
となりますことから、本年度の選考により残念ながら支給できなかった学生
につきましても、その後目指そうとする道が変わった、また家庭環境が変化
したなど自らを取り巻く環境が変わった場合をはじめ、現状と環境の変化が
ない場合にも再度申請いただくことが可能となります。
このことからも、まずは取組を始めました、この給付型奨学金制度を成熟
させることに重心を置きつつ、議員御案内の教育ローンに対する利子補給
制度など、保護者や学生たちの現状、ニーズを捉まえた上で、効果的な施策
につきまして今後とも調査・研究をしてまいりたいと考えております。
●再質問
金融機関の利子補給から発展した形として、鹿児島県長島町に「ぶり奨学金
制度」というのがあります。
これをつくられたのは、2016年に総務省から地方創生人材支援制度で、30歳
の若さで長島町の副町長、地方創生統括官に就任した井上貴至氏であります。
これは、卒業後に長島町に定住すれば少額ローンの返済を町が補填する制度
であります。
出世魚で回遊魚のブリ、ここら辺のはハマチですけど、このブリにちなんで、学校
卒業後、地元リーダーとして活躍してほしいとの願いを込めて名づけられました。
令和3年第1回定例会の中の三木議員の質問の中で、優れた人材となる意欲
のある学生がこの奨学金によって三豊市に帰ってこられないものかと、優秀な
子供たちに帰ってきてほしいとの質問がありました。
山下市長のほうからは、「この条件が子供たちの夢を実現するに当たっての
可能性を狭めてはならない。条件は設けず、自由に自らの進むべき道を選んで
ほしい。そして、三豊出身の子供たちに日本中、いや世界を股にかけて活躍して
ほしいと思っています。きっとそういった子供たちは、三豊市におらずとも三豊市
のことを考え、行動してくれるものと私は信じています」と、すばらしい答弁があり
ましたが、一方では、三豊へ戻って夢を実現したいと考える子供もいるでしょうし、
本市に帰られて活躍いただく方もいるはずであります。
若者人口はますます減少します。
それゆえ、市内企業でも優秀な学生人材を求めているし、学生に選ばれる企業
づくりへも変貌していく必要もあります。
余談ですが、先日の新聞で、内閣府の報告書「地域の経済2020-2021」が
発表され、2022年卒業予定の大学生や大学院生の57%が「テレワークなどが
進み、働く場所が自由に決められる場合には地方に住みたい」と回答し、新型
コロナウイルス感染拡大でテレワークの導入が進んで、若者を中心に地方移住
への関心が高まっているとも報告されました。
それゆえ、地方出身の大学生がふるさとに戻ることも半分以上の確率である
ような時代へとなっております。
一昨日の詫間議員の人口減少の質問の中でも、「三豊で育つ子供たちが夢を
諦めることなくチャレンジできる環境をつくり、進学などで三豊を離れても、必ず
ふるさとへ帰りたいと思えるようなまちづくりを目指して、行政、市民が一体と
なってまちづくりに取り組んでまいります」と貞廣政策部長からの御答弁があり
ました。
それゆえ、本市でも若者のUターンも奨励するべく、ふるさとで活躍できないこと
はありませんので、ぜひ検討いただきたいところであります。
長島町のぶり奨学金は、利息分は町が全額負担し、元金分も卒業後10年
以内に長島町に戻れば全額補填であります。
また、ぶり奨学金制度の基金は町の皆様からの寄附やふるさと納税で成り立ち、
町の皆様が安心して子育てできるよう、これから生まれてくる子供たちが高校、
大学などを卒業後、10年かけて返済・補填する期間は制度として持続する必要
があります。
行政だけでぶり奨学金を運営するのではなく、町の皆様の寄附を幅広く募ること
によって持続可能な形で制度化されており、現在は全国で1市3町が賛同し、
導入がされているようです。
よく調べてみますと、この制度は長島本島という小さな島での町による取組です。
私が一番に感銘を受けましたのは、地元の金融機関と連携することと併せて、
地元に戻れば返済を補填する原資を皆さんの寄附で集めるという点です。
それゆえ、地域のみんなで子育てを応援しようということを分かりやすく伝えて
いる点、特に行政だけの財政負担ではないので、より長く、多くの人が利用できる
点、持続可能なシステムを確立している点であります。
やはり行政だけだと財政負担のことをどうしても考えざるを得ません。
今回も奇特な方から100万円の寄附金があり、財源充当されるようですが、基金
としての運用も検討いただき、将来的にはぶり奨学金のような持続可能なシス
テムも検討するべきだと考えますが、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁(西川昌幸教育部長)
議員御案内のとおり、鹿児島県長島町におきましては、町の発展と活性化を
図るため、地域で育った人材が町外でふるさとの活性化を担う人材に成長し、
町内に戻ってくることを支援するため、町内の金融機関から借りたぶり奨学
ローンの返済をした場合、元金相当額については卒業後に町内に戻って居住
している期間分を、利子相当額については全期間分をぶり奨学基金から補填
する制度でございまして、単なる就学支援だけではなく、まちに戻ってきた際の
支援までトータルに行うことで、地域経済に好循環を生み出す仕組みとして
設定されたものであると認識いたしております。
また、その基金の原資は、御案内がありましたように、行政の負担だけでは
なく、町民や事業者の皆様ができる範囲内での寄附金、これで賄っており
まして、地域参加型、地域が支える持続可能な仕組みとされており、この点、
現行の投資給付型奨学金制度を安定的、発展的かつ継続的に維持していく
ために必要な財源調達の範ともなり得るものと考えております。
いずれにいたしましても、当制度につきましては、教育観点のみならず、人口
減少が急激に進む中での定住対策として、また、雇用確保対策として検討
すべき手法であると考えますことから、教育委員会のみならず政策部共々に
検討いたします中で、今後の方向性を見いだしてまいりたいというふうに考えて
ございます。
以上、浜口議員の再質問にお答えいたします。
●再質問
最後に給付型奨学金の分析といいますか、エビデンスも必要だと考えます。
この月額5万円が何に一番使われているのか検証が必要だと思います。
給付型奨学金が終わって、きちんと調査やアンケートなどを行い、奨学金の
使い道といいますか、使途を実態として、家賃などの住居費なのか、生活費
なのか、それとも授業料なのか、これらをきちっと分析していくことが持続可能
な奨学金制度につながると考えます。
県内の大学と県外の大学、また都市部の大学と地方の大学、国公立と私立の
大学や医学部、歯学部など、また専門学校においても、やはり給付型奨学金の
使用用途が違ってくると考えますので、給付すれば終わりではありませんし、
エビデンスを持って次の制度につなげていくことが非常に重要だと思うんですが、
どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁(西川昌幸教育部長)
三豊市給付型奨学金制度につきましては、コロナ禍の中、家庭の事情などに
より窮地に追い込まれた子供たちが進学を諦め、また夢を諦めることがないよう、
少しでも早く助け出したいというところで急遽立案したものでございます。
こちらの立案、施行に当たりましては議員各位の本当に御協力をいただいた
ものと感謝いたしておりますが、そういった実感的なこともございましたことから、
手探りで始めたところも多々ございます。
そういったところを踏まえまして、今後につきましてはこの制度をより学生たちの
実態に寄り添った形にしていきたいというふうに考えております。
御案内の卒業後も含めました効果、何に使われたのかといった部分につきましても、
給付対象者の御迷惑にならない範囲内で御意見なりをお伺いする中、いただいた
御意見を一つの重大なエビデンスと捉まえまして、よりこの制度を成熟させて
いきたいというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。
以上が一問目でした。
今後拡充するいい答弁が得られて、四国新聞にも掲載されましたー。
少し嬉しかったです 。
。
明日の2問目に続く・・・。
1.給付型奨学金制度について
今年度からスタートした「三豊市奨学金支給制度」については、本市独自の
施策として、問い合わせや相談も多いと聞く。
申請書提出期限が終了した現在の申請状況などを含めた現状を聞く。
また市民ニーズが高ければ、今後はどのような拡充策などが検討されている
のかを聞きたい。
2.旧大浜小学校跡地利用について
旧大浜小学校跡地については旧大浜幼稚園跡地での大浜地区コミュニティ
センター(仮称)の建設が急がれると思うが、今後のスケジュールを聞く。
また先日の台風被害や長雨などの自然災害を考えるに、大浜地域での
新たな避難所の整備も必要であると考える。
公有財産処分等事務取扱マニュアルに基づく処分フローによらない、当面の
旧大浜小学校校舎の利活用などは考えられないのか。
またこの地域の一体的な、学校跡地を核とした「小さな拠点」整備を希望する
が、その辺りの検討がされていくのか当局の整備方針を聞きたい。
の2問でした。
高校生の子どもを持つシングルマザーで頑張っている同級生からの質問と、
2問目は、校舎を解体して欲しくない、利活用できないのか?という大浜の
地域の方からのご意見をいただいての質問でした。
●質問1
19番、清風会、浜口恭行です。
通告に従いまして一般質問をさせていただきますので、よろしくお願い
します。
初めに、三豊市給付型奨学金制度についてお聞きいたします。
本市では、これまでも就学の意欲を持ちながら、家庭の経済的な理由に
より就学困難な人に対し、貸与型奨学金制度による貸付けを行ってきて
おりましたが、新型コロナウイルスの感染拡大による影響が深刻な中、
これから大学や短大、専修学校への進学を志す学生たちが夢や希望を
持ち、成長できる社会の実現に向けた取組の施策の一つとして、新たに
三豊市独自の給付型奨学金制度がスタートしようとしております。
6月1日からはこの受付が開始されましたが、この三豊市給付型奨学金
制度については、本市独自の施策として非常に問合せや相談が多いと
お聞きをしております。
この事業においてはふるさと納税が財源となっておりますが、5月末には
この事業に対して匿名の方から現金100万円の御寄附も頂き、本当に
ありがたく思いますが、申請者期限が終了し、現在の申請状況などを
含めた現状をお聞きいたします。
私自身、ちょうど私どもの子供世代でありますので、保護者からの問合せ
もあるのですが、市民ニーズが高ければ、今後はどのような拡充策が
検討されているかもお聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁(山下昭史市長)
三豊市奨学金支給制度は三豊市独自の施策であり、コロナ禍などに
よる家庭の事情により就学を諦めることなく、意欲ある学生たちが夢の
実現に専念できるよう、今年度新たに創設したものです。
制度開始に当たりましては、1人でも多くの対象者にこの制度を知って
いただくため、広報紙や防災行政無線、市のホームページ掲載だけで
なく、対象者である三豊市出身の子供たちがこの春まで在籍していた
坂出以西の全ての公立・私立高校に職員がお伺いして説明するなど、
制度の周知に努めたところであります。
その結果、募集を開始しました6月以降、対象者本人やその保護者、
親族の方から、また、県内の自治体や高等学校、報道機関も含め
129件の問合せがあるなど、本制度への関心の高さを肌で感じたところ
であります。
これら問合せの内容につきましては、主に制度や申請要件、申請書の
書き方に関するものがほとんどでありましたが、中には、家族に対象者
はいないが、ニュースを見てよい取組だと思うとの激励の言葉もあったと
聞いております。
このような反響の中、7月末の申請締切時には63名もの申請があり、
速やかに教育委員による選考会議を開催、委員各位の公平・公正な
視点での選考をもって合否を決定し、8月31日に選考結果の通知書を
発送したところであります。
そして、現在は支給決定となった20名に対し、今月末までに給付できる
よう手続を進めている状況であります。
議員御質問の当制度の拡充策につきましては、まずは現役学生たち
の生活の実態を把握するため、昨年度より新型コロナウイルスの影響
をじかに受けている現2年生を含む現役学生を対象にニーズ調査を
実施した結果、回答者139人中73人、約53%が「学生生活で困っている」
との回答がありました。
また、「在学生を対象とした新たな給付型奨学金制度があれば利用したい
か」の問いには、64%が「利用したい」と回答。そして、利用したい主な
理由として親の収入や学生本人のアルバイト収入の激減が挙げられ、
コロナ禍の収束が見えない中での不安かつ不安定な生活実態が読み
取れる結果となっております。
三豊市といたしましては、この結果を受け、将来を担う当市出身の現役
学生たちが経済的な理由で道半ばで夢を諦めることなく学びを継続できる
環境を実現するため、現行の新入学生に現役学生をも対象に加えること、
さらに新入学生につきましても当該年の3月に高校を卒業された方以外の
新1年生、すなわち浪人されて大学、短大及び専門学校に進学された方も
対象に含めた給付型奨学金制度に拡充したいと考えております。
●再質問
今年度入学の現役学生以外への拡充、特に、文部科学省の調査では、
コロナ禍で昨年度後期について全国の大学生の約6割が「授業の大部分を
オンラインで受けた」と回答しており、対面授業が受けられる普通の大学生活
が送れない、また大学で友達ができにくいなどの状況も報告が書かれており
ます。
それでも普通に授業料やアパートなどでの賃料は発生しておりますので、
やはり対象層の拡充、浪人生の進学も含めての対応も予定されていると、
とてもすばらしい取組でありますし、ぜひ応援をしたいと思います。
それと、やはり昨今は格差社会でも教育格差が叫ばれております。
格差とは、所得、資産、教育などにおいて生じた一定レベルの差が社会的な
階層化をもたらしている状況であり、階層化とは、当事者が選択性を持てない、
あるいは著しく制約を受ける身分的な一定の段階層的に位置することを余儀
なくされる状況を意味します。
自治体では、こうした格差社会の状態を地域内で認識して是正する取組が
必要で、地域内の格差状態を放置すれば地域力が劣化し、地域の持続性を
も担保することが難しくなります。
特にコロナ禍が長期化する中で、全国的に地域住民の生活などをめぐって
社会の格差が一段と拡大しているように感じます。
特に子育て世代で所得が減少している現状があり、足元での日常生活に
とどまらず、将来的にも負の連鎖による深刻な影響など、暗い影を落とし
始めております。
給付型奨学金でも20名は助かりますが、その他の皆さんも深刻な影響が
ある方もいると考えます。
それゆえ、金融機関の教育ローンなどの選択肢も出るかと思いますが、教育
ローンの利子補給などでの支援ができないでしょうか。
子育て世帯に対する経済的負担の軽減などを目的として、県や市などが金融
機関の教育ローンの利用者に対して、その利子の一部または全部に相当する
金額を給付する制度を設けている自治体があります。近隣では高松市が導入
しておりますが、市内に支店のある金融機関の融資を受けた資金に係る約定
利子、今年度支払った利子の合計金額のうち、年利1%相当の限度額2万円
の利子補給の制度を導入しております。
利子補給であれば財政負担も少ないですし、やはり給付型5万円とは別枠に
入学料や授業料は国公立でも数十万円かかっております。
施設整備費などの学校納付金の負担も含めれば、教育ローンに頼らざるを
得ないという方もおられると思います。
高松市の場合は、前年の世帯の合計所得金額が500万円以下で市税の滞納
がない方を対象としておりますが、この辺りのプラスでの導入を検討してもいい
かなと思うのですが、どうでしょうか。再質問をいたします。
○議長(為広員史君) ただいまの再質問に対し、理事者の答弁を求めます。
●答弁(西川昌幸教育部長)
議員御案内のとおり、教育ローンの利子補給制度は、子育て世代に対する
経済的負担の軽減等を目的として、県や市町、さらには大学などが教育ローン
利用者に対しその利子の一部または全額を給付する制度であり、県内では
高松市が導入いたしております。
子供の教育費は、ある地方銀行の試算によりますと、幼稚園から大学まで
全て国公立の学校に通うとすると約790万円、全て私立の学校に通うとする
と約2,290万円が必要とされており、これに交通費や家賃、生活費を加えると
膨大な金額となりますことから、家庭の状況によりましては、これを工面する
ため教育ローンや奨学金を利用せざるを得ないのが現状であると認識いた
しております。
三豊市教育委員会といたしましては、教育格差が叫ばれる中、これを是正
するための万策を打つことの必要性、重要性は認識いたしておりますが、先
ほど申し上げました現行の給付型奨学金制度の拡充により現役学生も対象
となりますことから、本年度の選考により残念ながら支給できなかった学生
につきましても、その後目指そうとする道が変わった、また家庭環境が変化
したなど自らを取り巻く環境が変わった場合をはじめ、現状と環境の変化が
ない場合にも再度申請いただくことが可能となります。
このことからも、まずは取組を始めました、この給付型奨学金制度を成熟
させることに重心を置きつつ、議員御案内の教育ローンに対する利子補給
制度など、保護者や学生たちの現状、ニーズを捉まえた上で、効果的な施策
につきまして今後とも調査・研究をしてまいりたいと考えております。
●再質問
金融機関の利子補給から発展した形として、鹿児島県長島町に「ぶり奨学金
制度」というのがあります。
これをつくられたのは、2016年に総務省から地方創生人材支援制度で、30歳
の若さで長島町の副町長、地方創生統括官に就任した井上貴至氏であります。
これは、卒業後に長島町に定住すれば少額ローンの返済を町が補填する制度
であります。
出世魚で回遊魚のブリ、ここら辺のはハマチですけど、このブリにちなんで、学校
卒業後、地元リーダーとして活躍してほしいとの願いを込めて名づけられました。
令和3年第1回定例会の中の三木議員の質問の中で、優れた人材となる意欲
のある学生がこの奨学金によって三豊市に帰ってこられないものかと、優秀な
子供たちに帰ってきてほしいとの質問がありました。
山下市長のほうからは、「この条件が子供たちの夢を実現するに当たっての
可能性を狭めてはならない。条件は設けず、自由に自らの進むべき道を選んで
ほしい。そして、三豊出身の子供たちに日本中、いや世界を股にかけて活躍して
ほしいと思っています。きっとそういった子供たちは、三豊市におらずとも三豊市
のことを考え、行動してくれるものと私は信じています」と、すばらしい答弁があり
ましたが、一方では、三豊へ戻って夢を実現したいと考える子供もいるでしょうし、
本市に帰られて活躍いただく方もいるはずであります。
若者人口はますます減少します。
それゆえ、市内企業でも優秀な学生人材を求めているし、学生に選ばれる企業
づくりへも変貌していく必要もあります。
余談ですが、先日の新聞で、内閣府の報告書「地域の経済2020-2021」が
発表され、2022年卒業予定の大学生や大学院生の57%が「テレワークなどが
進み、働く場所が自由に決められる場合には地方に住みたい」と回答し、新型
コロナウイルス感染拡大でテレワークの導入が進んで、若者を中心に地方移住
への関心が高まっているとも報告されました。
それゆえ、地方出身の大学生がふるさとに戻ることも半分以上の確率である
ような時代へとなっております。
一昨日の詫間議員の人口減少の質問の中でも、「三豊で育つ子供たちが夢を
諦めることなくチャレンジできる環境をつくり、進学などで三豊を離れても、必ず
ふるさとへ帰りたいと思えるようなまちづくりを目指して、行政、市民が一体と
なってまちづくりに取り組んでまいります」と貞廣政策部長からの御答弁があり
ました。
それゆえ、本市でも若者のUターンも奨励するべく、ふるさとで活躍できないこと
はありませんので、ぜひ検討いただきたいところであります。
長島町のぶり奨学金は、利息分は町が全額負担し、元金分も卒業後10年
以内に長島町に戻れば全額補填であります。
また、ぶり奨学金制度の基金は町の皆様からの寄附やふるさと納税で成り立ち、
町の皆様が安心して子育てできるよう、これから生まれてくる子供たちが高校、
大学などを卒業後、10年かけて返済・補填する期間は制度として持続する必要
があります。
行政だけでぶり奨学金を運営するのではなく、町の皆様の寄附を幅広く募ること
によって持続可能な形で制度化されており、現在は全国で1市3町が賛同し、
導入がされているようです。
よく調べてみますと、この制度は長島本島という小さな島での町による取組です。
私が一番に感銘を受けましたのは、地元の金融機関と連携することと併せて、
地元に戻れば返済を補填する原資を皆さんの寄附で集めるという点です。
それゆえ、地域のみんなで子育てを応援しようということを分かりやすく伝えて
いる点、特に行政だけの財政負担ではないので、より長く、多くの人が利用できる
点、持続可能なシステムを確立している点であります。
やはり行政だけだと財政負担のことをどうしても考えざるを得ません。
今回も奇特な方から100万円の寄附金があり、財源充当されるようですが、基金
としての運用も検討いただき、将来的にはぶり奨学金のような持続可能なシス
テムも検討するべきだと考えますが、どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁(西川昌幸教育部長)
議員御案内のとおり、鹿児島県長島町におきましては、町の発展と活性化を
図るため、地域で育った人材が町外でふるさとの活性化を担う人材に成長し、
町内に戻ってくることを支援するため、町内の金融機関から借りたぶり奨学
ローンの返済をした場合、元金相当額については卒業後に町内に戻って居住
している期間分を、利子相当額については全期間分をぶり奨学基金から補填
する制度でございまして、単なる就学支援だけではなく、まちに戻ってきた際の
支援までトータルに行うことで、地域経済に好循環を生み出す仕組みとして
設定されたものであると認識いたしております。
また、その基金の原資は、御案内がありましたように、行政の負担だけでは
なく、町民や事業者の皆様ができる範囲内での寄附金、これで賄っており
まして、地域参加型、地域が支える持続可能な仕組みとされており、この点、
現行の投資給付型奨学金制度を安定的、発展的かつ継続的に維持していく
ために必要な財源調達の範ともなり得るものと考えております。
いずれにいたしましても、当制度につきましては、教育観点のみならず、人口
減少が急激に進む中での定住対策として、また、雇用確保対策として検討
すべき手法であると考えますことから、教育委員会のみならず政策部共々に
検討いたします中で、今後の方向性を見いだしてまいりたいというふうに考えて
ございます。
以上、浜口議員の再質問にお答えいたします。
●再質問
最後に給付型奨学金の分析といいますか、エビデンスも必要だと考えます。
この月額5万円が何に一番使われているのか検証が必要だと思います。
給付型奨学金が終わって、きちんと調査やアンケートなどを行い、奨学金の
使い道といいますか、使途を実態として、家賃などの住居費なのか、生活費
なのか、それとも授業料なのか、これらをきちっと分析していくことが持続可能
な奨学金制度につながると考えます。
県内の大学と県外の大学、また都市部の大学と地方の大学、国公立と私立の
大学や医学部、歯学部など、また専門学校においても、やはり給付型奨学金の
使用用途が違ってくると考えますので、給付すれば終わりではありませんし、
エビデンスを持って次の制度につなげていくことが非常に重要だと思うんですが、
どうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁(西川昌幸教育部長)
三豊市給付型奨学金制度につきましては、コロナ禍の中、家庭の事情などに
より窮地に追い込まれた子供たちが進学を諦め、また夢を諦めることがないよう、
少しでも早く助け出したいというところで急遽立案したものでございます。
こちらの立案、施行に当たりましては議員各位の本当に御協力をいただいた
ものと感謝いたしておりますが、そういった実感的なこともございましたことから、
手探りで始めたところも多々ございます。
そういったところを踏まえまして、今後につきましてはこの制度をより学生たちの
実態に寄り添った形にしていきたいというふうに考えております。
御案内の卒業後も含めました効果、何に使われたのかといった部分につきましても、
給付対象者の御迷惑にならない範囲内で御意見なりをお伺いする中、いただいた
御意見を一つの重大なエビデンスと捉まえまして、よりこの制度を成熟させて
いきたいというふうに考えておりますので、御理解賜りたいと存じます。
以上が一問目でした。
今後拡充するいい答弁が得られて、四国新聞にも掲載されましたー。
少し嬉しかったです
 。
。明日の2問目に続く・・・。
Posted by はまぐちふどうさん at 08:25│Comments(0)
│一般質問
コメントは管理者承認が必要となります。