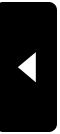2016年09月29日
一般質問その1~新しい仕事
定例議会報告は、自身の「一般質問」から。
1.新しい仕事を生み出す仕組み作りについて
仕事がないところに人は定着できない、という点で人口減少抑制対策としては
安定的な収入を確保したり、新しい仕事を地域で生み出す事が必要と言える。
仕事と人とのマッチングやシェアオフィス、ベンチャー起業支援、産学官連携等
に今こそ率先して取り組むべきであると考えるが、具体的施策を聞きたい。
2.JR詫間駅前振興について
JR詫間駅前の駐輪場が、無料化から駅前の景観を損ねている。
瀬戸内芸術祭2016を控え、駐輪場も含め、JR詫間駅の将来的振興をどう
考えているのか。当局の考えを聞きたい。
●質問1
4番、清風会、浜口恭行です。通告により一般質問をさせていただきます。
まず初めに、新しい仕事を生み出す仕組みづくりについてお聞きいたします。
実は、6月定例会の人口減少について一般質問をしてから、私なりにもいろいろ調査
研究していた中で、人口減が地方を強くするという藤波 匠氏の本を読ませていただ
きました。
この本の中では、仕事がないところに人は定着できないという点で、人口抑制対策と
しては、安定的な収入を確保したり、新しい仕事を地域で生み出すことが必要と言え
る、特に自然な都市への人口の流れを無理やり食いとめるのではなく、人口減少、
特に若い世代の減少を正面から捉え、東京、地方に限らず、未来を見据え、さまざま
な取り組みで持続的な地域を形づくる施策、一言で言えば豊かな田舎になるというこ
と、そこでの暮らしの中で富を生み出し、社会保障費や税を負担できるだけのしっか
りとしたなりわいを持てる人たちの暮らしの場をつくっていくことが重要であるという点、
また、行政が考えなければならないのは、移住先や空き家の紹介よりも、仕事と人と
のマッチングであり、大都市に向けて紹介すべきなのは、移住募集やその支援制度
も必要ではあるが、求人情報やベンチャー立ち上げに向けた事業環境であるという
考えに深い感銘を受けました。
地方にも人手不足の仕事が数多くありながら、人材の流動性の低さによって人材の
確保がままならない企業や産業があることが知られています。
せっかくのベンチャーの立ち上げに適した環境がありながら、それが一般に知られて
いない、そういう仕事や事業環境を新しく生み出すことを目指し、地域内はもちろん、
大都市からもうまく人が流れるような仕組みをつくることが、行政が移住フェアよりも
優先して取り組むべき課題であるという考え方であります。
大都市や中山間地域を問わず、若い世代が付加価値の高い仕事につけるような社会
を構築すること、人口が減っても安心して暮らし続けられる地域を築くことが重要であ
るということです。
特に、地方における企業環境を支える社会基盤として、近年は情報通信ネットワーク
の存在が不可欠となる中、本市でも光ファイバーの敷設により地方においてどこのエ
リアでも高速通信ネットワークにアクセスすることが可能となり、ICT技術が地方の企
業環境を劇的に変えました。
そういう点でも、新しい仕事を確保できないかと考えれば、仕事と人とのマッチングや、
空き家や使用しなくなった公共施設でのサテライトオフィス、シェアオフィスのような形
態、ベンチャー企業支援、香川高専と連携した本市独自の産・学・官連携などに、今
こそ率先して取り組むべきであると考えます。
本市として、新しい仕事や雇用についてどう取り組むべきであるか、具体的施策を
お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁1(横山市長)
三豊市では、平成27年10月、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しまして、
「住みたくなる“強く、やさしく、楽しい三豊”の創造」をテーマとし、諸施策を展開しながら
若者の地元定住とU・J・Iターンの促進を行っている。
議員の御質問にありました、大都市に向けて紹介すべきは、移住募集よりも求人情報
やベンチャー立ち上げのための事業環境であるという点は傾聴に値します。
確かに求人情報を地域内だけでなく、広く大都会に向けて発信するということは、住居
よりもまず仕事という大変重要な視点で、この点の具体化はぜひ検討していきたい。
先日、高松でのある会合において、起業するなら三豊がいいという評判を聞くのですが
と言われ、確かに三豊市では、先進的に三豊市地域経済循環創造事業補助金、がん
ばる企業応援事業補助金、みとよ創業塾等の制度を設けまして、新たな事業へのチャレ
ンジを行う企業を支援する体制を整えている。
しかしながら、サテライトオフィスやベンチャー企業誘致等に特化した支援施策は実施
をしておりません。
現在、総務省においてサテライトオフィスの受け入れの事前調査の費用助成、都市部
のベンチャー企業を誘致するための取り組みに対する支援等が計画されており、こう
いう制度を活用した新しい仕事確保のための施策を検討していきたい。
三豊市の課題でもある空き家や遊休施設を三豊市の資源と置きかえ、サテライトオフィ
スやシェアオフィスとしての新しい活用を検討していく。
●再質問2
実は、マッチングについてですけど、建設経済常任委員会の行政視察で、長野県塩尻
市へセンサーネットワークによる情報化と鳥獣被害対策の視察をさせていただきました。
塩尻市は、総合計画の中で「確かな暮らし 未来につなぐ田園都市」を掲げており、横山
市長と同じ田園都市構想があって、まずとても親近感を覚えたのですけど、この中で塩
尻市が、結構以前から情報化施策に取り組んでおり、この塩尻市が構築した情報基盤
を使って、子供の見守り、鳥獣対策、気象対策、防災等、地域が抱える分野での活用に
挑戦し、大きな成果を上げておりました。
このセンサーネットワークによる鳥獣対策は、けもの検知センサーで、イノシシの熱で昼
夜問わずイノシシを感知し、感知すると点滅する光を出して追い払い、塩尻市のネットワ
ークを通じて登録者の携帯電話にメールで通知、電源は太陽光であり、電力線につなが
っている必要がなく、軽量かつ簡素な構造で、場所も自由に移動可能なものでありました。
また、捕獲検知センサー、こちらは私ども建設経済常任委員は実物も見せていただきま
したけど、おりの扉が閉まり、イノシシを捕獲すると、塩尻市のセンサーネットワークを通
じて登録者の携帯電話にメールで通知され、現在はGPSの位置情報やカメラ撮影の写
真や動画までがスマホに送られるようなシステムまでが開発されておりました。
何より思いましたのは、私も香川高専の先生と話をしたんですけど、このセンサー技術
とか無線ネットワーク、これは香川高専の先生方が最も得意としている方もおりまして、
本市での産・学・官連携ができないのかということであります。
例えばイノシシ駆除で困っているのに、連携して地域の困り事が考えられないのでしょう
か。それをマッチングする窓口がどこであるのかを考えてしまいます。
香川高専には地域連携としての未来技術共同教育センターがあるようですけど、地元の
企業との連携があるのに、地域の困り事、特にこの農業分野での連携がちょっとできて
いないのはなぜかなと、このマッチングをするのが行政の仕事ではないかと思いました。
特に塩尻市が運営しております技術者の人材育成・新規創業育成を目的とした塩尻イン
キュベーションプラザ(SIP)これはシップと読むかもしれませんが、これが平成19年に設
置されまして、現在13余りの企業が入居し、ビジネスアイデアの具体化を展開していまし
た。
シップには入居企業が中心となり、農業分野でのICTの研究開発や普及・展開を図るIT
アグリ研究会が設置され、この研究会の存在によって地域のニーズに基づく具体的な
鳥獣対策ソリューションの構築を実施することが可能となったそうです。
このITアグリ研究会には、事業者11社、個人2名、協力機関として信州大学、長野高専
が入っておりました。
まさに地域のICT企業、産・学・官連携があって、イノシシの駆除にまでつながる、これで
新しい仕事や雇用が生み出されているような循環サイクルがそこには展開されておりま
した。
その中のポイントとして、塩尻市はみずからの情報通信基盤として、みずからの予算で
運用する施策、特に総務省所管の街中にぎわい創出事業や地域児童見守りシステム
モデル事業、ICTまちづくり推進事業などの交付金がうまく活用され、塩尻市が率先して
連携したまちづくり事業を継続してきたがゆえ、このアニマルセンサー等が開発された
ものだという点が、すごく勉強になりました。そのあたり、まずどうお考えでしょうか。
また、シェアオフィスやサテライトオフィス、高速なインターネット回線が県内全域に整備
されております。徳島県では非常に盛んであります。
神山町はIT企業が集まる先進地として有名ですけど、最近では美波町や三次市などへ
の集積が進んでいます。
特にサテライトオフィスは、地域に雇用を生み、そのために移住してくる若者がいて、本
市と友好都市協定のある美波町では、IT企業やデザイン会社などサテライトオフィスの
開設が13カ所もあり、神山町と並んで多いです。
三次市でも廃校などを活用して5社が進出しているようで、一歩先に進出した人たちが
町の魅力を高め、それが新たな企業を誘引しているという点、高速回線があれば地方
にもオフィスを開設していただけるという点、すばらしい取り組みであると言えます。
私も昨年度、美波町の地域活性化を目的とする会社、あわえさんを見学させていただき、
古民家を改装したサテライトオフィス体験施設「戎邸」も見させていただきました。
これは非常に素敵な施設でありましたが、私も香川高専の先生にサポートや相談もお願
いしていますけど、本当に美波町からサテライトオフィス事業を一番に学ばせてもらうべき
ではと思います。
また、一次産業も食える農業、食える漁業に成長させることが受け入れ地域の責務と言
えますが、現在、友好都市である美波町の伊座利漁港では、漁師になることを希望する
Iターン者のために、漁船の乗組員としての就労の機会を提供し、古くから地域の中心的
な漁法であるアワビやイセエビの素潜り漁で生計を立てようという新人漁師に漁業権を
開放しております。
この漁業権の開放というのは、これは非常に画期的で、今や以前からの漁業権を持つ
漁師よりも若いIターンの新人漁師のほうが多く収穫する場合もあって、これまでにない
手厚いサポート体制で移住者を受け入れ、一次産業を活性化し、若者に新しい仕事を
生み出し、サポートをしている点、本当に美波町にはお祭りでお互いの交流だけでなく、
非常に学ぶことが多いのではと思います。
そういう点でも、友好都市協定を拡大した産業分野と民間での交流、見直しが必要かと
思います。
もう一つ、島根県江津市では、空き家バンクとしては三豊市の先輩に当たり、10年以上
前から空き家バンクに取り組んでいますけど、ここにはてごねっと石見というNPO法人
があります。
この団体は小型商業施設の衰退が著しい江津駅周辺を本拠地に、地域における起業
支援や人材育成を目指して活動を続けています。
地域の人材やネットワークの構築を支援し、資金調達のサポートとして金融機関の紹介
なども行いますが、もちろんいきなり経営が順風満帆になり、急成長を遂げ、多くの雇用
を生むような企業が立ち上がるわけではありませんが、飲食店や宿泊施設などが中心と
なって、地域にとってはかけがえのない起業があり、移住者があると言えます。
もともと地方の地域コミュニティーは結束力が強いものの、悪く言えば排他的な面があり、
地域に流入する若い起業家にとって、一からネットワークを構築することは容易ではなく、
人材育成はさておき、地域の関係者や企業とのネットワーク構築を支援してくれる組織の
存在、どのような企業を立ち上げるにせよ、この上にない創業支援となります。
こうした着実な活動が地域経済を押し上げる種や芽となり、若い人の定着につながること
になるかと思います。
本市でも、企業家や事業者と銀行をつなぐ存在としてクラウドファンディング、銀行が融資
しづらい案件に対しクラウドファンディングによる資金調達を挟むことで、事業の可能性を
見きわめる橋渡しが市内企業により始まりましたけど、やはりどこかで市当局とかNPOが
取りまとめをして動くことが重要であると考えます。
本市ではいろんな事業がありますが、これがもう個々に単発で行われているという印象が
あるんですが、このあたりどうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(綾政策部長)
議員御指摘のように、人口減少対策、この中では仕事がないと人は定着できない、人を
呼び込み、また長期にわたって定着させていくためには、それ相当の仕事が必要である
と、そういったことから、仕事と人のマッチングというのは非常に大事だなと考えている。
また、議員御指摘の塩尻市におけます産・学・官連携事業の事例につきましては、有害
鳥獣問題等の住民の安心安全という地域課題に対しまして、ソフト会社と信州大学など
で構成しますITアグリ研究会が、市とともにクラウドシステムを構築しまして、大きな成果
を上げており、参考にすべき事例であると受けとめている。
御指摘のように、香川高専詫間キャンパスという、三豊市の非常に、日本ものづくり大賞
を受賞した最先端の技術集団があり、今現在、未来技術共同教育センターが設置されて
おり、これは学内での設置であり、例えばですけれども、香川県内におきましても、そう
いったインキュベーションセンターを香川高専内の詫間キャンパスに持ってくることにより
まして、例えばですけども、中西讃のインキュベーションセンター機能を生かしながら、
また第1次産業等々の連携等を図っていければなと思っています。
これは産・学・官連携、これも産・学、また金の連携も含めまして、いろいろな方策を立て
ていきたいかなと考えている。
中略
議員御指摘の産・学・官が目的ではなくて、人、物、仕事などの地域資源、これを友好的
に利活用しまして、地域課題を解決する中で、新たな仕事、それによる雇用を生んでいく
ことが重要ではないかなと考えている。
地域課題を見、聞き、考える中で、利活用できる国等の支援施策についても、注視しなが
らですけども、マッチングを考えていきたいかなと思う。
最後、友好都市であります美波町、神山町等々、IT環境の有利性を生かしましたサテラ
イトオフィス事業ですが、これについては当然承知しておりますけれども、このあたりは、
ただ単に一自治体ができるということではなくて、徳島県が非常にモデル指定を行って
注力しているということもお聞きしております。
香川県でもこういった資源、空き家、廃校になったもの等々、施設等もありますので、
そういったことを連携をとりながらこれは進めていきたいかなと考えております。
繰り返しになりますけれども、来年度に向けまして、三豊市の課題でもある空き家、遊休
施設を三豊の資源と置きかえまして、サテライトオフィスやシェアオフィス、またこれに
取り組んでいきたいと思います。
●再質問3
実は私自身、大都市や中山間地域を問わず、若い世代が付加価値の高い仕事につけ
るような社会を構築すること、また、人口が減っても安心して豊かな暮らしを続けられる
地域を築くというテーマは、ちょっと今からも継続して調査研究していかなければならな
いといいますか、非常にどんな施策が有効なのか難しく、すぐの答えが見つからないと
いうのが率直な考えであり、それゆえ、市当局にお聞きしたということもあります。
特に、先ほどから出ています隣県の徳島県には学ぶべきことが多く、上勝町には有名
な葉っぱビジネスがありますが、近年、上勝町に移住してくる若者もふえております。
この葉っぱビジネスが若い移住者に門戸が開かれているかといえば、必ずしもそうとは
言えず、これは葉っぱビジネスとともに並行して町が進めている「ゼロ・ウェイスト」、
リサイクルビジネスの業者の波及効果によって新たな仕事が生み出されているためだ
と考えられるそうです。
つい先日、神山町NPO法人グリーンバレーの大南理事長の講演を聞く機会がありまし
たが、このビジョンは創造的過疎による持続可能な地域づくりであります。
創造的過疎とは、将来的に人口が減ることを不可避とし、過疎化を受け入れた上で、
人口構成を持続可能な形に変えていく計画的な過疎対策のことでありまして、過疎と
いうとマイナスのイメージしか湧かないが、それを数値化し、計画的に過疎化を進める
ことで持続可能にできる、例えば移住定住者には人口維持のための若者や子連れの
方、また、産業活性化のために仕事を持っている方を優先し、ワーク・イン・レジデンス
という概念がありました。
このワーク・イン・レジデンスとは、将来、町にとって必要な働き手や起業家など、職種
を最初から指定して過疎をコントロールする、その考え方こそが創造的過疎であると
いう点の講演を聞きまして、非常に共感を受けました。
そういうことを考えれば、若者が好きな業種にまた雇用も発生しますし、本市も廃校に
ついての利用提案募集もされましたが、こちらから宿泊施設とかサテライトオフィスとか
の提案もありでないのかなと私は思います。
また、最近ですけど、岡山県和気町が起業支援補助金を拡充して、出店支援補助金
ですね、これはフランチャイズに特化しているんですけど、この企業支援補助金を、金
額が150万だったのを2,000万円と大きく引き上げて、出店補助支援補助金としていま
す。
三豊市もこの創業支援補助金というのがことしからできたと聞きましたが、金額が補助
対象経費の3分の2以内または30万以下のいずれか少ない金額ということなので、起
業支援、起こす業のほうですね、もちろん。
この起業支援補助金を増額して、今後、産業の活性化を考えれば、これをもっと増額し
ていくという方向、これは最近やはり眺めのよい場所、荘内半島でカフェやレストラン
とか工房をしたいという御相談がもう非常に、私どものほうにも御相談が寄せられて
おりますので、起業支援補助金の増額等も検討していただきたいと思いますが、どうで
しょうか。再々質問をいたします。
●答弁3(綾政策部長)
若者の起業支援をすることで、若い人が定着、定住していただける、そういった施策に
つきましては非常に重要であり、新たな仕事を生み出す仕組みづくりというのは重要
でないかなと思っている。
そういった点におきまして、議員御指摘のように、まずは先ほどのクラウドファンディング
であったり、産・学・官連携であったり、そういったものによりますスタートアップ資金の支
援、それによる商品づくりの補助、連携、加えてですけれども、その商品を展示会等へ
出品してマッチング等々を行い、商品の拡散を図っていくというような施策になっていこう
かと思いますけれども、そういった総合的な部分で三豊市でも創業支援等々を行ってお
ります。
これをさらにですけれども、人口減少対策と重ね合わせながら、若者に限定してみたり、
また、移住者等々の施策に合致してみたり、そういったことが考えられるのではないかな
と思います。
いずれにしましても、民間が活動しやすい環境づくりをしながら、新たな仕事を生み出して
いくと、それによって地域を活性化していくというようなことは非常に重要だと思っておりま
すので、今後も産業振興施策につきましては、いろいろ御意見をいただきながら進めて
いきたい。
当局の答弁は、概略です。
詳細をお聞きになりたい方は、三豊市HPから、録画配信をご覧下さい。
御意見やメールもお待ちしております。
hama2103_3104@yahoo.co.jp
1.新しい仕事を生み出す仕組み作りについて
仕事がないところに人は定着できない、という点で人口減少抑制対策としては
安定的な収入を確保したり、新しい仕事を地域で生み出す事が必要と言える。
仕事と人とのマッチングやシェアオフィス、ベンチャー起業支援、産学官連携等
に今こそ率先して取り組むべきであると考えるが、具体的施策を聞きたい。
2.JR詫間駅前振興について
JR詫間駅前の駐輪場が、無料化から駅前の景観を損ねている。
瀬戸内芸術祭2016を控え、駐輪場も含め、JR詫間駅の将来的振興をどう
考えているのか。当局の考えを聞きたい。
●質問1
4番、清風会、浜口恭行です。通告により一般質問をさせていただきます。
まず初めに、新しい仕事を生み出す仕組みづくりについてお聞きいたします。
実は、6月定例会の人口減少について一般質問をしてから、私なりにもいろいろ調査
研究していた中で、人口減が地方を強くするという藤波 匠氏の本を読ませていただ
きました。
この本の中では、仕事がないところに人は定着できないという点で、人口抑制対策と
しては、安定的な収入を確保したり、新しい仕事を地域で生み出すことが必要と言え
る、特に自然な都市への人口の流れを無理やり食いとめるのではなく、人口減少、
特に若い世代の減少を正面から捉え、東京、地方に限らず、未来を見据え、さまざま
な取り組みで持続的な地域を形づくる施策、一言で言えば豊かな田舎になるというこ
と、そこでの暮らしの中で富を生み出し、社会保障費や税を負担できるだけのしっか
りとしたなりわいを持てる人たちの暮らしの場をつくっていくことが重要であるという点、
また、行政が考えなければならないのは、移住先や空き家の紹介よりも、仕事と人と
のマッチングであり、大都市に向けて紹介すべきなのは、移住募集やその支援制度
も必要ではあるが、求人情報やベンチャー立ち上げに向けた事業環境であるという
考えに深い感銘を受けました。
地方にも人手不足の仕事が数多くありながら、人材の流動性の低さによって人材の
確保がままならない企業や産業があることが知られています。
せっかくのベンチャーの立ち上げに適した環境がありながら、それが一般に知られて
いない、そういう仕事や事業環境を新しく生み出すことを目指し、地域内はもちろん、
大都市からもうまく人が流れるような仕組みをつくることが、行政が移住フェアよりも
優先して取り組むべき課題であるという考え方であります。
大都市や中山間地域を問わず、若い世代が付加価値の高い仕事につけるような社会
を構築すること、人口が減っても安心して暮らし続けられる地域を築くことが重要であ
るということです。
特に、地方における企業環境を支える社会基盤として、近年は情報通信ネットワーク
の存在が不可欠となる中、本市でも光ファイバーの敷設により地方においてどこのエ
リアでも高速通信ネットワークにアクセスすることが可能となり、ICT技術が地方の企
業環境を劇的に変えました。
そういう点でも、新しい仕事を確保できないかと考えれば、仕事と人とのマッチングや、
空き家や使用しなくなった公共施設でのサテライトオフィス、シェアオフィスのような形
態、ベンチャー企業支援、香川高専と連携した本市独自の産・学・官連携などに、今
こそ率先して取り組むべきであると考えます。
本市として、新しい仕事や雇用についてどう取り組むべきであるか、具体的施策を
お聞きしたいと思いますので、よろしくお願いします。
●答弁1(横山市長)
三豊市では、平成27年10月、まち・ひと・しごと創生総合戦略を策定しまして、
「住みたくなる“強く、やさしく、楽しい三豊”の創造」をテーマとし、諸施策を展開しながら
若者の地元定住とU・J・Iターンの促進を行っている。
議員の御質問にありました、大都市に向けて紹介すべきは、移住募集よりも求人情報
やベンチャー立ち上げのための事業環境であるという点は傾聴に値します。
確かに求人情報を地域内だけでなく、広く大都会に向けて発信するということは、住居
よりもまず仕事という大変重要な視点で、この点の具体化はぜひ検討していきたい。
先日、高松でのある会合において、起業するなら三豊がいいという評判を聞くのですが
と言われ、確かに三豊市では、先進的に三豊市地域経済循環創造事業補助金、がん
ばる企業応援事業補助金、みとよ創業塾等の制度を設けまして、新たな事業へのチャレ
ンジを行う企業を支援する体制を整えている。
しかしながら、サテライトオフィスやベンチャー企業誘致等に特化した支援施策は実施
をしておりません。
現在、総務省においてサテライトオフィスの受け入れの事前調査の費用助成、都市部
のベンチャー企業を誘致するための取り組みに対する支援等が計画されており、こう
いう制度を活用した新しい仕事確保のための施策を検討していきたい。
三豊市の課題でもある空き家や遊休施設を三豊市の資源と置きかえ、サテライトオフィ
スやシェアオフィスとしての新しい活用を検討していく。
●再質問2
実は、マッチングについてですけど、建設経済常任委員会の行政視察で、長野県塩尻
市へセンサーネットワークによる情報化と鳥獣被害対策の視察をさせていただきました。
塩尻市は、総合計画の中で「確かな暮らし 未来につなぐ田園都市」を掲げており、横山
市長と同じ田園都市構想があって、まずとても親近感を覚えたのですけど、この中で塩
尻市が、結構以前から情報化施策に取り組んでおり、この塩尻市が構築した情報基盤
を使って、子供の見守り、鳥獣対策、気象対策、防災等、地域が抱える分野での活用に
挑戦し、大きな成果を上げておりました。
このセンサーネットワークによる鳥獣対策は、けもの検知センサーで、イノシシの熱で昼
夜問わずイノシシを感知し、感知すると点滅する光を出して追い払い、塩尻市のネットワ
ークを通じて登録者の携帯電話にメールで通知、電源は太陽光であり、電力線につなが
っている必要がなく、軽量かつ簡素な構造で、場所も自由に移動可能なものでありました。
また、捕獲検知センサー、こちらは私ども建設経済常任委員は実物も見せていただきま
したけど、おりの扉が閉まり、イノシシを捕獲すると、塩尻市のセンサーネットワークを通
じて登録者の携帯電話にメールで通知され、現在はGPSの位置情報やカメラ撮影の写
真や動画までがスマホに送られるようなシステムまでが開発されておりました。
何より思いましたのは、私も香川高専の先生と話をしたんですけど、このセンサー技術
とか無線ネットワーク、これは香川高専の先生方が最も得意としている方もおりまして、
本市での産・学・官連携ができないのかということであります。
例えばイノシシ駆除で困っているのに、連携して地域の困り事が考えられないのでしょう
か。それをマッチングする窓口がどこであるのかを考えてしまいます。
香川高専には地域連携としての未来技術共同教育センターがあるようですけど、地元の
企業との連携があるのに、地域の困り事、特にこの農業分野での連携がちょっとできて
いないのはなぜかなと、このマッチングをするのが行政の仕事ではないかと思いました。
特に塩尻市が運営しております技術者の人材育成・新規創業育成を目的とした塩尻イン
キュベーションプラザ(SIP)これはシップと読むかもしれませんが、これが平成19年に設
置されまして、現在13余りの企業が入居し、ビジネスアイデアの具体化を展開していまし
た。
シップには入居企業が中心となり、農業分野でのICTの研究開発や普及・展開を図るIT
アグリ研究会が設置され、この研究会の存在によって地域のニーズに基づく具体的な
鳥獣対策ソリューションの構築を実施することが可能となったそうです。
このITアグリ研究会には、事業者11社、個人2名、協力機関として信州大学、長野高専
が入っておりました。
まさに地域のICT企業、産・学・官連携があって、イノシシの駆除にまでつながる、これで
新しい仕事や雇用が生み出されているような循環サイクルがそこには展開されておりま
した。
その中のポイントとして、塩尻市はみずからの情報通信基盤として、みずからの予算で
運用する施策、特に総務省所管の街中にぎわい創出事業や地域児童見守りシステム
モデル事業、ICTまちづくり推進事業などの交付金がうまく活用され、塩尻市が率先して
連携したまちづくり事業を継続してきたがゆえ、このアニマルセンサー等が開発された
ものだという点が、すごく勉強になりました。そのあたり、まずどうお考えでしょうか。
また、シェアオフィスやサテライトオフィス、高速なインターネット回線が県内全域に整備
されております。徳島県では非常に盛んであります。
神山町はIT企業が集まる先進地として有名ですけど、最近では美波町や三次市などへ
の集積が進んでいます。
特にサテライトオフィスは、地域に雇用を生み、そのために移住してくる若者がいて、本
市と友好都市協定のある美波町では、IT企業やデザイン会社などサテライトオフィスの
開設が13カ所もあり、神山町と並んで多いです。
三次市でも廃校などを活用して5社が進出しているようで、一歩先に進出した人たちが
町の魅力を高め、それが新たな企業を誘引しているという点、高速回線があれば地方
にもオフィスを開設していただけるという点、すばらしい取り組みであると言えます。
私も昨年度、美波町の地域活性化を目的とする会社、あわえさんを見学させていただき、
古民家を改装したサテライトオフィス体験施設「戎邸」も見させていただきました。
これは非常に素敵な施設でありましたが、私も香川高専の先生にサポートや相談もお願
いしていますけど、本当に美波町からサテライトオフィス事業を一番に学ばせてもらうべき
ではと思います。
また、一次産業も食える農業、食える漁業に成長させることが受け入れ地域の責務と言
えますが、現在、友好都市である美波町の伊座利漁港では、漁師になることを希望する
Iターン者のために、漁船の乗組員としての就労の機会を提供し、古くから地域の中心的
な漁法であるアワビやイセエビの素潜り漁で生計を立てようという新人漁師に漁業権を
開放しております。
この漁業権の開放というのは、これは非常に画期的で、今や以前からの漁業権を持つ
漁師よりも若いIターンの新人漁師のほうが多く収穫する場合もあって、これまでにない
手厚いサポート体制で移住者を受け入れ、一次産業を活性化し、若者に新しい仕事を
生み出し、サポートをしている点、本当に美波町にはお祭りでお互いの交流だけでなく、
非常に学ぶことが多いのではと思います。
そういう点でも、友好都市協定を拡大した産業分野と民間での交流、見直しが必要かと
思います。
もう一つ、島根県江津市では、空き家バンクとしては三豊市の先輩に当たり、10年以上
前から空き家バンクに取り組んでいますけど、ここにはてごねっと石見というNPO法人
があります。
この団体は小型商業施設の衰退が著しい江津駅周辺を本拠地に、地域における起業
支援や人材育成を目指して活動を続けています。
地域の人材やネットワークの構築を支援し、資金調達のサポートとして金融機関の紹介
なども行いますが、もちろんいきなり経営が順風満帆になり、急成長を遂げ、多くの雇用
を生むような企業が立ち上がるわけではありませんが、飲食店や宿泊施設などが中心と
なって、地域にとってはかけがえのない起業があり、移住者があると言えます。
もともと地方の地域コミュニティーは結束力が強いものの、悪く言えば排他的な面があり、
地域に流入する若い起業家にとって、一からネットワークを構築することは容易ではなく、
人材育成はさておき、地域の関係者や企業とのネットワーク構築を支援してくれる組織の
存在、どのような企業を立ち上げるにせよ、この上にない創業支援となります。
こうした着実な活動が地域経済を押し上げる種や芽となり、若い人の定着につながること
になるかと思います。
本市でも、企業家や事業者と銀行をつなぐ存在としてクラウドファンディング、銀行が融資
しづらい案件に対しクラウドファンディングによる資金調達を挟むことで、事業の可能性を
見きわめる橋渡しが市内企業により始まりましたけど、やはりどこかで市当局とかNPOが
取りまとめをして動くことが重要であると考えます。
本市ではいろんな事業がありますが、これがもう個々に単発で行われているという印象が
あるんですが、このあたりどうでしょうか。再質問をいたします。
●答弁2(綾政策部長)
議員御指摘のように、人口減少対策、この中では仕事がないと人は定着できない、人を
呼び込み、また長期にわたって定着させていくためには、それ相当の仕事が必要である
と、そういったことから、仕事と人のマッチングというのは非常に大事だなと考えている。
また、議員御指摘の塩尻市におけます産・学・官連携事業の事例につきましては、有害
鳥獣問題等の住民の安心安全という地域課題に対しまして、ソフト会社と信州大学など
で構成しますITアグリ研究会が、市とともにクラウドシステムを構築しまして、大きな成果
を上げており、参考にすべき事例であると受けとめている。
御指摘のように、香川高専詫間キャンパスという、三豊市の非常に、日本ものづくり大賞
を受賞した最先端の技術集団があり、今現在、未来技術共同教育センターが設置されて
おり、これは学内での設置であり、例えばですけれども、香川県内におきましても、そう
いったインキュベーションセンターを香川高専内の詫間キャンパスに持ってくることにより
まして、例えばですけども、中西讃のインキュベーションセンター機能を生かしながら、
また第1次産業等々の連携等を図っていければなと思っています。
これは産・学・官連携、これも産・学、また金の連携も含めまして、いろいろな方策を立て
ていきたいかなと考えている。
中略
議員御指摘の産・学・官が目的ではなくて、人、物、仕事などの地域資源、これを友好的
に利活用しまして、地域課題を解決する中で、新たな仕事、それによる雇用を生んでいく
ことが重要ではないかなと考えている。
地域課題を見、聞き、考える中で、利活用できる国等の支援施策についても、注視しなが
らですけども、マッチングを考えていきたいかなと思う。
最後、友好都市であります美波町、神山町等々、IT環境の有利性を生かしましたサテラ
イトオフィス事業ですが、これについては当然承知しておりますけれども、このあたりは、
ただ単に一自治体ができるということではなくて、徳島県が非常にモデル指定を行って
注力しているということもお聞きしております。
香川県でもこういった資源、空き家、廃校になったもの等々、施設等もありますので、
そういったことを連携をとりながらこれは進めていきたいかなと考えております。
繰り返しになりますけれども、来年度に向けまして、三豊市の課題でもある空き家、遊休
施設を三豊の資源と置きかえまして、サテライトオフィスやシェアオフィス、またこれに
取り組んでいきたいと思います。
●再質問3
実は私自身、大都市や中山間地域を問わず、若い世代が付加価値の高い仕事につけ
るような社会を構築すること、また、人口が減っても安心して豊かな暮らしを続けられる
地域を築くというテーマは、ちょっと今からも継続して調査研究していかなければならな
いといいますか、非常にどんな施策が有効なのか難しく、すぐの答えが見つからないと
いうのが率直な考えであり、それゆえ、市当局にお聞きしたということもあります。
特に、先ほどから出ています隣県の徳島県には学ぶべきことが多く、上勝町には有名
な葉っぱビジネスがありますが、近年、上勝町に移住してくる若者もふえております。
この葉っぱビジネスが若い移住者に門戸が開かれているかといえば、必ずしもそうとは
言えず、これは葉っぱビジネスとともに並行して町が進めている「ゼロ・ウェイスト」、
リサイクルビジネスの業者の波及効果によって新たな仕事が生み出されているためだ
と考えられるそうです。
つい先日、神山町NPO法人グリーンバレーの大南理事長の講演を聞く機会がありまし
たが、このビジョンは創造的過疎による持続可能な地域づくりであります。
創造的過疎とは、将来的に人口が減ることを不可避とし、過疎化を受け入れた上で、
人口構成を持続可能な形に変えていく計画的な過疎対策のことでありまして、過疎と
いうとマイナスのイメージしか湧かないが、それを数値化し、計画的に過疎化を進める
ことで持続可能にできる、例えば移住定住者には人口維持のための若者や子連れの
方、また、産業活性化のために仕事を持っている方を優先し、ワーク・イン・レジデンス
という概念がありました。
このワーク・イン・レジデンスとは、将来、町にとって必要な働き手や起業家など、職種
を最初から指定して過疎をコントロールする、その考え方こそが創造的過疎であると
いう点の講演を聞きまして、非常に共感を受けました。
そういうことを考えれば、若者が好きな業種にまた雇用も発生しますし、本市も廃校に
ついての利用提案募集もされましたが、こちらから宿泊施設とかサテライトオフィスとか
の提案もありでないのかなと私は思います。
また、最近ですけど、岡山県和気町が起業支援補助金を拡充して、出店支援補助金
ですね、これはフランチャイズに特化しているんですけど、この企業支援補助金を、金
額が150万だったのを2,000万円と大きく引き上げて、出店補助支援補助金としていま
す。
三豊市もこの創業支援補助金というのがことしからできたと聞きましたが、金額が補助
対象経費の3分の2以内または30万以下のいずれか少ない金額ということなので、起
業支援、起こす業のほうですね、もちろん。
この起業支援補助金を増額して、今後、産業の活性化を考えれば、これをもっと増額し
ていくという方向、これは最近やはり眺めのよい場所、荘内半島でカフェやレストラン
とか工房をしたいという御相談がもう非常に、私どものほうにも御相談が寄せられて
おりますので、起業支援補助金の増額等も検討していただきたいと思いますが、どうで
しょうか。再々質問をいたします。
●答弁3(綾政策部長)
若者の起業支援をすることで、若い人が定着、定住していただける、そういった施策に
つきましては非常に重要であり、新たな仕事を生み出す仕組みづくりというのは重要
でないかなと思っている。
そういった点におきまして、議員御指摘のように、まずは先ほどのクラウドファンディング
であったり、産・学・官連携であったり、そういったものによりますスタートアップ資金の支
援、それによる商品づくりの補助、連携、加えてですけれども、その商品を展示会等へ
出品してマッチング等々を行い、商品の拡散を図っていくというような施策になっていこう
かと思いますけれども、そういった総合的な部分で三豊市でも創業支援等々を行ってお
ります。
これをさらにですけれども、人口減少対策と重ね合わせながら、若者に限定してみたり、
また、移住者等々の施策に合致してみたり、そういったことが考えられるのではないかな
と思います。
いずれにしましても、民間が活動しやすい環境づくりをしながら、新たな仕事を生み出して
いくと、それによって地域を活性化していくというようなことは非常に重要だと思っておりま
すので、今後も産業振興施策につきましては、いろいろ御意見をいただきながら進めて
いきたい。
当局の答弁は、概略です。
詳細をお聞きになりたい方は、三豊市HPから、録画配信をご覧下さい。
御意見やメールもお待ちしております。
hama2103_3104@yahoo.co.jp
Posted by はまぐちふどうさん at 07:09│Comments(0)
│一般質問