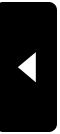2012年11月28日
第3回議員特別セミナーその1
先週、滋賀県大津にある、JIAM(ジャイアム)「全国市町村国際文化研修所」の
「第3回市町村議会議員特別セミナー」に参加してきました。
(JIAMの概要は2012年4月14日のブログ参照下さい)
副議長に「会派で行かんな~」と、お誘いいただいとりましたが、所用で参加できなく
なったそうで迷いましたが・・・4月のセミナーがとても勉強になりましたので、今回は
1人で参加。
ちなみに北海道から沖縄まで全国から208名が参加していました。



11月21日(水)
●「活気あるまちへの挑戦~リーダーに必要なもの」
(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役 竹中 功 氏
●「地域再生に必要なもの」
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏
11月22日(木)
●「地域の再生と活性化~市民が豊かになる地域再生策~」
地域再生プランナー 久繁哲之介 氏
●「まちの文化人類学~住み続けたいまちとは~」
東京大学名誉教授 船曳建夫氏
●「活気あるまちへの挑戦~リーダーに必要なもの」
(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役 竹中 功 氏
河本準一や島田紳助の記者会見の時、隣で謝罪していた人らしいです 。
。
全国の町おこしにもたくさん携わっており、「あなたの街に住みますプロジェクト」の紹介も
ありました。それでも商売人?らしく、きっちり吉本興業の宣伝していました。
全国どこからでも自治体・後援会・企業等団体利用のご案内ができるところは・・・。
さすがです !
!
それでも民間人であり、実体験上勉強になるところが多数・・・。
町おこしを考えるに、コンサルとか外部の人の提案を鵜呑みにするのはどうかと?
ポイントは地域住民が一緒に考え、決定し、動く(行動する!)事が重要だという点。
良い点も悪い点もみんな地域住民が共有し、歴史・文化・言葉・食事等々・・・地域独自の
財産を地域住民が考えて行動することの大切さを説いていました。
(ようは外部の人に頼むと失敗するらしい ・・・それって
・・・それって ・・・。)
・・・。)
竹中先生は、まちづくり・物づくり・人づくりをプロデュースすることが最後に「金づくり」へと
なる点を説いていただきました。これこそ実体験からのお話しなワケで・・・良かったです!
●「地域再生に必要なもの」
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏
東京でも講演お聞きしましたが、新川先生の専門は「議会改革」や「議員のあり方」。
今回は「地域の再生に必要なもの」
はじめに:地域再生の考え方
・なぜ、地域を考えるのか。地域再生なのか。
身近な地域、顔の見える範囲、人の関係ができる範囲の地域が成立しなくなった?
1 地域が直面している問題
・身近な地域は今どうなっているのか:縮退社会、少子高齢化、人口減少、
・経済成長の停滞、雇用問題、財政危機、福祉の切り下げ、教育問題
・社会を支えてきた地域が崩壊し始めている:全国の現場から
2 地域課題を解決するまちづくりを進めるために
・地域を取り巻く環境の変化に対応する:地域分権、市町村合併、行政構造変化
・社会経済環境変化に応える:少子高齢、人口減少、経済停滞、地域の担い手の不足
・「新しい公共」の考え方:住民、事業者、地域団体、NPOが支える公共
「新しい公共」とは行政だけではなく住民や地域団体も公共活動を担うこと
真の豊かさを求めて:身近な暮らしを「みんなの問題解決手段」から再構築していく
まちづくり・地域づくりを支える場:地域自治組織、住民団体(まちづくり推進隊?)
3 地域自治による地域再生
・まちづくり・地域づくりにおける市民団体、地域組織の役割
・市民(住民)による主体的な活動と社会参加が重要
・地縁団体、地域団体の衰退現象:活動の不活発、組織の硬直
・地域自治組織の再生:地域自治区、地域自治協議会、まちづくり協議会等々
・地域自治によるコミュニティ再生:地域の「きずな」を取り戻す
・地域自治を目指す市町村行政の方向転換
4 地域資源によるまちづくりに向けて
・まちづくりを目指す市町村行政の方向転換:身近な地域への視線
・まちづくりの方向:内発的発展、地域内循環、地産地消、新地域主義経済へ
・まちづくりのための地域資源:多様な価値を持つ地域資源
・地域資源を発見する:「ないものねだり」から「あるもの探し」への意義
・あるもの発見から「ないものづくり」へ
●ポイント
地域経済発展と地域振興から地域力重視の方向へ:地域内の充実、地域循環重視へ
多様で個性的な地域づくりが、活力あるまちづくりへ
地域重視、内需シフトの地域活性化へ:視点の転換
(大企業を誘致し、雇用を確保する時代の終了、大企業は地方進出せず海外に)
地域資源とは:その存在によってまちづくりが変わる条件
地域経済、自然、伝統文化、生活様式
地域にある資源を探す:優れた産品、見逃していた評価されていない資源
(これらは市内の中小企業や個人事業主が得意とするところかと!)
必要な資源をつくりだす:地域の条件にあったものづくり
必要な人材を作り出すひとづくり:人的資源
地域の外にある資源を活用する:ネットワーク
5 まちづくりは人づくりから
・まちを育む人育てを考える:共に学び、共に変わり、共に成長する
・まちづくり人材像:地域への熱い関心、地域資源への深い洞察、地域の将来への展望、
自らの主体的な選択と集中
結局地域づくりを進めるためには人づくりが基本:人材がなければ始まらない
おわりに:協働型まちづくりが地域力を高めるこれからの方向
地域力を高めるために
・住民、地域団体、地元業者、自治体が力をつける:自律自助が基本
・それぞれが単独では解決できない問題に連携協力して取り組む:地縁型からNPO・NGO
型の機能的な活動に向かう協働へ
・協働を進める条件や環境をつくる:地域資源の再発見、地域の相互理解、内外ネット
ワークの組織化、中間支援組織による支援
非常に抽象的な部分もあり難しかったですが、概念的なものは理解できました・・・。
夕方からの懇親会では1人で来られた静岡県沼津市議のIさんと隣になり交流。
60代後半の父みたいな方でしたが、いろんな話しも聞いていただき感謝!
その他大勢の全国の議員と交流でき ・・・これがJIAMの魅力かな!
・・・これがJIAMの魅力かな!

1日目は無事終了・・・。
「第3回市町村議会議員特別セミナー」に参加してきました。
(JIAMの概要は2012年4月14日のブログ参照下さい)
副議長に「会派で行かんな~」と、お誘いいただいとりましたが、所用で参加できなく
なったそうで迷いましたが・・・4月のセミナーがとても勉強になりましたので、今回は
1人で参加。
ちなみに北海道から沖縄まで全国から208名が参加していました。
11月21日(水)
●「活気あるまちへの挑戦~リーダーに必要なもの」
(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役 竹中 功 氏
●「地域再生に必要なもの」
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏
11月22日(木)
●「地域の再生と活性化~市民が豊かになる地域再生策~」
地域再生プランナー 久繁哲之介 氏
●「まちの文化人類学~住み続けたいまちとは~」
東京大学名誉教授 船曳建夫氏
●「活気あるまちへの挑戦~リーダーに必要なもの」
(株)よしもとクリエイティブ・エージェンシー専務取締役 竹中 功 氏
河本準一や島田紳助の記者会見の時、隣で謝罪していた人らしいです
 。
。全国の町おこしにもたくさん携わっており、「あなたの街に住みますプロジェクト」の紹介も
ありました。それでも商売人?らしく、きっちり吉本興業の宣伝していました。
全国どこからでも自治体・後援会・企業等団体利用のご案内ができるところは・・・。
さすがです
 !
!それでも民間人であり、実体験上勉強になるところが多数・・・。
町おこしを考えるに、コンサルとか外部の人の提案を鵜呑みにするのはどうかと?
ポイントは地域住民が一緒に考え、決定し、動く(行動する!)事が重要だという点。
良い点も悪い点もみんな地域住民が共有し、歴史・文化・言葉・食事等々・・・地域独自の
財産を地域住民が考えて行動することの大切さを説いていました。
(ようは外部の人に頼むと失敗するらしい
 ・・・それって
・・・それって ・・・。)
・・・。)竹中先生は、まちづくり・物づくり・人づくりをプロデュースすることが最後に「金づくり」へと
なる点を説いていただきました。これこそ実体験からのお話しなワケで・・・良かったです!
●「地域再生に必要なもの」
同志社大学大学院総合政策科学研究科教授 新川 達郎 氏
東京でも講演お聞きしましたが、新川先生の専門は「議会改革」や「議員のあり方」。
今回は「地域の再生に必要なもの」
はじめに:地域再生の考え方
・なぜ、地域を考えるのか。地域再生なのか。
身近な地域、顔の見える範囲、人の関係ができる範囲の地域が成立しなくなった?
1 地域が直面している問題
・身近な地域は今どうなっているのか:縮退社会、少子高齢化、人口減少、
・経済成長の停滞、雇用問題、財政危機、福祉の切り下げ、教育問題
・社会を支えてきた地域が崩壊し始めている:全国の現場から
2 地域課題を解決するまちづくりを進めるために
・地域を取り巻く環境の変化に対応する:地域分権、市町村合併、行政構造変化
・社会経済環境変化に応える:少子高齢、人口減少、経済停滞、地域の担い手の不足
・「新しい公共」の考え方:住民、事業者、地域団体、NPOが支える公共
「新しい公共」とは行政だけではなく住民や地域団体も公共活動を担うこと
真の豊かさを求めて:身近な暮らしを「みんなの問題解決手段」から再構築していく
まちづくり・地域づくりを支える場:地域自治組織、住民団体(まちづくり推進隊?)
3 地域自治による地域再生
・まちづくり・地域づくりにおける市民団体、地域組織の役割
・市民(住民)による主体的な活動と社会参加が重要
・地縁団体、地域団体の衰退現象:活動の不活発、組織の硬直
・地域自治組織の再生:地域自治区、地域自治協議会、まちづくり協議会等々
・地域自治によるコミュニティ再生:地域の「きずな」を取り戻す
・地域自治を目指す市町村行政の方向転換
4 地域資源によるまちづくりに向けて
・まちづくりを目指す市町村行政の方向転換:身近な地域への視線
・まちづくりの方向:内発的発展、地域内循環、地産地消、新地域主義経済へ
・まちづくりのための地域資源:多様な価値を持つ地域資源
・地域資源を発見する:「ないものねだり」から「あるもの探し」への意義
・あるもの発見から「ないものづくり」へ
●ポイント
地域経済発展と地域振興から地域力重視の方向へ:地域内の充実、地域循環重視へ
多様で個性的な地域づくりが、活力あるまちづくりへ
地域重視、内需シフトの地域活性化へ:視点の転換
(大企業を誘致し、雇用を確保する時代の終了、大企業は地方進出せず海外に)
地域資源とは:その存在によってまちづくりが変わる条件
地域経済、自然、伝統文化、生活様式
地域にある資源を探す:優れた産品、見逃していた評価されていない資源
(これらは市内の中小企業や個人事業主が得意とするところかと!)
必要な資源をつくりだす:地域の条件にあったものづくり
必要な人材を作り出すひとづくり:人的資源
地域の外にある資源を活用する:ネットワーク
5 まちづくりは人づくりから
・まちを育む人育てを考える:共に学び、共に変わり、共に成長する
・まちづくり人材像:地域への熱い関心、地域資源への深い洞察、地域の将来への展望、
自らの主体的な選択と集中
結局地域づくりを進めるためには人づくりが基本:人材がなければ始まらない
おわりに:協働型まちづくりが地域力を高めるこれからの方向
地域力を高めるために
・住民、地域団体、地元業者、自治体が力をつける:自律自助が基本
・それぞれが単独では解決できない問題に連携協力して取り組む:地縁型からNPO・NGO
型の機能的な活動に向かう協働へ
・協働を進める条件や環境をつくる:地域資源の再発見、地域の相互理解、内外ネット
ワークの組織化、中間支援組織による支援
非常に抽象的な部分もあり難しかったですが、概念的なものは理解できました・・・。
夕方からの懇親会では1人で来られた静岡県沼津市議のIさんと隣になり交流。
60代後半の父みたいな方でしたが、いろんな話しも聞いていただき感謝!
その他大勢の全国の議員と交流でき
 ・・・これがJIAMの魅力かな!
・・・これがJIAMの魅力かな!1日目は無事終了・・・。
Posted by はまぐちふどうさん at 09:09│Comments(0)
│視察研修